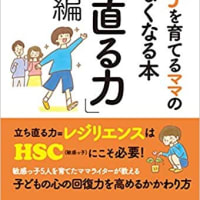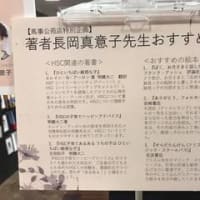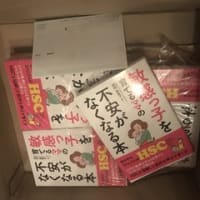編集者さんから提案していただき、
「ギフテッドという言葉を最近初めて聞いた」
といった読者を対象に記事を書きました。
11月に全国上映された映画「ギフテッド」でも、
小学校時代から、大学数学に取り組む天才児ちゃんが、
主人公になってましたね。
こうした「飛びぬけた才能を持つ子こそがギフテッドなんだ」
というイメージが行き渡る中
「勉強のできる天才児だけがギフテッドではないですよ」、
そんなメッセージをこめました。
記事では、ギフテッドの専門家が示す、
「ギフテッドの6タイプ」を
それはそれはシンプルに紹介してあります。
興味ある方、是非どうぞ!
・勉強ができる天才児だけじゃない!「ギフテッド」のタイプ6つ
6つのタイプについて、
より知りたい方は、こちらが参考資料の原文です。
英語ですが、それぞれのタイプへの対応ヒントも載っています。
私自身、たびたび、
メール等でギフテッドについての相談を受けます。
そのたびに、日本の学校でも、
個々の子どもたちのレベルやペースがもう少し考慮されるならば、
随分と楽になる子たちがいるのだろうなと思っています。
日本では、小学校、中学校、高校受験を通して、
自分の学習レベルに合った学校へ進むのも方法ですが、
そのために受験勉強に入れ込むというのは、
記事でとりあげた「タイプ1」のような
「学校システム内での成功タイプ」でないと、
難しい面がありますね。
といって、米国でなら、
「理想のギフテッド教育を受けられる!」かというと、
地域によって「ギフテッドプログラム」も様々です。
米国の「ギフテッドプログラム」の大半が「学校内で成功するタイプ」向け?
例えば、記事であげた参考文献にも、
「米国の学校で認められるギフテッドの90%が、
学校システム内で成功するタイプ」とあります。
確かに、
現在の米国の「ギフテッドプログラム」というのは、
結局、学校の成績や学力テストの点数によって振り分けられることがほとんどです。
年齢が下になるほど、
IQテストや心理学者による観察が重視される場合もありますが、
年齢が上になるほど、
学力がより重視されるようになります。
また、特に都市部では、キンダーや小学校から、
「ギフテッドプログラム」に入るためのトレーニングをする家庭もあります。
学力の先取りやIQをあげるトレーニングをするんです。
こうした場合も、「ギフテッドプログラム」の子たちというのは、
日本でいう、
「受験を勝ち抜き、偏差値の高い学校へ入る学力の高い生徒たち」
に似ていますよね。
また、今我が家が暮らす学区の隣の学区では、
学区の各地に小学校から「ギフテッドプログラム」がありますが、
入学には、先生の推薦状が必要で、
「教室での素行」や「周りとコラボレーションできるか」なども重視されます。
そうして、「学校にフィットできないタイプの子」は、どうしても、もれていきます。
「学校というシステムの中で成功していく子」のみが、
「ギフテッド」として認められていくんですね。
また、求められる「学力のレベル」というのも、
プログラムによって変わってきます
例えば、他の隣の学区では、
「大学を目指す生徒向けのクラス」の全てが、
「ギフテッドクラス」と呼ばれています。
こうなると、学校によっては、生徒の過半数が「ギフテッド」です。
←ちなみに、我が家の学区では「オナーズクラス」という名前。
こうして、こちら米国でも、
「ギフテッド」と認められていくのは、
多くの場合、「学校システムの中で成功していくタイプ」なんですね。
ちなみに、アラスカでは、
学力、認知テスト、心理学者によるIQテスト&観察で
一定のパーセンタイルをこえた子が入学してましたが、
キンダーや低学年時に入る子も多かったですし、
入学の際も「教室での素行」については問題とならず、
一旦入ってしまえば学力がどんなになろうが追い出されることもなかったですから、
かなりユニークでやんちゃな子達もいました。
それで、他の学校の先生からも、いろいろな意味で、
「あそこは、普通の学級ではやっていけない子たちが入るところ」
というような見方をされていた面もありました。
中に入ってみれば、実際は、本当にいろんな子がいて、
大人しめの子も多かったですけど、
全体的に「勉強ができる子」というより、
より多様性があったなあと感じてます。
(こちら東海岸にこしてきてから今暮らす学区では、
「ギフテッドプログラム」と名付けられたものはなく、
小学校では、通常の学級で英語と算数がレベル別にグループ分けされ、
中学校では、「高度な学習者プログラム(Highly Able Learner's program)」と、
その上に数学は「促進プログラム(accelerated program)」があり、
高校では、アドバンスクラス(AP)、国際バカロレアプログラム(IB)、
そして、コミュニティーカレッジの授業や、オンラインコースもとることできるようになっています。
いずれも、学力、成績、統一テストの点数などで、プログラムに入ることができるかが決まります)
昨年始まった渋谷区の「ギフテッドプログラム」は世界的にみても画期的?
「ギフテッド教育が盛ん」とされる米国でも、
結局は、「学校システム内で成功するタイプが大半」となると、
昨年9月に渋谷区で始まった日本初の「ギフテッドプログラム」というのは、
世界的にも、かなり画期的な試みじゃないでしょうか?
こちらの記事にある渋谷区のギフテッドプログラムへの「入学基準」には、
こうあります:
”プログラムは、小学3年生から中学3年生までの
(1)特別支援教室拠点校の巡回指導教員による指導を受ける児童
(2)情緒障害等通級指導学級に在籍する生徒
(3)長期欠席児童・生徒
が対象となっていて、本人と保護者が希望すれば参加することができる。”
ということは、
『It Mama』さんの記事にあげたタイプによると、
「2の創造的で挑戦タイプ」、
「4の学校を中退するタイプ(不登校)」
「5の発達障害を併せ持ったタイプ(2E)」
「6の学校をこえて活躍するタイプ」
なども含まれるんですよね。
ということは、
米国ではもれがちな「1の学校システム内で成功タイプ以外」の生徒達にも、
日本では、「ギフテッドプログラム」として
受け皿が用意されていくわけです。
こうした試みが渋谷区のみといわず増えるならば、
日本では、「1の学校システム内で成功するタイプ」は、
受験をして自分に合った学校へとすすみ、
残りのタイプは、こうした「ギフテッドプログラム」で学ぶ、
ということも可能になりますね。
ちなみに、米国では、
「ギフテッドプログラム」という名前でなくとも、
ホームスクールや、オンラインスクールや、チャータースクールなどの通常の学級以外の選択肢が、
「もれていく子」の受け皿となっています。
日本でも、「ギフテッドプログラム」が広がるとともに、
フリースクールなどが認可され、
ホームスクールの支援も整いと、
受け皿もますます多様になっていくといいですね。
渋谷区のギフテッドプログラムのカリキュラム、
試行錯誤を繰り返しながら磨かれ
充実していきますように。
「誰がギフテッドか」より「目の前の子のギフテッドネスをどう伸ばすか」
「本人と親が希望するなら入学可能」とし、
通常の学校にはフィットすることが難しい子の「ギフテッドネス」を伸ばしていこうという渋谷区のあり方に、
私自身、とても共感します。
ギフテッドには世界的には明確な定義があるわけではないですし、
「どんな力や、どれほどの力があればギフテッドなのか」ということは、
映画の主人公ちゃんみたいな分かりやすい例でないならば、
明確な答えなどでないでしょう。
また、そんな分かりやすい数値ではかれるような
「ギフト」ばかりじゃないでしょうし。
ですから、「本人と親が希望するなら」とは、
まさしく的を得てますよね。
そして、もちろん、
学校にフィットしない子の凹面ばかりに注目するより、
凸面を励まし、伸ばしていこうという姿勢は、
その子にとって、大きな支えになります。
そしてまた、凹面へ向き合う意欲も、
高まることでしょう。
「誰がギフテッドか」より、
今目の前にいる子の「ギフテッドネス」をどう伸ばせるか。
子どもに向き合う大人として、
思い出していきたいですね。
(・消費するだけでなく創造できる「ギフテッドネス」をどう開発する?教育学者レンズーリ氏の研究紹介)
そのためには、とにかく、
より1人1人に合った学びや探索のできる教育環境の実現、
そう思います。
それは、ギフテッドの線引きがどこにあろうとなかろうと、
どんな子にとっても、メリットのあることですから。
そしてそれには教員の人数がとてもたりませんから、
ITの大活用が必須、じゃないでしょうか。
(【どんな教育環境が子供にとってよりよい?】ITの活用と先生の役割)
できることを、できる範囲で
こつこつとしていきます。
さて、明日の勤務先の学校では、
団子づくりですよ。楽しみです!
我が家ではピザづくり。

残りものたっぷりのせピザ。

ブロッコリーにケールに。
みなさん、温もり溢れる週末を!