チェスのクラスは、
1.チェス初年グループ
2.チェスを1年以上してきたグループ
という2つに分けられている。
そしてグループごとにチェスマスターの講義を聞き、
グループ内の対戦相手とゲームをするというように進められる。
今週のクラスでは、
チェスを始めて2ヶ月の三女と次男が、
チェスを1年以上してきたグループに入ることになった。
他の親御さん曰く、逆はあっても、上のグループに入るのは異例とのこと。
え、こんなちびっ子と対戦しろって言うの?
そう笑いながら次男に向き合い、
しばらくすると、
引きつって頭を抱える高学年の子。
それで、
私自身10年近く「ギフテッドプログラム」を見てきて思う
「子供たちのパターン」というようなものを、
ふつふつと思い出す。
ある程度までは、
何だか楽しんでいる内にできてしまう子供達。
それで、ちょっと周りの気を引いたり、
「ギフテッド」などの名称をもらったりもする。
それでも、
何年かこういう子達を見てきて、
その「ある程度」から上へいくには、
本人や周りにとって、
また全く違ったパラダイムが必要になってくるというのを、
つくづく思う。
自分でもよく分からない内にできてしまう。
それでも「ある程度」から上は、
再現できる説明可能なスキルや努力というものを積み重ねていく必要がある。
チェスマスターが、毎日チェス盤に向き合い、
過去40万近くのゲームを分析し続け、
その中での戦略など何万もの動きを記憶してきたと言うように。
何となく「ある程度」までできてしまう子にとって、
そうした姿勢へとシフトするのは、
全く違った習慣を学び直すということでもある。
また「ある程度」までそれほど苦労せず達するため、
それより上へ行くにつれ負けたり、
それまでのようにはあっさりとできないことも増えてきて、
だったら楽しくないからやーめよ、
とあっさり投げ出してしまうこともあるだろう。
ピアノについても似たようなパターンを思い出す。
初めのうちは、何となく楽しんでいる間に、
周りに比べてちょっと目を引くほど上達が早かったり、音がいいと褒められたり。
それでも、それ以上先へ行くには、
一日何時間もの継続した練習が必要ということになってくると、
すっかりやる気を失ってしまったり。
上の学年に行くほど、
学業面で落ちこぼれていく「ギフテッド」とされる子も多くいる。
小さな頃から何となく何学年も先のことができてしまって、
周りからも注目されたりして、
それでも「ある程度」から先は、
日々こつこつと続ける努力がより必要になってくる。
あれ?と思っている内に、
なんでこんなこともできないんだろう?といつも不思議に思ってきた子達が、
自分よりできるようになり。
それで小さな頃からちやほやされることでしっかり培われてきたプライドや、
周りの反応に敏感だったりすることなども作用して、
全くやる気を失ってしまったり。
それはロッククライミングの仕方を教わらないまま、
どんどん険しくなる急斜面を登ろうとするのにも似ているかもしれない。
ある程度の高さまでは、
何となく手足を動かしている内に他の子たちより速く登ってきたかもしれない。
それでもより険しくなるにつれ「より確実な技術」も必要となってくる。
そうして以前ははるか下に眺めてきた「しっかり登り方を習得した子達」が、
いつしかじわじわと追い越していく。
私自身、神童と思うような子に多く接してきて、
「神童も大きくなるにつれただの人」の過程には、
こんな仕組みもあるのだろうなと思っている。
「ギフテッド」とされる子の半数近くが、
実は学業的には落ちこぼれていき、
ましてや、「ギフテッド」と公には見出されない子を含めるなら、
その数は半数どころじゃないだろう、そんな統計もある。
http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10442.aspx
理由は、やる気の欠如や学習障害(凹があるから凸があることも)などとされている。
アラスカのギフテッドプログラムでも、
「ギフテッドのアンダーアチーバー」をテーマにしたミーティングが
毎月のように催されていた。
最近こちらの隣の学区でも、ギフテッド会議というようなものがあったのだけれど、
そこでも、「ギフテッドのアンダーアチーバー」が大きなテーマとなっていたようだ。
長男長女と年長や小学校低学年から一緒だった子供達も今は高校生。
その歩みを見てきて、
確かにトップを駆け抜ける子は、
半数もいないように感じている。
ちなみにギフテッドのアンダーアチーバーについては、
何十年もの間研究がされてきているけれど、
それでもこちらの一般の教育者の間でも、
あまり知られていない。
ギフテッド=ハイアチーバーという認識が一般的。
また「ユア子育てスタジオ」の方にまとめていけたらと思う。
「ある程度」から先を歩き続けるための習慣、
そんなことを念頭にいれて、
サポートをしていけたらなと思いつつ、
同時に、
まあ、学校の勉強が満遍なくできるのも素晴らしいことだけれど、
皆が皆、学校でいい成績を収めて、いい大学へとならなくてもいいじゃない。
そして、それができないことに傷つく必要などなくて。
今遠回りに見えるところにいたとしても、
自分なりのギフトを大切に育てて、
いつかどこかで発揮できる場を見つけていこう、
そんなことも思いつつ。










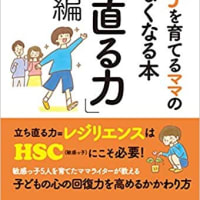





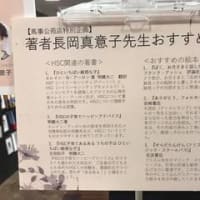

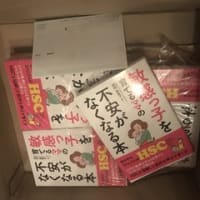

どの分野においても、その道で秀でている方々は皆さん「確実な技術」をお持ちで、更に、日々「再現できる説明可能なスキルや努力というものを積み重ねて」おられますね。
母としては、せめて日々の中で「日常生活を確かに送れる確実なスキル」を習得できるようにと接しているのですが。 寝坊や忘れ物しないようにするにはどうするかとか(笑)。
本当に、こつこつと日々積み重ねるための姿勢や筋力を培ってやれたらなと思うのだけれど、これはもう、家の場合は親子で修行ですね。「寝坊や忘れ物しないように」といった「日常生活を確かに送れる確実なスキル」、私自身毎日の食事準備や掃除などの母親業を通して、ましになってきたのかもと思ってます。
「させられてる、してもらってる」と感じている内は、なかなか身につかないんだよね。周りに対して自分自身で何とかしないと、と自分の足で立とうとするときに、変わってくるんだなと。
私の中でYさんは、「日常生活を確かに送れる確実なスキル」をしっかり身につけられた代表のような方と捉えているんですが、いつも周りに対して何をしていけるか、そう歩いてらっしゃるなあと思うのよ。