以前聞いたときは、ふーん、とさらりと通り過ぎたのですが、
最近、ああ、そういうことかあ、と心と身体に染み入ったイメージです。
自らの心理面での癖、
そして、子育てで繰り返している「習慣」。
こうしたイメージに出合うことで、
体感してきたことが、よりはっきりとした形になり、
決着するというか、次にいけるというか、
「言葉の力」を思います。
歌手、作曲家、俳優として活躍したポーシャ・ネルソン氏(Portia Nelson: 1920-2001)による、
「五つの短い章からなる自叙伝(Autobiography in Five Short Chapters)」を訳してみます。
「五つの短い章からなる自叙伝(Autobiography In Five Short Chapters)」
第一章
通りを歩いていく。
歩道に、深い穴がある。
落ちてしまう。
途方に暮れ...、希望を失い。
私が悪いわけじゃない。
穴から這い上がるのにとてつもなく長い時間がかかる。
第二章
通りを歩いていく。
歩道に、深い穴がある。
見ないふりをする。
また落ちてしまう。
同じ穴にはまってしまったなんて信じられない。
でも、私が悪いわけじゃない。
穴から這い上がるのに、まだとてつもなく長い時間がかかる。
第三章
同じ通りを歩いていく。
歩道に、深い穴がある。
今度は穴があるのだとしっかり見届ける。
それでも、落ちてしまう...。癖...。 でも、
私の目は見開いている。
どこにいるのかも分かっている。
誰のせいでもなく、私が落ちたのだ。
すぐに這い出す。
第四章
同じ通りを歩いていく。
歩道に、深い穴がある。
穴の周りを歩いていく。
第五章
他の通りを歩いていく。
心理面の癖についての感覚的な話ですが:
こうして穴に落ちては何度も這い上がってきたからこそ、
再び穴に落ちたとしても、
どうしたらよいのかがより分かるようになり。
また今度「違う穴」に落ちたとしても、
どうすればよいかの流れも、より見えてきますね。
そう思うと、
真っ暗な穴の底で悶えていたあの日々も、
連なる章の一過程だったんだなあと。
また、穴の存在が把握できるようになってきたら、
わざと落ちて、
よりさっと這い上がることができるよう筋肉を鍛えるという手もありますね。
「曝露療法」。
穴を必死で「避けている内」は、
まだ穴が「力」を持っているんですよね。
「落ちてもさっと這い上がれるし、まあ、わざわざ落ちなくてもいいか」
そうなってくると、穴はあってもなくてもよくなり、「力」を失う。
そして、
「何のために通りを歩いているのか」
によりフォーカスできるようにもなる。
穴の周りを通ったり、
他の通りを選んでいくことも、
より自然に、できるようになるんですね。
子供達にも、
この流れをつかんでほしいなと思いつつ。










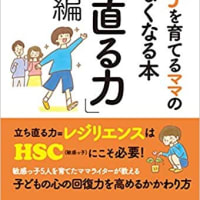





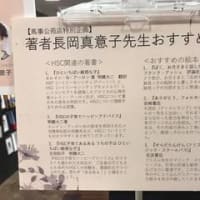

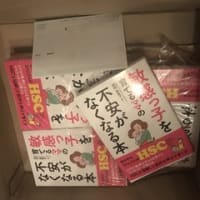

これ、じわじわきますね。
とてもいい詩・・・。
またこれが、子供に(というか、他人にも)教えられる類の話でないところもいいです。
自分で自分を鍛えるしかない、というか。
親の私には、見守って、抱きしめてやるしか出来ませんけど、せめて発想の転換が出てきやすくなるような環境作りなんかは大事だな、と思います。
(こんなのすぐ出られるよ、とか、落ちてもパニックにならない、なっても落ち着けるように、等々そういうことです)
この為にも非認知能力を伸ばすことが大事なんでしょうね。
今、長男を行かせたいな、と思っている小学校がやはり、この非認知能力の大事さを言っているのですね。
でも、所謂「お受験」しないと入れないところでして、周りに圧倒されて危うく穴に落ちかけていたところだったので、なんだか救われました。
いつも有難うございます!!
ところで、ポーシャ・ネルソン氏、「サウンド・オブ・ミュージック」のシスターなのですね!
存じ上げませんでした~。
「見守って、抱きしめてやる」、これほどパワフルな支えはないですよね!
そこへ、「こんなのすぐ出られるよ、とか、落ちてもパニックにならない、なっても落ち着けるように」といった「発想の転換がしやすくなる環境づくり」があるのなら、息子君も、自分の道に心行くまま、邁進できるのではないでしょうか。
「非認知能力が必要」、本当ですね。数値に表れるような分かりやすい力を伸ばす以外に、どれほど大切な力があるかを思います
その「行かせたいなあ」と思われている学校、非認知能力を育む場で学ぶために、早い時期に、「認知能力をはかる受験」を通る必要があるのですね。
早い時期に認知能力を伸ばす働きかけは、非認知能力の大切さを理解してのぞむのならば、無理も少なくすむのだろうなと思います。
認知能力を伸ばす勢い満々の方々に圧倒されながら、「穴」に気づかれたんですね。るまさんの感性に寄り添われつつ、息子さんも最善の道へ進まれることと思います。
ポーシャ・ネルソン氏について、私もこの詩に出合い、ちょっとだけ調べてみて、「へー」と知りましたよ。「Maria makes me laugh」と歌うシスターさんたちの姿を思い出します。『サウンド・オブ・ミュージック』、まだ子供たちが小さなころ、家族皆で何度か観ました~。