「The National Institute for Play(遊びのための国立施設)」というNPO団体の創設者で元精神科医のBrown Stuart氏は、
12年間スタンフォード大学の二年生に「遊び」についての研究を講義し、リーダーシッププログラムを率いる中で、気づいた変化をこう表している:
「学生達が皆本当に聡明だという気持ちは変わらない。それでも最近スタンフォード大学へ入学するための競争が熾烈化する中で、彼らの『自主性』が減退しつつあるのに気づく。
少なくとも私にとっては、率先する力や、自発的なジョイというものが、以前より少なく見える。彼らは一貫して、教授をどう喜ばせるを目指し、自らを磨き続けているようだ。
わずかな例外を除き、彼らは、私の意見では、慢性的な遊び剥奪状態に苦しんでいるように見える。
彼らは超多忙、ハイプレッシャー、ハイパフォーマンスなライフにあまりにも慣れてしまい、アカデミックな優秀さや成功を追う中で、失ってきたものに気づいていない。」
また、「Caltech's Jet Propulsion Laboratory (JPL)」のマネージャー達曰く:
「若い世代のエンジニアの方が、トップの大学でより高い成績をおさめているわけだけれど、年代が上のエンジニアよりも、問題解決能力や創造力を欠いている。
そしてそれは、年代が上のエンジニアの方が、子供時代により遊び、探索したためじゃないかという結論に達したんです。
年代が上のエンジニアは、子供時代、時計を解体して戻してみたり、石鹸の箱でレーシングカーを創って遊んだり、日用品を直したりしてきたもの。
それでも新しい年代の人々は、こうした遊びをしてきてないんです」
そこで、JPLでは、就職面接で、「遊びの背景」について聞くようになったとのこと。そうして、タフなエンジニアデザインの問題と取っ組み合い解決するための従業員能力を改善したと。
("The Self-Motivated Kid" by Shimi Kangより)
テストの点や、入学審査やということはさておき、長い目で見るならば、現実社会で力を発揮していくためには、子供時代の「遊び」が大切と。
「問題」というものには「ふたつのタイプ」があるとされている:
1.「convergent(収斂的)」
答えはひとつ。正しい答えを学ぶことで解決できる。
2.「divergent(散開的)」。
答えはひとつではない。解くためには探索する力や創造力が必要。
現実社会で大切になるのは、もちろん2の「散開的問題」を解決する力。
そして「遊び」こそが、こうした「散開的問題」を解決する力を鍛えるというんですね。
「遊び」について、改めてまとめ中なのだけれど、これまで出会ってきた子供達を思い、
調べて考えてとすればするほど、「遊び」の大切さが迫ってくる。
精神科医として多くの患者を診つつ、
「遊び」の大切さを痛感しNPO団体を立ち上げたBrown Stuart氏は、
「大人が遊ぶ」ことの大切さも訴えている。
子育てする上でよい影響をもたらしたり、メンタルヘルス面でもより健やかに、ということもあるけれど、
私自身、魅力的だなーと思う人って、「遊び心」のある人なのじゃないかなと思う。
点と点とを一直線にいかに効率よく結ぶか、と走り続ける中で、
時に、曲線だったりジグザグ線を取り入れてみる。
すると、味わいが生まれる。
目先の結果からは「寄り道」に見えるかもしれない。
それでも結局そうした寄り道が、長い目でみるならば「急がば回れ」となり、より大きなゴールへと繋がっていく、そう心に留め、子供達に接していきたい。










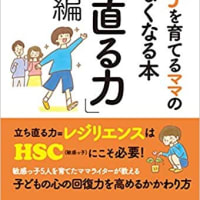





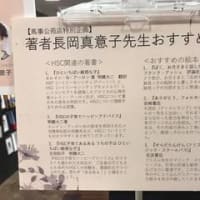

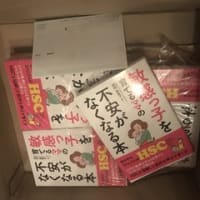

こちらの記事をブログにリンクさせていただいています。よろしくお願いします。
「遊び不足が危険!」というコンセプトは、「ゆとり教育」の基ともなっていて、それでも、結果から見ても一目瞭然なように、表面的な「形」だけ真似しても、何も変わらないんですよね。変わらないどころか、ダメージさえもたらしてしまったり。息子さんの言葉、私も考えてみますね。