
新しい音楽が産まれる時の煌き。
以前このブログでも書いたが、ポピュラー音楽とは、異文化の交流によって誕生する。
簡単に言うと、民族音楽と民族音楽のコンフュージョンがポピュラー音楽の元になる。
その世界最初のポピュラー音楽は、インドネシアの「クロンチョン」と言われている。
一方、ポピュラー音楽が、異文化ポピュラー音楽とコンフュージョンすると、どうなるだろうか。
これには、とても興味深いことが起こる。受け入れるポピュラー音楽の解釈の誤りが起こす一大カオスである。
日本に例えて言えば、1950年代から1960年代の「カバーポップス」流行時には、それは起こらなかった。
それは当たり前で、音楽そのものは、アメリカから輸入した旋律にアレンジを少し変え、日本語の詞を乗せただけのものだったからだ。
しかし、ビートルズが隆盛を極めた1960年代後半から、一大カオスが日本でも巻き起こる。
その代表例が「B級グループサウンズ」だ。
彼らはメジャーな「タイガース」や「スパイダース」とは違い、楽曲にひどい「勘違い」が盛り込まれ、その結果、とても珍しい「グループサンド」を生み出した。
同じことは、僅かではあるが、1960年代のカバーポップス隆盛期にもあった。
いつか紹介するつもりであるが、その代表例が、日本版「ツイスト」として発表されたジェリー藤尾の「インデアンツイスト」だろう。
だが、そのカオス的楽曲も、徐々に日本人的な解釈を深め、慣れてくるとクオリティの高い楽曲も作られるようになる。
そして、1970年代、世界の特にロック界が不確定な状況の中、日本のロックもようやく世界に追いついてくる。
しかし、やはり一番面白いのは、異文化ポピュラー音楽の初期の「誤った解釈」から産まれる「カオス的音楽の煌き」なのだ。
作った本人達は、全く持って真面目に楽曲を作っていると思っているが、後日それを聴いてみると、その本人達でも、赤面するのではないかと思うほど「大いなる勘違い」が、それを形成している。
やはり音楽は面白い。五線譜に音符を載せれば、それは全て音楽と解釈される。詞もその旋律に合わせたものを作れば、それはポピュラー音楽と呼べる。
しかし、解釈しだいで、今まで聴いたことのない、まさに「迷曲」が誕生する。
このことは、日本だけではない。世界各国で同じ現象は起こる。
今回は下に、パキスタンの1970年代から1980年代に作られた「誤った解釈」が産んだポピュラー音楽を貼った。
本人達は真面目だが、その「誤った解釈」の音楽を堪能していただきたい。
M. Ashraf Feat Ahmed Rushdi -[1]- Dama Dam Mast Qalandar (The Sound Of Wonder)
以前このブログでも書いたが、ポピュラー音楽とは、異文化の交流によって誕生する。
簡単に言うと、民族音楽と民族音楽のコンフュージョンがポピュラー音楽の元になる。
その世界最初のポピュラー音楽は、インドネシアの「クロンチョン」と言われている。
一方、ポピュラー音楽が、異文化ポピュラー音楽とコンフュージョンすると、どうなるだろうか。
これには、とても興味深いことが起こる。受け入れるポピュラー音楽の解釈の誤りが起こす一大カオスである。
日本に例えて言えば、1950年代から1960年代の「カバーポップス」流行時には、それは起こらなかった。
それは当たり前で、音楽そのものは、アメリカから輸入した旋律にアレンジを少し変え、日本語の詞を乗せただけのものだったからだ。
しかし、ビートルズが隆盛を極めた1960年代後半から、一大カオスが日本でも巻き起こる。
その代表例が「B級グループサウンズ」だ。
彼らはメジャーな「タイガース」や「スパイダース」とは違い、楽曲にひどい「勘違い」が盛り込まれ、その結果、とても珍しい「グループサンド」を生み出した。
同じことは、僅かではあるが、1960年代のカバーポップス隆盛期にもあった。
いつか紹介するつもりであるが、その代表例が、日本版「ツイスト」として発表されたジェリー藤尾の「インデアンツイスト」だろう。
だが、そのカオス的楽曲も、徐々に日本人的な解釈を深め、慣れてくるとクオリティの高い楽曲も作られるようになる。
そして、1970年代、世界の特にロック界が不確定な状況の中、日本のロックもようやく世界に追いついてくる。
しかし、やはり一番面白いのは、異文化ポピュラー音楽の初期の「誤った解釈」から産まれる「カオス的音楽の煌き」なのだ。
作った本人達は、全く持って真面目に楽曲を作っていると思っているが、後日それを聴いてみると、その本人達でも、赤面するのではないかと思うほど「大いなる勘違い」が、それを形成している。
やはり音楽は面白い。五線譜に音符を載せれば、それは全て音楽と解釈される。詞もその旋律に合わせたものを作れば、それはポピュラー音楽と呼べる。
しかし、解釈しだいで、今まで聴いたことのない、まさに「迷曲」が誕生する。
このことは、日本だけではない。世界各国で同じ現象は起こる。
今回は下に、パキスタンの1970年代から1980年代に作られた「誤った解釈」が産んだポピュラー音楽を貼った。
本人達は真面目だが、その「誤った解釈」の音楽を堪能していただきたい。
M. Ashraf Feat Ahmed Rushdi -[1]- Dama Dam Mast Qalandar (The Sound Of Wonder)










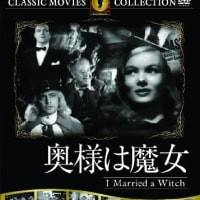
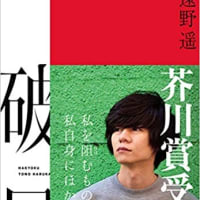

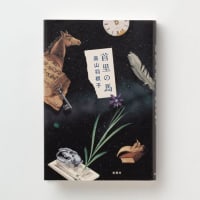


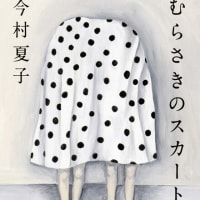
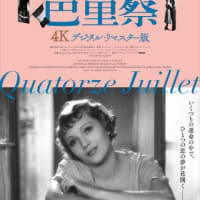


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます