(愛知県豊橋市 1999年1月5日)
この日は母なる川の河口へ自転車で訪れ、私のこれまでの生き方を見つめた。 河口から渥美半島を望む
河口から渥美半島を望む 神野新田堤防に180m間隔で置かれている西国三十三観音像
神野新田堤防に180m間隔で置かれている西国三十三観音像 北島町とよばし付近
北島町とよばし付近 天王の渡し跡付近 石巻山遠望
天王の渡し跡付近 石巻山遠望
(川崎市宮前区鷺沼)
横浜市青葉区美しが丘(たまプラーザ)と境を接するこのまちは、東急により開発された地である。かつては橘樹(たちばな)郡有馬村で、鷺沼は小字として存在した。鷺の住む谷あいの湿地を表す地名であるが、今はそれを想像できる光景はない。







(愛知県宝飯郡御津町佐脇浜 1998年12月29日)
昭和52年(1977)から整備が開始された三河臨海緑地の一角である。面積49,800平米の日本列島ゾーンには、日本列島のミニチュアを庭園風に表現し、北から大雪山、八甲田山、磐梯山、富士山、御嶽山、大山、剣山、石鎚山、阿蘇山、大文字山の10山を築山として表現。川は、雄物川、北上川、信濃川、隅田川、長良川、淀川、江の川、四万十川の8河川を園路としてそれぞれ表現し、琵琶湖、浜名湖を休憩所としている。また、隣接して74,700平米の汐入の池ゾーンがあり、砂浜や岩礁を設け、水際の景観整備を図っている。
(東京都目黒区)
東横線の駅名の基となっている東京学芸大学は、昭和39年(1964)小金井市に移転したが、駅名は地域ブランドとして残った。この地域は元来、荏原郡碑文谷(ひもんや)村であり、その後、今の自由が丘や、八雲付近である荏原郡衾(ふすま)村と合併し、碑衾村大字碑文谷となった。昭和2年(1927)東横線開通時は碑文谷駅であったが、昭和11年(1936)東京横浜電鉄(1942-東京急行電鉄)が青山師範学校を誘致し、駅名も青山師範に改称。昭和18年(1943)には第一師範、昭和27年(1952)には学芸大学に改称された。碑文谷の地名は、鎌倉街道沿いにあった石碑の碑文説や、檜物屋(木工品)説がある。













 碑文谷公園
碑文谷公園
 目黒通りに面するダイエー旗艦店の碑文谷店
目黒通りに面するダイエー旗艦店の碑文谷店

 カトリック碑文谷教会
カトリック碑文谷教会
(愛知県豊川市御油町橋際 1998年12月28日)
昭和2年(1927)に築造された音羽川新御油橋の解体が始まっていた。この橋は、一つ下流の幅の狭かった旧東海道の橋である御油橋に代わって、新道の橋として架けられたものである。 1999年2月13日の光景
1999年2月13日の光景
(愛知県宝飯郡音羽町赤坂字宮路 1998年12月28日)
天武天皇と持統上皇の皇子である草壁皇子(くさかべのみこ 662-89)がこの地に住み、宮路山(みやじさん 標高360m)の頂きに祠を建てたのが宮道天神社の始まりである。また、大宝二年(702)持統上皇が行幸した際、この宮路山の頂きで国見をしたと伝わる。元亀二年(1571)里から離れているため麓の現在地に遷宮され、現在の拝殿は元禄八年(1695)造営されたものである。明治13年(1880)には山頂に元宮が再建された。宮路山は、平安時代の「更級日記」にも、「嵐こそ 吹きこざりけれ 宮路山 まだもみぢ葉の ちらで残れる」と記載されている。また、日本武尊(やまとたけるのみこと)の皇子、建貝児王(たてかいごのきみ)の末裔、宮路氏が代々この地に住み、長者となった。正暦年間(990-995)三河国に国司として赴任した大江定基は、三河赤坂の長者、宮路長富の娘力寿姫を愛した。然し、定基が赴任を終え京に戻ることとなり、その別離を苦しんだ力寿は舌を噛み切って亡くなった。力寿の父長富は、長保年間(999-1003)娘の菩提を弔うため赤坂に長富寺(1522-長福寺)を建て、定基は夢に現れた文殊菩薩のお告げの場所に力寿の舌を埋め、財賀村に力寿山舌根寺を建立した。
(関連記事:持統上皇行在所跡)
(中原街道 東京都品川区五反田)
東五反田に所用があり、池上線で3年振りに五反田を訪れる。目黒川を越えた高い鉄橋上にある東急池上線五反田駅は、9階建ての東急五反田ビル4階部分に接続するが、これは山手線を跨いで白金方面に延伸する構想があったからである。昭和3年(1928)開業当時の光景を残すトレッスル橋は、山陰線余部鉄橋等と同様の形式で、幾つもの支柱で台形に鉄骨を組み合わされた橋脚が特徴である。鉄橋のある場所は西五反田であり、目黒川を挟んでオフィス街となっている。山手線の東側は東五反田であり、駅前は歓楽街で、その奥は斜面となり島津山の住宅地や清泉女子大学となる。










 目黒川
目黒川 清泉女子大
清泉女子大
 島津家の屋敷があった島津山
島津家の屋敷があった島津山
(関連記事:東五反田 西五反田)
(愛知県豊橋市石巻本町 1998年11月22日)
豊川支流馬越川の上流、赤石山系日名倉山の麓に水を湛える大池は、旧馬越村の農業用溜池として築造されたものである。池の背後、馬越城跡でもある日名倉山は、かつて標高259.3mあり、その頂に生えていた一本松が三河湾から見えたというが、今は砕石により大きく姿を変えてしまっている。
(愛知県稲沢市大塚南 1998年11月8日)
真言宗大塚山性海(しょうかい)寺は、同寺所蔵「住持頼景撰性海寺由来記」によると、弘仁年間(810-24)空海により創建され、一時衰退したが、建久年間(1190-99)当地中島郡領主の長谷部源政が再興し、熱田神宮家出自の良敏が中興開山としている。文永八年(1271)後堀河天皇の中宮鷹司院近衛長子から令旨を受けて官寺となり、弘安三年(1280)には中興第三世浄胤(じょういん)は蒙古襲来に備え、花園上皇の要請で祈祷を行ったという。また、応長二年(1312)京東林寺尼僧尊如より寺内修理料として田畑が寄進され、元弘三年(1333)後醍醐天皇の綸旨(りんじ:蔵人(くろうど:律令下の官職)が天皇の意を受けて発給する命令文書)、文和二年(1353)には後光厳天皇より院宣(いんぜん:天皇の命令を伝達する文書)を受けている。建武の争乱の際には足利尊氏・直義の制札を得て破壊を免れ、三十四世良円の甥浅野長政より寺領百石、そして慶長五年(1600)には清洲城主松平忠吉、慶長十二年(1607)後の初代尾張藩主で忠吉の弟である徳川義直からそれぞれ寺領百石を寄進されている。境内には大聖歓喜天の彫像を埋納した伝説のある大塚古墳があり、平成4年に歴史公園として整備された。 国重文 本堂 慶安元年
国重文 本堂 慶安元年 国重文 多宝塔 伝建長五年
国重文 多宝塔 伝建長五年
(東京都世田谷区玉川)
新二子橋の袂、国道246号線の高架横に社殿の基礎が嵩上げされた諏訪神社がある。言い伝えでは、この地に帰農した吉良氏臣川辺氏が、多摩川が洪水の際に流れ着いた木像を神体とし、鎌田村の鎮守、諏訪神社として創建したという。旧社地は鎌田地内であったが、多摩川改修により堤外に遷座し、現在の玉川地内となった。また、境内には「筏道」の標柱がある。かつて木材を多摩川の流れを利用し筏(いかだ)として下流へ運んだが、帰りは筏師の自らの足で帰らなくてはならないため、筏師が川沿いの道を通って上流へ帰る道を筏道と呼んだ。
(愛知県稲沢市大塚南 1998年11月8日 市指定史跡)
性海寺境内にある直径40m,高さ5mの円墳である。埴輪と周濠を持つ。以前訪れた際は、文化財指定もされておらず、単なる土盛りという感じであったが、昭和58年に文化財指定、平成4年に歴史公園として整備された。伝説では、この大塚古墳に大聖歓喜天の彫像を埋納したという。
(東京都目黒区自由が丘)
過去何度となく訪れ、当初は駅のごく近くだけ商店があるという感じだったが、次第に拡大し、今の賑わいとなった。然し、東横線に沿う昭和23年(1948)創業の商業施設「自由が丘デパート・ひかり街」は、衰退の一途を辿り、店主達も道楽でやっているような感は否めない。「目黒区自由が丘」自体は狭い範囲であり、南西側はすぐ世田谷区奥沢、東側もすぐ緑が丘、北側も八雲である。











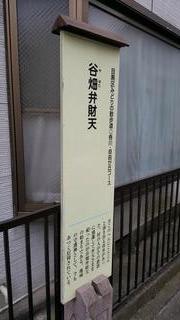
 庚申塔
庚申塔
 旧衾(ふすま)村鎮守熊野神社
旧衾(ふすま)村鎮守熊野神社









 九品仏川緑道の桜
九品仏川緑道の桜
(関連記事:自由が丘平成二十三年)













































 御成道(万世橋寛永寺間)
御成道(万世橋寛永寺間)












