【戦後70年~東京裁判とGHQ(4)】戦後史は闇市から始まった 占領政策の後遺症とWGIPの呪縛はなお…(産経ニュースより転載)

占領下の日本で長く首相を務めた吉田茂。茶目っ気のある皮肉でマッカーサーとの信頼関係を築き上げた
2015.12.23
連合国軍総司令部(GHQ)の占領統治が始まった昭和20年9月。全国の都市部は焼け野原が広がり、バラック建ての闇市が点在した。東京では、新宿、新橋、上野、池袋などに闇市ができた。
江戸東京博物館館長の竹内誠(82)は毎日のように上野の闇市を通って旧制上野中学に通った。
饅頭、クジラベーコン、ピーナツ、タワシ、茶碗-。食料や生活用品が所狭しと並び、「これを足して、さらにおまけで」と威勢のよい声が響いた。飲み屋のバラック街もあり、夜になると「カストリ」と呼ばれる密造焼酎を求め、男たちが集まった。21年に入ると瓦礫は次第に撤去され、並木路子の「リンゴの唄」があちこちで流れるようになった。
上野駅前には小箱を脇に抱えた子供たちが進駐軍相手の靴磨きをしていた。上野山の坂道には米兵相手の娼婦「パンパンガール」が並び、理由は分からないが、頻繁に髪の毛をつかみ合ってけんかしていた。
竹内と母親が上野公園で弁当を開いたら、後ろから子供の手がニュッと伸びて握り飯をつかんだ。戦災孤児だった。仕方なしに「どうぞ」と渡すとニヤッと笑って走り去った。竹内は懐かしそうにこう振り返る。
「戦争で敗れてどん底だったが、みんなは意外と明るく活気があった。今日より明日、明日より明後日と世の中がよくなっていくイメージをみんな持っていたんだな…」
******************
連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーの主要な任務は、「戦争犯罪人の処罰」「非軍事化」「民主化」の3つだった。そこでマニラの極東司令官時代からの部下「バターン・ボーイズ」をGHQの要所に配し、権力をより固めた。
中でも信頼を寄せたのが、弁護士出身の将校である民政局(GS)局長、コートニー・ホイットニーだった。GHQ内で唯一マッカーサーとアポなしで面会でき、ほぼ毎夕1時間ほど面談した。これにより、ホイットニー率いるGSはGHQ内で覇権を握り、主要な占領政策をほぼ独占して推し進めることになった。
だが、GSの「民主化」は急進的かつ社会主義的だった。戦前の政府要人や大物議員、財界人は「反動的」とみなして次々に公職追放し、日本社会党に露骨に肩入れしたため、政界は混乱が続いた。
GSは、外相を経て首相となる吉田茂も敵視した。吉田の孫で、現副総理兼財務相の麻生太郎(75)はこう語る。
「祖父はマッカーサーとの信頼関係を醸成することでGSの介入を排除しようとしたんだな。ホイットニーに呼ばれても『わしはトップとしか会わんよ』と無視を決め込んでいたよ」
では、どうやって吉田は、気難しいマッカーサーの信頼を勝ち得たのか-。
*****************
マッカーサーは執務中ほとんど席に着かず、室内を歩き回るのが癖だった。しかも軍人らしく7歩歩くと回れ右、また7歩歩くと回れ右-。これを見た吉田は茶目っ気たっぷりにつぶやいた。
「まるで檻の中のライオンだな…」
マッカーサーは一瞬ムッとした後、ニヤリと笑った。マッカーサーがフィリピン製の葉巻を勧めると、吉田は「私はキューバ製しか吸わないんだ」と懐から葉巻を取り出した。
誰もが恐れる最高権力者に対して不遜極まりない態度だが、マッカーサーは「面白い奴だ」と思ったらしく、吉田との面会には応じるようになったという。
ある日、吉田は「食糧難がひどく、このままでは大量に餓死者が出る。至急食糧支援をお願いしたい」と申し出た。マッカーサーは「では必要量を統計から弾いてくれ」と即答し、米国から大量の小麦粉や脱脂粉乳などを送らせた。
ところが大量の在庫が出た。マッカーサーが吉田に「一体どんな統計データを元に必要量を弾いたんだ」と迫ると、吉田は平然とこう言ってのけた。
「日本がきちんと統計をできるなら米国と戦争なんてしていない」
*****************
果たしてGHQの「民主化」は成功といえるのか。
マッカーサーのせっかちな性格を反映し、その動きは確かに素早い。20年10月4日には内相の山崎巌と特高警察の警官ら約4千人を罷免、政治犯の即時釈放を命じた。11日には婦人解放や労組活動の奨励などの5大改革指令を出した。
12月には日本政府に農地改革を命じ、国家神道を禁じる神道指令を発した。国会では婦人参政権を付与する衆院議員選挙法を改正・公布。その後も警察や内務省の解体などを着々と進めた。
翌21年2月3日、マッカーサーは「戦争の放棄」など3原則を示し、GSに憲法草案の作成を命じ、憲法草案はわずか1週間ほどで完成した。4月には戦後初の衆院選を実施、11月に新憲法の公布にこぎ着けた。
農地改革は全国の小作農の喝采を浴び、GHQの求心力を高めた。だが、あまりに農地を細分化したため、専業農家はその後減り続けた。後継者不足で耕作放棄地ばかりとなった農業の現状を見ると手放しでほめることはできない。
20万人超の公職追放は政財界に大混乱をもたらし、社会党や労組への肩入れは労働運動の先鋭化を招き、社会不安が深刻化した。財閥解体も産業界の復興を遅らせただけ。鉄道や道路などインフラ整備などにはほぼ無関心で、激しいインフレが人々を苦しめた。
****************
GHQの占領政策の当初目標は、日本が二度と米国に歯向かわないよう、その潜在力をたたきのめすことにあった。「平和憲法」制定を含め、その目的は達成したといえる。
だが、国際情勢がそれを許さなかった。欧州で米ソの対立が深刻化し、米政府内で「反共」の防波堤としての日本の重要性が再認識され始めたからだ。これに伴い戦前に駐日米大使を務めたジョセフ・グルーら知日派の「ジャパン・ロビー」が復権した。GHQ内ではGSと他部局の覇権争いがあり、23年10月の第2次吉田内閣発足時にはGSは力を失っていた。
占領政策は「民主化」から「経済復興」に大きく舵が切られた。だが、超緊縮財政を強いるドッジ・ラインで大不況となり、日本の本格的な復興が始まったのは、皮肉にも昭和25年6月に勃発した朝鮮戦争により特需となったからだった。
*****************
GHQの「非軍事化」「民主化」の切り札はもう一つあった。民間情報教育局(CIE)が担った「ウオー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」だった。
これは徹底的な言論統制とプロパガンダ(政治宣伝)で日本人に贖罪意識を植え付けるという非民主的な策謀だった。
言論統制の象徴である「新聞報道取締方針」は戦艦ミズーリでの降伏調印式から8日後の昭和20年9月10日に発せられた。GHQへの批判はもとより、進駐軍の犯罪・性行為、闇市、飢餓-など30項目が削除・発禁対象として列挙された。
GHQは手始めに9月14日に同盟通信社(共同、時事両通信社の前身)を翌15日正午まで配信停止とし、事前検閲を始めた。9月18日には朝日新聞を2日間の発禁処分にした。原爆投下を批判する鳩山一郎(後の首相)の談話を掲載したためだった。これ以降、各紙はGHQの礼賛記事を競って掲載するようになった。
「日本軍=悪」「米軍=正義」という歴史観を刷り込む宣伝工作も着実に進められた。
20年12月8日、日米開戦の日に合わせて新聞連載「太平洋戦争史」(計10回)が全国の日刊紙で始まった。中国やフィリピンで行った日本軍の残虐行為を断罪する内容で、GHQは連載終了後、文部省に対して太平洋戦争史を教科書として買い取るよう命じた。
12月9日にはNHKラジオ番組で「真相はこうだ」の放送を始めた。反軍国主義の文筆家が少年の問いかけに答える形で戦争中の政治・外交を解説するこのシリーズは2年間も続いた。
CIEの手口は巧妙だった。「誰が日本を戦争に引きずり込んだのか」という問いには「人物を突き止めるのは不可能。責任者は日本人自身だ」と答えて「一億総懺悔」を促した。自らの言論統制は巧みに隠しながら、戦時中の検閲や言論弾圧を糾弾し、開戦時の首相、東條英機に怒りの矛先が向くよう仕向けた。
放送当初は懐疑的・批判的な日本人も多かったが、情報に飢えた時代だけに聴取率は高く、次第に贖罪意識は浸透していった。
ところが、昭和23年に入るとCIEは方針をジワリと転換させた。2つの懸念が出てきたからだ。1つは広島、長崎への原爆投下への憎悪。もう1つは、東條英機が東京裁判で主張した「自衛戦争論」だった。この2つに共感が広がると日本人の怒りは再び米国に向きかねない。
こう考えたCIEは「侵略戦争を遂行した軍国主義の指導者層」と「戦争に巻き込まれた一般国民」という構図を作り出し、批判をかわすようになった。宣伝工作や検閲も日本政府に代行させるようになった。
GHQの洗脳工作は見事に成功した。昭和26年9月8日のサンフランシスコ講和条約を経て独立を回復した後も、GHQの占領政策は肯定され、戦前は負の側面ばかりが強調された。
文芸評論家の江藤淳が『閉された言語空間』でGHQの言論統制を暴いたのは戦後30年以上たった昭和50年代後半。ジャーナリストの櫻井よしこが『真相箱の呪縛を解く』でさらに詳しく告発したのは21世紀に入ってからだ。WGIPは戦後70年を経た今もなお日本人の歴史観を束縛し、精神を蝕んでいる。
(敬称略)

占領下の日本で長く首相を務めた吉田茂。茶目っ気のある皮肉でマッカーサーとの信頼関係を築き上げた
2015.12.23
連合国軍総司令部(GHQ)の占領統治が始まった昭和20年9月。全国の都市部は焼け野原が広がり、バラック建ての闇市が点在した。東京では、新宿、新橋、上野、池袋などに闇市ができた。
江戸東京博物館館長の竹内誠(82)は毎日のように上野の闇市を通って旧制上野中学に通った。
饅頭、クジラベーコン、ピーナツ、タワシ、茶碗-。食料や生活用品が所狭しと並び、「これを足して、さらにおまけで」と威勢のよい声が響いた。飲み屋のバラック街もあり、夜になると「カストリ」と呼ばれる密造焼酎を求め、男たちが集まった。21年に入ると瓦礫は次第に撤去され、並木路子の「リンゴの唄」があちこちで流れるようになった。
上野駅前には小箱を脇に抱えた子供たちが進駐軍相手の靴磨きをしていた。上野山の坂道には米兵相手の娼婦「パンパンガール」が並び、理由は分からないが、頻繁に髪の毛をつかみ合ってけんかしていた。
竹内と母親が上野公園で弁当を開いたら、後ろから子供の手がニュッと伸びて握り飯をつかんだ。戦災孤児だった。仕方なしに「どうぞ」と渡すとニヤッと笑って走り去った。竹内は懐かしそうにこう振り返る。
「戦争で敗れてどん底だったが、みんなは意外と明るく活気があった。今日より明日、明日より明後日と世の中がよくなっていくイメージをみんな持っていたんだな…」
******************
連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーの主要な任務は、「戦争犯罪人の処罰」「非軍事化」「民主化」の3つだった。そこでマニラの極東司令官時代からの部下「バターン・ボーイズ」をGHQの要所に配し、権力をより固めた。
中でも信頼を寄せたのが、弁護士出身の将校である民政局(GS)局長、コートニー・ホイットニーだった。GHQ内で唯一マッカーサーとアポなしで面会でき、ほぼ毎夕1時間ほど面談した。これにより、ホイットニー率いるGSはGHQ内で覇権を握り、主要な占領政策をほぼ独占して推し進めることになった。
だが、GSの「民主化」は急進的かつ社会主義的だった。戦前の政府要人や大物議員、財界人は「反動的」とみなして次々に公職追放し、日本社会党に露骨に肩入れしたため、政界は混乱が続いた。
GSは、外相を経て首相となる吉田茂も敵視した。吉田の孫で、現副総理兼財務相の麻生太郎(75)はこう語る。
「祖父はマッカーサーとの信頼関係を醸成することでGSの介入を排除しようとしたんだな。ホイットニーに呼ばれても『わしはトップとしか会わんよ』と無視を決め込んでいたよ」
では、どうやって吉田は、気難しいマッカーサーの信頼を勝ち得たのか-。
*****************
マッカーサーは執務中ほとんど席に着かず、室内を歩き回るのが癖だった。しかも軍人らしく7歩歩くと回れ右、また7歩歩くと回れ右-。これを見た吉田は茶目っ気たっぷりにつぶやいた。
「まるで檻の中のライオンだな…」
マッカーサーは一瞬ムッとした後、ニヤリと笑った。マッカーサーがフィリピン製の葉巻を勧めると、吉田は「私はキューバ製しか吸わないんだ」と懐から葉巻を取り出した。
誰もが恐れる最高権力者に対して不遜極まりない態度だが、マッカーサーは「面白い奴だ」と思ったらしく、吉田との面会には応じるようになったという。
ある日、吉田は「食糧難がひどく、このままでは大量に餓死者が出る。至急食糧支援をお願いしたい」と申し出た。マッカーサーは「では必要量を統計から弾いてくれ」と即答し、米国から大量の小麦粉や脱脂粉乳などを送らせた。
ところが大量の在庫が出た。マッカーサーが吉田に「一体どんな統計データを元に必要量を弾いたんだ」と迫ると、吉田は平然とこう言ってのけた。
「日本がきちんと統計をできるなら米国と戦争なんてしていない」
*****************
果たしてGHQの「民主化」は成功といえるのか。
マッカーサーのせっかちな性格を反映し、その動きは確かに素早い。20年10月4日には内相の山崎巌と特高警察の警官ら約4千人を罷免、政治犯の即時釈放を命じた。11日には婦人解放や労組活動の奨励などの5大改革指令を出した。
12月には日本政府に農地改革を命じ、国家神道を禁じる神道指令を発した。国会では婦人参政権を付与する衆院議員選挙法を改正・公布。その後も警察や内務省の解体などを着々と進めた。
翌21年2月3日、マッカーサーは「戦争の放棄」など3原則を示し、GSに憲法草案の作成を命じ、憲法草案はわずか1週間ほどで完成した。4月には戦後初の衆院選を実施、11月に新憲法の公布にこぎ着けた。
農地改革は全国の小作農の喝采を浴び、GHQの求心力を高めた。だが、あまりに農地を細分化したため、専業農家はその後減り続けた。後継者不足で耕作放棄地ばかりとなった農業の現状を見ると手放しでほめることはできない。
20万人超の公職追放は政財界に大混乱をもたらし、社会党や労組への肩入れは労働運動の先鋭化を招き、社会不安が深刻化した。財閥解体も産業界の復興を遅らせただけ。鉄道や道路などインフラ整備などにはほぼ無関心で、激しいインフレが人々を苦しめた。
****************
GHQの占領政策の当初目標は、日本が二度と米国に歯向かわないよう、その潜在力をたたきのめすことにあった。「平和憲法」制定を含め、その目的は達成したといえる。
だが、国際情勢がそれを許さなかった。欧州で米ソの対立が深刻化し、米政府内で「反共」の防波堤としての日本の重要性が再認識され始めたからだ。これに伴い戦前に駐日米大使を務めたジョセフ・グルーら知日派の「ジャパン・ロビー」が復権した。GHQ内ではGSと他部局の覇権争いがあり、23年10月の第2次吉田内閣発足時にはGSは力を失っていた。
占領政策は「民主化」から「経済復興」に大きく舵が切られた。だが、超緊縮財政を強いるドッジ・ラインで大不況となり、日本の本格的な復興が始まったのは、皮肉にも昭和25年6月に勃発した朝鮮戦争により特需となったからだった。
*****************
GHQの「非軍事化」「民主化」の切り札はもう一つあった。民間情報教育局(CIE)が担った「ウオー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」だった。
これは徹底的な言論統制とプロパガンダ(政治宣伝)で日本人に贖罪意識を植え付けるという非民主的な策謀だった。
言論統制の象徴である「新聞報道取締方針」は戦艦ミズーリでの降伏調印式から8日後の昭和20年9月10日に発せられた。GHQへの批判はもとより、進駐軍の犯罪・性行為、闇市、飢餓-など30項目が削除・発禁対象として列挙された。
GHQは手始めに9月14日に同盟通信社(共同、時事両通信社の前身)を翌15日正午まで配信停止とし、事前検閲を始めた。9月18日には朝日新聞を2日間の発禁処分にした。原爆投下を批判する鳩山一郎(後の首相)の談話を掲載したためだった。これ以降、各紙はGHQの礼賛記事を競って掲載するようになった。
「日本軍=悪」「米軍=正義」という歴史観を刷り込む宣伝工作も着実に進められた。
20年12月8日、日米開戦の日に合わせて新聞連載「太平洋戦争史」(計10回)が全国の日刊紙で始まった。中国やフィリピンで行った日本軍の残虐行為を断罪する内容で、GHQは連載終了後、文部省に対して太平洋戦争史を教科書として買い取るよう命じた。
12月9日にはNHKラジオ番組で「真相はこうだ」の放送を始めた。反軍国主義の文筆家が少年の問いかけに答える形で戦争中の政治・外交を解説するこのシリーズは2年間も続いた。
CIEの手口は巧妙だった。「誰が日本を戦争に引きずり込んだのか」という問いには「人物を突き止めるのは不可能。責任者は日本人自身だ」と答えて「一億総懺悔」を促した。自らの言論統制は巧みに隠しながら、戦時中の検閲や言論弾圧を糾弾し、開戦時の首相、東條英機に怒りの矛先が向くよう仕向けた。
放送当初は懐疑的・批判的な日本人も多かったが、情報に飢えた時代だけに聴取率は高く、次第に贖罪意識は浸透していった。
ところが、昭和23年に入るとCIEは方針をジワリと転換させた。2つの懸念が出てきたからだ。1つは広島、長崎への原爆投下への憎悪。もう1つは、東條英機が東京裁判で主張した「自衛戦争論」だった。この2つに共感が広がると日本人の怒りは再び米国に向きかねない。
こう考えたCIEは「侵略戦争を遂行した軍国主義の指導者層」と「戦争に巻き込まれた一般国民」という構図を作り出し、批判をかわすようになった。宣伝工作や検閲も日本政府に代行させるようになった。
GHQの洗脳工作は見事に成功した。昭和26年9月8日のサンフランシスコ講和条約を経て独立を回復した後も、GHQの占領政策は肯定され、戦前は負の側面ばかりが強調された。
文芸評論家の江藤淳が『閉された言語空間』でGHQの言論統制を暴いたのは戦後30年以上たった昭和50年代後半。ジャーナリストの櫻井よしこが『真相箱の呪縛を解く』でさらに詳しく告発したのは21世紀に入ってからだ。WGIPは戦後70年を経た今もなお日本人の歴史観を束縛し、精神を蝕んでいる。
(敬称略)













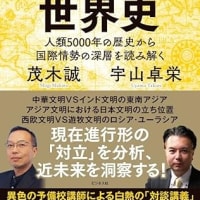
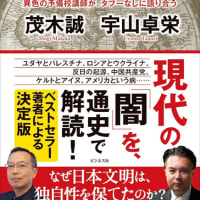

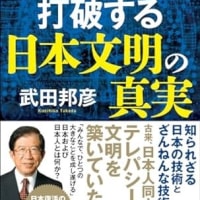

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます