【カシャリ!庭園めぐりの旅】 宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 1 主庭園
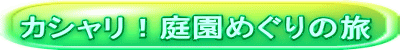
若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間に旅をしたのか、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。
旅のテーマは寺社や庭園めぐりです。
日本には「日本庭園」と呼ばれる庭園だけではなく、「イングリッシュガーデン」など、海外の庭園形式をした庭園も多数あります。寺社を訪れたときに、想定していなかったところに、庭園を発見することがあります。
下手の横好きで、【カシャリ! ひとり旅】を続けていますが、その一環で訪れた庭園を順次紹介してまいりたいと思います。
■ 宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 1 主庭園池泉部
「齋藤氏庭園」(さいとうしていえん)は、宮城県石巻市前谷地にあります。“東北三大地主”のひとつとして挙げられ、9代当主により明治時代に作庭された池泉回遊式庭園で、国指定名勝(平成17年7月14日 )でもあります。邸宅から背後の丘陵地まで、一体感のある空間は見る者を圧倒します。
園内は、大きく4つのエリア(除受付・駐車場)に分けることができます。
1 宝ケ峰縄文記念館エリア
2 主庭園エリア
3 奥池エリア
4 東池エリア
斎藤氏は、秋田県の池田市酒田の本間氏と並び近代における東北三大地主と言われています。江戸時代、二代目善兵衛の時に酒造業を始め、9代目善右衛門の時に酒造業を辞め、莫大な資産を背景に会社を設立して社長となり、衆議院議員を勤めました。
齋藤氏庭園は、複数の池泉回遊式庭園でなり、国の名勝に指定された美しい庭園で、近代庭園として学術上も高く評価されています。園内には茅葺き屋根、一部は江戸時代から残る土蔵などの外観を見学でき、たくさんの建物や石灯籠等があります。
齋藤氏庭園内にある宝ヶ峰遺跡に関わる縄文記念館には、遺跡から発掘された縄文時代後期の土器や矢尻などが保存展示されています。
アクセス
JR石巻線 前谷地駅より徒歩10分
三陸道矢本ICから車で約15分、石巻河南ICから車で約15分
〒987-1101 宮城県石巻市前谷地字黒沢73-1
開園時間
4月1日から11月30日まで 9時30分から16時30分まで
12月1日から翌年の3月31日まで 9時30分から16時まで
休園日
月曜日(注)休日を除く、休日の翌日、12月28日から翌年1月4日まで
観覧料
個人 一般:500円 高校生:300円 小・中学生 :150円(団体割引あり)
斉藤氏庭園は、宮城県石巻市前谷地に位置します。
一般的には、仙台駅から東北本線で小牛田(こごた)まで50分弱、北上し
JR石巻線に乗り換え、20分ほどのところにある前谷地駅で下車します。
前谷地駅から南東方向に徒歩10分ほどのところにあります。
庭園全景(園内表示板より)(北:▼)
主庭園は❻❼前を中心としたエリア
宝ケ峰縄文記念館エリア
受付を通って右手
左:中門 右:木小屋・宝ヶ峰縄文記念館
反対側(左手後方)が、主庭園エリア
主庭園エリアへの入り口
正面のかやぶき屋根の建物が「広間」
かつては小座敷として利用
この建物の二方が主庭園エリア
主庭園エリアへ
前土蔵前の池
奥池に繋がる
前土蔵前から見る主庭園
左手に奥池、右奥が主庭園に附属する小池
主庭園
左:前土蔵 右:広間
主庭園 正面:広間
主池に懸かる石橋
主池右手から見る広間
主屋側から見る前土蔵
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 1 主庭園
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 2 主庭園 主屋横小池
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 3 奥池エリア
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 4 東池エリア
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 5 建物編
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 6 主屋とその周辺
宮城県石巻市 齋藤氏庭園 東北三大地主作庭の池泉廻遊式庭園 7 宝ヶ峯縄文記念館
![]()
ユーチューブで視る 【カシャリ!庭園めぐりの旅】
写真集は、下記URLよりご覧いただくことができます。
静止画: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmeisho.htm
映像: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm
【 注 】 映像集と庭園めぐりは、重複した映像が含まれています

































































