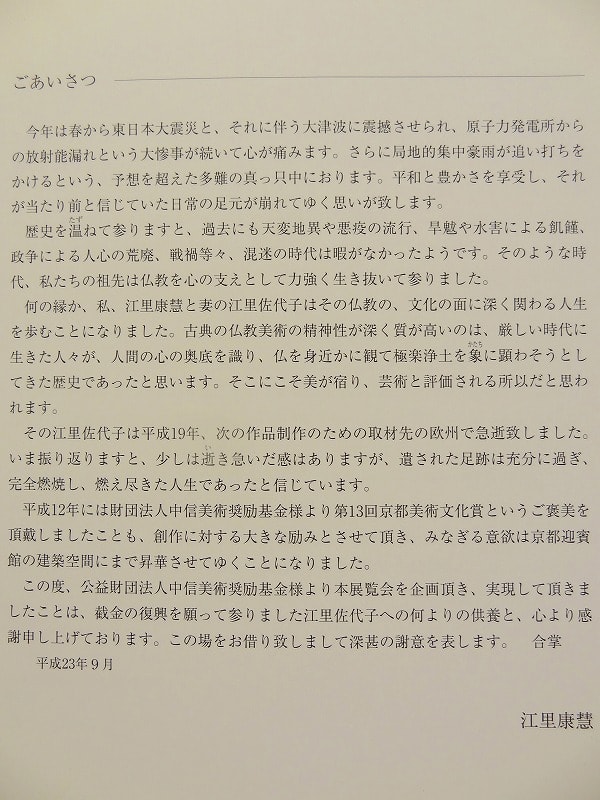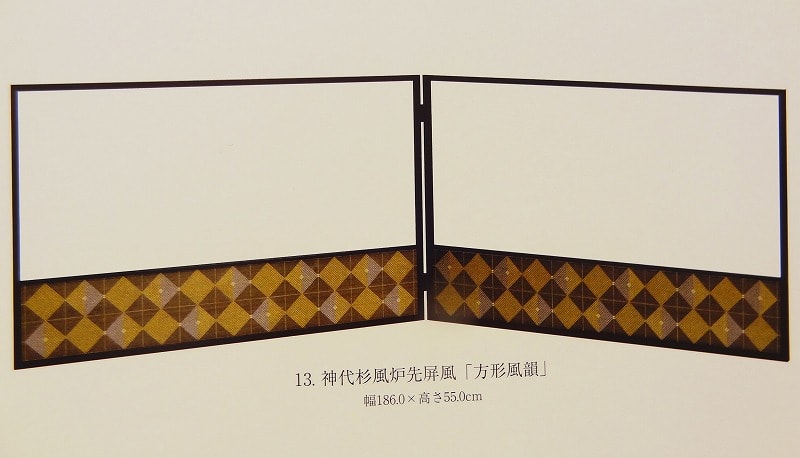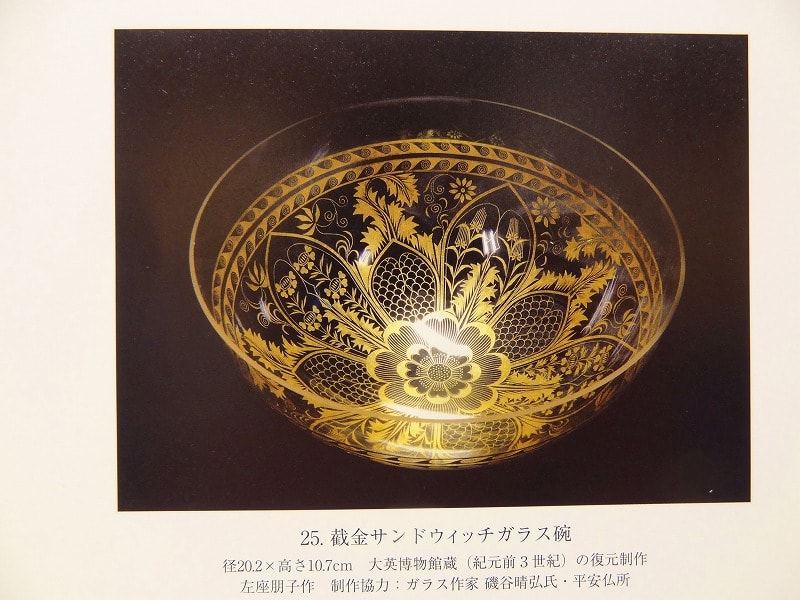梨木神社で萩を見た後に初めて御苑に足を踏み入れました。 いつもは車で周辺を通り抜けるだけでしたが、歩いてみて広さを実感いたしました。

地図の右側中央の清和院御門から入り、御所の建礼門から南下し厳島神社から

清和院御門を西に進み右手の芝生の向こうに京都迎賓館があり、左手が大宮御所、正面が御所の東側の塀になります。

御所東側の建春門です。 京都御所は、794年、桓武天皇が平安京へ遷都した当時の内裏(御所)で、この京都御苑から約2km西に位置していま
した。現在の京都御所は内裏の焼失等の際に、天皇の仮住まいとなった里内裏のひとつである東洞院土御門殿に由来するもので、1331年(元弘元
年)、光厳天皇がここで即位されて以来、御所とされたものです。 1392年(明徳3年)の南北朝合一によって名実ともに皇居に定まり、明治に至るま
での約500年の間、天皇の住まいでした。建物自体はその間も焼失を繰り返し、現在の建物は安政2年(1855年)に平安時代の内裏の姿にならっ
て再建されたものです。 御所内の参観には宮内庁への事前の許可が必要ですが、春と秋の年2回、一般公開されます。

京都御苑は、江戸時代二百もの宮家や公家の邸宅が立ち並ぶ町でしたが、明治になって都が東京に移り、これら邸宅は取り除かれ、公園として整備
され市民へ開放されました。戦後は国民公園として位置づけられ、御所と一体となった景観を維持しつつ、散策や休養等の場として親しまれています。
現在苑内には百年を越える樹林が育ち、旧公家屋敷跡や庭園等歴史的遺構が点在し、古都の中心で特別な空間となっております。

建春門前を北側(今出川)への大通りです。 右手に、京都迎賓館があります。

御所の南東角から南側を見たところです。 左手は、大宮御所と仙洞御所です。右手は、有栖川宮邸跡

右手は、御所の南側壁と正面に蛤御門があります。 御苑の周りには、かつての公家町と市中の境界であった九つの御門があります。この蛤御門は、
もとは新在家御門と呼ばれ常に閉ざされていましたが、江戸時代の大火で初めて開門されたことから「焼けて口開く蛤」にたとえられ「蛤御門」と呼ば
れるようになりました。また、幕末の禁門の変では、御苑一帯が主戦場となり、この戦いに長州藩が敗れたことで幕末動乱の転機となりましたが、そ
の最大の激戦地だったのが蛤御門で、弾傷らしき跡が残っています。

御所南側の建礼門前から南側(丸太町)の建礼門前大通りです。

建礼門と夏の名残の百日紅


秋の訪れを知らす彼岸花





車体には、消防署ではなく皇宮警察本部の文字が見て取れます。

仙洞御所の御門

建礼門と大通り 京都御所の正門である建礼門前から南に延びる大通りは、沿道の広々とした芝生地とマツと合わせ、京都御苑を代表する風景です。
明治10年に京都に還幸された明治天皇は、東京遷都にともなって荒廃した九門内を嘆かれ、京都府に旧観を保存するよう御沙汰を下されました。こ
れに基づき、明治16年まで行われた大内保存事業により、御苑の骨格となる整備が行われ、この大通りもこの時、初めて設けられました。その後、大
正2~3年に大正天皇の即位大礼を行うための改良工事で、現在の規模に拡幅されています。
京都三大祭りのうち5月には葵祭、10月には時代祭の行列が建礼門前から出発し、この通りを通って市中に出て行きます。

建礼門前大通りの南側の突き当たりには、九条邸跡と厳島神社があります。

九条邸跡前、東山方面です。



九條池と拾翠亭は、五摂家の一つであった九條家の屋敷内に設けられた庭園の遺構です。このうち、拾翠亭は今から200年ほど前の江戸時代後期
に茶室として建てられたもので、貴族の茶室らしく、遊び心にあふれた建築と言われています。 今でもお茶会等に利用されている他、春から秋にかけ
ての毎週金曜日と土曜日に一般公開されています。拾翠亭の前面に広がる池は九條池と呼ばれており、安永7年(1778年)頃、東山を借景とし、拾
翠亭からの眺めを第一につくられたといわれています。今は、木々が伸びるなど、当時の景色とは様子が違っていますが、京都の中心部とは思えない
ようなゆったりとした雰囲気を楽しむことができます。

九条池と高倉橋


橋の西側に建つ茶室の拾翠亭は、週末の金曜、土曜日に公開されております。 また、拾翠亭の九條池の畔にあるサルスベリは、7月下旬から9月
下旬までが花の時期で、漢字で百日紅と書くほど、長い間紅い花を咲かせます。九條池に架かる高倉橋から見るサルスベリは、江戸時代後期の九
條邸遺構の拾翠亭を背後にして夏の京都御苑を代表する風景の一つとなっています。

九条池の北側に建つ厳島神社

厳島神社は、平清盛が母・祇園女御のために安芸の厳島神社を勧請したのが始まりといいます。当初は兵庫の築島にありましたがのちにこの地に
移されたと伝わります。祭神は、市杵島姫命、田心姫命、湍津姫命の宗像三女神を主祭神に、祇園女御を配祀いたします。配祀神は下述するように
本来は平清盛の母の霊であったと思われておりますが、後に著名なその姉(つまり清盛の伯母)の祇園女御に変えられたようです。
安芸国厳島社を崇敬した平清盛が、摂津国兵庫津に築島(経が島)を造成した際に、同島に社殿を構えて厳島社を勧請し、後に清盛の母の霊を合祀
したものに起源を持ち、その神社を時期不詳ながら当地へ遷座させたものと云われております。鎮座地は後世九条家の邸宅に取り込まれて同家の鎮
守として崇敬されるとともに、池泉廻遊式庭園の1部を構成するものともなりました。明治になって九条家は東京へ転宅し、その邸宅も東京へ移築され
ましたが、当神社はそのまま残され、昭和2年(1927年)には社殿が改築されました。

社殿の前に建つ鳥居は、「唐破風鳥居」と称され、北野天満宮境内社の伴氏社の石造鳥居、蚕ノ社の木嶋坐天照御魂神社の三柱鳥居と合わせて
「京都三鳥居」「京都三珍鳥居」とされております。


橋の上に居たおじさんが鯉のエサやりをされており、鯉が集まっておりました。

おじさんの叩く手の音に鴨も寄ってまいりました。




無防備すぎる猫


「誰やオマエ。」と言う声が聞こえてきそうな気怠い様子で、また寝てしまいました。







正面の木が、終わってしまいましたが百日紅の木です。


厳島神社を後にし、北側の宗像神社にまいります。

御苑南部にある宗像神社周辺のクスノキの大木には、毎年4月下旬頃から10月頃までアオバズクが訪れ営巣します。この時期、運が良ければ夕方
から夜にかけて、ホウホウという鳴き声が聞けたり、また、7月以降になると、2羽の親と数羽のヒナと仲良く肩を並べている姿を見ることができます。
平成4年に「アオバズクのすむ森」として、京都府の自然200選に選定されました。

アオバズク(青葉木菟)とは、フクロウ目フクロウ科アオバズク属に分類される鳥で、
夏季に中華人民共和国、日本、朝鮮半島、ウスリーで繁殖し、冬季になると東南ア
ジアへ南下し越冬いたします。インドやスリランカ、中華人民共和国南部、東南アジ
アでは周年生息し、日本では亜種アオバズクが九州以北に繁殖のため飛来(夏鳥)
するそうです。和名は青葉が芽生える季節に飛来することが由来と説明されてます。

宗像神社は、社伝によりますと、延暦14年(795年)、藤原冬嗣が桓武天皇の勅命を蒙り、皇居鎮護の神として筑前宗像神を勧請し、自邸である東京
第(東京一条第ともいう)の西南隅に祀ったものと伝わりますが、当神社の鎮座由来を記す最古のものとしては『土右記』が挙げられ、東京第は冬嗣の
没後、東の花山院と西の小一条第に分けられましたが、同書には当時の小一条第第主師成の語った以下の話を載せております。小一条第は藤原内
麻呂が息子の冬嗣に買い与えた邸宅ですが、その理由は、冬嗣がまだ内舎人であった頃、参内の途中で虚空から宗像大神が呼びかけ、父に頼んで
小一条第を買ってもらいそこに居住して傍らに宗像大神を祀れば、子々孫々にわたって守護しようとの神託があったためであると記されております。

花山稲荷大明神



手水場ですが、水は出ておりませんでした。

元紫宸殿の左近の桜です。 昭和11年に植え替えられる前の桜で、5年前には衰退して枯れそうでしたが、樹勢
回復処置により、元気を取り戻したそうです。




現在の烏丸竹屋町より夷川の両側を小将井町、小将井御旅町と云いますが、昔八坂神社の御旅所があったところで、その地に祀られていた神社で
す。京都市民となじみの深い祇園祭の後祭りの7月24日には、八坂神社より神職がお参りされ幣帛を供進されます。幣帛(へいはく)とは、神道の祭祀
において神に奉献するもののうち、神饌以外のものの総称で、「幣物(へいもつ)」とも言うそうです。 「帛」は布の意味であり、古代においては貴重であ
った布帛が神への捧げ物の中心となっていた そうです。

繁盛稲荷社 京都御所にも古くより、この地を外からの侵入者を防ぐ神として祀られ白狐が稲荷山に繁殖して神社を護ったとの伝説により土地を護り
子孫繁栄、事業発展を願う信仰があります。
左側の琴平神社(金毘羅宮) 讃岐・丸亀藩主の京極能登の神が1807年、常に崇敬厚き象徴の金毘羅宮を京都に祀り旅の都にて、国や藩の泰平
無事を日夜祈願されたとのとの事です。旅行の安全や海産に関係のある方々の守り神として崇敬されております。


宗像神社を後にし、神社の西側、御苑の西南角に位置する閑院宮邸跡に向かいます。

閑院宮家は伏見宮家、桂宮家、有栖川宮家と並ぶ四親王家の一つで、1710年に東山天皇の皇子直仁親王を始祖として創立され、公家町南西部の
この場所に屋敷を構えました。創建当初の建物は天明の大火(1788年)で焼失し、その後再建されていますが、現在の建物との関係など詳しいこと
はわかっていないそうです。 明治2年の東京遷都に伴い、閑院宮が東京に移られてからは、華族会館や裁判所として一時使用され、御苑の整備が
一段落した明治16年、宮内省京都支庁が設置されています。 第2次世界大戦後の昭和24年、京都御苑が国民公園となってからは、厚生省、のち
に環境庁の京都御苑管理事務所などに使用されていました。平成18年3月に改修工事を終え、京都御苑の自然と歴史についての写真・絵図・展示
品・解説を備えた収納展示室と庭園などを開放しております。
|
収納展示室 |
|
|
休館日 |
月曜日・年末年始(12月29日~1月3日) |
| 参観時間 | 午前9時~午後4時半 ※受付は午後4時まで |
| 入場料 | 無料(ご予約の必要はありません) |






ちなみに、御存じの方も多いと思いますが、京都御所とは中央の天皇の住居及び施設の事を指し、その周り全
体は京都御苑と云います。
管轄省庁は、御所が宮内庁、御苑が環境省、迎賓館が内閣府となり御苑内の警備は、皇宮警察が担当いたし
ます。 迎賓館が建つ前は、市民が利用できる球技場があり、30年のはるか昔に早朝野球で先輩に怒鳴られ
ながら走り回っていたことを思い出しました。