
立花登シリーズの第3弾。「小説現代」の昭和56年1月号から翌年の1月号までの期間に発表された6つの短編連作がまとめられている。1984年11月に文庫本が出版された。手許の文庫が1992年2月時点で第16刷発行だから、この立花登シリーズはやはりロングセラーになっている人気本の1つなのだろう。テレビドラマ化されているのもうなづける。
この第3弾を読んでいてふと気づいたこと。それは、各短編が四季という自然の大きな時の流れにそっているのだが、具体的な「時」つまり江戸時代の「○○年××月」という日月表記が捨象されていて、出て来ない。だが、短編を読み進める中で何ら違和感はない。
例えば最初の短編「秋風の女」を例にとってみよう。時間軸に関わる記述は次のようなフレーズが記されることでストーリーが繋がっている。
五つ半(午後九時)を過ぎていて/数日後だった/その日の夜になって/登はその日/西空に傾いた力ない日射しが町を染めている。その中を/さっき・・・・牢役人から説諭をうけて放されたばかり:こんな表現でストーリーの時が流れていく。「季節は秋で、暑くもなく寒くもなく、一年のうちで一番しのぎやすい時期である」(p16)という記述があり、背景となる季節がきちっと特定されているのだ。江戸時代の具体的な年月情報など無関係な次元で、人間の存在と生き様、入牢した人々の背景にある人間関係と人々の思い・思惑が問題事象の解明に関わっているというストーリーの展開にすんなりと乗っていける。換言すれば、時代を超えた人間の意思と行動、有り様を切り出して、読者に提示していると言えるのかもしれない。
収録作品の第6編、最後は「影法師」である。ストーリーの冒頭は、女牢の前の縁側で立花登が女囚のおちせを診察している場面から始まる。その場面で、著者は登に語らせている。「夏の疲れが出たのかも知れんな。風が涼しくなると、いつでもどっと病人が出て来る。今年も暑かったからな」(p232)と。この短編の背景の季節は「秋」と特定できる。つまり、この第3弾は、立花登が秋という時季に関わり合った問題事象の解明についての手控えと言えるのかもしれない。
この第3弾でおもしろいのは、登の叔父は相変わらずだが、娘のおちえがかなり行動変容を起こしてきていることである。この第3弾に相当する流れのテレビドラマ番組を視聴して、『春秋の檻』から読み始めた時は、ドラマで設定されたおちえのキャラクターとの間にギャップがあり違和感を感じていた。だが、この『愛憎の檻』でそのギャップが解消される展開になってきている。
「秋風の女」の中で、叔母が登に「あの子、このごろ少し変わったと思いませんか?」と語りかける。「何か、急におとなしくなってねえ。近ごろはお針の方が、それは熱心なの。むかしのことを考えると気味が悪いくらいですよ」(p28)と感じるようになってきたのだ。読者にとっては、このシリーズの底流のサブ・ストーリーとなる登とおちえの関係は・・・・どうなる? という興味につながっていく。楽しみが増す。
さて、ここに収録された6編について、少し触れておきたい。
<秋風の女>
夜分に女牢で急病人が出る。登がその女囚おきぬを診察した。齢は27,8。顔も身体つきも、どことなく垢抜けた女で、新入りである。数日後に、登は女牢の名主およねに呼び止められる。下男の佐七に気をつけろと助言される。佐七がおきぬにいいように使われているというのだ。佐七はおきぬの買物を身銭で貢いでいるという。およねはおきぬを新入りのくせにしたたかな女と評価する。
登は下男の万平を介して佐七に注意を促させる手を打つ。一方で、おきぬが入牢した罪状について同心の平塚から話を聞くことにした。置き引きをしたのだという。その内容を聞き、一方、おきぬに舞い上がる佐七の話と併せて、登は疑問を抱き始める。置き引きの事実解明と佐七を目覚めさせることが表裏一体の課題事象になっていく。
恋は人を盲目にする。窮地に陥らないと目が覚めないもの。そんなストーリーである。
<白い骨>
登は病人の辰平から実は女房も子供もいると聞く。病状が良くないと判断する登は出牢したら、頭を下げてでも女房の許へ戻れと勧める。叔父の代診に行った序でに、登は辰平の女房の家を訪れて話し合った後、辰平の出牢後に二人を引き合わす仲介をする。
20日ばかり後、登は両国橋東詰で入牢していた弥次郎に声をかけられた。弥次郎から辰平が10日ほど前に殺されたと教えられる。河岸で溺れた恰好で発見されたのだが、本当は殺しなのだと。辰平や弥次郎が入牢中のある事情を聞かされたことから、登は動き出す。辰平が白い骨となったことに対し、己の腹の虫をおさめたい登の心理的行動の発露が描かれて行く。熱血漢立花登の面目躍如という事件顛末譚ストーリーが楽しめる。
<みな殺し>
牢内で研ぎ屋の芳平が死んだ。叔父の家にも回ってきていた男で、いわば登の顔見知りだった。微罪程度の泥棒で入牢したのだ。登と土橋は検死を行った。登は奥歯のあたりに白いもののひっかかりに気づいた。ごく小さな紙の切れはしだった。だが二人は、これといって不審な点はなく、心ノ蔵の発作ということにした。牢内の仕組みを知る役人たちを当惑させても意味がないからだ。登は建て前とは別に、芳平の死に対する疑問について調べ始める。
非番の日に叔父の家に戻ると、登が懇意にする岡っ引きの藤吉が訪ねてきていた。芳平が本当に病死なのかどうかという確認だった。藤吉は、連続して変死人が発生している事件を調べていた。ある自身番に這い込んできた瀕死の怪我人から、藤吉は思わぬ悪党の名前を聞き出した。そして、芳平との繋がりがでてきたという。
藤吉の情報は、登が探索をさらに推し進める要因になる。登と藤吉がタッグを組み事件を解決する。登と藤吉の間には良い人間関係がますます形成されていく。
<片割れ>
久しぶりの休み。叔父夫婦が川崎のお大師様に出かけているので登はのんびりできると思っていた。だが、町医者の家と知っている訪ね人が来た。人相の悪い男だった。登は金瘡の傷口の縫合をする。おちえもその男の顔をこの町で見たことはないという。ならばなぜ、ここが町医者と知っていたのか。
数日後に、登は奉行所から送られてきた囚人簑吉の太腿の化膿している傷口の手当てのやり直しと縫合を行うことになる。簑吉は押し込みを働いた二人組の片割れだったが、奉行所の取り調べに対し、相方について白状しないという。事件を起こしたという時期を平塚同心から聞き、登は叔父の家で縫合の手当を施した男のことを思いだす。
疑点を抱く登は、簑吉の治療をする折に質問を投げかけることから、事件の解明に関わって行く。登の勘違いが逆に事件の解決、つまり二人組の片割れを逮捕する結果へと導くことに。この短編にはおもしろいオチがついていて、エンディングを楽しめる。
<奈落のおあき>
おちえが数人の莫連娘たちと遊びほうけていたころ、常連の仲間におあきが居た。小伝馬町の牢獄の石垣下の道で、厚化粧したおあきが登に声を掛けてきた場面から始まる。伊勢蔵の牢見舞いに来たのだという。平塚同心に尋ねると伊勢蔵はゆすりの罪で入牢した。腑に落ちないのは、日雇いと言うことだが、真っ白な肌をしていたと言う。
おあきに頼まれて、伊勢蔵に声をかけに行った登は、嘉吉という40近い囚人から、5歳の子供が病気との報せを聞いたので、登に非番の日に往診に行って欲しいと懇願される羽目に。医者として聞いた限りは捨て置けないので、嘉吉の家に赴くことになる。結果的に手遅れ直前の子供の命を助けるという顛末に。嘉吉は登に恩返しのつもりで七人殺しの泥棒に関連した情報を伝えようとした。だが、嘉吉は言いそびれた。その翌朝西の大牢の名主から嘉吉を病死人としてとどけが出された。その時牢医として一応「心ノ蔵の発作」という見立てで処理することに。
だが、その後の牢名主の登に対する一言がきっかけで、登は嘉吉が殺されたという仮説を追うこととなる。
この短編のタイトルは、次の一文に由来する。「おあきの細々としたすすり泣きが、二度と這い上がれない奈落の底から聞こえて来る嘆きの声のように聞こえた。」
<影法師>
この短編もまた、登が20歳の女囚おちせを診察する場面から始まる。料理茶屋で女中をしていたおちせは、加賀屋伝助の妾になっていた母親が首吊りで見つかったが、伝助が殺したのだと判断し、伝助を刺して召し捕られた。伝助は大怪我をしたが命に別状なく、おちせの思い違いとして嘆願書を奉行所に上げて穏便な裁きを願い、白洲にも出たのだ。おちせはその結果、100日の過怠牢の刑となった。
おちせの入牢中、檜物師の杉蔵が差し入れに来ていた。だが、出牢の日に杉蔵は現れず来たのは町役人の多兵衛という年寄りの大家だけだった。登が見送っていると、町屋の通りに出ようとしたところに、一丁の駕籠が現れ、一騒動がおこる。駕籠かきは加賀屋からの迎えだと言ったそうだ。おちせが牢を出た後についての登の予測がすこしずつズレていく。そこで登はおちせの事件を詳しく知ろうとする。杉蔵が登の所に来て、おちせの行方がわからなくなったと告げる。登は藤助に相談をもちかけると千助が捜索を協力してくれることに。一方、登は加賀屋伝助に直接話を聞きに行くという行動に出る。
一連の行動現象は、そこに付加される情報によって、真逆の解釈が成立する。そんな状況設定を巧みに採り入れたおもしろい構想の短編と言える。
藤沢周平は1997(平成9)年69歳で没した。文庫本末尾の年譜を読むと、昭和55(1980)年、著者53歳の時に『春秋の檻』が刊行された。このシリーズはまさに著者の円熟期に創作されている。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『風雪の檻 獄医立花登手控え2』 講談社文庫
『春秋の檻 獄医立花登手控え1』 講談社文庫
この第3弾を読んでいてふと気づいたこと。それは、各短編が四季という自然の大きな時の流れにそっているのだが、具体的な「時」つまり江戸時代の「○○年××月」という日月表記が捨象されていて、出て来ない。だが、短編を読み進める中で何ら違和感はない。
例えば最初の短編「秋風の女」を例にとってみよう。時間軸に関わる記述は次のようなフレーズが記されることでストーリーが繋がっている。
五つ半(午後九時)を過ぎていて/数日後だった/その日の夜になって/登はその日/西空に傾いた力ない日射しが町を染めている。その中を/さっき・・・・牢役人から説諭をうけて放されたばかり:こんな表現でストーリーの時が流れていく。「季節は秋で、暑くもなく寒くもなく、一年のうちで一番しのぎやすい時期である」(p16)という記述があり、背景となる季節がきちっと特定されているのだ。江戸時代の具体的な年月情報など無関係な次元で、人間の存在と生き様、入牢した人々の背景にある人間関係と人々の思い・思惑が問題事象の解明に関わっているというストーリーの展開にすんなりと乗っていける。換言すれば、時代を超えた人間の意思と行動、有り様を切り出して、読者に提示していると言えるのかもしれない。
収録作品の第6編、最後は「影法師」である。ストーリーの冒頭は、女牢の前の縁側で立花登が女囚のおちせを診察している場面から始まる。その場面で、著者は登に語らせている。「夏の疲れが出たのかも知れんな。風が涼しくなると、いつでもどっと病人が出て来る。今年も暑かったからな」(p232)と。この短編の背景の季節は「秋」と特定できる。つまり、この第3弾は、立花登が秋という時季に関わり合った問題事象の解明についての手控えと言えるのかもしれない。
この第3弾でおもしろいのは、登の叔父は相変わらずだが、娘のおちえがかなり行動変容を起こしてきていることである。この第3弾に相当する流れのテレビドラマ番組を視聴して、『春秋の檻』から読み始めた時は、ドラマで設定されたおちえのキャラクターとの間にギャップがあり違和感を感じていた。だが、この『愛憎の檻』でそのギャップが解消される展開になってきている。
「秋風の女」の中で、叔母が登に「あの子、このごろ少し変わったと思いませんか?」と語りかける。「何か、急におとなしくなってねえ。近ごろはお針の方が、それは熱心なの。むかしのことを考えると気味が悪いくらいですよ」(p28)と感じるようになってきたのだ。読者にとっては、このシリーズの底流のサブ・ストーリーとなる登とおちえの関係は・・・・どうなる? という興味につながっていく。楽しみが増す。
さて、ここに収録された6編について、少し触れておきたい。
<秋風の女>
夜分に女牢で急病人が出る。登がその女囚おきぬを診察した。齢は27,8。顔も身体つきも、どことなく垢抜けた女で、新入りである。数日後に、登は女牢の名主およねに呼び止められる。下男の佐七に気をつけろと助言される。佐七がおきぬにいいように使われているというのだ。佐七はおきぬの買物を身銭で貢いでいるという。およねはおきぬを新入りのくせにしたたかな女と評価する。
登は下男の万平を介して佐七に注意を促させる手を打つ。一方で、おきぬが入牢した罪状について同心の平塚から話を聞くことにした。置き引きをしたのだという。その内容を聞き、一方、おきぬに舞い上がる佐七の話と併せて、登は疑問を抱き始める。置き引きの事実解明と佐七を目覚めさせることが表裏一体の課題事象になっていく。
恋は人を盲目にする。窮地に陥らないと目が覚めないもの。そんなストーリーである。
<白い骨>
登は病人の辰平から実は女房も子供もいると聞く。病状が良くないと判断する登は出牢したら、頭を下げてでも女房の許へ戻れと勧める。叔父の代診に行った序でに、登は辰平の女房の家を訪れて話し合った後、辰平の出牢後に二人を引き合わす仲介をする。
20日ばかり後、登は両国橋東詰で入牢していた弥次郎に声をかけられた。弥次郎から辰平が10日ほど前に殺されたと教えられる。河岸で溺れた恰好で発見されたのだが、本当は殺しなのだと。辰平や弥次郎が入牢中のある事情を聞かされたことから、登は動き出す。辰平が白い骨となったことに対し、己の腹の虫をおさめたい登の心理的行動の発露が描かれて行く。熱血漢立花登の面目躍如という事件顛末譚ストーリーが楽しめる。
<みな殺し>
牢内で研ぎ屋の芳平が死んだ。叔父の家にも回ってきていた男で、いわば登の顔見知りだった。微罪程度の泥棒で入牢したのだ。登と土橋は検死を行った。登は奥歯のあたりに白いもののひっかかりに気づいた。ごく小さな紙の切れはしだった。だが二人は、これといって不審な点はなく、心ノ蔵の発作ということにした。牢内の仕組みを知る役人たちを当惑させても意味がないからだ。登は建て前とは別に、芳平の死に対する疑問について調べ始める。
非番の日に叔父の家に戻ると、登が懇意にする岡っ引きの藤吉が訪ねてきていた。芳平が本当に病死なのかどうかという確認だった。藤吉は、連続して変死人が発生している事件を調べていた。ある自身番に這い込んできた瀕死の怪我人から、藤吉は思わぬ悪党の名前を聞き出した。そして、芳平との繋がりがでてきたという。
藤吉の情報は、登が探索をさらに推し進める要因になる。登と藤吉がタッグを組み事件を解決する。登と藤吉の間には良い人間関係がますます形成されていく。
<片割れ>
久しぶりの休み。叔父夫婦が川崎のお大師様に出かけているので登はのんびりできると思っていた。だが、町医者の家と知っている訪ね人が来た。人相の悪い男だった。登は金瘡の傷口の縫合をする。おちえもその男の顔をこの町で見たことはないという。ならばなぜ、ここが町医者と知っていたのか。
数日後に、登は奉行所から送られてきた囚人簑吉の太腿の化膿している傷口の手当てのやり直しと縫合を行うことになる。簑吉は押し込みを働いた二人組の片割れだったが、奉行所の取り調べに対し、相方について白状しないという。事件を起こしたという時期を平塚同心から聞き、登は叔父の家で縫合の手当を施した男のことを思いだす。
疑点を抱く登は、簑吉の治療をする折に質問を投げかけることから、事件の解明に関わって行く。登の勘違いが逆に事件の解決、つまり二人組の片割れを逮捕する結果へと導くことに。この短編にはおもしろいオチがついていて、エンディングを楽しめる。
<奈落のおあき>
おちえが数人の莫連娘たちと遊びほうけていたころ、常連の仲間におあきが居た。小伝馬町の牢獄の石垣下の道で、厚化粧したおあきが登に声を掛けてきた場面から始まる。伊勢蔵の牢見舞いに来たのだという。平塚同心に尋ねると伊勢蔵はゆすりの罪で入牢した。腑に落ちないのは、日雇いと言うことだが、真っ白な肌をしていたと言う。
おあきに頼まれて、伊勢蔵に声をかけに行った登は、嘉吉という40近い囚人から、5歳の子供が病気との報せを聞いたので、登に非番の日に往診に行って欲しいと懇願される羽目に。医者として聞いた限りは捨て置けないので、嘉吉の家に赴くことになる。結果的に手遅れ直前の子供の命を助けるという顛末に。嘉吉は登に恩返しのつもりで七人殺しの泥棒に関連した情報を伝えようとした。だが、嘉吉は言いそびれた。その翌朝西の大牢の名主から嘉吉を病死人としてとどけが出された。その時牢医として一応「心ノ蔵の発作」という見立てで処理することに。
だが、その後の牢名主の登に対する一言がきっかけで、登は嘉吉が殺されたという仮説を追うこととなる。
この短編のタイトルは、次の一文に由来する。「おあきの細々としたすすり泣きが、二度と這い上がれない奈落の底から聞こえて来る嘆きの声のように聞こえた。」
<影法師>
この短編もまた、登が20歳の女囚おちせを診察する場面から始まる。料理茶屋で女中をしていたおちせは、加賀屋伝助の妾になっていた母親が首吊りで見つかったが、伝助が殺したのだと判断し、伝助を刺して召し捕られた。伝助は大怪我をしたが命に別状なく、おちせの思い違いとして嘆願書を奉行所に上げて穏便な裁きを願い、白洲にも出たのだ。おちせはその結果、100日の過怠牢の刑となった。
おちせの入牢中、檜物師の杉蔵が差し入れに来ていた。だが、出牢の日に杉蔵は現れず来たのは町役人の多兵衛という年寄りの大家だけだった。登が見送っていると、町屋の通りに出ようとしたところに、一丁の駕籠が現れ、一騒動がおこる。駕籠かきは加賀屋からの迎えだと言ったそうだ。おちせが牢を出た後についての登の予測がすこしずつズレていく。そこで登はおちせの事件を詳しく知ろうとする。杉蔵が登の所に来て、おちせの行方がわからなくなったと告げる。登は藤助に相談をもちかけると千助が捜索を協力してくれることに。一方、登は加賀屋伝助に直接話を聞きに行くという行動に出る。
一連の行動現象は、そこに付加される情報によって、真逆の解釈が成立する。そんな状況設定を巧みに採り入れたおもしろい構想の短編と言える。
藤沢周平は1997(平成9)年69歳で没した。文庫本末尾の年譜を読むと、昭和55(1980)年、著者53歳の時に『春秋の檻』が刊行された。このシリーズはまさに著者の円熟期に創作されている。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『風雪の檻 獄医立花登手控え2』 講談社文庫
『春秋の檻 獄医立花登手控え1』 講談社文庫















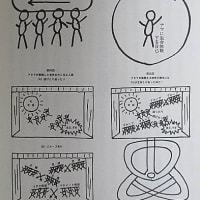




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます