秋晴れの週末2日間、3社の出版関係の方達と歩きました。
昨日は、山頂口バス停~火口一周~裏砂漠~樹海~温泉ホテルへ抜けるフルコースへ。
なんと豪華お弁当を山頂で食べるという初企画。

観光協会の岡田さんが、段ボールに入れた6人分のお弁当を持って山に登ってくれました!
重そうでみんなで心配しましたが「大丈夫です」とニコニコ。
いつもの通り、溶岩や植物を観察しながら山を登っていきました。
遊歩道の両脇の草が刈られて明るくなったからか、意外な花が咲いていることに気がつきました。

センブリです。何株も咲いていました。
今まで大きな草に覆われながらも、ひっそりと生きていたんですね。
センブリは下痢、腹痛などに効くと言われる植物で、その苦みが有名です。全員で葉を口に含み「苦い~!」と言い合いながら山頂を目指しました。(疲れを忘れる苦さでした・笑)
海を見下ろしながらのランチタイムは、島の食材をふんだんに使った「島弁当」をいただきました。
(岡田さん、ありがとうございました!)

眼下に外輪山や光る海を見下ろしながら、島料理に舌鼓…最高に贅沢な気分でした~。
(普段はオニギリなので・笑)
火口一周コースにある火山弾に座ってポーズ。

「この岩、寝心地いい~」

「奇麗~!」

キラキラ輝くススキで、山全体が光って見えました。
広範囲のキラキラのみならず(笑)、風に揺れるキラキラ越しに真っ黒の山を見上げるのも素敵です。

新動物の発見もありました(?)Aさんが溶岩のカエルを発見。みなさんも次々に「あ!本当だ。カエルに見える!」と賛同されるのですが、私だけなかなか見つけられません…。

でも、じ~っと見つめていたらやっとカエルが見えてきました。
読者のみなさんも、この画像の中のカエル探してみてください。
(ヒント。ツルツルの溶岩です。目玉が2個飛び出ています~)
さて、今日です。
今日は裏砂漠を中心に、森や海に立ち寄りました。
うわ~。

バ、バランス良いですね。
うわ~。

飛びますねぇ…。
伊豆大島、体感取材って感じですね!

いや~、いっぱい笑って面白かったです。
そうそう、今日はこんな素敵なものも見つけました。
なんと、レースのようになったガクアジサイの飾り花。

時々、葉脈だけになったレースのような葉は見かけますが、飾り花もこんなふうになるんですね。
芸術的!
芸術的と言えば…2日間ともコース上に、強風でスコリアが飛んでできたと思われる横筋がついているのが面白かったです。

きっと先日の強風で、細かい溶岩の粒が飛んで地面を削って模様をつけたのでしょう。
荒れ狂う風を思い描いたら、ちょっとドキドキしました。
地面の横筋、うまく写真に撮れないのが残念です。

風が刻んだ縞模様って感じで、素敵だったのですけれど。
目の前の風景いっぱいのキラキラから、足もとの小さな模様まで…楽しい2日間でした!
(カナ)
昨日は、山頂口バス停~火口一周~裏砂漠~樹海~温泉ホテルへ抜けるフルコースへ。
なんと豪華お弁当を山頂で食べるという初企画。

観光協会の岡田さんが、段ボールに入れた6人分のお弁当を持って山に登ってくれました!
重そうでみんなで心配しましたが「大丈夫です」とニコニコ。
いつもの通り、溶岩や植物を観察しながら山を登っていきました。
遊歩道の両脇の草が刈られて明るくなったからか、意外な花が咲いていることに気がつきました。

センブリです。何株も咲いていました。
今まで大きな草に覆われながらも、ひっそりと生きていたんですね。
センブリは下痢、腹痛などに効くと言われる植物で、その苦みが有名です。全員で葉を口に含み「苦い~!」と言い合いながら山頂を目指しました。(疲れを忘れる苦さでした・笑)
海を見下ろしながらのランチタイムは、島の食材をふんだんに使った「島弁当」をいただきました。
(岡田さん、ありがとうございました!)

眼下に外輪山や光る海を見下ろしながら、島料理に舌鼓…最高に贅沢な気分でした~。
(普段はオニギリなので・笑)
火口一周コースにある火山弾に座ってポーズ。

「この岩、寝心地いい~」

「奇麗~!」

キラキラ輝くススキで、山全体が光って見えました。
広範囲のキラキラのみならず(笑)、風に揺れるキラキラ越しに真っ黒の山を見上げるのも素敵です。

新動物の発見もありました(?)Aさんが溶岩のカエルを発見。みなさんも次々に「あ!本当だ。カエルに見える!」と賛同されるのですが、私だけなかなか見つけられません…。

でも、じ~っと見つめていたらやっとカエルが見えてきました。
読者のみなさんも、この画像の中のカエル探してみてください。
(ヒント。ツルツルの溶岩です。目玉が2個飛び出ています~)
さて、今日です。
今日は裏砂漠を中心に、森や海に立ち寄りました。
うわ~。

バ、バランス良いですね。
うわ~。

飛びますねぇ…。
伊豆大島、体感取材って感じですね!

いや~、いっぱい笑って面白かったです。
そうそう、今日はこんな素敵なものも見つけました。
なんと、レースのようになったガクアジサイの飾り花。

時々、葉脈だけになったレースのような葉は見かけますが、飾り花もこんなふうになるんですね。
芸術的!
芸術的と言えば…2日間ともコース上に、強風でスコリアが飛んでできたと思われる横筋がついているのが面白かったです。

きっと先日の強風で、細かい溶岩の粒が飛んで地面を削って模様をつけたのでしょう。
荒れ狂う風を思い描いたら、ちょっとドキドキしました。
地面の横筋、うまく写真に撮れないのが残念です。

風が刻んだ縞模様って感じで、素敵だったのですけれど。
目の前の風景いっぱいのキラキラから、足もとの小さな模様まで…楽しい2日間でした!
(カナ)


















































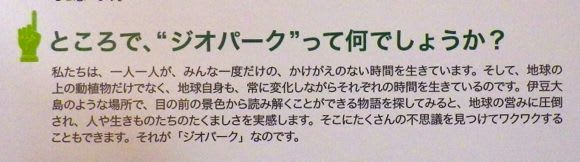





















 ヤクシソウ
ヤクシソウ ツリガネニンジン
ツリガネニンジン 恥ずかしがり屋の蜘蛛
恥ずかしがり屋の蜘蛛 拉致して道路に 撮影後は又元の処に帰しました
拉致して道路に 撮影後は又元の処に帰しました イヌホウズキ
イヌホウズキ 実も付いています
実も付いています ツルソバ
ツルソバ ムカシヒメヨモギ
ムカシヒメヨモギ イヌタデ(アカマンマ)
イヌタデ(アカマンマ) 形が可愛かったススキ
形が可愛かったススキ 隣に出ていたススキ
隣に出ていたススキ オオバコの上に止まっていたヤマトシジミ
オオバコの上に止まっていたヤマトシジミ アザミに夢中な蜂
アザミに夢中な蜂 ノコンギクにも蜂
ノコンギクにも蜂 ミズヒキ
ミズヒキ ホトトギスも咲いていました
ホトトギスも咲いていました 誰でしょう?
誰でしょう? 目が3つ有るの!
目が3つ有るの! 帰りは遠くに夕焼けが…
帰りは遠くに夕焼けが…


























