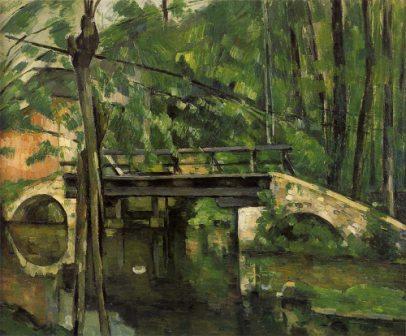★ Earth Hour(アースアワー)2011年 明日開催です。 ★
日時: 2011年3月26日 夜8:30 から 9:30 まで
つながる気持ちが 世界を変える
そして、省エネ・節電を通じて、被災地を応援しよう
>>>温暖化の防止を求める世界の願い
>>>被災地の救済を願い、支援の気持を込めて
>>>被災地にむけて世界が祈ります
>>>やってみよう!省エネ、節電アクション
・アースアワーに参加しよう! 思いをみんなに伝えよう!
--------------------------------------------------------------------
★温暖化の防止を求める世界の願い
「Earth Hour(アースアワー)」は、
世界中の人々が、同じ日・同じ時刻に電気を消すなどのアクションを通じて、
地球温暖化を止めたい!という思いを示す、国際的なイベントです。
2011年は、3月26日の午後8時30分から9時30分まで、さまざまな国の人たちが参加して行なわれます。
 https://krs.bz/wwfjapan/c?c=457&m=23485&v=2ee71fe1
https://krs.bz/wwfjapan/c?c=457&m=23485&v=2ee71fe1 
★被災地の救済を願い、支援の気持を込めて
日本でも同日の午後8時30分から「アースアワー」が開催されます。
しかし、WWFジャパンでは国内でのこのイベントを、地球温暖化防止という
本来の趣旨にとどめず、全国にあらためて広く節電・省エネを呼びかけ、
3月11日に起きた東北関東大震災の被災地の人たちを応援しよう!という
イベントとして行なうことにいたしました。
▼現在の参加状況
 https://krs.bz/wwfjapan/c?c=458&m=23485&v=ccbc70fe
https://krs.bz/wwfjapan/c?c=458&m=23485&v=ccbc70fe 
WWFジャパン メールマガジン - PANDA 通信 - より

M15号(652㎜×455㎜)













 色が違いすぎっ!
色が違いすぎっ!  ひどくないか、、、
ひどくないか、、、