
塩野七生さんの名を知ったのは、とある人が私に、次のように言ったからだった。
「最初は男性作家だと思っていた人に、塩野七生さんという人がいる。ローマ人の物語など、歴史物を書いているけど、あまり勧められないな」
聞くところによると、そう言った本人は、歴史好きで、塩野さんの著書もよく読んでいるようなのだ。私は以前、「小学生のころから歴史が好きだった」と話したことがあったが、どうも信じてもらえていないようだな、と感じたため、証拠品(小6の社会科ノート:自分で調べたこと編)と共に『桶狭間の戦い、観た?』というタイトルでブログ記事を書いた。
いずれにせよ、
「この私に
 あまり勧められない塩野七生さんの本って、一体、どんな本なのか!?」
あまり勧められない塩野七生さんの本って、一体、どんな本なのか!?」
逆に
 好奇心を持つきっかけとなった。あっという間に『ローマ人の物語』43巻読了
好奇心を持つきっかけとなった。あっという間に『ローマ人の物語』43巻読了


そのことを告げると、
「 余程の読書家で、歴史好きにしか勧められないね」という答えが返ってきた。ということはだね、つまり私は大した読書家でも歴史好きでもない、という認識だったのかああああああああ!
余程の読書家で、歴史好きにしか勧められないね」という答えが返ってきた。ということはだね、つまり私は大した読書家でも歴史好きでもない、という認識だったのかああああああああ!


そのローマ人の物語、第1巻には、ギリシアが出てくる。遥か昔、幼児期から、最も親しみを感じた外国だ。『ソフィーの世界』でもお馴染みのソクラテスを生んだアテナイ。塩野さんが、まだ『ギリシアの物語』をその時点で(2016年)書いていなかったことが、逆に不思議に思えたくらいだ。
21歳の頃、いつも話を聴く側だった私に、Ramirは言った。”It's your turn, Suzu. Tell me your story." (次は、すずの番だよ。何か話を聴かせて)
少し考えた私は言った。
"Have you ever noticed that most Japanese cars
 are white? "
are white? "
(日本の自動車は、殆ど白だと気付いたことある?)
当時、今から30年前は、白が好まれ、今のようにカラフルじゃなかったんだよなぁ。トヨタカローラは白が多かったし、我が家もそうだった。何より”皆と同じ”が好まれる日本人気質。レストランへ行っても、一人が注文すると、私も、私も、私も!と後に続くケースが多い日本人。ちょっと論ずるには面白い話題ではないかと思ったのだ。
”Your stories always begin with questions!" (君の話はいつも質問で始まるね!)
Belongings ....right? 賢いRamirにはすぐに隠されたテーマを見抜かれてしまった!まぁ、10歳もあちらが年上だったわけだし。お陰で会話から多くを学ばせてもらった。
その2年後、豪州の下宿先で出会った、かの国(K国)出身者から、毎晩のように「米国の州の数はいくつか?」などの問題が出され、即答出来なければ、
「そんなことも日本人は知らないのか!」
と大いにバカにされたものだった。当時の回答者は、🐭Disneylandでミッキーマウスと一緒に踊っていたという日本人女子留学生、(スタイルが良く可愛いだけでなく、感じのいい子だった!)何故か私をディスコへ誘うことに熱心だった(踊れないし、行かないっていってるでしょ!) 大阪出身の男の子、そして
大阪出身の男の子、そして 私の3人。
私の3人。
いつもは、さして気にしない私も、一度だけ、
「サモアを知らないの? オーストラリアに住んでいて、米国の州の数より、こっちの方が知っておくべきなんじゃないの?」
と遂、言い返してしまった。珍しく、K国の相手が しゅん となったのを見て、これまでの鬱憤を晴らすかの如く、日本人チーム3人で
となったのを見て、これまでの鬱憤を晴らすかの如く、日本人チーム3人で
「イエーイ





 やったね!」
やったね!」
と、ハイタッチした。
その頃はまだ、ソフィーの世界は出版されておらず、ソクラテスの言葉は知らなかったが、かの国の彼に馬鹿にされる度に、私は言ったものだぁ~
"The only thing I know is the fact that I know nothing. Life is too short for me to learn everything!!"
(私が唯一知っていることは、実は私は何も知らない、ということ。人生はすべてを学ぶには短すぎるから)
『ソフィーの世界』を読んで、何が自分を興奮させたかといえば、何かを軽く議論するつもりである場合、(それが出来る相手は極めて稀ではあるけれど)
「 質問で始まる自分の話」
質問で始まる自分の話」
「何も知らない自分...という自覚 」
」
...という若かった頃の自分の特徴と、
(20代後半の自分は、23歳までが 若く、それ以降は
若く、それ以降は 婆だと思っていた
婆だと思っていた )
)
あの哲学者、ソクラテスと自分に共通点があるではないの!ってこと。
着るもの(衣装)に拘らず、シンプル イズ ベスト👍な考えも 同じである。 アテナイ(アテネ)に生まれていたら、弟子入りしたのに! という興奮だった。 それ以来、 よく知りもしないのに、心の中では、「ソクラテスこそ、わが師」だと思っている。
よく知りもしないのに、心の中では、「ソクラテスこそ、わが師」だと思っている。
 思うのは自由です
思うのは自由です







『ギリシア人の物語 Ⅰ』
ここから本題です。(長っ!)
紀元前480年と479年、2度に渡るペルシア戦役。海はサラミスで、アテネ主導で完勝。翌年、陸のプラタイアでスパルタ主導により圧勝。
騎兵隊、歩兵隊、ガレー船の数ではペルシアの10分の1程度だったアテネ、スパルタ、その他のギリシア都市国家による連合軍が、一体、どうやって勝利したのか!?
思えば、その後の時代に登場するハンニバル、スキピオ・アフリカヌス、カエサルも同じ布陣を取った。
...と、いうことは、つまり、『ハンニバル戦記』 或は 『ユリウス・カエサル ルビコン川 前・後』をワクワクしながら読破した方は、『ギリシア人の物語 Ⅰ』の後半とⅡも、同じように楽しめる筈。ただ単に、戦術や闘いぶりに目を見張りながら...というだけではなく、アテネ市民をまるごと疎開させ、都市をモヌケノ殻にした! (非戦闘員の命を守った)等、民主政アテネで暮らしていた人々を想像しながらお読み下さいませ。そういう訳でして、ここでは敢えて詳細には触れないことにしませう。
ギリシア人の物語 Ⅱ
ペルシアの脅威から ギリシアの都市国家はその後も協力し合うべく結成されたペロポネス同盟。スパルタの呼びかけにより結成。しかし、スパルタは今で言うトランプ元大統領時代の米国、「一国主義;アメリカファースト」と似たようなもので、一国平和主義で、他国に無関心。(いや、米国とはちょっと違うか!)
ギリシア南部のペロポネス半島にある都市国家を集めて結成されたため、この名となった。(79ページ4行目)
いざとなれば、スパルタの戦士が救援に駆けつけてくれるという期待を持って、加盟したのでしょうね。 分担金を支払う必要もなかったそうなので。(81ページ)
遅れること70年、イオニア地方の都市や島に住むギリシア人が結成を持ち掛け、結成されたのがデロス同盟。この人達が頼りにしたのは、こちらは加盟国となるにサラミスの海戦で勝利し、その翌年、エーゲ海のペルシア海軍基地となっていたサモス島奪還に成功したアテネだった。加盟国となるには、負担金が必要だった点がペロポネス同盟と異なる。海軍は陸軍よりお金がかかるから、らしい。(84ページ)
実際には、祖父、そして父の代に コテンパンに ギリシアの都市国家に海上で「やられた」様子を父と共に丘の上から眺めていたペルシアの王は、ギリシアに攻め込むことはしなかった。
こうして円熟期に入ったアテネとスパルタの30年。
ところがその後、コルフとコリントの争いで点火した火が他の地まで飛び火。アテネを統治していたペリクレスと、スパルタの王、アルキダモスは1歳違い。アルキダモスは、プライベートでペリクレスの別荘を訪問する仲だったらしい。 飛び火からアテネとスパルタは 止むを得ず戦闘を開始することとなるのだが... お互いを熟知した統治者と王は、言葉を交わさずとも、お互いが考えることは分かった筈だと、塩野氏。実際、
陸のスパルタは、アテネが管轄する陸地(アッティカ地方)をちょこっと荒し...
海のアテネは、スパルタが管轄するペロポネソス半島をちょこっと荒し...
お互い、正面衝突することを避け、一年目の戦役は終了✋した。
塩野さんの仮説通り、このまま5年間休戦したあと、再び30年の和平協定を結ぶということになった「かも」しれないのに。
翌年には、ギリシア全土を襲った不幸 (チフスではないか、という噂も)により、『ペロポネソス戦役』は不幸にも27年も続いてしまったのだった。




しかも、開戦2年目に、長年、アテネとギリシア一帯の平和維持に貢献した一人である、アテネのペリクレスは病死した。享年66歳。更には、同じくギリシア平穏に貢献したスパルタの王、アルキダモスも、その2年後に亡くなった。更にさらに、ギリシア世界の平和維持に遠くペルシアから貢献した、ペルシア王アルタ・クセルクセスも2年後にこの世を去った。
パクス・ロマーナならぬ、パクス・ギリシアに貢献した3人が相次いで亡くなったことで、いわゆる「終わりのはじまり」となっていく。
ペリクレスが亡くなった年、ソフォクレスの悲劇、『オイディプス王』が上演された。神頼みだった、この時代において、最もリアリスティックで現実的だったペリクレス。 塩野さん曰く、
「予言によって定められた運命に逆らう想いで一生を生きてきたのに、結局は予言されたとおりの一生をおくってしまった人間の哀しみを、深く極めた傑作である」
「ペリクレスは生涯にわたって、運命とは神々が定めるものではなく、われわれ人間が切り開くものだと言い続けてきた人である。だが、最後になって、考えていた『大戦略』は、彼自身の死によって中途での挫折を強いられる。これが運命でなくて、何が運命であろうか」と...。 (175ページ10行目~15行目)
ここまで第一部。 『ギリシア人の物語 Ⅱ』後半、ペリクレス以後(紀元前429~404年までの26年間)は、明日の夜、読む予定。(182ページ以降)
ここから~追記;
後半も読み終えた。昨夜&翌日、職場の昼休みに読了。帰りに図書館へ寄って返却したため、本はすでに手元にはない。
27年続いた『ペロポネソス戦役』の舞台は、最後の数年間、アテネからもスパルタからも遠く離れた東方へ移った。ペルシアに利があったため、裏で誰かが糸を引いていたの「かも」。あくまで仮説。当時から謎なのだから、現代の歴史家の間でも謎。
もしも、ペリクレスが生きていれば...三大悲劇の作者ソフォクレスまで担ぎ出されたのだから。彼はすでに80歳代。本国アテネにいて、実戦に加わることはなくとも、ちょっとばかし長生きしたために、アテネの哀しい行く末を見守ることになってしまった。
ペリクレスであれば、和平交渉に入ったであろう場面で、アテネは無益な戦役を続行してしまう。
ペリクレス亡き後、アテネには、市民の不安を煽り、扇動していく、いわゆる扇動者が幅をきかせる。彼の名は... 忘れたが、こういう輩は、批判すること、反対することが目的だから、「では、どうぞ、ご勝手に」と、実際になったのだが、何も出来なかった。今で言うところの、日本の野党やマスコミのような存在。
扇動されれば、市民は熱狂的になる。和平交渉、という選択肢よりも、民主政のアテネの市民議会の結論は、『ペロポネソス戦役』の状態続行。当時、世界最強と言われたアテネの海軍を 市民たちはイケイケドンドンで、熱狂的に送り出している。
そんな市民たちの期待に反して、状況が劣勢になる。ここへきても『撤退』ではなく、『続行、及びに追加派遣』を決めたのは、市民たち。民主政では、法案を出すのは統治者でも、可決か否かを決めるのは、選挙権を持つ市民だったから。
アテネの国庫がカラになろうとも、市民たちは自分の身を削ってでも、カンパで造船に協力した。ソクラテスは免れたらしいが、殆どの家庭から歩兵隊を送り出している。しかも高揚した市民たちに見送られて...
しかし結果は惨敗。生き残り、シラクサから本国アテネへ戻れた人は一人もいなかったらしい。
悪いニュースほど、アテネ本国に早く届く。
ひとことでいえば、ソクラテスは正しかった。
敵は自分自身の中にある。
塩野さんの言葉でいえば、アテネは自滅した。
アテネは もはやギリシアの覇者ではなくなってしまった。
アテネという都市国家を更地にし、女子供は奴隷として売り飛ばせ!とシラクサは意気込む。(スパルタの王によって、それは免れた。)捕虜となった男たちの中からアテネ人、3000人を選び出し、全員斬首。その他のポリスの連合軍の生き残りは、石切り場で強制労働させられたのだ。
石切り場といっても、地下へ、地下へと掘っていき、食事は一日に地上から地下へと投げ込まれるわずかなパンと水のみ。夜になれば、地上のフタは閉じられる。要するに、地下はそのまま、牢獄だった。
戦いの後で怪我人もいたらしいが、何の手当も処置もなく、亡くなってもすぐには地上へ引き上げてもらうこともなかったそうだから、悪臭も凄かっただろう。
これでは健康な人も病気になる。『タイムマシン』の地下に住む種族を思い出してしまった。もしかしたら、ウェルズは、この歴史を念頭に書いたのでは?と思ってしまった。
平和は主要国のパワーバランスが取れて、ようやく成し遂げられるもの、だと思ってしまう。50年続いた平和は、ペルシア、アテネ、スパルタという3つの覇権者のパワーバランスが保たれていたから...こそだ。
米ソの冷戦時代も、とりあえずは戦闘状態にならなかったのも、パワーバランスが...とはいえない? 当時の首脳陣は、各国、個性派、リーダーたるリーダーたちだったように思う。サッチャー、ゴルバチョフ、レーガン、中曽根氏...
今現在は、かつて世界の警察官といわれた米国の力は弱まり(世界の中で)中国があまりにも...
日本国内には、いわゆる市民の不安を煽り、扇動していく、扇動員なら、いくらでもいる。野党も国民も悪い方へ、悪い方へと...
ペリクレスは、民主政の中にあって、市民を話術でもって、先導していくことに長けていた。だからか、のちの歴史家たちからは、「独裁」統治者、と呼ばれているらしい。何かを成し遂げるには、多くの敵も持つことになる。いわゆる反対派。彼の手腕が時には「独裁」と映ったとしても、「安定」「平和」のみならず、彼は「繁栄」までアテネとギリシアにもたらしたのだから!
日本にも、『扇動』ではなく、『先導』してくれる総理大臣が欲しいところだ。
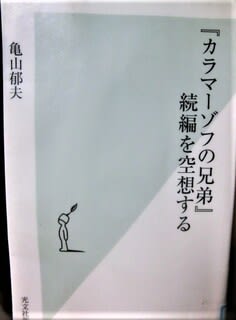











 塩野七生さんによる”小説”です!
塩野七生さんによる”小説”です!
 推測;すなわち、ローマ帝国とユダヤ教の狭間で、苦しい立場だったのではないでしょうか。
推測;すなわち、ローマ帝国とユダヤ教の狭間で、苦しい立場だったのではないでしょうか。 古代ローマ
古代ローマ ファン、或は、塩野七生ファンにお勧めです。
ファン、或は、塩野七生ファンにお勧めです。


 あまり勧められない塩野七生さんの本って、一体、どんな本なのか!?」
あまり勧められない塩野七生さんの本って、一体、どんな本なのか!?」
 好奇心を持つきっかけとなった。あっという間に『ローマ人の物語』43巻読了
好奇心を持つきっかけとなった。あっという間に『ローマ人の物語』43巻読了
 余程の読書家で、歴史好きにしか勧められないね」という答えが返ってきた。ということはだね、つまり私は大した読書家でも歴史好きでもない、という認識だったのかああああああああ!
余程の読書家で、歴史好きにしか勧められないね」という答えが返ってきた。ということはだね、つまり私は大した読書家でも歴史好きでもない、という認識だったのかああああああああ!

 are white? "
are white? " 大阪出身の男の子、そして
大阪出身の男の子、そして 私の3人。
私の3人。 となったのを見て、これまでの鬱憤を晴らすかの如く、日本人チーム3人で
となったのを見て、これまでの鬱憤を晴らすかの如く、日本人チーム3人で





 質問で始まる自分の話」
質問で始まる自分の話」 若く、それ以降は
若く、それ以降は 婆だと思っていた
婆だと思っていた )
) よく知りもしないのに、心の中では、「ソクラテスこそ、わが師」だと思っている。
よく知りもしないのに、心の中では、「ソクラテスこそ、わが師」だと思っている。















 ご覧の通り!
ご覧の通り!

 怪物を作った科学者の名前だったのねぇ~
怪物を作った科学者の名前だったのねぇ~
 作者も違いますしね。
作者も違いますしね。 …
… 主人公は男性なので、面白さが倍増します。
主人公は男性なので、面白さが倍増します。 どんでん返しが何回、繰り返されたっけ
どんでん返しが何回、繰り返されたっけ 」
」 見事なプロット
見事なプロット





