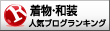百々子は類い稀な美貌を持ち、裕福な家の一人娘として生まれるが、12歳の時に両親を惨殺される。
犯人が分からないまま家政婦の家で百々子は育ち、様々な苦難を乗り越え、音楽家を目指すが…
冒頭、「男」が幼少期の記憶を思い起こすシーンがあります。
”ある時、いつものように仲間と共に石で叩いてマムシを弱らせ、男がとどめをさすように蛇を何度も強く踏みつけた瞬間、その腹から、生まれる直前だったらしい蛇の子がわらわらと、溢れ出てきた。細い蕎麦のように見える蛇の子だった。あまりの光景に、男は声を失った。蛇の子は、オレンジがかった鎖模様の母蛇とよく似た色をしてた。蛇が鳴くことなど、あり得ない。だが、男はその時、無残なやり方でこの世に生を受けた直後の蛇の子たちの、絶望の呻き声を聞いたように思った。”
これは「男」の禍々しい一生を暗示するような、なんとも意味あり気なシーンです。
百々子という女性の、昭和から令和に渡る苦難の生涯を通して、人間の生き抜くという姿を描きたかったのでしょうか。
著者は昨年、御夫君(藤田宜永氏)を亡くすという悲しみの中で、これを書き上げたといいます。
サスペンスの要素も含んでいて、秋の夜長に夢中で読んでしまいました。
タイトルのマタイ受難曲第39曲のアリアの切ない響きは、確かにこの作品にピッタリです。
しかし、あの結末は…
600ページ弱にわたって百々子の生涯を濃密に書き込んで、あの結末は最初から用意されていたのか?
あまりにも悲しく、あまりにも想定外で、脱力してしまいました。
「神よ憐れみたまえ」