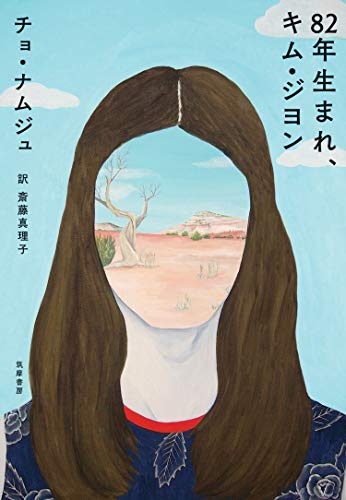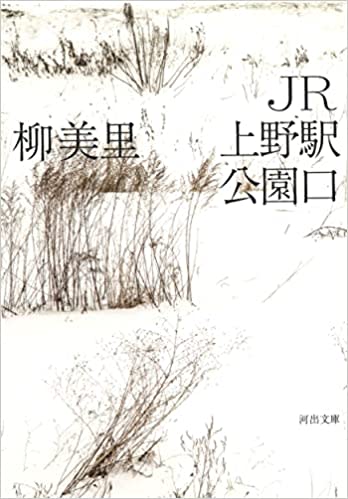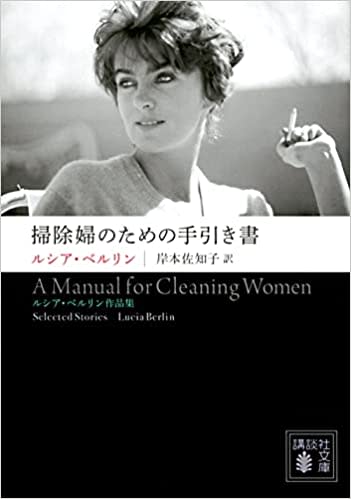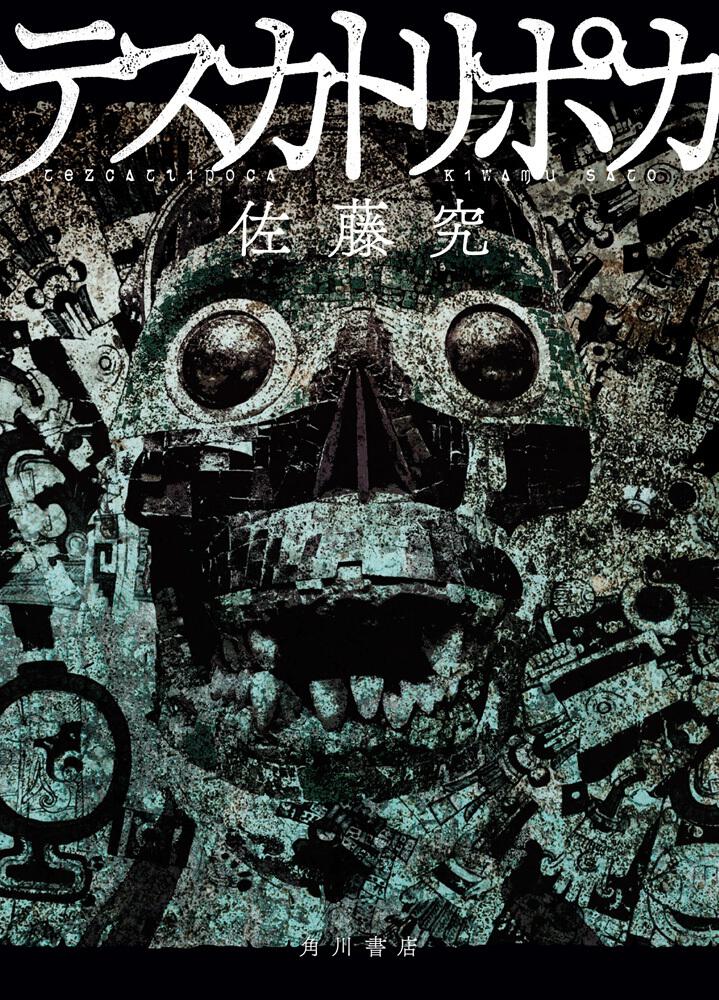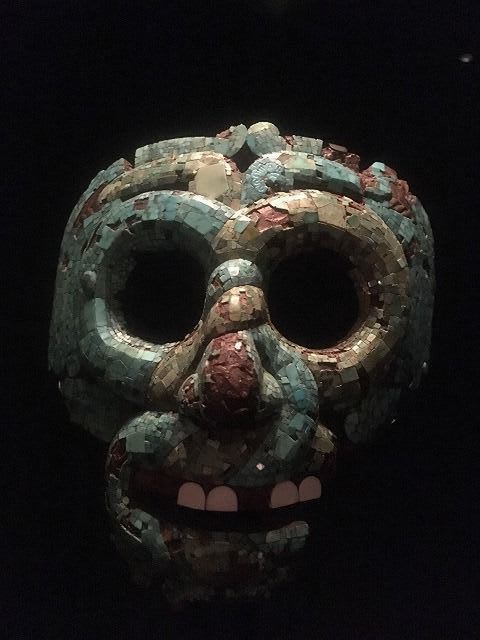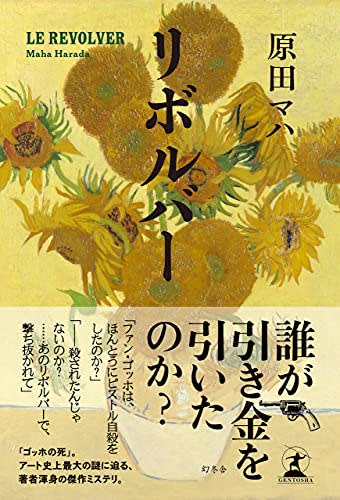「戻ってきた娘」 ドナテッラ・ディ・ピエトラントニオ著
イタリアでベストセラーとなり、二大文学賞のひとつカンピエッロ賞を受賞、28か国に翻訳され、映画化も進行しているのだそうです。
13歳の時にそれまで育った裕福な家庭から、実の親と兄妹が暮らす田舎の貧しい家庭に突然戻されてしまった「わたし」。
優しく愛に包んで育ててくれた養親は、その理由も説明してくれなかった。
何故?どうして私はこんな目に遭うの!?
13年間育ててくれた養親とは、中々連絡を取ることもできない。
劣悪な住環境、粗暴な実の親、好色な目を向ける兄たち、食べるものにも事欠く暮しで、何故急に戻ってきたのだと厄介者扱いされる。
大人達の事情で「まるで荷物のように」住む家を移され、嘆き悲しむ 多感な年頃の「わたし」。
その理由が最後に明らかになった時、その残酷さに言葉を無くしました。
唯一の救いは、繊細な姉に何くれと教えてくれる、逞しい実の妹との愛情だった。
「わたしの妹。岩にへばりついたわずかな土くれから芽を出した、思いもかけない花。わたしは彼女から、抗うことを教わった」。
訳者後書きによると、この小説の舞台となった1960年代のイタリアでは、親同士の合意だけで、子沢山の家庭から子供のいない家庭に乳幼児が引き取られるということが、頻繁に起こっていたのだそうです。
「チョウセンアサガオの咲く夏」柚月裕子著
柚月裕子の短編集。
この中で私には、表題作が印象的でした。
母が倒れ、娘は仕事も辞めて故郷に戻り、献身的に介護する。
認知症で半分寝たきりの母の介護は重労働で、往診に来る医師の賞賛と慰めの言葉だけが救いであった。母はよく下痢や嘔吐などして体調を崩し、その度に医師が往診に来るのだった。
今日も娘は庭に花を植える。
”庭にはキョウチクトウやジンチョウゲ、シャクナゲ、スズランなどが植えられていた。全て毒性がある花だ。美津子は縁側の奥の部屋で、布団に横たわっている芳江を見つめた。母さん、私は母さんを恨まないよ。今ならあなたの気持ちがわかる。だから、私の気持ちもわかるよね。ねえ、母さん。”
「代理ミュンヒハウゼン症候群」という言葉の意味が、分かりやすく理解出来ました。