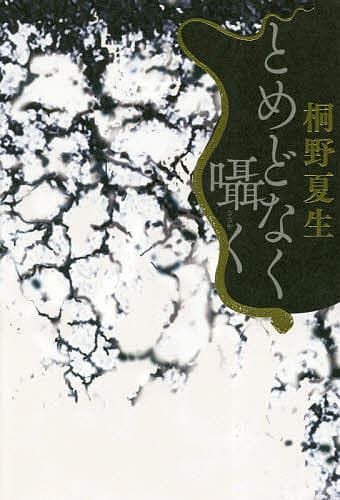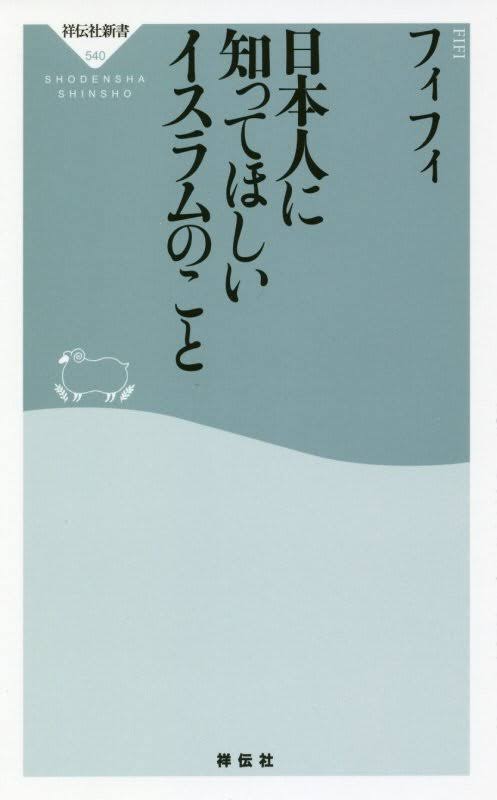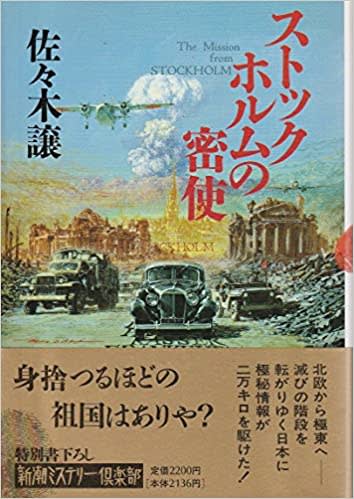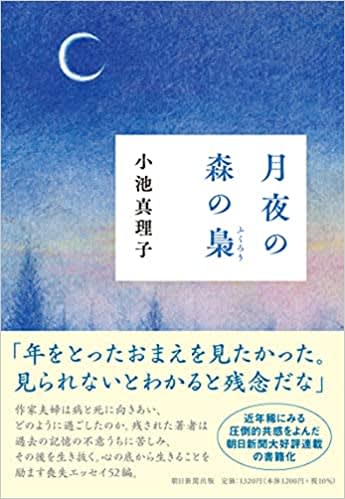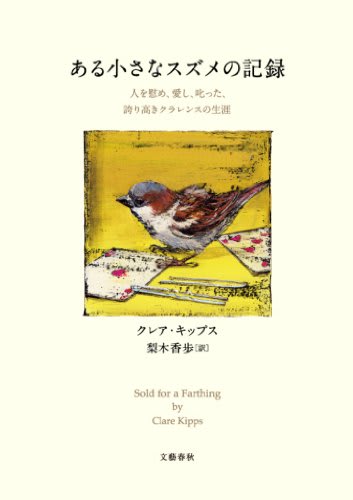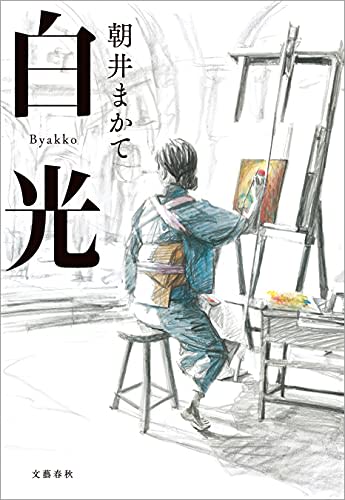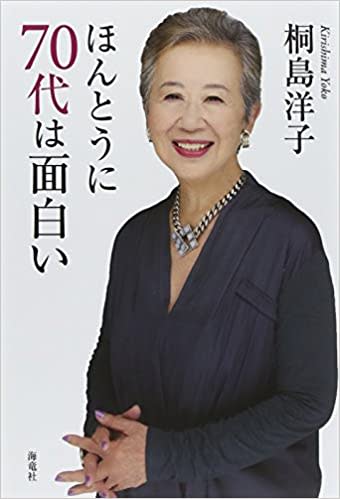この過酷で壮大な旅行記を、私の拙い文章で何処まで簡潔に(長々とは書きたくない)ご紹介できるか甚だ自信がないのですが、民族問題や政治問題など難しい部分はすっ飛ばして、根幹的な部分だけ書いてみます。
「王立文学協会賞」「スコットランド芸術協会賞」受賞作。
29歳のスコットランド人ローリー・スチュワートは、アフガニスタンの西部ヘラートから東部カブールまで歩き通す旅に出る。
時は2002年、同時多発テロの報復としてアメリカが、その首謀者をかくまったアフガニスタンのタリバンを攻撃し、タリバンが撤退した直後の混迷の頃。
ローリーはオックスフォード大を出た元外交官であり、ペルシャ語とインドネシア語を話し、イスラム圏の文化にも通じている。
しかし、零下40℃、積雪3m標高4千mの山岳地帯、しかも内戦が続くアフガニスタンを歩き通すとは。
イスラム圏では、有力者の紹介状を持っている客人は最大限にもてなし、食事と寝床を提供するという習慣があるのだそうです。
しかし実際には、タリバンが暴挙を尽くした後のアフガニスタンの村は殆どを焼き払われ、男は殺され、客人をもてなす余裕など何処にもない。
扉を叩いても居留守を決め込んだり、ようやく開けてもモスクへ行かせたり。
パンのかけらと薄いスープ、或いは腐った肉を提供するのがやっと。
ローリーは降りしきる雪の中で方向を誤ったり、凍った川の中に落ちたり、地雷が爆発するすぐ横を歩いたり、赤痢を患ったり、オベイ村の司令官から銃撃されたり、カリリ州知事の兵士から殴られたりと、文字通り命からがらの旅をするのです。
しかも途中から、大きな犬がお供となる。
実は私は、表題の「犬と歩く」に惹かれてこの本を読んだのですが、私が思い描いたような、犬と人間が信頼し合い、助け合いながら旅するような話ではまるでありませんでした。
65㎏もある大きなアフガン・マスティフ、人間に耳を切り落とされ、歯を叩き割られた用済みの老いぼれ犬。
ある村でこの犬と出会ったローリーは見捨てることもできず引き取り、15世紀末にアフガン一帯を征服した皇帝バーブルから名前をつけるのです。
このムガール帝国を築いた皇帝バーブルの回想記が、この本には度々引用されています。
イスラム圏では犬は不浄のものとされ、忌み嫌われている。
生まれて以来、可愛がってもらったことも肉を与えられたこともないバーブルはローリーに懐くこともなく、歩くのも時に嫌がる。
65㎏の大型犬を引きずらなければならず、犬が一緒ということで宿泊を断られたりと、ローリーにとっては文字通りお荷物でしかないのです。
大体、自分の食料でさえ覚束ないのに、65㎏の大型犬の食料をどうしたのだろう?と心配になる。
それでもローリーはこの犬と共に、下痢でズボンを汚しながら歩き続けるのです。
旅のお終いの頃のローリーの状態。
”私の腹は完全に行かれてしまい、激しい空咳にも苦しんでいた。ジャケットのファスナーは引っかかり、片方の靴の紐はちぎれ、リュックに被せていたビニールのコメ袋はぼろぼろになっていた。南京虫に喰われ、汗疹ができ、爪は伸び、髪は4ヶ月も切っていなかった。ダハニ・シアル・サンダの司令官の家の玄関で、できそこないの顎髭と殴られて痣になった目と水ぶくれのできた唇と皮の剥けた鼻を汚い手で撫で、三週間も洗っていない自分の服を見た。なぜ司令官がすぐには自分の家の床で私を眠らせたくなかったかは、理解できた。”
そして400ページ近い本書の、最後の1ページで私は落涙する。
アフガニスタンの徒歩旅行記を読む人がそうそういるとは思えないのでネタバレします。
一足先に故郷に戻ったローリーは、バーブルが飛行機に乗る予定の前日に死んだという電話を受け取るのです。
生まれてこの方パンだけを食べて来たバーブルは、誰かに与えられたあばら肉を喜んで食べ、骨の尖ったかけらに胃を切り裂かれて死んだのだと。
ようやくローリーの前で、腹をくすぐって貰おうと仰向けに寝転ぶようになったバーブルが。
そしてこの本は、バーブルの為に書かれたのだということが、悲しいほどに伝わりました。
原題は「The Places in Between」。