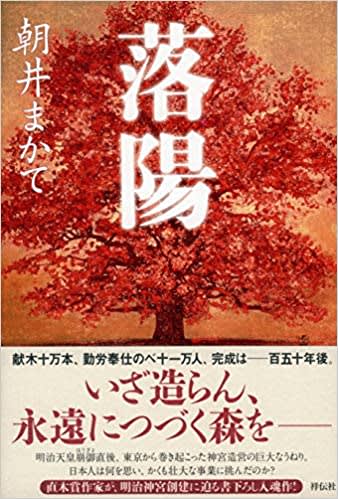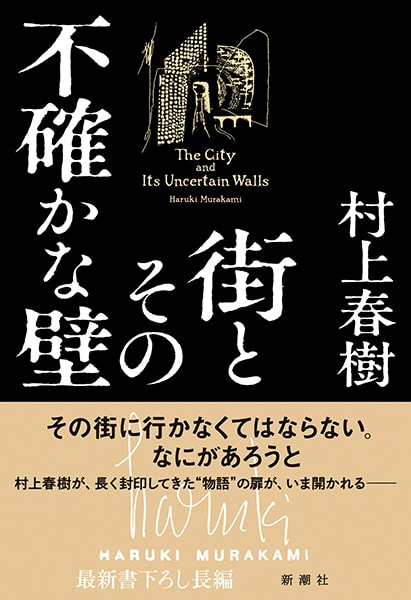現在公開されている映画の原作本、直木賞受賞作。
宮沢賢治の生涯を、父・政次郎の目を通して描いたもの。
宮沢賢治は花巻の裕福な質屋の長男として生まれたが、商売を継ぐ気は更々なく、上の学校に進み、理想を追い求める。父は勤勉な商人であり地元の名士であったが、そんな息子にどう接するべきか迷いながらも否定することなく、あたたかい目で見守る。しかし賢治の作品は、中々世に認められず…
明治時代の家父長制度全盛期、しかも東北という地方に、こんな過保護な父親がいたとは。
何しろ賢治が子供の頃に赤痢で入院すると、医者の制止も聞かず、病院に泊まり込んで看病するのです。
そんな父親に育てられた賢治は、夢を追い求める青年にと成長するのですが、しかし純粋に文学の道を進んでいたわけではない。
イリジウム採掘だの、製飴工場だの、人造宝石だの、富と名声を求めて様々な分野に手を出し(出そうとし)、挙句の果ては宗教にものめり込む。その間、黙って仕送りをして賢治を支え続けていたのは、父親だったのでした。賢治は最後に学校の教師をしながら「文章を書くこと」を天職として見つけたものの、世間には中々認めて貰えず、そのうち結核に倒れてしまう。享年37という若さ。
「虔十公園林」「セロ弾きのゴーシュ」「なめとこ山の熊」など、子供の頃大好きで何度も読み返しました。
「よだかの星」「オツベルと象」「グスコーブドリの伝記」などはあまりに悲しくて好きになれないのに、いつまでも心に残りました。
こんな悲しく美しい話を造った人は、どんな人だったのだろうかと長いこと思っていました。
賢治が中々自分の夢を定められず迷走するさまは他人が見てもイライラするほどなのに、この父親はよく黙って応援し続けたものだと思います。
政次郎の息子愛、家族愛が伝わる作品であり、この父この家族あっての、愛に溢れる宮沢賢治文学だったのですね。
宮沢賢治の生涯を、父・政次郎の目を通して描いたもの。
宮沢賢治は花巻の裕福な質屋の長男として生まれたが、商売を継ぐ気は更々なく、上の学校に進み、理想を追い求める。父は勤勉な商人であり地元の名士であったが、そんな息子にどう接するべきか迷いながらも否定することなく、あたたかい目で見守る。しかし賢治の作品は、中々世に認められず…
明治時代の家父長制度全盛期、しかも東北という地方に、こんな過保護な父親がいたとは。
何しろ賢治が子供の頃に赤痢で入院すると、医者の制止も聞かず、病院に泊まり込んで看病するのです。
そんな父親に育てられた賢治は、夢を追い求める青年にと成長するのですが、しかし純粋に文学の道を進んでいたわけではない。
イリジウム採掘だの、製飴工場だの、人造宝石だの、富と名声を求めて様々な分野に手を出し(出そうとし)、挙句の果ては宗教にものめり込む。その間、黙って仕送りをして賢治を支え続けていたのは、父親だったのでした。賢治は最後に学校の教師をしながら「文章を書くこと」を天職として見つけたものの、世間には中々認めて貰えず、そのうち結核に倒れてしまう。享年37という若さ。
「虔十公園林」「セロ弾きのゴーシュ」「なめとこ山の熊」など、子供の頃大好きで何度も読み返しました。
「よだかの星」「オツベルと象」「グスコーブドリの伝記」などはあまりに悲しくて好きになれないのに、いつまでも心に残りました。
こんな悲しく美しい話を造った人は、どんな人だったのだろうかと長いこと思っていました。
賢治が中々自分の夢を定められず迷走するさまは他人が見てもイライラするほどなのに、この父親はよく黙って応援し続けたものだと思います。
政次郎の息子愛、家族愛が伝わる作品であり、この父この家族あっての、愛に溢れる宮沢賢治文学だったのですね。