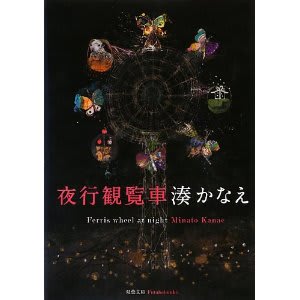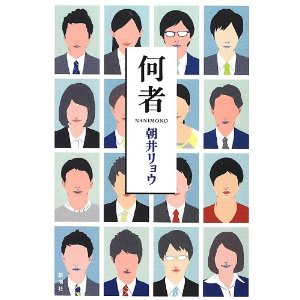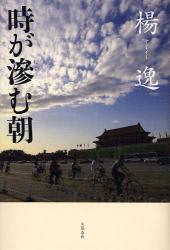実に贅沢な本です。
B5版の横型のような変形サイズで、殆ど全ページに写真が載っているのです。
大正期から戦後までの軽井沢の様子、朝吹家の豪華なポートレート。
皇室、華族、財界、政界、各方面の著名な人物との華麗なる交流。
「私の東京物語」と似ていますが、こちらの方が著者の子ども時代の思い出が
よりみずみずしく、郷愁を込めて書かれているような気がします。
そこに描かれる何と華やかな世界!
日常的に行われたという、樅の木の下の、白いクロスをかけたテーブルでのお茶会。
女中たちはイギリス製のメイドの制服を着て白いエプロンをかけ、
「マミー」(著者の母親)はオーガンジーのロングドレス、西洋の婦人は帽子とパラソル。
特に印象的だった子どもの為の「インディアン・パーティ」というのは、
”下の兄たち二人がアメリカ製の子供用インディアンの服を着て、七色の羽飾りを
つけ、パイプを持ってドラムを叩き、インディアンの三角のテントを張った”もの。
”ハリウッド映画のインディアンの話が現実に、
樅の樹々は遠いアメリカ大陸の森林に変じる。”
というのですから…
このインィアン・パーティが行われたのは、実に大正12年、関東大震災の一か月前。
そして、乗馬にテニスにゴルフにパーティに興じる毎日。
しかし、華美な生活の裏には当然、厳しい現実もあって、
大正時代のこの頃には軽井沢には水道はまだ引かれておらず、
別荘には当時”水汲みばあさん”と呼ばれた、棒縞の木綿の着物を着、
手拭を姐さんかぶりにした女の人たちが、天秤棒の前後に桶を吊るし、
小川から水を、一日に何度も何度も運んだのだそうです。
それで飲料水からお風呂の水からすべて運んでいたというのですから。
幸せだった子ども時代の思い出から一変して日本は戦争に突入。
東京から軽井沢に疎開した著者は、冬の寒さと食糧不足に苦しむことになります。
多感な思春期を経て、財閥の御曹司と結婚、離婚、そして再婚。
私としては一番知りたいその辺りのことが殆ど何の説明もないのが、とても残念。
身重の体で焼け野原の東京から軽井沢に脱出し、
食料不足の中で赤ちゃんをなんとか産んだことだけがさらりと書いてあります。
著者としては、幸せではないことについては
多くを語りたくなかったのかも知れません。
この本の中で私が一番共感を持ったのは、この部分でした。
”(家庭教師の)ミス・リーは子供たちを膝もとに寄せて、イギリスの本を沢山読んでくれた。
私はディキンズの、蛇と戦う勇敢なマングース、リキティキタヴィの話や、
ピーター・ラビット一家の話が好きだった。
「昔、昔、四匹の子ウサギがいました。その名前はフロップシー、モプシー、
コットン・テール、とピーターでした。」(中略)
イギリスの動物たちは、軽井沢の自然にぴったりしていた。
樅の大木や、小川の畔や、灌木の茂みから、今にも空色のジャケットを着た
ピーター・ラビットが飛び出してきそうだった。
ハリネズミのミセス・ティギ―・ウィンクルもそのあたりにいるかもしれない。”
子供の頃にワクワクして読んだ童話、
大人になってもそれを懐かしく思いだす気持ちだけは
富豪も庶民も変わらないのかも知れませんね。
私もピーター・ラビットの冒頭のこの文は
今でも暗記しております。
「私の軽井沢物語」 http://tinyurl.com/m7krqv3