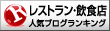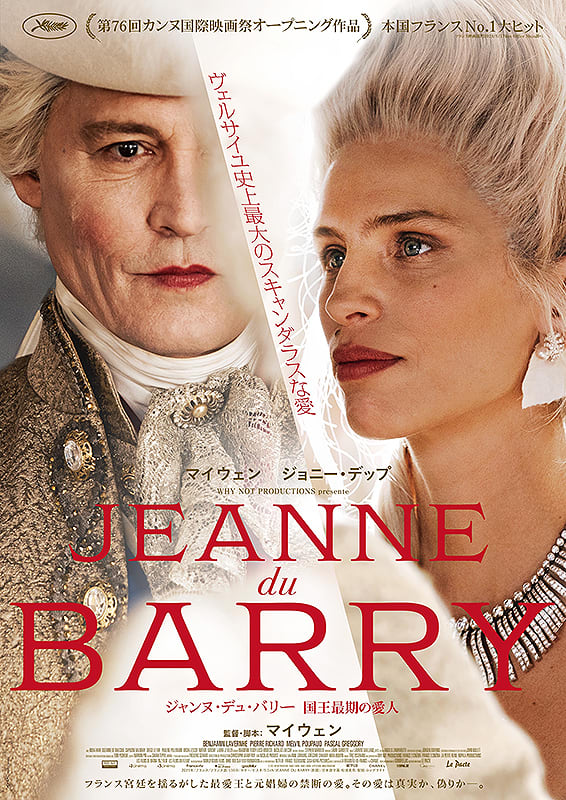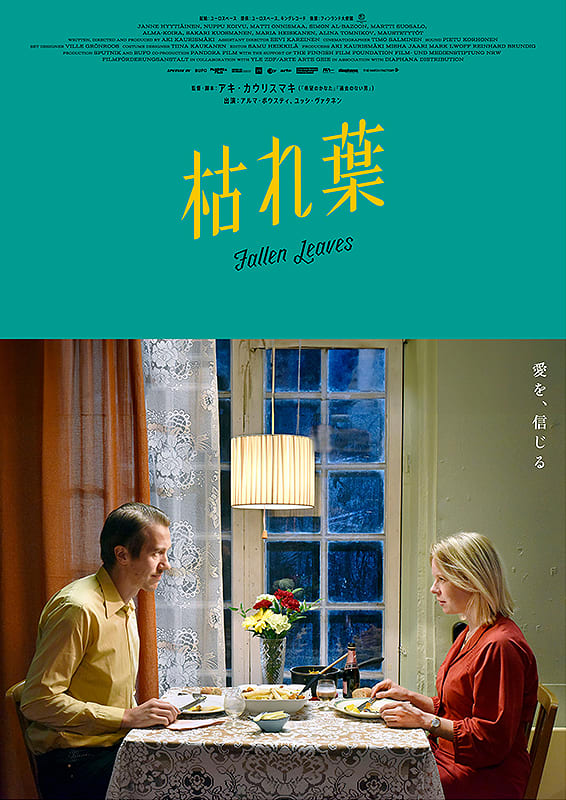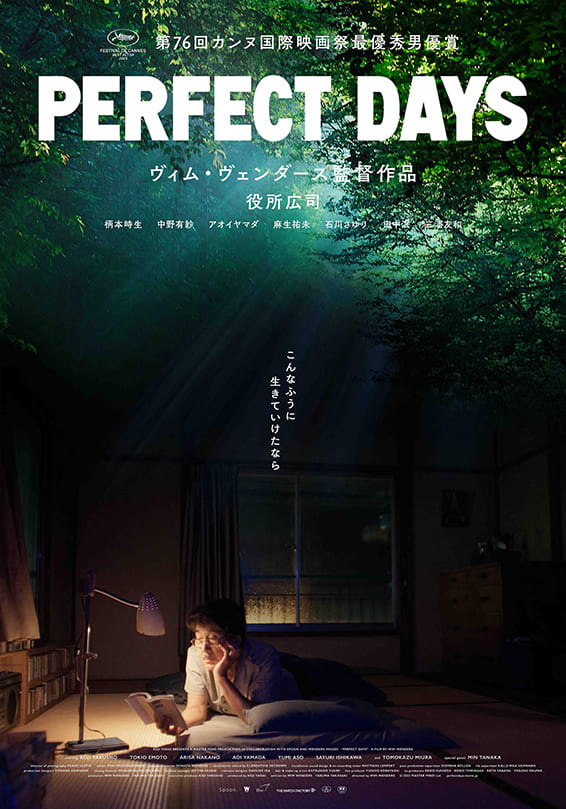FIFAランキングで世界最下位の米領サモアのサッカーチーム、2001年にはW杯予選史上最悪の0−31でオーストラリアに大敗、その後も1ゴールすらできず10年以上が経過。次の予選を4週間後に控えた所に、アメリカを追われたコーチ、トーマス(マイケル・ファスベンダー)がやってきて、最弱チームの立て直しを図る。
「ジョジョ・ラビット」のタイカ・ワイティティ監督というので楽しみにしていたら、いきなり画面に出て来ました。
この人はニュージーランドの先住民マオリの血を引いているのだそうで、だからこの独特なポリネシアン気質に詳しいのでしょう。
必死に鍛え上げようとする鬼コーチと、暖簾に腕押し、人生は頑張ることより楽しむことが何より大事という選手たち。
なんともすれ違う様が面白い。

トランスジェンダーの選手が結構重要な役割で出て来て、近年の映画界のLGBTに対する忖度かと思いきや、「ファファフィネ(第3の性)」と呼ばれるその存在は、あちらでは何千年も続く文化の一部なのだそうです。
そして、往年の名作「ベストキッド」のオマージュがあちこちに出て来て笑えました。
ユニフォームに「MIYAGI」の名前が入っていたり、ゴールキーパーがあの鶴のようなポーズをとってみたり、
「Next Goal Wins」とはまた分かりやすいタイトルだと思ったら、負けているチームが休み時間が終わる直前にゴールを入れたら逆転勝利する、子供たちのゲームのことなのだそうです。