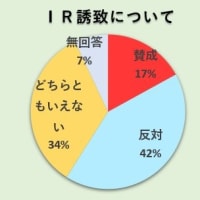映画「母(かあ)べえ」を観た。山田洋次監督が次のように語っている。「でき上がって最初の試写をみたとき、『おー、こんな映画になったか』という思いがわいてきました。母と娘たちのささやかな話を描いたつもりが、完成してみると別のにおいがたちこめていたと言いますか、お茶の間の向こうに戦争が見えている。僕たちが描きたかったのは、恐ろしい戦争の時代だったんだ、と気付かされたのです」(「しんぶん赤旗」日曜版2008年1月20日号)―天皇制国家の15年戦争下の庶民の様子をただ淡々と描く。庶民のなかには、「一億一心」とならなかった者もいる。伊丹万作さんのいう「だまされた」人びとが大部分だが、だまされない人びともいる。そのような人びとのささやかな話が、自ずと天皇制国家の恐ろしい戦争の時代を静かに告発している。山田洋次監督・脚本のまさに円熟の境地といってよいだろう。
野上家では、ドイツ文学者の夫・滋(坂東三津五郎)と妻・佳代(吉永小百合)、そしてしっかり者の長女・初子(志田未来)と天真爛漫な次女・照美(佐藤未来)の4人が貧しくも明るく暮らしていた。お互いを「父(とう)べえ」「母べえ」「初べえ」「照べえ」と呼び合う仲睦まじい家族だったが、1940年(昭和15年)2月、滋が治安維持法違反で検挙されてから苦難の日々が始まった。そんな折、滋の教え子・山崎徹(浅野忠信)が訪ねてくる。それ以降、徹は一家の手助けをするのだった…。
原作は、黒澤明監督作品のスクリプター(記録係)を長く務めた野上照代さんの自伝的小説『父へのレクイエム』。山田洋次、平松恵美子の脚本は、素材を豊かに発展させ、すっかり「だまされた」ひと、少しだけ「だまされた」ひと、「治安維持法」に最期まで歯向かうひと、途中で転向するひと、肩を寄せ合って耐える人びとなど多様な庶民の生活をリアリティ豊かに描く。
初めから特定のテーマを主張するために、映画の各場面を構成するのではなく、戦時下の多様な庶民の多様な生活を再現するなかで、もっとも主張しなければならいテーマが映画全体から見えてくる。山田監督は、「素材を詳細にわがものとし、素材のさまざまな発展諸形態を分析し、それらの発展諸形態の内的紐帯をさぐりだす」(マルクス『資本論Ⅰ』第二版へのあとがき)ことによって、全体を一つの芸術作品に仕上げた。
「今も戦争はなくならず、イラクやアフガンで毎日死者が出ていますね。その人たちの人生や生活について、みんなが想像力を磨いて思いをはせれば、戦争はなくなるのではないか。そんなふうに考えながら映画をつくりました」と山田監督。体が弱くて徴兵を免れていた山崎にもついに赤紙が・・。もう会えないの?と問う母べえに、「戦地にいくのだから、(死ぬ)覚悟はできています」「何が覚悟よ、偉そうに。なんで山ちゃんが、そんな覚悟をしなくちゃいけないの」監督がせりふを8回書き換えた見せ場である(「しんぶん赤旗」2007年12月21日)。
国外で戦争をやるとき、国内でも日本国民を対象に「戦争」が必要である。「反戦平和」の動きが絶対にあってはならないからである。戦争と自由・民主主義は絶対に両立しない。「治安維持法」による逮捕、送検者は数10万人にのぼり、言語に絶する残虐な拷問、長期拘留、苛酷な懲役が通例のこととしておこなわれた。
『世界』2008年2月号で、原作者の野上さんと対談した山田監督は、最後のほうで次のように締めくくっている。「『父べえ』たちを非人道的に迫害した、その罪の責任を誰もとろうとしないし、追及もしない。優しい『母べえ』は、戦後何十年もそれを胸の中に、納得のできないこととして、抱き続けていた、というのが、まあ、この作品のメッセージでしょうか」(「『母べえ』の時代を語る」『世界』2008・2)
アメリカ兵が上陸したら一人一殺といって竹槍訓練をした当時の人たちにくらべて、私たち日本人ははるかに賢くなったといえるのか。アメリカ軍が上陸してくるということを想像すれば、もうこの国は敗けたということではないのか。空自はイラクの人びとを殺す米軍に物資を輸送し、海自は米軍の戦闘機に給油している。私たちは、想像力を磨かなければならない。
野上家では、ドイツ文学者の夫・滋(坂東三津五郎)と妻・佳代(吉永小百合)、そしてしっかり者の長女・初子(志田未来)と天真爛漫な次女・照美(佐藤未来)の4人が貧しくも明るく暮らしていた。お互いを「父(とう)べえ」「母べえ」「初べえ」「照べえ」と呼び合う仲睦まじい家族だったが、1940年(昭和15年)2月、滋が治安維持法違反で検挙されてから苦難の日々が始まった。そんな折、滋の教え子・山崎徹(浅野忠信)が訪ねてくる。それ以降、徹は一家の手助けをするのだった…。
原作は、黒澤明監督作品のスクリプター(記録係)を長く務めた野上照代さんの自伝的小説『父へのレクイエム』。山田洋次、平松恵美子の脚本は、素材を豊かに発展させ、すっかり「だまされた」ひと、少しだけ「だまされた」ひと、「治安維持法」に最期まで歯向かうひと、途中で転向するひと、肩を寄せ合って耐える人びとなど多様な庶民の生活をリアリティ豊かに描く。
初めから特定のテーマを主張するために、映画の各場面を構成するのではなく、戦時下の多様な庶民の多様な生活を再現するなかで、もっとも主張しなければならいテーマが映画全体から見えてくる。山田監督は、「素材を詳細にわがものとし、素材のさまざまな発展諸形態を分析し、それらの発展諸形態の内的紐帯をさぐりだす」(マルクス『資本論Ⅰ』第二版へのあとがき)ことによって、全体を一つの芸術作品に仕上げた。
「今も戦争はなくならず、イラクやアフガンで毎日死者が出ていますね。その人たちの人生や生活について、みんなが想像力を磨いて思いをはせれば、戦争はなくなるのではないか。そんなふうに考えながら映画をつくりました」と山田監督。体が弱くて徴兵を免れていた山崎にもついに赤紙が・・。もう会えないの?と問う母べえに、「戦地にいくのだから、(死ぬ)覚悟はできています」「何が覚悟よ、偉そうに。なんで山ちゃんが、そんな覚悟をしなくちゃいけないの」監督がせりふを8回書き換えた見せ場である(「しんぶん赤旗」2007年12月21日)。
国外で戦争をやるとき、国内でも日本国民を対象に「戦争」が必要である。「反戦平和」の動きが絶対にあってはならないからである。戦争と自由・民主主義は絶対に両立しない。「治安維持法」による逮捕、送検者は数10万人にのぼり、言語に絶する残虐な拷問、長期拘留、苛酷な懲役が通例のこととしておこなわれた。
『世界』2008年2月号で、原作者の野上さんと対談した山田監督は、最後のほうで次のように締めくくっている。「『父べえ』たちを非人道的に迫害した、その罪の責任を誰もとろうとしないし、追及もしない。優しい『母べえ』は、戦後何十年もそれを胸の中に、納得のできないこととして、抱き続けていた、というのが、まあ、この作品のメッセージでしょうか」(「『母べえ』の時代を語る」『世界』2008・2)
アメリカ兵が上陸したら一人一殺といって竹槍訓練をした当時の人たちにくらべて、私たち日本人ははるかに賢くなったといえるのか。アメリカ軍が上陸してくるということを想像すれば、もうこの国は敗けたということではないのか。空自はイラクの人びとを殺す米軍に物資を輸送し、海自は米軍の戦闘機に給油している。私たちは、想像力を磨かなければならない。