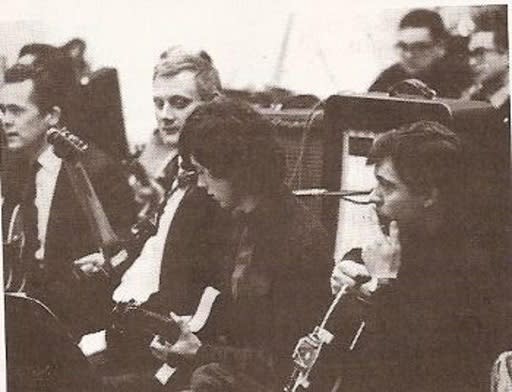エレクトリック・ギターに限ったことではないのだが、アメリカのものづくりを見てみると、手仕事をよしとする中世から続くクラフトマンシップはヨーロッパからの移民によって受け継がれていて、リッケンバッカーやグレッチといったメーカーやディアンジェリコのようなルシアーにその精神を感じることができる。その一方で機械にできることは機械に任せ、規格を揃え、シンプルな構造で職人芸を必要とせず、効率的に誰でも組み上げることができるという生産システムが発達し、それによって誰もが安く製品を手に入れることができるという「大量生産、大量消費」が実現していくというわけだが、こうしたシステムの中で生まれたのがダンエレクトロということになるだろう。
それでは蛇足ながらギブソンやフェンダーはどうなのかといえば、廉価なものから一流クラフトマンによるカスタムメイドまでを幅広く取り揃え、大手メーカーとしてあらゆるニーズに応えている。
こんなふうにメーカーの立ち位置を見てみることで、それぞれの特徴が浮かび上がってくるのを確認したところで本題に入ることにする。
ダンエレクトロの製品といえば、レトロでかわいらしいデザインが「売り」ということになっている。現在から見れば、1969年にいったん幕を下ろしたダンエレクトロに対してレトロという表現は妥当であるだろうし、1999年頃にダンエレクトロが復活したのも、当時のギター業界のレトロスペクティブな流行の中で起きたことであるわけだ。しかし、忘れてはいけないことは、1947年に、ということはつまり、フェンダーと同じ年にアンプメーカーとして創業したダンエレクトロが最初のエレクトリック・ギターを開発、製品化したのは1954年のことであり、このときにはギブソンのレスポールもフェンダーのストラトキャスターもすでに世に出ていたということだ。
現在にあってもエレクトリック・ギターを代表するモデルが未だにレスポールとストラトキャスターであることを踏まえれば、エレクトリック・ギターの歴史は1954年頃には一つのピークをすでに迎えていたといっても過言ではないわけで、ダンエレクトロはそのピークの後にギターの開発・製造を始めた後発のメーカーということになるのである。
ダンエレクトロにとって幸いだったのは、アンプメーカーとしてすでにシアーズと取引があり、その販路を持っていたこと、そしてシアーズにはジョセフ・フィッシャーという優秀なバイヤーがいたことだ。また、創業者のネイサン・ダニエルがジョン・ディアンジェリコのようなルシアーと友人関係にあったことと、そして法螺吹きではあるが(であるがゆえに、というべきか)豊かな発想力を備えた発明家気質のスタジオ・ミュージシャンであるヴィンセント・ベルと協力関係を築けたことも大きい。
ダンエレクトロはエレクトリック・ギターの後発メーカーとして新たにマーケティング戦略をしなければならなかったが、それはつまり、プロミュージシャンではなく、初心者や子供をターゲットに廉価なギターを販売するということであった。シアーズではすでにシルバートーンというブランド名で廉価なギターを販売していたが、そこに製品を供給していたメーカーはハーモニーであり、ケイであり、日本のテスコなどであった。当時シルバートーンのギターで一番売れていたものはハーモニー製のアコースティック・ギターでH605というモデルであった。ジョセフ・フィッシャーはネイサン・ダニエルにH605と同じように初心者向けの低価格のエレクトリック・ギターをつくることはできないかと尋ね、それを引き受けたネイサンが生み出したもの、それがアンプを内蔵したケースにギターを収納することができるという発想の「アンプ・イン・ケース」モデルであった。

このほかにもニッチを狙ったモデルの製品化がなされた。通常のギターを1オクターブ低くした6弦ベース、通常のギターと同じサイズの15フレットまでしかない4弦ベース、マンドリンの音域をカバーした31フレットのギター(ギターリン)などなど。その中で、ヴィンセント・ベルと協力しながら開発した12弦ギター「ベルズーキ」(ブズーキをモチーフにしたティアドロップ型のボディを持つ)や独自に開発したブリッジで弦を点ではなく面で支えることでシタールに似た倍音成分を発生させ、それを電気的に増幅することができる「エレクトリック・シタール」はダンエレクトロを象徴するモデルとなっている。
ダンエレクトロはともすれば奇妙なデザインだったり、使い道が良くわからなかったり、そのようなギターを製造した変態的なメーカーとされることも多いのだが、実際に製造に関わった人たちはそんな思いで製造したわけではなかったはずだし、他のメーカーが考えたこともない、ギターという楽器の新たな可能性を追求した結果、そうなってしまったというだけのことである。
例えばメゾナイトをギターのトップ材に使用するということについても、このことを単にコストカットのためとしか見ないのはあまりに一面的な見方であって、メゾナイトを採用した背景にあるのは、ナショナルがエアラインやスプロというブランドで製造したレゾグラスをボディの材にしたギターや、マキャフェリのようにプラスティックをボディの材にしたギターと同様、当時の新素材を使ってつくられたギターであるという側面があったことに気がつけば、ダンエレクトロはむしろモダンで未来志向的であろうとしていたことがおのずと理解されるだろう。
「だのじゃん」的にはダンエレクトロが潜在的に持っている可能性を未来へ向けて開いていくことがその商標権を持っている企業の義務だと思うわけで、モズライトのコピーモデルなどをつくっている場合ではないだろうと思うわけで。
それでは蛇足ながらギブソンやフェンダーはどうなのかといえば、廉価なものから一流クラフトマンによるカスタムメイドまでを幅広く取り揃え、大手メーカーとしてあらゆるニーズに応えている。
こんなふうにメーカーの立ち位置を見てみることで、それぞれの特徴が浮かび上がってくるのを確認したところで本題に入ることにする。
ダンエレクトロの製品といえば、レトロでかわいらしいデザインが「売り」ということになっている。現在から見れば、1969年にいったん幕を下ろしたダンエレクトロに対してレトロという表現は妥当であるだろうし、1999年頃にダンエレクトロが復活したのも、当時のギター業界のレトロスペクティブな流行の中で起きたことであるわけだ。しかし、忘れてはいけないことは、1947年に、ということはつまり、フェンダーと同じ年にアンプメーカーとして創業したダンエレクトロが最初のエレクトリック・ギターを開発、製品化したのは1954年のことであり、このときにはギブソンのレスポールもフェンダーのストラトキャスターもすでに世に出ていたということだ。
現在にあってもエレクトリック・ギターを代表するモデルが未だにレスポールとストラトキャスターであることを踏まえれば、エレクトリック・ギターの歴史は1954年頃には一つのピークをすでに迎えていたといっても過言ではないわけで、ダンエレクトロはそのピークの後にギターの開発・製造を始めた後発のメーカーということになるのである。
ダンエレクトロにとって幸いだったのは、アンプメーカーとしてすでにシアーズと取引があり、その販路を持っていたこと、そしてシアーズにはジョセフ・フィッシャーという優秀なバイヤーがいたことだ。また、創業者のネイサン・ダニエルがジョン・ディアンジェリコのようなルシアーと友人関係にあったことと、そして法螺吹きではあるが(であるがゆえに、というべきか)豊かな発想力を備えた発明家気質のスタジオ・ミュージシャンであるヴィンセント・ベルと協力関係を築けたことも大きい。
ダンエレクトロはエレクトリック・ギターの後発メーカーとして新たにマーケティング戦略をしなければならなかったが、それはつまり、プロミュージシャンではなく、初心者や子供をターゲットに廉価なギターを販売するということであった。シアーズではすでにシルバートーンというブランド名で廉価なギターを販売していたが、そこに製品を供給していたメーカーはハーモニーであり、ケイであり、日本のテスコなどであった。当時シルバートーンのギターで一番売れていたものはハーモニー製のアコースティック・ギターでH605というモデルであった。ジョセフ・フィッシャーはネイサン・ダニエルにH605と同じように初心者向けの低価格のエレクトリック・ギターをつくることはできないかと尋ね、それを引き受けたネイサンが生み出したもの、それがアンプを内蔵したケースにギターを収納することができるという発想の「アンプ・イン・ケース」モデルであった。

このほかにもニッチを狙ったモデルの製品化がなされた。通常のギターを1オクターブ低くした6弦ベース、通常のギターと同じサイズの15フレットまでしかない4弦ベース、マンドリンの音域をカバーした31フレットのギター(ギターリン)などなど。その中で、ヴィンセント・ベルと協力しながら開発した12弦ギター「ベルズーキ」(ブズーキをモチーフにしたティアドロップ型のボディを持つ)や独自に開発したブリッジで弦を点ではなく面で支えることでシタールに似た倍音成分を発生させ、それを電気的に増幅することができる「エレクトリック・シタール」はダンエレクトロを象徴するモデルとなっている。
ダンエレクトロはともすれば奇妙なデザインだったり、使い道が良くわからなかったり、そのようなギターを製造した変態的なメーカーとされることも多いのだが、実際に製造に関わった人たちはそんな思いで製造したわけではなかったはずだし、他のメーカーが考えたこともない、ギターという楽器の新たな可能性を追求した結果、そうなってしまったというだけのことである。
例えばメゾナイトをギターのトップ材に使用するということについても、このことを単にコストカットのためとしか見ないのはあまりに一面的な見方であって、メゾナイトを採用した背景にあるのは、ナショナルがエアラインやスプロというブランドで製造したレゾグラスをボディの材にしたギターや、マキャフェリのようにプラスティックをボディの材にしたギターと同様、当時の新素材を使ってつくられたギターであるという側面があったことに気がつけば、ダンエレクトロはむしろモダンで未来志向的であろうとしていたことがおのずと理解されるだろう。
「だのじゃん」的にはダンエレクトロが潜在的に持っている可能性を未来へ向けて開いていくことがその商標権を持っている企業の義務だと思うわけで、モズライトのコピーモデルなどをつくっている場合ではないだろうと思うわけで。