//////////校正7回目//////////
〇P.78(原文P.92): 「エディット・ピアフが彼のアドバイスを聞きに来たときも、こんな感じだったのだろう」とある。ここはJean Wienerが自分の口ではっきりと「かつてエディット・ピアフも君と同じように僕のところに突然来てそんな相談をしていったんだよ」とIl m'a dit que...となっていてこれは彼自身の言葉で、ここを勝手にBarbaraの推量のように訳してはいけない。Jean Wienerはla Fontaine des Quatre Saisonsを紹介しただけでなく、ピアフの名を挙げ、君もいずれきっと本格的なプロになれるよ、僕は確信してるよ、と言ってくれたのだ。この励ましは大きい。その世界をめざすBarbaraには大きな希望と自信に繋がった筈だ。「こんな感じだったのだろう」などという訳を一体どこからひねり出されたのか理解に苦しむ。
●私は視力に弱点があり校正作業には全く向かない。プロの校正者のように、最初から厳密に読んで赤ペンを入れているわけではない。この原本は友人のJeanneが十数年前、発売と同時に私にプレゼントしてくれた。その時に読んだ内容や、訳出した記憶を思い出しながら、ペラペラとペイジをめくり、目で文字を追う。記憶と符合しない内容の箇所で立ち止まり、取り出し検討を加え、間違いと判断した部分を校正しているに過ぎない。人物紹介に校正を付記するのは、人物ごとにペラペラとペイジをめくることが多いからだ。従って校正のペイジがあちこち飛ぶのはそのためだ。人物との関係は重要なので、人物紹介はこれからも独自に書き足していくつもりでいる。
ただペラペラめくっていても、人物関係以外に、ごくごく単純なミスに気づく時もある。形容詞のかけ方、つまり単なる修飾、被修飾の関係が、おかしいと思うこともたまにある。私は昔短詩型文学の世界で、言語論を書いていた時期があるので、修飾・被修飾の関係には、ことのほか敏感になってしまう。以下は今までに気づいた其の辺の間違いを集めてみたものである。
〇P.97. 「9時からの出番」は9時半から
〇P.137. 「木曜日のシャンソン」は火曜日のシャンソン
(バカバカしい話だがこんなうっかりミスでも原書を所有していなければ誰も間違いに気づけない。間違いにはこのような単純な校正不足の他に、仏語読解ミス、Barbaraに関する知識不足からくる内容取り違え、また「訳者解題」等に於いては資料を厳選せずに丸写しすることによる検証不足に起因するものなどがある)
〇P.131 (原文P.153) 「私の生きがいであるピアノも、シャンソンも、観衆にも怒り狂う」となっている。がIl va se battre contre un piano, contre des chansons, contre un piblique peu nombreux, mais qui constitue deja ma raison de vivre. 「私の生きがいである」は観衆すなわちファンにだけかけるのが正しい。つまり下線部はun publiqueのみにかかるのである。更に翻訳では太字部分が抜け落ちている。まだ少ししかいなかったとは言え、既に私の生きがいにさえなっていたファンたちに対しても、という訳が正しい。
〇P.86 固有名詞でもないune brasserieがそのままブラッスリーと訳されていた。たとえば、ピアノとかブランディ、アルコールなどはカタカナにすればそのまま日本語として通用するが「ポルト・ド・ナミュールのブラスリーで待っていた」では、このブラスリーは固有名詞のように受け止められる可能性がある。フランス語にはその辺りを明快にするためにuneという不定冠詞がついている。「ポルト・ド・ナミュールにある(ある)カフェレストランで待っていた」とすれば、読者はよりたやすくイメージ創造することができる。より正確な翻訳とは、そういった言語的配慮を言う。
●校正というのは決して楽しい作業ではない。苦痛である。せっかく知り合えた翻訳者への敬意や翻訳者のプロの仕事に、クレイムをつけているようで、気分は良くない。最悪である。しかしこれはBarbara自身の手になる、彼女の唯一の貴重な自書である。しかもその間違いのほとんどはBruxellesにしか気づくことができない。PLANETE BARBARAは世界の人たちにBARBARAをより広くより正しく知っていただくためにこの世に存在する。気分が悪いからといってこの作業から逃げ出せば、BruxellesはもはやBruxellesではなくなってしまう。その人にしかできないことはその人がやるしかない。と私の中のBarbaraが言う。書くということは快不快でする行為ではない。使命感につき動かされる行為なのだと。
昨晩から今日の午前中にかけて読んだ漫画にこういうセリフが出てきた。
「私は写真を撮るために山に登ってたわ。でも祐介は山が好きで...その好きな山だからこそ写真を撮っていたんだわ。ひとを好きになるのと同じように、被写体に愛が必要だって...」
(山靴と疾走れ!! Vol.3 P.113より)
ペラペラと読みながらこの訳本には何故これほど誤訳が多いのか、敵を多く作る結果しか生まない、誰も望まない校正を何故続けるのか?毎日苦悩の中で自問を続けてきた。この漫画で解答がでた。Barbaraが好きでBarbara研究の原稿を長年書き続けてきた者と、本を出版するためにテーマ素材としてBarbaraの「Il etait un piano noir...」を選んだ者とが、この翻訳書を介して出会ってしまったからだ。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
Rappelle-toi Barbara, hors-serie d’On connait la musique ?
一番長時間のBarbaraの特番。
Daphnéの歌声が長々と続くので
(Daphnéはどう考えてもBarbara歌手ではない)、
さすがにBruxellesもくたびれて未だに最後まで聞いていない。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
・・・・・追記:2013年7月4日・・・・・
訳本P.53&P.54に1948年の初めにモガドール劇場のオーディションを受ける場面が出てくる。バルバラはLudwig van BeethovenのIn Questa Tomba Oscuraを歌う。
In questa tomba oscura(この暗い墓の中で)
Lachiami reposar(わたしを休ませてくれ)
Quando vivevo ingrata...(私が生きていた時に、不実な人よ・・・)
おかしな単語がある、ことに気づいた。あれれ。原本を見ると、同じになっている。これは原本のミスプリを間違いのまま丸写ししているのだ。私はこの部分は訳していないので今まで気づかなかった。
正しくはLasciami riposar; またQuando vivevo ingrataはQuando vivevo, ingrata,でなくてはならない。日本語訳から見てingrataの前にカンマが必要。Lachiami reposarはともに存在しないスペリングだ。Lasciami riposarならlet me reposeで意味が出る。
訳者が手を抜くならせめてプロの校正者の目を通して欲しい。
In Questa Tomba Oscura Cecilia Bartoli:
最新の画像[もっと見る]
-
 Barbara論の誕生 Junges Theater 番外
8年前
Barbara論の誕生 Junges Theater 番外
8年前
-
 Barbara論の誕生 Junges Theater 番外
8年前
Barbara論の誕生 Junges Theater 番外
8年前
-
 Barbara論の誕生 ゲッチンゲン(3)
8年前
Barbara論の誕生 ゲッチンゲン(3)
8年前
-
 Barbara論の誕生 ゲッチンゲン(2-2)
8年前
Barbara論の誕生 ゲッチンゲン(2-2)
8年前
-
 dans la cour des Invalides à Paris
9年前
dans la cour des Invalides à Paris
9年前
-
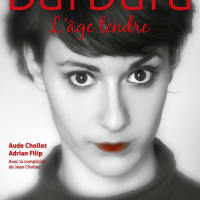 Barbara - Spectacle Musical
9年前
Barbara - Spectacle Musical
9年前
-
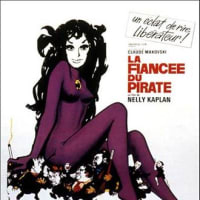 Moi je me balance +映画
9年前
Moi je me balance +映画
9年前
-
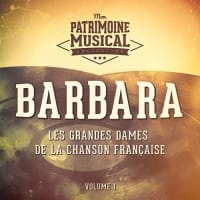 Les grandes dames de la chanson française, Vol. 1
9年前
Les grandes dames de la chanson française, Vol. 1
9年前
-
 Serge Reggiani - Le temps qui reste
9年前
Serge Reggiani - Le temps qui reste
9年前
-
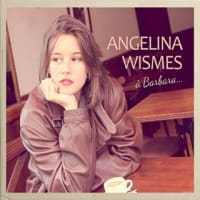 Angelina Wismes chante Barbara
9年前
Angelina Wismes chante Barbara
9年前









