
冬至のゆずが店先を賑わせたのもつかの間、もうクリスマスです。。
クリスマスとは何か、サンタクロースとは誰かを考えるために、葛野浩昭氏著「サンタクロースの大旅行」のご紹介を続けさせていただきます。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
ここに書かれている、〝ヨーロッパの異形の神々”たち、日本人にはなじみがないですね。
でも、これがどういう感じのものなのか感じることができないと、ヨーロッパについてなにも分からないままですね。
年内いっぱい、このことにかかりきりになるかもしれません。
*****
(引用ここから)
「聖ニコラウス祭」に登場する異形の神々
ヨーロッパにはキリスト教の聖人にちなんだ祭りが少なくありませんが、12月6日に行われる「聖ニコラウス祭」もその一つです。
ところが、中部ヨーロッパのカトリック圏の村々で今も行われている「聖ニコラウス祭」では、子供たちの守護聖人「聖ニコラウス」のイメージにはおよそ似つかわしくないような、実におどろおどろしい〝異形の神々″が姿を現します。
オーストリア中部の祭の様子を見てみましょう。
・・・
(福嶋正純著「魔物たちの夜・聖ニコラウス祭の習俗」より
カトリックの地方では、その前夜、赤い祭司帽を頭にし、司教の衣装を身に着けた「聖ニコラウス」が、恐ろしい姿のお伴を連れて、子供のいる家を訪れて、子供の行状を調べて回る風習がある。
キリストの救いの技を念じる「ロザリオの祈り」を空で唱えることができた子や、行儀の良い子には、リンゴ、くるみ、クッキーなどの褒美を与えるが、
お祈りがうまく出来なかった子や、素行の悪い子には、恐ろしい姿のお伴が、肩にした袋に入れて連れて帰るそぶりを見せたり、鞭で脅して手荒に説教を加えたりする。
聖者には、恐ろしい姿をしたクランプスがお伴として付き添っている。
このお伴は、黒いもじゃもじゃの毛皮を身にまとっていて、後ろには〝悪魔のしっぽ″をつけている。
頭に2本の角、お面からは炎のような舌が突き出ている。
クランプスが姿を見せると、子供は皆、不安と恐怖にからだがこわばる。
・・・
他にも、麦わらで身を包んだシャープが、激しく鞭を打ち鳴らしながら姿を現します。
また、冬・死者・太陽・魔術の神であり、ゲルマンの神々の長とされる「ヴォータン」も、白馬のハリボテに跨って登場します。
サンタクロースの裏側に生きる神々
オーストリア生まれの民俗学者ヨーゼフ・クライナーは、中部ヨーロッパの年間行事が11月中旬から翌年6月中旬までの7か月に集中していること、
そしてこの行事に、はっきりと3つのサイクルが認められることを指摘しています。
第1のサイクルは、クリスマスと正月を中心として、11月から1月6日までの祭で、これには「聖ニコラウス祭」(1月6日)の他に、聖マーチン祭、聖ルチア祭が含まれます。
第2のサイクルは、3月~4月あたりの、「復活祭」を中心とするもの。
第3のサイクルは、「5月祭」や「聖霊降臨祭」を含む5月の一連の行事祭です。
そして第1のサイクルが、中部ヨーロッパの古代ゲルマン民族の正月を、
第2のサイクルが、地中海文化の古代ローマの正月を、
そして第3のサイクルは、北欧のゲルマン文化の正月を中心にしていると言います。
「聖ニコラウス祭」を含む「第1のサイクル」の性格を最も端的に現しているのが、「12夜」あるいは「荒々しい夜」と呼ばれる正月前後の12日間です。
その中でも「クリスマスイブ」にあたる12月24日、大晦日、そしてギリシア正教の正月にあたる1月6日の3つの夜が最も危険で、絶対に外を出歩いてはいけないとされています。
この「12夜」、「荒々しい夜」は、年の変わり目ですから、時間の流れに裂け目ができ、それゆえこの世とあの世との境にも裂け目ができるとされます。
そこでこの夜には、死者たちの魂が、この世を荒らしにやって来て、闇の大空を駆け巡ると信じられたわけです。
この死者の魂たちの大群の先頭に立つのが、古代ゲルマンの神々の長である「ヴォータン」(この「ヴォータン」が英語の水曜日=wednesdayの語源)です。
「ヴォータン」は、北欧神話の中で第一の神「オーディン」としても有名です。
「オーディン」は死者の国との間を行き来する神であり、魔術の神です。
また彼は、太陽や月の運行を司る神でもあります。
この年の変わり目はすでに、12月6日の「聖ニコラウス祭」の時に始まっています。
というのも「聖ニコラウス祭」には「ヴォータン」「オーディン」が姿を現しているからです。
「聖ニコラウス祭」もまた、時の流れが割けて、この世とあの世の境が割ける、年の変わり目の季節儀礼だと考えるべきでしょう。
そして「ヴォータン」達と一緒に姿を現す「聖ニコラウス」も、年の変わり目にあの世から来訪する「来訪神」だと考えなけらばなりません。
それではどうして今の「クリスマス」と「正月」を中心とした季節が、年の変わり目と考えられてきたのでしょうか?
それは、この季節が「冬至」に当たるからです。
冬へと向かって太陽の力が徐々に弱まってゆき、そして「冬至」を境に再び力を盛り返す、この太陽の死と再生のシンボリズムが「冬至」に年の変わり目を設定させたのです。

ヨーロッパでは古くから、各地でさまざまな「冬至祭」が催されてきました。
帝政時代のローマでは、「太陽神ミトラ」を祀る「冬至祭」が行われました。
ミトラは「無敵の太陽」と呼ばれ、祭は12月25日に行われました。
また、種蒔きと農耕の神であるサトゥルヌスの祭も、12月17日~24日まで、どんちゃん騒ぎとして祝われました。
このサトゥルヌスは、英語の土曜日(saturday)の語源です。
イエス・キリストの誕生日が12月25日に定められたのは、「ミトラの冬至祭」を取り入れたからです。
さらに北欧でも「冬至」を年の変わり目とする祭「ユール」があり、主神「オーディン」や雷神「トール」(=木曜日thursdayの語源)、豊穣神フレイ(=金曜日fraydayの語源)を祭りました。
今でも北欧では、「クリスマス」のことを「ユール」または「ヨウル」と呼びます。
(引用ここまで・写真(上)はゆず、写真(下)は我が家のアドベントカレンダー)
*****
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
 「古代キリスト教」カテゴリー全般
「古代キリスト教」カテゴリー全般















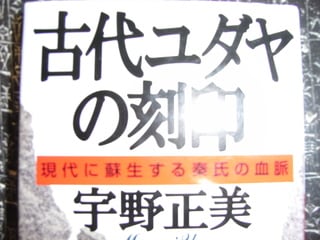
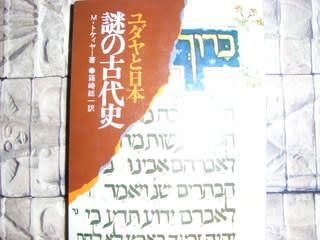


 wikipedia「大谷探検隊」より
wikipedia「大谷探検隊」より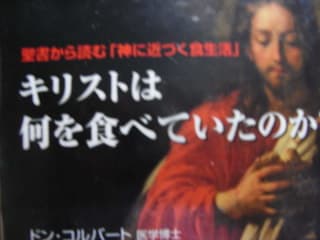

 Wikipedia「エトルリア」より
Wikipedia「エトルリア」より




