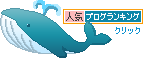「平成」とか「昭和」とか「明治」とか。
元号と言われる
「君主が特定の時代を指してつける称号」
の元祖って「大化」なのです。
この国では。
大化といえば、教科書的には「大化の改新」
その当時、大和朝廷の独裁的有力氏族であった
蘇我氏(そがし)を滅ぼした一大改革!
とされていますが......
要すれば......
「クーデター」
です。
内実はそれ以前の国を治めていた天皇と
政治的有力氏族に対する軍事的クーデター。
この言葉がなぜか?使われませんが、
「明治維新」とも似たようなものです。
この国の歴史の大転換期の一つ。
この後、元号どころか現在に至るまで続いている
律令制(りつりょうせい)が整備されるのです。
法治国家......と言った方が伝わりやすいのでしょうか。
僕らもキチンと、
大きく影響を受けているのです。
古事記、日本書紀などの歴史書もこの直後から編纂されます。
まだ文字を読める人も少なく、
ましてや書物などホンノ僅かしか無なかった様な時代。
監視の目も限られ、
文書の改ざんなども比較的容易にできたであろう時代。
歴史は正当性を示さんとする勝者によってどれくらいボヤかされたのでしょうか?
二つの書物も、
そのまんま読むわけにはいきませんのね......
( ̄  ̄)ええ。ええ。
そんな大化の改新は後に天智天皇(てんじてんのう)を名のる
中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と、
後に「藤原」の姓を名のる中臣鎌足(なかとみのかまたり)とが、
強力タッグを組んで実行しました。
その藤原氏。
この時以来、千年以上にわたり......
恐らくは今も皇室を裏で支えていると思われます。
決して表に出てきませんが......
興味深いのはクーデター成功後、
中臣氏がなぜ?「藤原」という姓名にしたのか。
「uzmetさん......わたくし、なぜか?
導かれるように奈良の高鴨神社(たかがもじんじゃ)
という所に行ったのです。
不思議に、突然呼ばれまして。
とても行きたくなったのですね。
とても素晴らしいところでした。
地元のタクシーの運転手さんも知らないような山奥だったのですけど。
面白いことです。
ありがたきことです。。」
と、つい先日、
飛び抜けて!?不思議な力を持つ、
高貴な佇まいとオーラを放つ「MT先生」さんが言うのです。
おケーキをお食べして、お茶をしてたら。
お背筋をおピン!と、お伸ばしあそばせながら
こんなことをお言いいになったのです。ええ。
「行ったのでござーいますのよ。。おほほほほほ。。。」
みたいに。ええ。
決してこの方は
「ワハハハ......」
とは笑いませんのよ。
ええ。ええ。
手をかる~く口にあてて
「オホホホ」
ですのよ。ええ。
この奈良県、葛城市にある高鴨神社。
何をかくそうこの神社。
京都にある有名な世界遺産「上賀茂神社」「下鴨神社」
の本宮なのでございます。
もっと言えば、全国にある「賀茂=加茂=鴨=カモ」系神社の
総本宮でもあるのです。
僕さんも幾度も訪れているとても魅力あるお神社なのです。ええ。
MT先生さんが自然と導かれる所以もわからないでもなく......
そんな「カモ」と呼ばれる神社を遡ると、京都から奈良、
葛城(かつらぎ)の地へと来てしまうのです。自然と。
それでもって、この「葛城」という名前が、
まぁ、実は大変な名前で。
大化の改新よりさらに前。
「初期大和朝廷」を司る有力氏族の名前だったわけです......が......
この葛城氏。掘れば掘るほど......
深く、重く、限りなく透明に近いブルーで......
日本史の深淵に漂う氏族であるわけです。
今も!?この国の裏側の方で.......
ヒソーーリと影響を与え続けている!?氏族さんなわけです。
そんな地に全国カモ系神社の総本宮があるわけです。
ここにも深いワケがあるのです。
葛城氏が権力を振るっていた時代は、
天文、地理、風水、占術、戦術......
天地神明の智に長けた人が天皇の側近となり、
実質的な国の統治担当者になる形で。
その代表が葛城氏でした。
実質的な大和王朝の支配者。
それが葛城氏。
葛城の葛(くず=かつら)というのは、
そんな天皇の地位に対して、
自らの力と立場を表した「姓」と考えられるのです。
国の大きな「幹」とも呼べるような人.......天皇を大木とすると、
その大木に絡まるように、
覆い隠すように「生い茂る」ツタ=ツル系の植物。
「カズラ=蔓=葛=クズ」
一見、大木からしたら迷惑で、鬱蒼として、胡散臭く、
百害あって一利無し......とも思えそうなツル系の植物。
しかし、それは大きく広く茂り過ぎさえしなければ、
大木を害虫や病原菌、日光や風雪の当たり過ぎや、
鳥や虫が幹に穴を開けちゃったり、入り込んだり......
っといった様なことから守るような働きもするわけです。
それがツタ系の植物。
絡まる「何か」がなければ栄えることはでき無い植物。
大木がなければ生い茂ることができ無い植物。
持ちつ持たれつ。
王様あっての私。
王の私は、あなたあってこそ護られるのです。
ツタと木の関係。
葛城氏の持っていたこの力をクーデターで手にした中臣氏は、
パートナーだった中大兄皇子(ナカノオオエノオウジ)が「新天皇!!」
と成る際に自らも真新しい姓を授かり、名乗ることとなります。
それは、
あなたあっての私です。
私あってのあなたです。
あなたが木ならば私はそこに絡まる藤(ふじ)となろう。
藤原。
葛城からその力と権力を引き継がんと付けられた名前。
古の葛城氏の様な力を持たん!と付けられた名前。
藤と葛。
生い茂りすぎると、
頼れる大木そのものをも取り殺してしまうようなもの。
しかし、その時は、同じく自らも地に倒れる時。
つかまるものが無くなる時。
藤原を辿ると中臣、カモ氏に行き着き、
カモ氏を辿ると奈良、高鴨神社に行き着き、
高鴨神社を尋ねれば葛城の地に辿り着き。
葛城を辿れば「一言主神=ひとことぬしのかみ」に行き着いて、
一言主神を辿れば同じ葛城の地、一言主神社に辿り着き......
ここから先はまたいつかの機会に......でしょうか。
ええ。ええ。(^^)
中臣という姓にも大きな秘密があるわけで。
MT先生さんは、それわ、もぅ、国の行く末、
祭祀を司る高貴な魂の血統であり、御生れなのでしょうね。ええ。
きっとそーでござぁーーーますのよ。
すげーでござーーますのよ。
ええ。ええ。( ̄ー ̄)ニヤリ


高鴨神社。
オヤジにならないとわからないくらい!?美しき境内。

ここが賀茂氏発祥の地とも言われていて、
賀茂氏はこの丘陵から奈良盆地に出て、葛城川に沿って
「上津鴨」と呼ばれる鴨山口神社(かもやまぐちじんじゃ)や、

下鴨と呼ばれる鴨都波神社(かもつばじんじゃ)

などを祀ったようです。
どちらも畑の中にあるこじんまりとした神社。
これらを京都に移した時、葛城の地でいう鴨山口神社を上鴨社、
鴨都波神社を下鴨社と呼ぶようになったのです。
さてさて......
藤(フジ)も葛(クズ)もツタ系の植物。
正確には「ツル植物=蔓植物」と呼ばれます。
「♪ ツールとカーメがすーーーべった、、、、、♪」
ツルとは何で、カメとは何で......
今回のこんな話とも色々な意味が重なってくるのです。
「カゴメ」というこの時記した記事と合わせて読んでもらっても......
面白いかもしれません(^^)
元号と言われる
「君主が特定の時代を指してつける称号」
の元祖って「大化」なのです。
この国では。
大化といえば、教科書的には「大化の改新」
その当時、大和朝廷の独裁的有力氏族であった
蘇我氏(そがし)を滅ぼした一大改革!
とされていますが......
要すれば......
「クーデター」
です。
内実はそれ以前の国を治めていた天皇と
政治的有力氏族に対する軍事的クーデター。
この言葉がなぜか?使われませんが、
「明治維新」とも似たようなものです。
この国の歴史の大転換期の一つ。
この後、元号どころか現在に至るまで続いている
律令制(りつりょうせい)が整備されるのです。
法治国家......と言った方が伝わりやすいのでしょうか。
僕らもキチンと、
大きく影響を受けているのです。
古事記、日本書紀などの歴史書もこの直後から編纂されます。
まだ文字を読める人も少なく、
ましてや書物などホンノ僅かしか無なかった様な時代。
監視の目も限られ、
文書の改ざんなども比較的容易にできたであろう時代。
歴史は正当性を示さんとする勝者によってどれくらいボヤかされたのでしょうか?
二つの書物も、
そのまんま読むわけにはいきませんのね......
( ̄  ̄)ええ。ええ。
そんな大化の改新は後に天智天皇(てんじてんのう)を名のる
中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と、
後に「藤原」の姓を名のる中臣鎌足(なかとみのかまたり)とが、
強力タッグを組んで実行しました。
その藤原氏。
この時以来、千年以上にわたり......
恐らくは今も皇室を裏で支えていると思われます。
決して表に出てきませんが......
興味深いのはクーデター成功後、
中臣氏がなぜ?「藤原」という姓名にしたのか。
「uzmetさん......わたくし、なぜか?
導かれるように奈良の高鴨神社(たかがもじんじゃ)
という所に行ったのです。
不思議に、突然呼ばれまして。
とても行きたくなったのですね。
とても素晴らしいところでした。
地元のタクシーの運転手さんも知らないような山奥だったのですけど。
面白いことです。
ありがたきことです。。」
と、つい先日、
飛び抜けて!?不思議な力を持つ、
高貴な佇まいとオーラを放つ「MT先生」さんが言うのです。
おケーキをお食べして、お茶をしてたら。
お背筋をおピン!と、お伸ばしあそばせながら
こんなことをお言いいになったのです。ええ。
「行ったのでござーいますのよ。。おほほほほほ。。。」
みたいに。ええ。
決してこの方は
「ワハハハ......」
とは笑いませんのよ。
ええ。ええ。
手をかる~く口にあてて
「オホホホ」
ですのよ。ええ。
この奈良県、葛城市にある高鴨神社。
何をかくそうこの神社。
京都にある有名な世界遺産「上賀茂神社」「下鴨神社」
の本宮なのでございます。
もっと言えば、全国にある「賀茂=加茂=鴨=カモ」系神社の
総本宮でもあるのです。
僕さんも幾度も訪れているとても魅力あるお神社なのです。ええ。
MT先生さんが自然と導かれる所以もわからないでもなく......
そんな「カモ」と呼ばれる神社を遡ると、京都から奈良、
葛城(かつらぎ)の地へと来てしまうのです。自然と。
それでもって、この「葛城」という名前が、
まぁ、実は大変な名前で。
大化の改新よりさらに前。
「初期大和朝廷」を司る有力氏族の名前だったわけです......が......
この葛城氏。掘れば掘るほど......
深く、重く、限りなく透明に近いブルーで......
日本史の深淵に漂う氏族であるわけです。
今も!?この国の裏側の方で.......
ヒソーーリと影響を与え続けている!?氏族さんなわけです。
そんな地に全国カモ系神社の総本宮があるわけです。
ここにも深いワケがあるのです。
葛城氏が権力を振るっていた時代は、
天文、地理、風水、占術、戦術......
天地神明の智に長けた人が天皇の側近となり、
実質的な国の統治担当者になる形で。
その代表が葛城氏でした。
実質的な大和王朝の支配者。
それが葛城氏。
葛城の葛(くず=かつら)というのは、
そんな天皇の地位に対して、
自らの力と立場を表した「姓」と考えられるのです。
国の大きな「幹」とも呼べるような人.......天皇を大木とすると、
その大木に絡まるように、
覆い隠すように「生い茂る」ツタ=ツル系の植物。
「カズラ=蔓=葛=クズ」
一見、大木からしたら迷惑で、鬱蒼として、胡散臭く、
百害あって一利無し......とも思えそうなツル系の植物。
しかし、それは大きく広く茂り過ぎさえしなければ、
大木を害虫や病原菌、日光や風雪の当たり過ぎや、
鳥や虫が幹に穴を開けちゃったり、入り込んだり......
っといった様なことから守るような働きもするわけです。
それがツタ系の植物。
絡まる「何か」がなければ栄えることはでき無い植物。
大木がなければ生い茂ることができ無い植物。
持ちつ持たれつ。
王様あっての私。
王の私は、あなたあってこそ護られるのです。
ツタと木の関係。
葛城氏の持っていたこの力をクーデターで手にした中臣氏は、
パートナーだった中大兄皇子(ナカノオオエノオウジ)が「新天皇!!」
と成る際に自らも真新しい姓を授かり、名乗ることとなります。
それは、
あなたあっての私です。
私あってのあなたです。
あなたが木ならば私はそこに絡まる藤(ふじ)となろう。
藤原。
葛城からその力と権力を引き継がんと付けられた名前。
古の葛城氏の様な力を持たん!と付けられた名前。
藤と葛。
生い茂りすぎると、
頼れる大木そのものをも取り殺してしまうようなもの。
しかし、その時は、同じく自らも地に倒れる時。
つかまるものが無くなる時。
藤原を辿ると中臣、カモ氏に行き着き、
カモ氏を辿ると奈良、高鴨神社に行き着き、
高鴨神社を尋ねれば葛城の地に辿り着き。
葛城を辿れば「一言主神=ひとことぬしのかみ」に行き着いて、
一言主神を辿れば同じ葛城の地、一言主神社に辿り着き......
ここから先はまたいつかの機会に......でしょうか。
ええ。ええ。(^^)
中臣という姓にも大きな秘密があるわけで。
MT先生さんは、それわ、もぅ、国の行く末、
祭祀を司る高貴な魂の血統であり、御生れなのでしょうね。ええ。
きっとそーでござぁーーーますのよ。
すげーでござーーますのよ。
ええ。ええ。( ̄ー ̄)ニヤリ


高鴨神社。
オヤジにならないとわからないくらい!?美しき境内。

ここが賀茂氏発祥の地とも言われていて、
賀茂氏はこの丘陵から奈良盆地に出て、葛城川に沿って
「上津鴨」と呼ばれる鴨山口神社(かもやまぐちじんじゃ)や、

下鴨と呼ばれる鴨都波神社(かもつばじんじゃ)

などを祀ったようです。
どちらも畑の中にあるこじんまりとした神社。
これらを京都に移した時、葛城の地でいう鴨山口神社を上鴨社、
鴨都波神社を下鴨社と呼ぶようになったのです。
さてさて......
藤(フジ)も葛(クズ)もツタ系の植物。
正確には「ツル植物=蔓植物」と呼ばれます。
「♪ ツールとカーメがすーーーべった、、、、、♪」
ツルとは何で、カメとは何で......
今回のこんな話とも色々な意味が重なってくるのです。
「カゴメ」というこの時記した記事と合わせて読んでもらっても......
面白いかもしれません(^^)