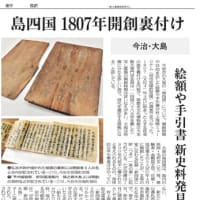1 空海の生涯
空海は平安時代前期に活躍した真言宗僧である。幼名は真魚といった。生まれは奈良時代後期の宝亀五(七七四)年、讃岐国(香川県)多度郡であり、父は佐伯氏、母は阿刀氏である。延暦七(七八八)年に入京し学問の研鑽を積んだ後、仏道に入り山林修行をし、四国の大瀧嶽(徳島県)、室戸(高知県)、石鎚山、出石山(愛媛県)でも修行をした。二四歳で『三教指帰』を著すが、これは日本文化史上、個人名で残された最初の文学作品ともいわれる。延暦二三年に留学僧として入唐し、唐の都長安の青龍寺恵果和尚と出会い、師主とすることを得た。空海は恵果について胎蔵界、金剛界、そして伝法阿闍梨灌頂に沐し、「遍照金剛」の密号を受けた。大同元(八〇六)年に帰国し、多くの経典や仏具等を請来した上に密教の本義を日本に伝えたことにより、その後の平安仏教の在り方に大きな影響を与えた。弘仁六(八一五)年、空海四二歳(厄年とされる年)に四国を巡り、四国霊場を開創したとの伝承もあるが、平安時代の史料からは史実か否かは確認できない。翌七年、嵯峨天皇から高野山(和歌山県)を賜り、金剛峯寺を建立し、同一四年には東寺を給預され、真言宗の基礎を築いた。宗教者としてだけではなく三筆の一人に数えられる書家として、『文鏡秘府論』など漢詩、文学者として、綜芸種智院の創設など教育者としてなど、様々な分野で大きな功績を残している。承和二(八三五)年三月に高野山で入定し、その後、延喜二一(九二一)年に醍醐天皇から「弘法大師」の号を賜っている。
2 空海誕生期の仏教
空海(真魚)が誕生した奈良時代後期。律令制下では教団が独自に出家を承認して僧尼となるのではなく、出家得度には朝廷の許可を得なければならなかった。許可を得ずに出家することを私度僧と呼び、禁止されていた。空海も若き日に山林修行をするが私度僧としての修行であり、正式な出家得度は延暦二三(八〇四)年、三一歳の時であった。奈良時代の仏教の特徴は「鎮護国家」の性格が強く、個人救済を前面に押し出したものではなかった。その最たるものが国分寺の建立や東大寺大仏の造営である。天平年間から疱瘡や飢饉に加え、新羅の来襲の恐れもあり、国ごとに大般若経を書写し、宮中で最勝王経の転読を行う等、鎮護国家を祈るための性格が強くなった。国分寺でも「最勝王経」が護国、外敵撃払のため、「法華経」が滅罪のため、「大般若経」が除災招福のため用いられた。空海が誕生する約三〇年前、『続日本紀』巻天平十三(七四一)年三月乙巳条の「国分寺建立の詔」を読むと聖武天皇は皇后の光明子とともに深く仏教に帰依し、「最勝王経」、「法華経」により王が四天王より擁護され一切の災障が消除されるといった鎮護国家の要素が強かったことがよくわかる。称徳天皇が百万塔陀羅尼を東大寺や法隆寺など十大寺に納めたのも恵美押勝の乱後の国家安穏を祈願したものであり、鎮護国家仏教は平安時代前期の空海等の密教の時代にも引き継がれていくことになる。
なお、奈良時代には南都六宗(法相、三論、律、倶舎、成実、華厳宗)が成立している。後の宗派とは異なり一種の学派のようなものであったが、桓武天皇は奈良仏教の権勢を敬遠するため遷都を決意したり、天台宗の最澄は奈良仏教への対抗意識が強かったりしたが、空海は奈良仏教界とは人的交流で対立は避ける傾向にあり、空海の遺言書とされる「御遺告」にて「末代の弟子等に三論・法相を兼学せしむべき縁起」とあるように真言以外に奈良時代からの仏教を兼学させることを弟子たちにも伝えている。
また、奈良後期からは神仏習合が進んでいくが、『太神宮諸雑事記』天平十四年十一月三日条を見ると、聖武天皇が東大寺大仏建立の趣旨を申すため、橘諸兄を伊勢大神宮に遣わしたところ「本朝は神国なり。神明をうやまい仰ぎ奉りたまうべきなりが、日輪は大日如来なり。本地は盧舎那仏なり。衆生はこれを悟り、まさに仏法に帰依すべし」とある。神仏習合、本地垂迹説について早期の事例であるが、後に空海が主尊とする大日如来が登場しており、それが伊勢神宮、そして天皇とも繋がっている。空海が大日如来を通して鎮護国家仏教の担い手になった前提と見ることもできるだろう。
3 庶民の苦しみと若き空海
空海(真魚)の幼少期にあたる奈良時代後期は、庶民にとっては労役、兵役、そして飢饉、地震等の災害に苦しんだ時期であった。空海が生誕した同月の史料である『続日本紀』宝亀五(七七四)年六月条を見ると、伊予国が飢饉で賑給(物資の救援)されている記事がある。翌七月には土佐国が飢えていたことも記されており、四国全体が飢饉に悩まされていた時期に空海は生誕した。また『日本後紀』延暦十八(七九九)年五月辛未条には讃岐国の飢饉記事が載っており、同六月条によると南海道諸国が前年の凶作のため田租が免除されている。この延暦十八年は空海二六歳。その一年半前に出家宣言の書『三教指帰』を著したばかりであり、空海は山林修行をしていた頃である。この時期、四国では飢饉で人々は苦しみ、空海もその様子を目の当たりにしていたのかもしれない。
さて、延暦三(七八四)年に桓武天皇が平城京で強まった寺社勢力から距離を取る等の理由で長岡京への遷都を決めたが新都の造成には多くの庶民が工事に携わっていた。『続日本紀』延暦三年七月癸酉条によると、長岡京への遷都で阿波、讃岐、伊予の三国に山城国山崎橋の造材を進めるよう命じている。長岡京の遷都、造営に関して空海出身地の四国の多くの庶民も工事に携わっていたのであり、これは給金を貰う勤務ではなく、歳役や雑徭など労働力で支払う税として徴用されたもので、庶民にとっては苦役であった。『続日本紀』延暦十年九月甲戌条によると越前、丹波、但馬、播磨、美作、備前、阿波、伊予国などに命じて、平城宮の諸門を長岡宮に移させている。四国の庶民も諸門移転に苦使された。この延暦十年は空海が大学明経科に入り学び始めた年である。空海は平城京に滞在していたが、その建物が出身地の四国の人々によって苦役、移転されていたことを間近に見ながら、自らは学問に取り組んでいたのである。この長岡京も造宮使の藤原種継が暗殺される等したため、わずか十年で再度新しい都城を造成することになり平安京へ遷都し、労役が重ねられることになった。
飢饉だけではなく延暦十三(七九四)年には西日本で地震が多発し、京畿内で死者が出たり、四国でも復旧のために新しい官道が整備されたりするなど、大きな被害があったことが『日本紀略』延暦十三年六月甲寅条、七月庚辰条に見える。この地震は一説に南海トラフを震源とする大地震とされ、古代における南海トラフ地震は、天武十三(六八四)年に太平洋岸で津波被害があり、土佐国が広範囲にわたって浸水している。また仁和三(八八七)年にも起こり、摂津国などで多くの津波被害者が出るなど全国的に被害が大きかった。本史料もその中間時期にあたり、記録上では京畿内のみの被害記述であるが、空海出身の四国(南海道)にも大きな被害があった可能性も否定できない。菅原道真が六国史を基に編纂した歴史書『類聚国史』災異部によると、この延暦十三年だけではなく数年前の延暦九年から地震が頻発していることがわかる。この史料は六国史の性格上、畿内中心の記述が多く、当時畿内中心に活動していた空海はそれらの地震を経験し、被害状況を把握していたことは想像に難くない。
また、宝亀年間以降、朝廷は蝦夷征討を何次にもわたって行った。宝亀五(七七四)年から弘仁二(八一一)年まで蝦夷征討が続き、三八年戦争とも称されている。多くの兵士が東北地方に派遣され、そして東北地方から四国など西日本に俘囚が移配された。この蝦夷征討の時代が始まったまさに宝亀五年に空海が讃岐国に誕生している。『続日本紀』宝亀七年十一月癸未条によれば、光仁天皇の即位以降、蝦夷征討に関する動きが盛んとなり、宝亀五年に按察使大伴駿河麻呂が蝦狄征討を命じられ、全国から多くの兵士が東北地方に派遣されたが、宝亀七年に出羽国俘囚三五八人が九州と讃岐国に移配されたことが記されている。空海二歳の時である。また、『続日本紀』延暦七(七八八)年三月辛亥条には東海道、東山道、坂東諸国から兵士五万二千八百余人を徴発し、東北の多賀城に集結させることが記されている。結局、延暦九年には坂東諸国の疲弊が甚だしくなったとの報告もあり、蝦夷との戦争は地方疲弊の一因となっていた。
このように飢饉や、都の造営の負担に加え、地震災害の頻発、そして蝦夷との三八年戦争での動員などで庶民が苦しむ時代を若き日の空海は過ごした。この状況を目の当たりにして空海はどのように考えたのだろうか。空海著『三教指帰』の序文には「一多の親識」(多くの親族・知人)が儒教で守るべき道(いわば朝廷での出世の道)を以って自分を束縛し、それを断ることは「忠孝」に背くものだという。空海はそれに悩み、「物の情、一つならず」つまり儒教、道教、仏教と三つの聖説があり、その一つ(仏教)に入る事で「忠孝」に背くことにはならないと主張した。自らが衆生を救うためには、儒教中心の学問では限界を感じ、「唯憤懣の逸気を写せり」と記しているように、自らが仏道修行に入っていく動機や沸き出てくる気持ちを一気に記したのが二四歳の時に執筆した『三教指帰』なのである。それまでに飢饉、苦役、災害、戦争により苦悩する庶民を実見したり、交流したりした経験、体験が宗教者・空海を誕生させたといえるのだろう。
大本敬久「空海の誕生―仏道修行の動機となった時代背景―」(『一遍会報』396号、2018年1月発行)より
空海は平安時代前期に活躍した真言宗僧である。幼名は真魚といった。生まれは奈良時代後期の宝亀五(七七四)年、讃岐国(香川県)多度郡であり、父は佐伯氏、母は阿刀氏である。延暦七(七八八)年に入京し学問の研鑽を積んだ後、仏道に入り山林修行をし、四国の大瀧嶽(徳島県)、室戸(高知県)、石鎚山、出石山(愛媛県)でも修行をした。二四歳で『三教指帰』を著すが、これは日本文化史上、個人名で残された最初の文学作品ともいわれる。延暦二三年に留学僧として入唐し、唐の都長安の青龍寺恵果和尚と出会い、師主とすることを得た。空海は恵果について胎蔵界、金剛界、そして伝法阿闍梨灌頂に沐し、「遍照金剛」の密号を受けた。大同元(八〇六)年に帰国し、多くの経典や仏具等を請来した上に密教の本義を日本に伝えたことにより、その後の平安仏教の在り方に大きな影響を与えた。弘仁六(八一五)年、空海四二歳(厄年とされる年)に四国を巡り、四国霊場を開創したとの伝承もあるが、平安時代の史料からは史実か否かは確認できない。翌七年、嵯峨天皇から高野山(和歌山県)を賜り、金剛峯寺を建立し、同一四年には東寺を給預され、真言宗の基礎を築いた。宗教者としてだけではなく三筆の一人に数えられる書家として、『文鏡秘府論』など漢詩、文学者として、綜芸種智院の創設など教育者としてなど、様々な分野で大きな功績を残している。承和二(八三五)年三月に高野山で入定し、その後、延喜二一(九二一)年に醍醐天皇から「弘法大師」の号を賜っている。
2 空海誕生期の仏教
空海(真魚)が誕生した奈良時代後期。律令制下では教団が独自に出家を承認して僧尼となるのではなく、出家得度には朝廷の許可を得なければならなかった。許可を得ずに出家することを私度僧と呼び、禁止されていた。空海も若き日に山林修行をするが私度僧としての修行であり、正式な出家得度は延暦二三(八〇四)年、三一歳の時であった。奈良時代の仏教の特徴は「鎮護国家」の性格が強く、個人救済を前面に押し出したものではなかった。その最たるものが国分寺の建立や東大寺大仏の造営である。天平年間から疱瘡や飢饉に加え、新羅の来襲の恐れもあり、国ごとに大般若経を書写し、宮中で最勝王経の転読を行う等、鎮護国家を祈るための性格が強くなった。国分寺でも「最勝王経」が護国、外敵撃払のため、「法華経」が滅罪のため、「大般若経」が除災招福のため用いられた。空海が誕生する約三〇年前、『続日本紀』巻天平十三(七四一)年三月乙巳条の「国分寺建立の詔」を読むと聖武天皇は皇后の光明子とともに深く仏教に帰依し、「最勝王経」、「法華経」により王が四天王より擁護され一切の災障が消除されるといった鎮護国家の要素が強かったことがよくわかる。称徳天皇が百万塔陀羅尼を東大寺や法隆寺など十大寺に納めたのも恵美押勝の乱後の国家安穏を祈願したものであり、鎮護国家仏教は平安時代前期の空海等の密教の時代にも引き継がれていくことになる。
なお、奈良時代には南都六宗(法相、三論、律、倶舎、成実、華厳宗)が成立している。後の宗派とは異なり一種の学派のようなものであったが、桓武天皇は奈良仏教の権勢を敬遠するため遷都を決意したり、天台宗の最澄は奈良仏教への対抗意識が強かったりしたが、空海は奈良仏教界とは人的交流で対立は避ける傾向にあり、空海の遺言書とされる「御遺告」にて「末代の弟子等に三論・法相を兼学せしむべき縁起」とあるように真言以外に奈良時代からの仏教を兼学させることを弟子たちにも伝えている。
また、奈良後期からは神仏習合が進んでいくが、『太神宮諸雑事記』天平十四年十一月三日条を見ると、聖武天皇が東大寺大仏建立の趣旨を申すため、橘諸兄を伊勢大神宮に遣わしたところ「本朝は神国なり。神明をうやまい仰ぎ奉りたまうべきなりが、日輪は大日如来なり。本地は盧舎那仏なり。衆生はこれを悟り、まさに仏法に帰依すべし」とある。神仏習合、本地垂迹説について早期の事例であるが、後に空海が主尊とする大日如来が登場しており、それが伊勢神宮、そして天皇とも繋がっている。空海が大日如来を通して鎮護国家仏教の担い手になった前提と見ることもできるだろう。
3 庶民の苦しみと若き空海
空海(真魚)の幼少期にあたる奈良時代後期は、庶民にとっては労役、兵役、そして飢饉、地震等の災害に苦しんだ時期であった。空海が生誕した同月の史料である『続日本紀』宝亀五(七七四)年六月条を見ると、伊予国が飢饉で賑給(物資の救援)されている記事がある。翌七月には土佐国が飢えていたことも記されており、四国全体が飢饉に悩まされていた時期に空海は生誕した。また『日本後紀』延暦十八(七九九)年五月辛未条には讃岐国の飢饉記事が載っており、同六月条によると南海道諸国が前年の凶作のため田租が免除されている。この延暦十八年は空海二六歳。その一年半前に出家宣言の書『三教指帰』を著したばかりであり、空海は山林修行をしていた頃である。この時期、四国では飢饉で人々は苦しみ、空海もその様子を目の当たりにしていたのかもしれない。
さて、延暦三(七八四)年に桓武天皇が平城京で強まった寺社勢力から距離を取る等の理由で長岡京への遷都を決めたが新都の造成には多くの庶民が工事に携わっていた。『続日本紀』延暦三年七月癸酉条によると、長岡京への遷都で阿波、讃岐、伊予の三国に山城国山崎橋の造材を進めるよう命じている。長岡京の遷都、造営に関して空海出身地の四国の多くの庶民も工事に携わっていたのであり、これは給金を貰う勤務ではなく、歳役や雑徭など労働力で支払う税として徴用されたもので、庶民にとっては苦役であった。『続日本紀』延暦十年九月甲戌条によると越前、丹波、但馬、播磨、美作、備前、阿波、伊予国などに命じて、平城宮の諸門を長岡宮に移させている。四国の庶民も諸門移転に苦使された。この延暦十年は空海が大学明経科に入り学び始めた年である。空海は平城京に滞在していたが、その建物が出身地の四国の人々によって苦役、移転されていたことを間近に見ながら、自らは学問に取り組んでいたのである。この長岡京も造宮使の藤原種継が暗殺される等したため、わずか十年で再度新しい都城を造成することになり平安京へ遷都し、労役が重ねられることになった。
飢饉だけではなく延暦十三(七九四)年には西日本で地震が多発し、京畿内で死者が出たり、四国でも復旧のために新しい官道が整備されたりするなど、大きな被害があったことが『日本紀略』延暦十三年六月甲寅条、七月庚辰条に見える。この地震は一説に南海トラフを震源とする大地震とされ、古代における南海トラフ地震は、天武十三(六八四)年に太平洋岸で津波被害があり、土佐国が広範囲にわたって浸水している。また仁和三(八八七)年にも起こり、摂津国などで多くの津波被害者が出るなど全国的に被害が大きかった。本史料もその中間時期にあたり、記録上では京畿内のみの被害記述であるが、空海出身の四国(南海道)にも大きな被害があった可能性も否定できない。菅原道真が六国史を基に編纂した歴史書『類聚国史』災異部によると、この延暦十三年だけではなく数年前の延暦九年から地震が頻発していることがわかる。この史料は六国史の性格上、畿内中心の記述が多く、当時畿内中心に活動していた空海はそれらの地震を経験し、被害状況を把握していたことは想像に難くない。
また、宝亀年間以降、朝廷は蝦夷征討を何次にもわたって行った。宝亀五(七七四)年から弘仁二(八一一)年まで蝦夷征討が続き、三八年戦争とも称されている。多くの兵士が東北地方に派遣され、そして東北地方から四国など西日本に俘囚が移配された。この蝦夷征討の時代が始まったまさに宝亀五年に空海が讃岐国に誕生している。『続日本紀』宝亀七年十一月癸未条によれば、光仁天皇の即位以降、蝦夷征討に関する動きが盛んとなり、宝亀五年に按察使大伴駿河麻呂が蝦狄征討を命じられ、全国から多くの兵士が東北地方に派遣されたが、宝亀七年に出羽国俘囚三五八人が九州と讃岐国に移配されたことが記されている。空海二歳の時である。また、『続日本紀』延暦七(七八八)年三月辛亥条には東海道、東山道、坂東諸国から兵士五万二千八百余人を徴発し、東北の多賀城に集結させることが記されている。結局、延暦九年には坂東諸国の疲弊が甚だしくなったとの報告もあり、蝦夷との戦争は地方疲弊の一因となっていた。
このように飢饉や、都の造営の負担に加え、地震災害の頻発、そして蝦夷との三八年戦争での動員などで庶民が苦しむ時代を若き日の空海は過ごした。この状況を目の当たりにして空海はどのように考えたのだろうか。空海著『三教指帰』の序文には「一多の親識」(多くの親族・知人)が儒教で守るべき道(いわば朝廷での出世の道)を以って自分を束縛し、それを断ることは「忠孝」に背くものだという。空海はそれに悩み、「物の情、一つならず」つまり儒教、道教、仏教と三つの聖説があり、その一つ(仏教)に入る事で「忠孝」に背くことにはならないと主張した。自らが衆生を救うためには、儒教中心の学問では限界を感じ、「唯憤懣の逸気を写せり」と記しているように、自らが仏道修行に入っていく動機や沸き出てくる気持ちを一気に記したのが二四歳の時に執筆した『三教指帰』なのである。それまでに飢饉、苦役、災害、戦争により苦悩する庶民を実見したり、交流したりした経験、体験が宗教者・空海を誕生させたといえるのだろう。
大本敬久「空海の誕生―仏道修行の動機となった時代背景―」(『一遍会報』396号、2018年1月発行)より