冷戦が終わってから、トルコは目覚ましい経済瀬長を遂げた。それまでは、アメリカとソ連が戦争すると戦場になるリスクもあったし、1975年にはキプロス内戦に介入するなど、戦後のトルコは戦争の可能性がかなり高かった国である。でも、アメリカとソ連の戦争の可能性が消えたため、国を挙げて経済開発をして、日本もかなり経済援助をしたわけである。
ただし、日本人は知らない人も多いが、トルコは潜在的な内紛を抱えている。トルコ人の他に、「クルド民族」という言葉も、文化も違う少数民族がかなりいて、独立運動さえしている。独立を認めれば、トルコの領土が減るわけだから、経済損失もするため、それはトルコ政府としては認められない。そうして、経済成長をある程度して、その利益配分をするわけだが、当然ながら、トルコではトルコ人の政治家や官僚の数が多い。クルド人の政治家や官僚は少ないわけである。政治家も、官僚も人民を向いて利益配分する訳だが、トルコ人の方が多い以上はそこに利益配分を集中し、クルド人が多い地区には少なくする。トルコ人は豊かになり、クルド人は貧しいまま。格差も広まれば、治安も悪くなる。例え内戦は起きなくても、強盗や、金絡みの殺人事件も増える。経済成長しても、社会は安定しないどころか、更に不安定になる。ならば、リーマン・ショックみたいなものが外国で起これば、トルコの経済は悪化する。こんな経済構造である。(参考.高橋和夫・放送大学教授の諸々のトルコ解説)
何もトルコに限った事ではない。シリアはもっと複雑な民族対立を抱えているし、今は経済がかなり伸びているアフリカのケニアやガーナなども、複雑な種族対立を抱えている。利益配分も多数民族に偏っているから、更に経済が伸びれば、トルコと同じ状態が生まれると。中南米諸国にしても。
あるいは、かつての日本の高度経済成長期のイメージをトルコに当てはめて、投資した日本人もかなりいるかもしれないが、確かに、日本でもアイヌや琉球、韓国系の人たちの民族差別はあり、深刻な問題にしろ、内戦になるような気配はない。1960年代もそうだった。それに、冷戦で、アメリカが経済優遇してくれた事もあり、高度経済成長できたわけだ。確かに、若者が多いなど、人口構成だけを見れば、60年代の日本と2000年以降のトルコは同じだが、それ以外の条件は大違いである。
有効な投資先は少なくなっているし、先進国は少子高齢化で人口は停滞。減少を始めた国もある。それに代わる経済制度は出ないだろうから、株式会社という形式は今後も続くが、「資本金を次々と増やして成長する」という資本主義はすでに終焉に入り始めたのかもしれない。経済評論家の水野和夫氏はそのような説を各著書で述べているし、故人だが、船井幸雄氏もそのように述べている。ならば、投資頼みは難しいわけだ。確かに、資本主義は人口が増加し始めたヨーロッパで起きた。人口の頭打ちとなった時に、それは終わってもおかしくない。我々は文明の転換期にいる。そして、どう考えても、今回の金融庁の委員の人達はそれを意識していない。バブル崩壊前、1970年ごろの発想で議論したように僕には思える。
投資が当てにならなければ、これからは介護に限らず、人々が人格や心をまず認め合い、助け合う事も説かなければならない。今回の委員たちはそのような事は説いておらず、その面からもおかしいと言わざるを得ない。お粗末である。
ただし、日本人は知らない人も多いが、トルコは潜在的な内紛を抱えている。トルコ人の他に、「クルド民族」という言葉も、文化も違う少数民族がかなりいて、独立運動さえしている。独立を認めれば、トルコの領土が減るわけだから、経済損失もするため、それはトルコ政府としては認められない。そうして、経済成長をある程度して、その利益配分をするわけだが、当然ながら、トルコではトルコ人の政治家や官僚の数が多い。クルド人の政治家や官僚は少ないわけである。政治家も、官僚も人民を向いて利益配分する訳だが、トルコ人の方が多い以上はそこに利益配分を集中し、クルド人が多い地区には少なくする。トルコ人は豊かになり、クルド人は貧しいまま。格差も広まれば、治安も悪くなる。例え内戦は起きなくても、強盗や、金絡みの殺人事件も増える。経済成長しても、社会は安定しないどころか、更に不安定になる。ならば、リーマン・ショックみたいなものが外国で起これば、トルコの経済は悪化する。こんな経済構造である。(参考.高橋和夫・放送大学教授の諸々のトルコ解説)
何もトルコに限った事ではない。シリアはもっと複雑な民族対立を抱えているし、今は経済がかなり伸びているアフリカのケニアやガーナなども、複雑な種族対立を抱えている。利益配分も多数民族に偏っているから、更に経済が伸びれば、トルコと同じ状態が生まれると。中南米諸国にしても。
あるいは、かつての日本の高度経済成長期のイメージをトルコに当てはめて、投資した日本人もかなりいるかもしれないが、確かに、日本でもアイヌや琉球、韓国系の人たちの民族差別はあり、深刻な問題にしろ、内戦になるような気配はない。1960年代もそうだった。それに、冷戦で、アメリカが経済優遇してくれた事もあり、高度経済成長できたわけだ。確かに、若者が多いなど、人口構成だけを見れば、60年代の日本と2000年以降のトルコは同じだが、それ以外の条件は大違いである。
有効な投資先は少なくなっているし、先進国は少子高齢化で人口は停滞。減少を始めた国もある。それに代わる経済制度は出ないだろうから、株式会社という形式は今後も続くが、「資本金を次々と増やして成長する」という資本主義はすでに終焉に入り始めたのかもしれない。経済評論家の水野和夫氏はそのような説を各著書で述べているし、故人だが、船井幸雄氏もそのように述べている。ならば、投資頼みは難しいわけだ。確かに、資本主義は人口が増加し始めたヨーロッパで起きた。人口の頭打ちとなった時に、それは終わってもおかしくない。我々は文明の転換期にいる。そして、どう考えても、今回の金融庁の委員の人達はそれを意識していない。バブル崩壊前、1970年ごろの発想で議論したように僕には思える。
投資が当てにならなければ、これからは介護に限らず、人々が人格や心をまず認め合い、助け合う事も説かなければならない。今回の委員たちはそのような事は説いておらず、その面からもおかしいと言わざるを得ない。お粗末である。










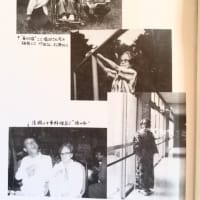

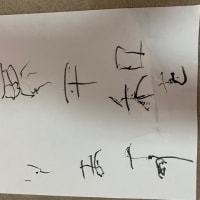



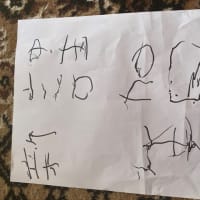
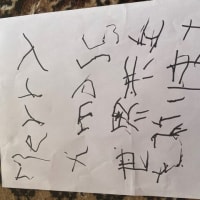

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます