早く寝たら早く目が醒めた。
まだ日の出前。
空気が凍っている。

寒いから珈琲淹れる。
出た出た、太陽。


キリキリ冷え込んだ早朝は珈琲が格別ウマい。
ブラジルカラメリッチ。
香ばしい。
今日は元々休みを取ってあった。
教会に行く。
礼拝の後マルコを皆で読む会があるので参加する。
・・・・・
!
まだ早過ぎると思って二度寝したら10:00!!
やばっ礼拝に遅刻!


主日礼拝
黙祷
招詞 詩編98;1~3
讃美歌(21) 230 387
聖句唱和 詩編67;5~6
子供のための紙芝居
使徒信条
メノナイト信仰告白
祈り
讃美歌(21) 239 163
聖書朗読 申命記16;13~17
説教
讃美歌(21) 426
献金 讃美歌(21) 512
祈り
頌栄 讃美歌(21) 29
祝祷
今年はアドベントが遅くて12月の第1週から始まるので11月は収穫感謝を歌う讃美歌が多い。
農業を営む高齢の教会仲間がキクイモを収穫したので1袋購入した。
食べ方がわからないがきんぴらにするとイケるという話なので母に持って行く事にした。
昼食の弁当を買いに行く。
求道者の方と一緒に弁当を選んだ。
ミニかつ丼にした。
280円也。
マルコを読む会は3;1~6、イエスが安息日に片手の萎えた人を癒した箇所。
手が萎えるというのは今で言う脳神経疾患の後遺症か或いは頸椎の疾患のために
手に麻痺のある人が治して貰える事を期待してイエスの元に来ていたのであろう。
ユダヤ教では福音書の時代も今も、安息日に労働行為をする事は厳しく禁止されている。
イエスが安息日に麻痺した手を癒した事は戒律を厳格に守るファリサイ派の人々の反感と憎悪を買った。
イエスは言う。
「安息日に律法で許されているのは、
善を行うことか、悪を行うことか。
命を救うことか、殺すことか。」(マルコ3;4)
厳格な律法主義のファリサイ派は“病人を癒す”という労働行為によって
律法破りを公然と犯したイエスを殺害する事を企てる。
本来律法は人間を細かい規則で縛り上げるためのものではなかった。
奴隷として抑圧されていたイスラエルの民を、神はモーセに引率させてエジプトを脱出させ荒野へ逃がした。
民が荒野を彷徨った時、神はモーセを通して民に十戒を与えた。
律法は荒野を彷徨うイスラエルの民が過酷な自然環境を生き延びるために神が与えたものだ。
もし律法が与えられていなかったら飢えた民は荒野で生き物を何でもかんでも手当たり次第捕まえて
血抜きもせずに口にして中毒や感染症が群れの中に拡大し絶滅した事であろう。(血を飲むなとはそういう意味)
群れの中で暴力や不倫や略奪が生じて争いによって散り散りになって死に絶えたであろう。
律法は着の身着のまま荒野に放り出された弱い人間達が過酷な環境を生き延びるために必要な
公衆衛生であり社会秩序を維持するためのルールであった。
律法は人間が安全安楽に過酷な環境を生き延びる事が出来るために、主なる神が慈しみを以て与えられた知恵だ。
旧約を読めばわかる事だ。
しかし長い歴史のうちに戒律を守る事が自己目的化し、より細分化し複雑化し、変質した。
律法を遵守出来るエリート(地位の高い者、宗教的指導者、律法学者、ファリサイ派、サドカイ派など)が
律法を守れない落伍者(貧者、身体に機能障害のある者、精神疾患者、感染症患者、寡婦、孤児、移民)を
虐げ裁く構図が出来上がっていた事が伺える。
神が慈愛によって与えた律法を本末転倒させ「規則だから守るのが当然」と弱者を縛り上げる口実に利用し
既得権益に胡坐をかいていた当時の宗教指導者達にとっては、
イエスが安息日に麻痺のある人の手を公然と癒した事は死に値する掟破りだった。
福音書の文字だけを見ると2000年も昔のお話のようにも思われるが、同じ事は今の時代にもある。
今日の参加者から
「今の時代も福音書と同じ、人間は2000年前から一つも進歩していない」
と発言があった。
その通りである。
世の中の大きな問題から小さな問題まで全く同様である。
キリスト教の教会も殊更その通りと私は思う。
特に我々キリスト教信者の足元には罠がある。
敬虔な信仰者は福音書に登場するファリサイ派や律法学者そのものになり得るからだ。
「敬虔な信仰者」は優等生の高みから落伍者を見下して裁く事を正義と思い込み、
キリストを殺した者達と同じ事をしている自覚が無い。
最も身近で矮小な例を挙げれば私の所属する教派の古い教会で半世紀も昔、
日曜日に人が教会に集まらない事をアメリカ人宣教師が嘆いて
「どうして日本人は教会に来ないで用事や学校の行事を日曜日にするのか」
と言ったと古い記念誌に載っていた。
日本では昔も今も何かの行事や学校の運動会は大抵日曜日に行われる。
週日は仕事なのでそれ以外の行事は日曜日に設定するしかない。
安息日だから守れ、仕事をするなと言われても、
実際日曜日に仕事を休めるのは学校の教師と公務員くらいのものであろう。
(なるほどそういえば教会には公務員や学校の先生と名の付く職業の人が多いかも知れない)
交通機関で働く人や医療介護従事者は年中無休同然で日曜日だからという理由で休むなどあり得ない。
安息日遵守の律法からは確実に落伍してしまう。
昔も今も同じ。
私がその話をすると、日本とアメリカでは事情が異なると宣教師が言った。
宣教師が子供だった大昔、北米の故郷では「日曜日は教会に行く日」という慣習が厳然と定着していたため
町では誰もが皆教会に集まり、商店なども日曜日は全く営業していなかったと言う。
宣教師の故郷は社会全体がキリスト教一色だったのだろうか。
日曜日は安息日だから「休まなければならない」と今よりも厳しく守られていたらしい。
マジメ、敬虔と言えばそれまでであるが、そこに教会に行く事の出来ない事情にある人への配慮は無い。
決まり事を守る事が自己目的化するとハードルが上がって脱落者を出し、
「敬虔な優等生信者と救われない落伍者」の如き図式が生まれる。
宣教師は故郷の昔のくりすちゃん達のあり方を馬鹿には出来ないと言った。
何故なら信仰者としてはマジメで一生懸命だったのだからと。
私はそのようには考えない。
それは優位にある者に対して甘く、人を裁こうとする者が自分を正当化するに都合の良い解釈であり
人間の生き方としてそのような信仰は死んだものだ。
何故なら誰でも自分に都合の良い事に対してならマジメで一生懸命になれるからだ。
キリストを憎悪し殺害したのは真面目に律法を遵守する敬虔な優等生信仰者であった。
彼らは彼らの正義に対して忠実であり一生懸命だったのだ。
私はここで言う「敬虔な優等生信仰者」をこの世の毒虫と思っている。
信仰者である以上、自分自身が毒虫になる可能性がある。
毒虫は踏み潰して根絶やしにすべきものだ。
マルコを読む会が終わった後も教会仲間達と別件で近況報告し合ったり立ち話をした。
間もなく日が暮れる。

そうそう、ささみを買っておいたのを早く調理してしまわなければ。
先日職場で食事介助しているとホールのテレビで料理番組をやっていたので試そうと思って。
ささみはたんぱく価が高いので一時期よく食べていたが何せ食感がボソボソして不味い。
胸肉も同様。
ささみ2枚をよく叩いて薄く伸ばし塩を振ってチーズと薄切りしたプチトマトを伸ばしたささみ同士の間に挟む。
マヨネーズを塗ってパン粉を塗し、フライパンに油を引いて焼く。
ささみ単独で調理すると口の中でボソボソするが薄く伸ばして間にチーズとプチトマトを挟めば
ささみの繊維質の食感が緩和されそうだ。
・・・と思ってやってみたが。

うーむ。
不味くはないが、パン粉要らないのでは?
番組と同じ手順でマヨネーズを塗ってパン粉を塗したが、焼くうちにパン粉が片っ端から剥がれた。
それにパン粉のおかげで熱量も糖度もうなぎ上りではないか。
味は良かったので次回からはパン粉無しで。
さて、教会で貰って来た紙。
「天に召される時が来た時に、読んでほしい聖書の言葉と歌ってほしい讃美歌」

そうそう、近年教会で親族の葬儀を何度か行なってみて出た声からのものだ。
「故人の愛唱讃美歌や聖書の好きな個所がわかっていたらスムーズだし心温まる葬儀になるよね」
「普段からお互いの愛唱讃美歌や聖書の好きな個所をわかるようにしておけばいいんじゃない?」
という事で実行。
皆既に提出済みで、私だけまだだった。
えーと。
どうしようかなぁ。
天に召される時が来た時にって、何歌っても何読んでも自分もう死んでるからなぁ。
皆の好きなのでいいよと言うのは皆が一番悩むから、生きている今のうち選んでおいた方がいいのか。
何にしようかな。
これはあれだな、終活と言うものの教会版であるな。
まだ日の出前。
空気が凍っている。

寒いから珈琲淹れる。
出た出た、太陽。


キリキリ冷え込んだ早朝は珈琲が格別ウマい。
ブラジルカラメリッチ。
香ばしい。
今日は元々休みを取ってあった。
教会に行く。
礼拝の後マルコを皆で読む会があるので参加する。
・・・・・
!
まだ早過ぎると思って二度寝したら10:00!!
やばっ礼拝に遅刻!


主日礼拝
黙祷
招詞 詩編98;1~3
讃美歌(21) 230 387
聖句唱和 詩編67;5~6
子供のための紙芝居
使徒信条
メノナイト信仰告白
祈り
讃美歌(21) 239 163
聖書朗読 申命記16;13~17
説教
讃美歌(21) 426
献金 讃美歌(21) 512
祈り
頌栄 讃美歌(21) 29
祝祷
今年はアドベントが遅くて12月の第1週から始まるので11月は収穫感謝を歌う讃美歌が多い。
農業を営む高齢の教会仲間がキクイモを収穫したので1袋購入した。
食べ方がわからないがきんぴらにするとイケるという話なので母に持って行く事にした。
昼食の弁当を買いに行く。
求道者の方と一緒に弁当を選んだ。
ミニかつ丼にした。
280円也。
マルコを読む会は3;1~6、イエスが安息日に片手の萎えた人を癒した箇所。
手が萎えるというのは今で言う脳神経疾患の後遺症か或いは頸椎の疾患のために
手に麻痺のある人が治して貰える事を期待してイエスの元に来ていたのであろう。
ユダヤ教では福音書の時代も今も、安息日に労働行為をする事は厳しく禁止されている。
イエスが安息日に麻痺した手を癒した事は戒律を厳格に守るファリサイ派の人々の反感と憎悪を買った。
イエスは言う。
「安息日に律法で許されているのは、
善を行うことか、悪を行うことか。
命を救うことか、殺すことか。」(マルコ3;4)
厳格な律法主義のファリサイ派は“病人を癒す”という労働行為によって
律法破りを公然と犯したイエスを殺害する事を企てる。
本来律法は人間を細かい規則で縛り上げるためのものではなかった。
奴隷として抑圧されていたイスラエルの民を、神はモーセに引率させてエジプトを脱出させ荒野へ逃がした。
民が荒野を彷徨った時、神はモーセを通して民に十戒を与えた。
律法は荒野を彷徨うイスラエルの民が過酷な自然環境を生き延びるために神が与えたものだ。
もし律法が与えられていなかったら飢えた民は荒野で生き物を何でもかんでも手当たり次第捕まえて
血抜きもせずに口にして中毒や感染症が群れの中に拡大し絶滅した事であろう。(血を飲むなとはそういう意味)
群れの中で暴力や不倫や略奪が生じて争いによって散り散りになって死に絶えたであろう。
律法は着の身着のまま荒野に放り出された弱い人間達が過酷な環境を生き延びるために必要な
公衆衛生であり社会秩序を維持するためのルールであった。
律法は人間が安全安楽に過酷な環境を生き延びる事が出来るために、主なる神が慈しみを以て与えられた知恵だ。
旧約を読めばわかる事だ。
しかし長い歴史のうちに戒律を守る事が自己目的化し、より細分化し複雑化し、変質した。
律法を遵守出来るエリート(地位の高い者、宗教的指導者、律法学者、ファリサイ派、サドカイ派など)が
律法を守れない落伍者(貧者、身体に機能障害のある者、精神疾患者、感染症患者、寡婦、孤児、移民)を
虐げ裁く構図が出来上がっていた事が伺える。
神が慈愛によって与えた律法を本末転倒させ「規則だから守るのが当然」と弱者を縛り上げる口実に利用し
既得権益に胡坐をかいていた当時の宗教指導者達にとっては、
イエスが安息日に麻痺のある人の手を公然と癒した事は死に値する掟破りだった。
福音書の文字だけを見ると2000年も昔のお話のようにも思われるが、同じ事は今の時代にもある。
今日の参加者から
「今の時代も福音書と同じ、人間は2000年前から一つも進歩していない」
と発言があった。
その通りである。
世の中の大きな問題から小さな問題まで全く同様である。
キリスト教の教会も殊更その通りと私は思う。
特に我々キリスト教信者の足元には罠がある。
敬虔な信仰者は福音書に登場するファリサイ派や律法学者そのものになり得るからだ。
「敬虔な信仰者」は優等生の高みから落伍者を見下して裁く事を正義と思い込み、
キリストを殺した者達と同じ事をしている自覚が無い。
最も身近で矮小な例を挙げれば私の所属する教派の古い教会で半世紀も昔、
日曜日に人が教会に集まらない事をアメリカ人宣教師が嘆いて
「どうして日本人は教会に来ないで用事や学校の行事を日曜日にするのか」
と言ったと古い記念誌に載っていた。
日本では昔も今も何かの行事や学校の運動会は大抵日曜日に行われる。
週日は仕事なのでそれ以外の行事は日曜日に設定するしかない。
安息日だから守れ、仕事をするなと言われても、
実際日曜日に仕事を休めるのは学校の教師と公務員くらいのものであろう。
(なるほどそういえば教会には公務員や学校の先生と名の付く職業の人が多いかも知れない)
交通機関で働く人や医療介護従事者は年中無休同然で日曜日だからという理由で休むなどあり得ない。
安息日遵守の律法からは確実に落伍してしまう。
昔も今も同じ。
私がその話をすると、日本とアメリカでは事情が異なると宣教師が言った。
宣教師が子供だった大昔、北米の故郷では「日曜日は教会に行く日」という慣習が厳然と定着していたため
町では誰もが皆教会に集まり、商店なども日曜日は全く営業していなかったと言う。
宣教師の故郷は社会全体がキリスト教一色だったのだろうか。
日曜日は安息日だから「休まなければならない」と今よりも厳しく守られていたらしい。
マジメ、敬虔と言えばそれまでであるが、そこに教会に行く事の出来ない事情にある人への配慮は無い。
決まり事を守る事が自己目的化するとハードルが上がって脱落者を出し、
「敬虔な優等生信者と救われない落伍者」の如き図式が生まれる。
宣教師は故郷の昔のくりすちゃん達のあり方を馬鹿には出来ないと言った。
何故なら信仰者としてはマジメで一生懸命だったのだからと。
私はそのようには考えない。
それは優位にある者に対して甘く、人を裁こうとする者が自分を正当化するに都合の良い解釈であり
人間の生き方としてそのような信仰は死んだものだ。
何故なら誰でも自分に都合の良い事に対してならマジメで一生懸命になれるからだ。
キリストを憎悪し殺害したのは真面目に律法を遵守する敬虔な優等生信仰者であった。
彼らは彼らの正義に対して忠実であり一生懸命だったのだ。
私はここで言う「敬虔な優等生信仰者」をこの世の毒虫と思っている。
信仰者である以上、自分自身が毒虫になる可能性がある。
毒虫は踏み潰して根絶やしにすべきものだ。
マルコを読む会が終わった後も教会仲間達と別件で近況報告し合ったり立ち話をした。
間もなく日が暮れる。

そうそう、ささみを買っておいたのを早く調理してしまわなければ。
先日職場で食事介助しているとホールのテレビで料理番組をやっていたので試そうと思って。
ささみはたんぱく価が高いので一時期よく食べていたが何せ食感がボソボソして不味い。
胸肉も同様。
ささみ2枚をよく叩いて薄く伸ばし塩を振ってチーズと薄切りしたプチトマトを伸ばしたささみ同士の間に挟む。
マヨネーズを塗ってパン粉を塗し、フライパンに油を引いて焼く。
ささみ単独で調理すると口の中でボソボソするが薄く伸ばして間にチーズとプチトマトを挟めば
ささみの繊維質の食感が緩和されそうだ。
・・・と思ってやってみたが。

うーむ。
不味くはないが、パン粉要らないのでは?
番組と同じ手順でマヨネーズを塗ってパン粉を塗したが、焼くうちにパン粉が片っ端から剥がれた。
それにパン粉のおかげで熱量も糖度もうなぎ上りではないか。
味は良かったので次回からはパン粉無しで。
さて、教会で貰って来た紙。
「天に召される時が来た時に、読んでほしい聖書の言葉と歌ってほしい讃美歌」

そうそう、近年教会で親族の葬儀を何度か行なってみて出た声からのものだ。
「故人の愛唱讃美歌や聖書の好きな個所がわかっていたらスムーズだし心温まる葬儀になるよね」
「普段からお互いの愛唱讃美歌や聖書の好きな個所をわかるようにしておけばいいんじゃない?」
という事で実行。
皆既に提出済みで、私だけまだだった。
えーと。
どうしようかなぁ。
天に召される時が来た時にって、何歌っても何読んでも自分もう死んでるからなぁ。
皆の好きなのでいいよと言うのは皆が一番悩むから、生きている今のうち選んでおいた方がいいのか。
何にしようかな。
これはあれだな、終活と言うものの教会版であるな。










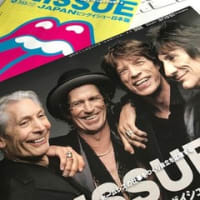









鶏ささみを塩胡椒してフライパンで焼きます。それだけ。
私はバターを使いますが、井上さんはバター嫌いでしょうしオリーブオイルでどうぞ。
裏返す度に菜箸でちょっとづづ押し広げます。
そうすると繊維で切れて「木の葉」のように広がります。
バターで焼く場合は最後に醤油をちょっと絡めます。
聖書の言葉について、聞きかじった程度の知識しかなく、
しかも、自分勝手な解釈で、悦に入っている不届き者では
ありますが、心に残る聖書の言葉は、幾つかありました。
井上さんのブログの影響で、聖書というものが、
身近に感じられるようになり、心の中で、宝の持ち腐れになっていた
珠玉の言葉が再浮上しました。
母と母の老後を見守る姉、その二人の関係性へのテコ入れの為に
月に一度、帰省するようになってから、物思いに耽る事が増えましたが、
『マルタとマリア』のお話を思い出したことで、生きる姿勢と勇気を頂き、
エネルギーがチャージされたように元気いっぱいです。
常に目的を念頭に据え置き、目的の為の手段である事を確認し、
目的を実現する為の手段を融通無碍に替えていく知恵の必要性・・
次回の帰省時には、姉と『マルタとマリア』の話で盛り上がってきます!
聖パウロ礼拝堂のチャプレンから頂いた絵葉書に
印刷されていた『平和を求める祈り』です。
葉書に印刷された「平和を求める祈り』の文字は、
手書きの写しで、すみれの花の水彩画が添えられています。
幼い頃、早春の線路端で見かけた紫色のすみれの花です。
もし、この印刷文字が手書きでなければ、
もし、文字だけで、清楚な水彩画が添えられていなかったら、
あんなにも感動して、まるで宝物を扱う様に大切にして、
お気に入りのフォトフレームに入れて飾り、
この十数年、引き出しの奥への左遷や、断捨離の対象にもならずに、
今もこうして、押し頂く様に、目で文字を追う事が、
私の場合、果たしてあり得ただろうか。
手仕事に込められた他者への思いの温もりや、ひたむきさ、
その求心力に改めて感動しています。