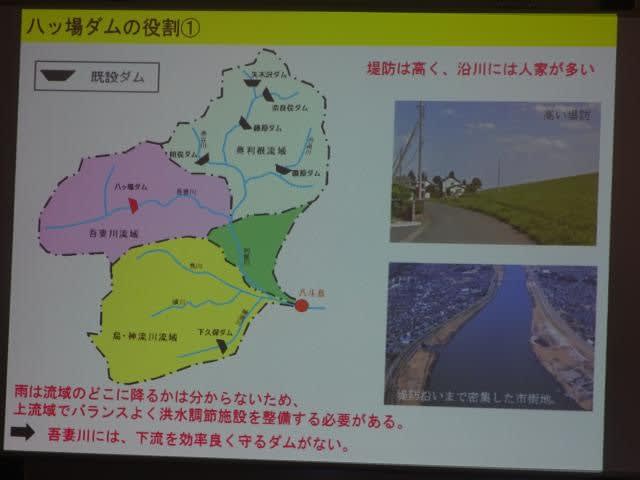八ッ場ダムの見学を終えて今夜の宿泊地は四万温泉。
関越高速道伊香保ICから約60分。かなり山奥に入った温泉地だ。
ここは上毛かるたに「世のちり洗う四万温泉」と読まれ、
国民保養温泉地第1号に指定を受けた温泉だ。(2014-8-28付積善館を参照)



一泊お世話になったやまぐち館。ここは一般客室57室、特別室3室(露天風呂付)
洋室16室。全室四万川を望むことができる、280名収容の
中型旅館で、トータル的にちょうどいい大きさの温泉宿といっていい。

玄関に掛かっているのれんのデザインがとてもシンプルそのもので
なんとなく微笑ましい。△口〇・・・はじめ三角次四角、まあるくなって
みんな円満 やまぐちかん。


昭和の懐かしさがあふれるロビー。なぜかとても心地の良い空間だ。
入口正面の大きな一枚ガラスの向こうに緑が見渡せるのがそうさせるのか。

通常のホテル、旅館はフロントと言うが、やまぐち館は大きく帳場と書かれ、
昭和の香りを徹底的に出している。フロアー表示もここ4階を
ふれあいの四丁目と表現する。


ロビーから俵町演芸広場に抜ける俵町通りの入口には
大量のつるし雛が飾らえ、その横には昭和の玩具懐かしい屋の品物が販売されていた。

旅館に到着すると一端ここ俵町演芸広場に集まり、やまぐち館の説明を受ける。
夜になると有名な名物女将による紙芝居、トークタイムが
ここで行われる。壁には沢山の手書きされた紙芝居が収納され、
これがディスプレーとなって一つの空間を形作っている。

七丁目にある月見台ラウンジ。とても素敵な場所でまったりとした時を過ごせる。
三丁目にも月見台ラウンジがあるようだが、今回は行きそびれてしまった。


各部屋、各風呂、各所から眼下にその清流四万川が見ることができる。
目の前には山が迫り、新緑、紅葉などの自然を満喫することができる。


温泉旅館には必須な土産物売場「延喜屋」それに漬物専門の上州蔵。
そして評判のやまぐち館女将が開発した「くみ子温泉化粧水」の売場「KUMIK」。


昭和というよりは大正ロマンに近い雰囲気の茶房「まゆの花」と「俵町サロン」。
着物の背中姿の女性が有名女将だ。

やまぐち館内には随所にパワースポットの仕掛けがある。パワースポットめぐり八宝。
1番 大願成就 2番 健康の宝 3番 繁盛の宝 4番 良縁の宝
5番 金運の宝 6番 美の宝 7番 子宝 8番 長寿の宝
なるほど、色々な事を考えるものだ。

そして何と言っても四万温泉の最大の魅力は温泉の湯だ。
特にやまぐち館のお風呂は素晴らしい。日本一のお題目大露天風呂、
渓流露天風呂四万川の湯檜大浴場薬師の湯、貸切展望風呂。
四万温泉の開場伝説は2つあり、坂上田村麻呂による発見説、
源頼光の家臣確井貞光による発見説だ。1563年(永禄6年)には
はじめての宿が開業している。四万の湯は四万もの病に効くと言われ
肌に優しく、ほんわか温まり本当に素晴らしい湯だ。


上が宴会食、下が朝食。団体料理ということを差し引いても、料理に関してはガッカリした。
多少値切ったのがここに出たのかは知らないが、何かインパクトが感じられず
やまぐち館らしくなくコンセプトがぼやけていた。夕食は宴会で
アルコールが入っていたので断言できないが、朝食は今や大事な
ファクターなのだからもっと工夫がほしいと感じだ。

この方が有名な名物女将。夕食が終わると俵町広場に宿泊客を
集めて紙芝居をやり、語らう。女将は伊香保温泉の出身と言っていたが
とにかく話術が上手だ。パンフレットの表紙も女将の姿で
「笑顔の物語はじまりはじまり」