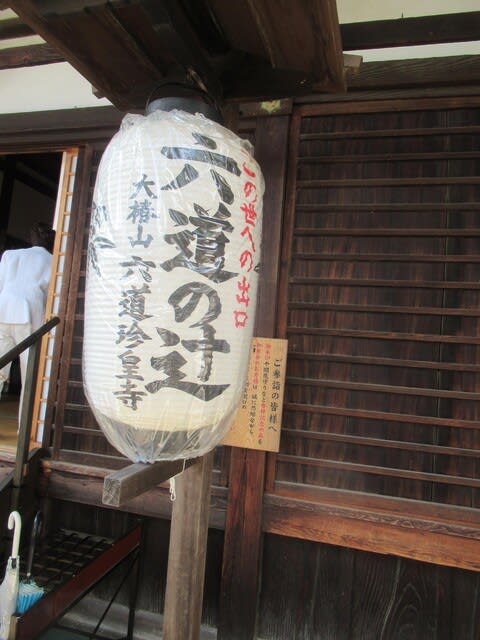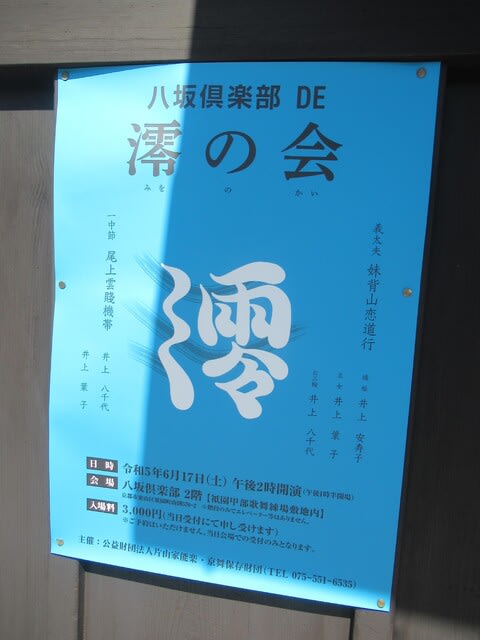2022-12-10寺町通りブラ散策、2022-12-13京漆器象彦 参照
御池通り(二条通り)から丸太通りを南北に通る寺町通りは
古い木造の日本家屋が並び趣きがある町並みが続く。
昨年に続き、また寺町通りにある名店を訪ねてみた。



一保堂茶舗京都本店は1717年(享保2年)創業の日本茶専門店。
屋号の由来は山階宮家から賜ったもので「茶一つを保つ」の意。
茶の加工と販売を主な事業とし、デパートなどの販路以外に茶道の家へ茶を納めている。
品揃えは茶の他に茶器も扱われている。
抹茶は表千家と裏千家好みの双方をそろえられている。
近年は京都市と協力したイベントも手掛けている。
https://www.ippodo-tea.co.jp/


お茶売り場の隣りには喫茶室「嘉木」がある。
お茶とお菓子を味わいながらほっとひと息。
銘柄や淹れ方によって味わいが変化する日本茶で常時14のメニューが用意されている。
抹茶の薄茶(ふんわりとした口当たり)、濃茶(とろりとしたペースト状)。
玉露は3種で「天下一」はなんと2,200円もする。
煎茶も3種、番茶はほうじ茶と玄米茶がある(全て和菓子付き)。
お茶は急須で3煎楽しむことができ、1煎目はスタッフがお淹れしてくれる。


一保堂から数軒下るとクッキー、ロシアンケーキなどで有名な西洋菓子舗「村上開進堂」がある。
当店は創業1907年(明治40年)で京都最古の洋菓子店。
このレトロな洋風建築は昭和初期に建てられたもの。
一歩店内に足を踏み入れると、そこは和洋折衷の昭和モダンの世界。
当時から変わらないショーケースや大理石の柱、タイル張りの床など
「タイムスリップできる空間」と老若男女から人気を集めている。
奥には自宅をリノベーションして2017年にオープンしたカフェもある。
ここのクッキー缶は予約制でたいへん人気があるため注文から数ヶ月待ちだとか。
昨年に続き今回もご覧のように定休日。
スミダマンにとっては縁がない店なのか?!


ある老舗有名店のおすすめで日本最古の御香調達所「薫玉堂」を訪ねてみた。
当店は創業文禄3年(1594年)本願寺出入りの薬種商として創業。
以来、この地に於いて420年以上に亘り香りを誂えてきた。
大地の恵みを受けて育った植物には人を優しく癒し元気つける力が秘められていると言われている。
香老舗ならではの調香へのこだわりを大切にしながらも、
現代の生活に寄り添った香りの在り方を提案している。
https://www.kungyokudo.co.jp/


御茶道具、書画、骨董、美術道具などを誠実に買い取りをしている古美術の「都屋」さん。
この古色蒼然とした建物がすごい。
一民家の家で象の彫刻が飾られているのにはビックリだ。
こんな古美術商、骨董商、アンティークショップが約28軒ほど、この通りに並んでいる。
まさに寺町美術通りと言われる所似だ。





スミダマンのブログで度々紹介をしてきた京都でのパンのパイオニア「進々堂」の寺町店。
進々堂は大正2年(1913年)京都に創業したベーカリーで京都市内に12店舗をかまえている。
寺町店はレストラン(モーニング、ランチ)、イートイン、ショップがあり、
ゆっくりしたスペースで美味しいパンが召し上がれる。
進々堂の願いはお客様の命の糧となる混じりけのないパンをつくりたい、
パンのある心豊かな生活をお客様と分かち合いたいだそうだ。
https://www.shinshindo.jp/



昨年秋に快くトイレをお借りしたホテル「THE SCREEN」。
あまり大きくないホテルだが、中に入ると素敵な空気が流れ、ホスピタリティも素晴らしい。
とても印象深い、記憶に残るホテルだった。
きっと京都にはこのようなホテルがまだまだいくつもあるのだろう。
他にも2022年12月13日アップした京漆器の名店「象彦」さん。
天保年間創業の蒸し寿司で有名な「末廣」もこの通りにある。