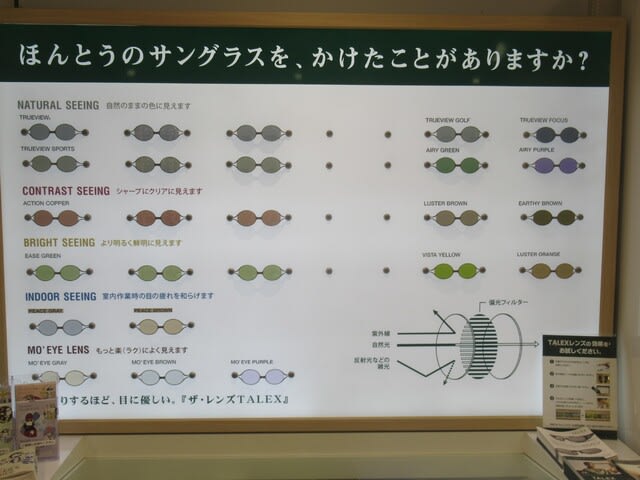(2014-12-6付ブログ参照)

1枚目の写真はたまたま「史跡重要文化財旧富岡製糸場」の木製看板と昔のレトロな郵便ポストと
前回のブログと同じアングルでスタート。
あれ?看板を見ると「世界遺産、国宝、重要文化財、史跡」とタイトルが変わっていた。

富岡製糸場の案内図。
敷地面積は53.738㎡(16.255坪)という広大な工場だ。
今回もガイドさんの話はここから始まった。

この方が我々グループの担当した解説員ガイドさん。
このガイドツアーは所要時間約40分、大人1人200円だ。
自分なりの工夫努力をしているようで興味深い。
この方も後ほどアップしますが貴重な資料を持っての説明は説得力があった。

正面の東置繭所(国宝)のトンネルゲートの上にはレンガの建物の中心に小さくだが
「明治五年」の刻銘が目に飛び込んできた。
富岡製糸場は日本で最初の官営模範製糸場で明治5年に建設された。

ガイドさん曰く、この東置繭所の長い建物は木骨レンガ造2階建てで
明治5年の創業当時からの建物だ。
よく見ると建物が波を打っていると言っていた。



国宝東置繭所隣りにあった乾燥場がガイドさんの話によると建物が台風で倒壊してしまったとのこと。
古い建物ということは色々なことが起きるのですネー。

こちらは「社宅76」。
体験室、おかいこ生態展示、暮らしのギャラリーとして公開されている。
スミダマンもそれなりの年齢になってこのような建物を見ると昔を思い出しホットするものを感じてしまう。

富岡製糸場で働いていた女工をキャラクターにした「お富ちゃん」。

ガイドさんはツアーで巡りながら、その都度のポイントで
様々な資料を使ってわかりやすく説明をしてくれる。
この写真は女人の座操り器を使った糸取りの様子。



国宝東置繭所は木骨煉瓦造りでできておりその組み合わせをアップで撮ってみた。
2枚目のスチール扉の蝶番はフランスから輸入したものだとか。
3枚目は重要文化財の検査人館。
お雇いフランス人用の宿舎として明治6年にたてられた。


「百閒は一見にしかず」。
ガイドさんがお蚕の幼虫から繭そして成虫のサンプルを見せて説明してくれた。
やはり現物を見ながらだと説得力がある。

こちらの建物は重要文化財で伝習女工に機械製糸の技術を教えたフランス女性教師4名のために
明治6年に建てられた「女工館」


やはり明治5年建築された「繰糸所」。
ここは繭から生糸を取る作業(繰糸)が行われていた場所で
創業に当たりフランス式の操糸器300釜が設置され、
その当時世界最大規模の製糸場だった。



いよいよ工場内の見学になった。
この工場の小屋組は「トラスト構造」という従来の日本になかった建築工法が用いられた。
さらに採光のために多くのガラス窓や屋根の上に蒸気抜きの越屋根が取り付けられた。
なお、繰糸の機械は自動車で一世を風靡したプリンス製だ。


ここでもガイドさんは写真パネルを持って説明。
この機械はフランス式繰糸機。
そしてこの機械を使った繰糸作業の再現した写真。



今度はガイドさん、本物の生糸を取り出し、その特徴などを話してくれた。

この写真は貴重なもので設立指導者として雇われたフランス人、ポール・ブリュナー一行のもの。


重要文化財の首長館(ブリュナ館)。
ブリュナは任期満了の明治8年12月までで、ここで家族とともに暮らしていた。


静かで懐の深い西上州の山々。
そして眼下に流れる鏑川。
製糸場創業当時、全国から500名を超える工女さんたちが電車や自動車もない時代遥々この地にやってきた。
この風景を眺め遠い故郷を思い出したのではないかと
ガイドさんがしみじみ話したのが一番印象深かった。