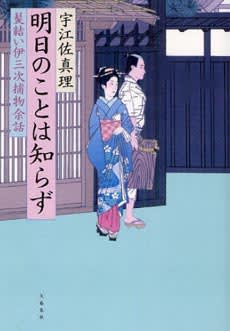 2012年8月発行
2012年8月発行シリーズ第11弾は、捕物劇よりも、人情味を搦め、中年となった伊三次のしっとりとした大人の味を描く。
あやめ供養
赤い花
赤のまんまに魚そえて
明日のことは知らず
やぶ柑子
ヘイサラバサラ 計6編の短編集
あやめ供養
八丁堀の町医者松浦桂庵の母がみまかった。だが、死後遺品が失せている事に疑念を抱いた桂庵は、伊三次に探索を依頼するが、疑いはなんと、嫌疑は直次郎にあった。
物語の本筋よりも、直次郎が登場した事に胸が震える思いだった。直次郎を信じたいが信じ切れない伊三次の葛藤。
ただ、直次郎もすっかり落ち着いて父親になっていた。若かりし頃の奔放さもなく、これからシリーズが続こうが、登場シーンはないだろうと思わせる。
赤い花
弟子の九兵衛に、嫁入りの話が持ち上がった。相手は、九兵衛の父親である岩次が奉公する魚佐の末娘おてん。どうやら、おてんの懸想らしいが、相談を持ち掛けられた伊三次は、九兵衛におてんをどう思っているか真意を問い質す役目を引き受けるのだった。
梅床と伊三次の確執。そして九兵衛の恋愛模様。あの小さかった九兵衛が…と思うと物語りながら月日の流れを実感する。
この実感が臨場感に違いなく、はかのどの物語にも感じた事はない。
赤のまんまに魚そえて
菓子屋金沢屋の庄助の髪結いを頼まれた伊三次。そこで、庄助の芳しくない過去に行き当たる。調べれば調べるほど庄助は匂う。だが、尻尾を出さない庄助に伊三次は遣る瀬ない思いを募らせる。
これは良い。伊三次シリーズ中、かなり胸が震えた話である。しかも、本筋に集中せず、九兵衛の話も交え、それを巧みに交差させ、日常の臨場感をあおらせる。
切ない恋心の話であるが、結末が悲壮に終わらずにほっとした。
明日のことは知らず
伊与太は、2階屋の物干に佇む、佃煮屋の若内儀を仕舞屋の影から写生しているが、その物悲しそうな表情が気になっていた。その若内儀が、物干から誤って転落したと耳にする。
一方の茜は、仕える大名家の跡目相続にまつわる御家騒動の渦中にあった。
これは、家を離れている伊与太と茜を無理矢理ぶち込んだのだろうか? 双方結末が描かれておらず、茜の方は続編が出来そうだが、佃煮屋の若内儀に関しては闇に葬られるのだろうか? そう感じたが、よくよく考えると、「髪結い伊三次捕物余話」なのである。捕物が主ではないのだ。改めてそう考えると、ここで伊与太が抱いた思いや葛藤が、この物語には相応しい。
似通った事件が「赤のまんまに魚そえて」となっている。明暗分かれた結末。
やぶ柑子
海野隼之助は、藩が御取り潰しになり早3年。父の遺言状ともなった仕官への助成を願う文を携え、毎度の門前払いに懲りず、幾度も元藩士の元を訪うのだった。
偶然にも知合った隼之助の為に、伊三次とお文は一肌脱ごうとするが…。
捕り物でもなく、事件でもないが、人の無情さを描きながらも、爽やかな後味の良い話である。
情けは人の為ならずは、通用しないと現代にも通じる話である。
ヘイサラバサラ
変わり者の元町医者が死に、奇妙な遺品が何かを突き止めて欲しいと、家主の扇屋八兵衛の依頼を受けた伊三次。里帰りしていた伊与太と共に、探索に走るのだった。
シリーズの中では一風変わった作品に仕上がっており、伊三次親子の絆と子たちの成長が、本筋の裏で静かに描かれる。
実はこのところ、不破龍之進絡みや、伊与太、茜の成長振りが描かれる事が多く、伊三次はすっかり脇に追いやられた感が否めず、本作品も読もうか否か迷ったのだが、結果、「読んで良かった」。
何故か満足感ではなく達成感にも似た、喜ばしさである。
大人になった子どもたちも良いのだが、やはり宇江佐さんデビュー作であり、最初に生み出した伊三次の魅力には変え難い物がある。今回は、表題の「明日のことは知らず」以外は伊三次が出ずっぱりであり、そして彼の抱く思いにいちいち「うんうん」頷けるのだ。
派手な捕物はないが、静かにしっとりとした伊三次に「参った」。
そして、今回の目玉は、何と言っても直次郎だろう。もはや登場する事はないだろうと、諦めていた直次郎だっただけに、これまた旧知の知り合いにでもふいに出会した気分であった。
伊三次と直次郎の掛け合いは楽しみである。
更に、こちらも驚いたのだが、ずっと脇役であろうと思われた伊三次の弟子の九兵衛が、俄にクローズアップされ、そしてまた、こちらも魅力的なキャラになっていった。
松助、おふさ、佐登里義親子のほのぼのとしたシーンも捨て難い。
一方で、お文は完全に伊三次の女房、不破友之進も龍之進の父親といった位置付けに甘んじるが、これだけ魅力的なキャラが多く登場する物語においては仕方ないだろう。
宇江佐さんの書籍を読み尽くし、ほかの作家の作品にも涙したり、胸を詰まらせたりしているが、やはり宇江佐さんでなければ味わい切れない物がある。
「明日にでも、次回作を読みたい」。そんな思いである。
余談ではあるが、宇江佐さんの作品であれば、登場人物が幾ら多くても、すっと頭に入ってくるのは、設定と最初のキャラ説明に巧さだろう。
主要登場人物
伊三次...廻り髪結い、不破友之進の小者
お文(文吉)...伊三次の妻、日本橋前田の芸妓
伊与太...伊三次の息子、芝愛宕下の歌川豊光の門人
お吉...伊三次の娘
九兵衛...伊三次の弟子、九兵衛店の岩次の息子
岩次...新場魚問屋魚佐の奉公人
お梶...九兵衛の母親
お園...髪結床梅床十兵衛の女房、伊三次の姉
不破友之進...北町奉行所臨時廻り同心
いなみ...友之進の妻
不破龍之進...友之進の嫡男、北町奉行所定廻り同心
茜(刑部)...友之進の長女、下谷新寺町蝦夷松前藩江戸屋敷の奥女中
きい...龍之進の妻
笹岡小平太...北町奉行所同心、元北町奉行所物書同心清十郎の養子、きいの実弟
松助...本八丁堀の岡っ引き(元不破家の中間)
おふさ...伊三次家の女中、松助の妻
佐登里...松助とおふさの養子
三保蔵...不破家下男
おたつ...不破家女中
橋口譲之進...北町奉行所年番方同心
古川喜六...北北町奉行所吟味方同心
直次郎(時助)...深川入舟町小間物屋・花屋播磨屋の主、(元掏摸)
おてん...新場魚問屋魚佐の末娘
利助...京橋炭町梅床の髪結い
松浦桂庵...八丁堀町医者
松浦美佐...桂庵の母親
おたに...松浦家の下女
浜次...新場魚問屋魚佐の奉公人、九兵衛の幼馴染み
伝次郎...新場魚問屋魚佐の奉公人、九兵衛の幼馴染み
庄助...八丁堀北紺屋町菓子屋金沢屋の若旦那
おあさ...金沢屋の女中
庄左衛門...金沢屋の主、庄助の父親
福次...歌川豊光の門人、伊与太の兄弟子
美濃吉...歌川豊光の門人、伊与太の兄弟子
栄吉...浜松町佃煮屋野崎屋の若旦那
おけい...栄吉の妻
お楽...芝神明社参道若松屋の矢場女
松前良昌...蝦夷松前藩藩主道昌の嫡男
金之丞...松前藩江戸屋敷の奥女中、茜の朋輩
馬之介...松前藩江戸屋敷の奥女中、茜の朋輩
お愛の方...前藩藩主道昌の側室
藤崎...松前藩江戸屋敷の老女
海野隼之助...元紀州吉川藩吉川家勘定方見習い
久慈七右衛門...肥後熊本藩細川家家臣、元吉川家家臣
ふじ...隼之助の妻
八兵衛...日本橋左内町箸屋翁屋の主










 2007年12月発行
2007年12月発行 2009年6月発行
2009年6月発行 2012年3月発行
2012年3月発行 2012年1月発行
2012年1月発行 2011年9月発行
2011年9月発行 2011年7月発行
2011年7月発行 2010年10月発行
2010年10月発行 2010年9月発行
2010年9月発行 2010年7月発行
2010年7月発行 2010年1月発行
2010年1月発行 2009年10月発行
2009年10月発行 2009年3月発行
2009年3月発行 2009年1月発行
2009年1月発行  2008年11月発行
2008年11月発行