本作まぁ普通に考えると「SF」ではないのでしょうが....。
1979年の発刊で、発刊当時世間的に不評であったため、本作を高く評価していた当時日本SF作家クラブの事務局長の筒井康隆が本作に受賞させようと「日本SF大賞」を創設したという話があります。(wikipediaー日本SF大賞)結局第一回は小松左京が強く推す「太陽風交点」が受賞しましたが、第二回は井上ひさしの「吉里吉里人」が受賞と、ジャンルとしての「SFにこだわらない」姿勢は貫かれた感じです。
「太陽風交点」の受賞はその後早川と徳間の抗争の基になっていますし、「吉里吉里人」に受章させるくらいなら、もっと他の作品を評価した方が後のSFの発展につながったような気もするので成り立ちからこの賞ジャンルSFにとってどうか?という気がしますが...。
と余談はともかく、昨年後半日本SFに凝ったからみもあって前述のような展開にも興味を持ち本書を手に取りました。
あとは大江健三郎くらい多少は読んでいないと、小説について「偉そうな(?)こといえないなー」という感もありましたー(大江作品は「万延元年のフットボール」を昔読んだだけ、こちらは世評も高いですが私も読んでとても面白かった記憶があります。)
本自体は「読まなきゃなー」という感があり10年位前に古本屋で入手済み。

内容紹介(裏表紙記載)
海に向って追放された武士の集団が、川を遡って、四国の山奥に《村=匡家=小宇宙》を創建し、長い〈自由時代〉のあと、大日本帝国と全面戦争に突入した!?壊す人、アポ爺、ペリ爺、オシコメ、シリメ、「木から降りん人」等々、奇体な人物を繰り出しながら、父=神主の息子〈僕〉が双生児の妹に向けて語る、一族の神話と歴史。特異な作家的想像力が構築した、現代文学の収穫1000枚。
とりあえずの感想としては....。
ものすごい「面白い」とは言えない作品でしたかねぇ。
本書は四国の山奥の<村=国家=小宇宙>の歴史を語るべく、父=神主ののスパルタ教育を受けた語り手「僕」が第一部ではメキシコから、第二部以降は東京から<村=国家=小宇宙>にいる妹へ向けて、<村=国家=小宇宙>の歴史をつづった書簡の形の形を取っています。
第一の手紙はプロローグ的なもの、、第二の手紙で<村=国家=小宇宙>(しつこいですが本の趣旨にそいます....)の神話的な部分が語られます。
神話の部分がかなり長く感じたのですが....(イメージ半分くらい)見直すと意外と短いんですね。
<村=国家=小宇宙>の「藩」からの離脱、創設の物語、創設者たる壊す人の不死性、巨大化したという伝説、それに対峙した女性オシコメの伝説などが語られます。
第三の手紙は江戸後期~幕末あたりなのでまぁ歴史とも民話ともつかない感じ。
第四の手紙は第二次世界大戦直前、第五の手紙が主人公の家族をめぐる話、歴史...というか近所のホラ話に近い感じ。
第六の手紙が僕と父=神主の関係外来者と「村」、外来者たるアポ爺、ペリ爺と国家権力とそれを守らない「村」のリアルなお話。
そして「神話」「民話」「歴史」「ホラ話」と実際の「僕」とみたところの着地点というお話かと思いました。
まぁ、つまらないということもなくそれなりに読めるのですが、全体的に「旧い」感じがしました。
wikipediaでも本作”文化人類学者の山口昌男の著書を下敷きにして書かれている。”と記載されていますが、この山口昌男氏が著作を発表してるのが1970年代。
「民族学やら神話に隠された真の歴史を読み解く」というような話が世の中でそれなりに一般化しだした時代だったのかなぁと。
「騎馬民族国家」が1967年、70年頃は邪馬台国ブームでしたし、高木彬光の「邪馬台国の秘密」が1973年。
松本清張るが古代史に興味を持ちだしたのも70年代、80年代前半まではそんな話がはやっていたような記憶があります。(高木彬光「古代天皇の秘密」は1986年。)
私もその辺の話好きなので当時いろいろ読んだ記憶があります。
そんあこんなもあり新鮮味を感じないのかもしれせん。
(最近の流行りは信長辺りの頃のヨーロッパ陰謀説、幕末期の幕府の当事者能力見直しというところ?)
また本書「民話」「神話」を「本当にあった歴史」として叙述していくという意味で、パロディでありそういう意味では斬新なんでしょうが...。
パロディとしては筒井康隆や清水義範の作品の方が徹底していて今読んでも楽しめそうな気がします。(「筒井順慶」とか「蕎麦ときしめん」とか、今読んで本当に楽しめるかは読んでないので???ですが...)。
政治思想的なもの、父子関係、土俗的意識と都市文化の対立、第二次世界大戦の意味、戦後の時代転換といったテーマがうっすらとではなくかなり鼻につくように思われるのがなんだか1960年代的で当時(1979年)としてもちょっと旧く感じられたんじゃないかと思うのですが....どうなんでしょう?
冒頭記載の通り文壇の一部からは本作ずいぶん不評をかったようですが...。
ほぼ同じテーマでのちに(1986年)著者は『M/Tと森のフシギの物語』を執筆した(MはMatriarch=オシコメ、TはTrickster=壊す人を意味するようです。)くらいですからこのテーマそうれなりに入れ込んでいたんでしょうね。
機会があればこちらも読んでみたいところですが....ずいぶん先かなぁ。
↓巨匠の作品お前にわかるのか?という方も、まぁいいんじゃない・・・という方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
1979年の発刊で、発刊当時世間的に不評であったため、本作を高く評価していた当時日本SF作家クラブの事務局長の筒井康隆が本作に受賞させようと「日本SF大賞」を創設したという話があります。(wikipediaー日本SF大賞)結局第一回は小松左京が強く推す「太陽風交点」が受賞しましたが、第二回は井上ひさしの「吉里吉里人」が受賞と、ジャンルとしての「SFにこだわらない」姿勢は貫かれた感じです。
「太陽風交点」の受賞はその後早川と徳間の抗争の基になっていますし、「吉里吉里人」に受章させるくらいなら、もっと他の作品を評価した方が後のSFの発展につながったような気もするので成り立ちからこの賞ジャンルSFにとってどうか?という気がしますが...。
と余談はともかく、昨年後半日本SFに凝ったからみもあって前述のような展開にも興味を持ち本書を手に取りました。
あとは大江健三郎くらい多少は読んでいないと、小説について「偉そうな(?)こといえないなー」という感もありましたー(大江作品は「万延元年のフットボール」を昔読んだだけ、こちらは世評も高いですが私も読んでとても面白かった記憶があります。)
本自体は「読まなきゃなー」という感があり10年位前に古本屋で入手済み。

内容紹介(裏表紙記載)
海に向って追放された武士の集団が、川を遡って、四国の山奥に《村=匡家=小宇宙》を創建し、長い〈自由時代〉のあと、大日本帝国と全面戦争に突入した!?壊す人、アポ爺、ペリ爺、オシコメ、シリメ、「木から降りん人」等々、奇体な人物を繰り出しながら、父=神主の息子〈僕〉が双生児の妹に向けて語る、一族の神話と歴史。特異な作家的想像力が構築した、現代文学の収穫1000枚。
とりあえずの感想としては....。
ものすごい「面白い」とは言えない作品でしたかねぇ。
本書は四国の山奥の<村=国家=小宇宙>の歴史を語るべく、父=神主ののスパルタ教育を受けた語り手「僕」が第一部ではメキシコから、第二部以降は東京から<村=国家=小宇宙>にいる妹へ向けて、<村=国家=小宇宙>の歴史をつづった書簡の形の形を取っています。
第一の手紙はプロローグ的なもの、、第二の手紙で<村=国家=小宇宙>(しつこいですが本の趣旨にそいます....)の神話的な部分が語られます。
神話の部分がかなり長く感じたのですが....(イメージ半分くらい)見直すと意外と短いんですね。
<村=国家=小宇宙>の「藩」からの離脱、創設の物語、創設者たる壊す人の不死性、巨大化したという伝説、それに対峙した女性オシコメの伝説などが語られます。
第三の手紙は江戸後期~幕末あたりなのでまぁ歴史とも民話ともつかない感じ。
第四の手紙は第二次世界大戦直前、第五の手紙が主人公の家族をめぐる話、歴史...というか近所のホラ話に近い感じ。
第六の手紙が僕と父=神主の関係外来者と「村」、外来者たるアポ爺、ペリ爺と国家権力とそれを守らない「村」のリアルなお話。
そして「神話」「民話」「歴史」「ホラ話」と実際の「僕」とみたところの着地点というお話かと思いました。
まぁ、つまらないということもなくそれなりに読めるのですが、全体的に「旧い」感じがしました。
wikipediaでも本作”文化人類学者の山口昌男の著書を下敷きにして書かれている。”と記載されていますが、この山口昌男氏が著作を発表してるのが1970年代。
「民族学やら神話に隠された真の歴史を読み解く」というような話が世の中でそれなりに一般化しだした時代だったのかなぁと。
「騎馬民族国家」が1967年、70年頃は邪馬台国ブームでしたし、高木彬光の「邪馬台国の秘密」が1973年。
松本清張るが古代史に興味を持ちだしたのも70年代、80年代前半まではそんな話がはやっていたような記憶があります。(高木彬光「古代天皇の秘密」は1986年。)
私もその辺の話好きなので当時いろいろ読んだ記憶があります。
そんあこんなもあり新鮮味を感じないのかもしれせん。
(最近の流行りは信長辺りの頃のヨーロッパ陰謀説、幕末期の幕府の当事者能力見直しというところ?)
また本書「民話」「神話」を「本当にあった歴史」として叙述していくという意味で、パロディでありそういう意味では斬新なんでしょうが...。
パロディとしては筒井康隆や清水義範の作品の方が徹底していて今読んでも楽しめそうな気がします。(「筒井順慶」とか「蕎麦ときしめん」とか、今読んで本当に楽しめるかは読んでないので???ですが...)。
政治思想的なもの、父子関係、土俗的意識と都市文化の対立、第二次世界大戦の意味、戦後の時代転換といったテーマがうっすらとではなくかなり鼻につくように思われるのがなんだか1960年代的で当時(1979年)としてもちょっと旧く感じられたんじゃないかと思うのですが....どうなんでしょう?
冒頭記載の通り文壇の一部からは本作ずいぶん不評をかったようですが...。
ほぼ同じテーマでのちに(1986年)著者は『M/Tと森のフシギの物語』を執筆した(MはMatriarch=オシコメ、TはTrickster=壊す人を意味するようです。)くらいですからこのテーマそうれなりに入れ込んでいたんでしょうね。
機会があればこちらも読んでみたいところですが....ずいぶん先かなぁ。
↓巨匠の作品お前にわかるのか?という方も、まぁいいんじゃない・・・という方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










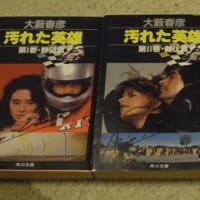
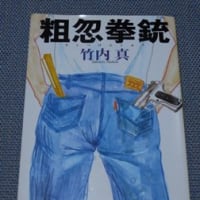
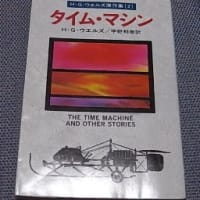
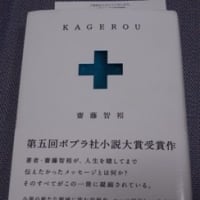
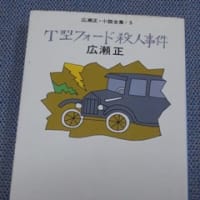
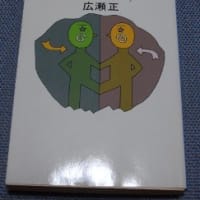


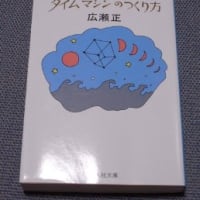
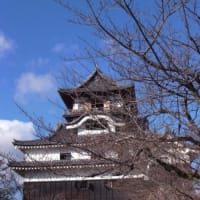






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます