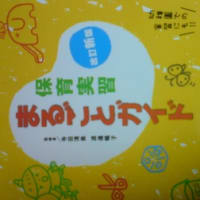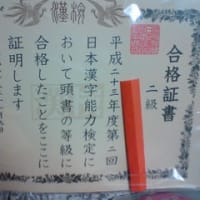「位をそろえて」
「足し算か引き算かを確かめて」
「一の位から順序良く」
「上から下に」
計算していく事を刷り込みつつ、
繰り下がりのある引き算に入っていきます。
繰り下がりは、
「お隣から借りてくる」
引き算です。
この意味を教えるのには、やはり「お金」の力を借りるのがいいと思うのですが、
我のんびり娘のように、2年生の段階では、お金を使ってもやはりチンプンカンプンのお子さんもいるかと思います。
それでも、今後の生活体験などを考えると、やはりここは「お金」で説明していくのがいいのではないかと思うのです。
今、完全に理解できなくても、今後学年があがって、
何度かおさらいをする機会に、同じようにお金で説明してあげると、
「あぁそうだったんだ。」と、ストンとおちる時がくる。
学校で、継続して子ども達を見てきて、実感する事です。
私の場合は、数字と一緒にお金を書いて説明しながら計算をする事が多いです。
別々に説明すると、「それはそれ・・」になってしまうお子さんがかなりますので。
写真は、携帯からしか送れないので(私の技術が無いためです)、後で入れます。
43
- 18
の場合、いつものように、
引き算である事、筆算は一の位からはじめることを確認して計算をはじめます。
こんな感じ。
「3から8は 引けません。」
ひけませんの、「せん」の部分を強調して、
この「せん」にあわせて、4に斜線を引かせちゃいます。
繰り下がりのある筆算を、機械的に覚えると、
繰り下がりのないときでも、反射的に10の位から借りてきて困ってしまうお子さんが多いんですね。
そういう混乱を避けるために、「引けません」の「せん」を使うんです。
引ければ数字を下に書く、引けなかったら、引けませんで線を引く。
線さえひてしまえば、結構手順は入っているという子が多いんですね。
絵のほうですが、
「引けなかったら借りてくる。
十円箱から、十円玉を1個借りてくるから、
4個が3個に減っちゃうね。
10円玉1個は1円玉いくつかなぁ?」
と聞いてみて、「10個!」と答えるお子さんの場合はすんなりと10個を一の位の箱に書き、
詰まるようなら、1円玉を「1円、2円、3円・・・」と数えながら「10円」になるまで書いてあげて、「何個だった?」って聞いてみます。
こうして絵を書きながら、お金が動くたびに数字のほうも操作してあげるんです。
「ほら、今十円玉を隣にあげたから十円玉箱には何個入ってる?3個だね。」といって、斜線を引いた4の上に3という数字を。
「1円玉の箱は、10個もらったから、13個だね。」
といいながら、3の横に1を書き足しちゃう。
この一の位の数字操作のやり方には、ふたつ方法がありまして、
今私が書いた、3の横に1を書いて13にして計算する方法と、
借りてきた10を3の上に10とそのまま書く方法。
順数を使った計算をするお子さんは、13-8の方が計算がスムーズだし、
10の補数(10から引いて残りをくっつけるやり方)を使うお子さんは、
10のまま書いておき、そこから8を引いて2。その2ともともとあった3をくっつけて5。というやり方の方が間違えないようです。
一の位が終わったら、十の位に移ります。
斜線を引いた4をそのまま使って計算するようなお子さんもいるのですけど、
お金を書いてあると、そういうミスはなくなります。
「この箱には今3個しか10円玉が無い。そこから1個とるから残りは2個。」
2,3回お金を書きながらやってみて、なんとなく納得したようなら、
数字だけの操作にします。
そのときも、声かけでは「十円を借りるよ」など、
頭の中に、先ほど書いたような絵が浮かぶようにしてあげると、
ただ数字だけの操作をするのより、定着が良いようです。
1度覚えても、また時間が経つと混乱してしまうお子さんも多いですが、
『引けません』とか『10円借りるよ』とか、
頭に引っかかりやすいキーワードを刷り込んでおくことで、
「あぁそうだった」と、思い出しやすくなるように思います。
「足し算か引き算かを確かめて」
「一の位から順序良く」
「上から下に」
計算していく事を刷り込みつつ、
繰り下がりのある引き算に入っていきます。
繰り下がりは、
「お隣から借りてくる」
引き算です。
この意味を教えるのには、やはり「お金」の力を借りるのがいいと思うのですが、
我のんびり娘のように、2年生の段階では、お金を使ってもやはりチンプンカンプンのお子さんもいるかと思います。
それでも、今後の生活体験などを考えると、やはりここは「お金」で説明していくのがいいのではないかと思うのです。
今、完全に理解できなくても、今後学年があがって、
何度かおさらいをする機会に、同じようにお金で説明してあげると、
「あぁそうだったんだ。」と、ストンとおちる時がくる。
学校で、継続して子ども達を見てきて、実感する事です。
私の場合は、数字と一緒にお金を書いて説明しながら計算をする事が多いです。
別々に説明すると、「それはそれ・・」になってしまうお子さんがかなりますので。
写真は、携帯からしか送れないので(私の技術が無いためです)、後で入れます。
43
- 18
の場合、いつものように、
引き算である事、筆算は一の位からはじめることを確認して計算をはじめます。
こんな感じ。
「3から8は 引けません。」
ひけませんの、「せん」の部分を強調して、
この「せん」にあわせて、4に斜線を引かせちゃいます。
繰り下がりのある筆算を、機械的に覚えると、
繰り下がりのないときでも、反射的に10の位から借りてきて困ってしまうお子さんが多いんですね。
そういう混乱を避けるために、「引けません」の「せん」を使うんです。
引ければ数字を下に書く、引けなかったら、引けませんで線を引く。
線さえひてしまえば、結構手順は入っているという子が多いんですね。
絵のほうですが、
「引けなかったら借りてくる。
十円箱から、十円玉を1個借りてくるから、
4個が3個に減っちゃうね。
10円玉1個は1円玉いくつかなぁ?」
と聞いてみて、「10個!」と答えるお子さんの場合はすんなりと10個を一の位の箱に書き、
詰まるようなら、1円玉を「1円、2円、3円・・・」と数えながら「10円」になるまで書いてあげて、「何個だった?」って聞いてみます。
こうして絵を書きながら、お金が動くたびに数字のほうも操作してあげるんです。
「ほら、今十円玉を隣にあげたから十円玉箱には何個入ってる?3個だね。」といって、斜線を引いた4の上に3という数字を。
「1円玉の箱は、10個もらったから、13個だね。」
といいながら、3の横に1を書き足しちゃう。
この一の位の数字操作のやり方には、ふたつ方法がありまして、
今私が書いた、3の横に1を書いて13にして計算する方法と、
借りてきた10を3の上に10とそのまま書く方法。
順数を使った計算をするお子さんは、13-8の方が計算がスムーズだし、
10の補数(10から引いて残りをくっつけるやり方)を使うお子さんは、
10のまま書いておき、そこから8を引いて2。その2ともともとあった3をくっつけて5。というやり方の方が間違えないようです。
一の位が終わったら、十の位に移ります。
斜線を引いた4をそのまま使って計算するようなお子さんもいるのですけど、
お金を書いてあると、そういうミスはなくなります。
「この箱には今3個しか10円玉が無い。そこから1個とるから残りは2個。」
2,3回お金を書きながらやってみて、なんとなく納得したようなら、
数字だけの操作にします。
そのときも、声かけでは「十円を借りるよ」など、
頭の中に、先ほど書いたような絵が浮かぶようにしてあげると、
ただ数字だけの操作をするのより、定着が良いようです。
1度覚えても、また時間が経つと混乱してしまうお子さんも多いですが、
『引けません』とか『10円借りるよ』とか、
頭に引っかかりやすいキーワードを刷り込んでおくことで、
「あぁそうだった」と、思い出しやすくなるように思います。