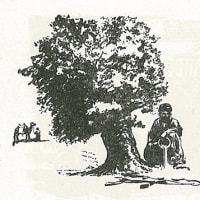古代ローマ帝国の建築、土木技術のレベルの高さは驚異的です。歴史の授業で、ローマ市内のコロッセウムなどの壮大な建築物の画像を見ては、ため息をついていたのを思い出します。
今回は、山の水源から都市まで、上水を運ぶ長大な導水路(以下、「水道」)と、それが谷を越えるために建設された水道橋の話題です。「ヨーロッパものしり紀行ーくらしとグルメ編ー」(紅山雪夫 新潮文庫)に拠り、小難しい話は抜きにし、そのスゴさをわかりやすくお伝えします。どうぞ気軽に最後までお付き合いください。
古代民族の多くは、上水として川の水を利用して来ました。水量は豊富ですし、特別な施設なしで、比較的手軽に利用できますから。でも、ローマ人は、川の水が伝染病の源と考え、得意の土木技術で、長大な水道と、水道橋を帝国領内のあちらこちらに建設しました。
紀元前1世紀から紀元後2世紀のローマ帝国最盛期が、建設の最盛期と重なります。戦えば必ず勝つ強大な軍事力を背景に、領土を拡大しました。そして、領土となった属州からの富を財源に、戦争で得た何万という捕虜を労働力として利用できたからこその建設ラッシュです。
本書が取り上げるのは、南フランス・ニームの水道と、その水道がガール川の谷をまたぐ水道橋(ポン・デュ・ガール)です。まずは、華麗で力強い水道橋をご覧ください(以下の画像は、すべて同書から)。

水源は、ニームの街から直線距離で約21キロ北の山間にある「ウールの泉」です。石灰岩質の山を背に、豊富な水量を誇ります。最短で結んでも、相当な距離ですが、途中には、山、谷などの障害物があります。山はトンネルを通し、ガール川の深い谷は、先ほどご覧いただいた水道橋を利用します。大きく迂回を強いられ、総延長は約50キロにもなりました。それでもこの程度の長さの水道は、いくらでも例があったといいますから、驚きです。
さて、橋の概要です。両側の緑の斜面を背景に、黄褐色の石をアーチ状に積み上げた3層式の水道橋で、最上段が導水路になっています。長さは275メートル、高さは52メートル(12階建のビル相当)と迫力満点。
そして、水道建設で大事なことは、適切な落差を設けることです。落差が大き過ぎれば、末端で水が溢れてしまいます。小さ過ぎれば、水がズムーズに流れず、濁りや汚染が発生します。
ニームの水道の場合、50キロで、落差は17メートルです。なんと、平均すれば1キロでわずか34センチの落差を実現しています。人工的な水路の中を水がスムーズに流れるための最低限ギリギリいっぱいの落差だというのです。建設だけでなく、測量の面でも卓越した技術を発揮していたことがわかります。
この水道は、その最盛期には、1日あたり2万トンもの上水を供給していました。しかしながら、ローマの衰退と、それによるニームの人口減で水道は放棄され、9世紀まで水は流れていたものの、現在は流れていないのが残念です。
最上段の導水路がどうなっているか、ちょっと興味が湧きますよね。かつては、歩いて渡ることができ、著者も横断したというのです(現在は、文化財保護のため、立ち入り禁止だそう)。

ご覧のように、石の蓋(ふた)がしてありますが、ところどころ無くなっている箇所があります。そこを通るには、両側の幅50センチほどの側壁の上を通るのが基本で、足がすくみそうです。ただし、強風とかで危険な場合は、導水路の中へ降りる、という裏技があります。中は、人が楽に立って歩けるほどの大きさなので、それが可能なのです。高所恐怖症気味の私などは、画像を見ただけで、頭がクラクラします。
さて、そんな水道を通った水の終着点が、旧市街の北方にある石造りで円形の大きな分水槽です。かつては、ここから10本の水道本管に分かれて、市民に上水が供給されていました。
現在、ニームの分水槽から先の設備は残っていず、代わりに、遺跡の街ポンペイに残っている設備が紹介されています。「ヴェッティイの家」と呼ばれる邸宅の外側に、水道の鉛管が何本も露出しています。金持ちは個別に上水を引き込んでいたのですね。市民は、街角にある公共の給水施設を利用しました。「豊穣(アッポンダンツァ)の泉」と呼ばれる給水施設です。

「豊穣の女神」の像の口から鉛管が出ていて、人々は、水を汲みに来たり、飲んだりしました。富裕層にはそれなりの便宜を図る一方で、市民にもきめ細かくサービスを行き渡らせる・・・・ローマ帝国といえば、大規模な建造物に目が向きがちです。でも、市民へのサービスにもぬかりはなかったのですね。帝国繁栄の秘密はこんなところにもあったのかな、と感じたことでした。
いかがでしたか?スゴい技術の一端に触れていただければ幸いです。それでは次回をお楽しみに。