バイデン米大統領が、再選を目指していた11月の大統領選からの撤退を表明しました。現職大統領の再選断念は同じ民主党のジョンソン大統領以来56年ぶりです。
返り咲きを狙うトランプ前大統領の有利が伝えられ、党内で噴き出した撤退論に抗(あらが)い切れなかったのでしょう。自ら身を引くことで後継を託したハリス副大統領を当選に導くことができたのなら、後年、見事な「引き際」と称賛されるかもしれません。
ちょうど50年前の今ごろ、引き際が注目されていた権力者がいました。ニクソン大統領です。
ウォーターゲート事件を巡り、司法妨害や権力の乱用などを理由に大統領弾劾の手続きが進む中、所属する共和党の辞任圧力が日増しに高まっていたのです。
発端は米大統領選の真っ最中だった1972年6月、ワシントンのウォーターゲート・ビルの民主党本部に盗聴装置を仕掛けようとして侵入した5人組が逮捕されたこと。5人組はニクソン氏の再選委員会からカネを受け取り、ニクソン氏自身が事件の隠蔽(いんぺい)に関与したことがその後、明らかになりました。
◆辞任を巡る「悪あがき」
この事件をスクープしたのが米紙ワシントン・ポストのボブ・ウッドワード、カール・バーンスタイン両記者。映画にもなった著書「大統領の陰謀」には、政府高官や大統領自身の関わりを緻密な取材で暴いていく過程が、その続編「最後の日々」は、辞任を巡るニクソン氏の葛藤が描かれます。
辞任表明前夜の74年8月7日、ニクソン氏がキッシンジャー国務長官に辞意を伝える場面では、2人は外交成果などを語り合い、ニクソン氏は涙を流しながら嘆きます。「単純な侵入事件がどうしてこんなことになったのか」「私が何をやったというのか」
辞任を促す上院議員の手紙に激怒したり、家族の反対を口実に続投を訴えたり。一方、辞任をほのめかしたり、周囲に自殺を心配されたりの不安定な精神状態。
「最後の日々」で描かれたニクソン氏の引き際は「悪あがき」とも言えるものですが、退陣圧力にも抗い、地位に執着することは権力者の本能かもしれません。
さて50年後、それも日本に目を転じると、岸田文雄首相(自民党総裁)が「岸田降ろし」に直面しています。内閣支持率の低迷が長引く岸田氏には、9月の党総裁選に立候補しないでほしいとの空気が党内に充満しているのです。
岸田氏本人は精力的に全国を回り、新たな政策への取り組みを表明し続けています。最近では史上最長の安倍晋三政権でも実現できなかった改憲の論議加速を党内に繰り返し指示し、続投に向けた布石との冷めた見方も広がります。
弾劾裁判を控えて、高まる退陣圧力に抗ったニクソン氏も所属する共和党の支持を引き留めようと最後まであがきました。総裁選を目前にして、党内の支持獲得に腐心する岸田氏の姿は、50年前のニクソン氏に重なります。
岸田氏の不人気の要因の一つは自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件への対応でしょう。盗聴事件への自身の関与をもみ消そうとしたニクソン氏とは単純に比較できませんが、不祥事が政権基盤を削ることは共通しています。
ただ、岸田氏には、どこかひとごとのような雰囲気が漂います。自民党という組織の金銭スキャンダルにもかかわらず、組織のトップである自分には何のおとがめもなし。政治の再生を期すための政治資金規正法の改正も「抜け穴」だらけです。本気で取り組んでいるとはとても思えません。
岸田氏の首相在職は1千日を超え、戦後8番目の「長期政権」となりました。その自信が、退陣圧力にも動じない「鈍感力」につながっているのでしょうか。
◆過った決断を貫く習性
任期途中で辞任した初の米大統領という不名誉を歴史に刻むニクソン氏は、優れた政治批評家でもありました。チャーチル英首相、ドゴール仏大統領、周恩来中国首相ら各国指導者との交流を通じたリーダー論「指導者とは」は次のように記します。
「権力を振るい慣れると、その技術はますます上達する。自分の決断から大きい結果が流れ出すのを見るにつけ、指導者はますます自信を持って決断をするようになり、他人の過誤の責任をかぶるよりは、たとえ過っても自分の決断を貫こうとする」
岸田氏にも当てはまる洞察に思えてなりません。
















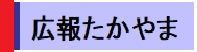












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます