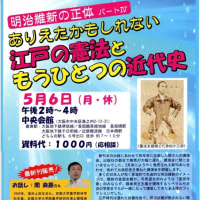『現代思想』2018年6月臨時増刊号は「明治維新の光と影」。いろいろ考えさせられた。
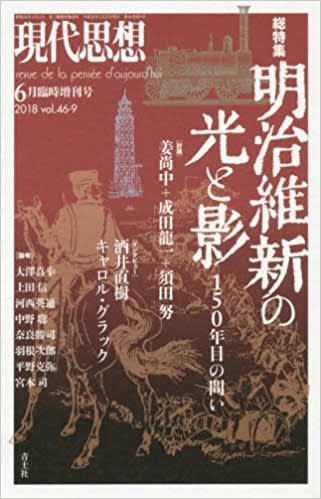
巻頭論文は、大澤真幸氏の「日本人はあの『革命』の敗者に共感している」。同氏の主張の骨子は以下のようなものであった。
日本人は、戦後民主主義体制は、所詮アメリカに与えられたものであり、日本人自らの力で何かを成し遂げたとは思っていない。それゆえ、日本人は、明治維新の記憶に立ち返ろうとする。しかし、実際のところ明治維新も所詮は単なる西洋の模倣にすぎず、日本人自らが何か価値あるものを成し遂げたわけではない。そこで日本人は、明治維新の敗者となった武士にむしろ共感することになる。今後、日本人が明治維新の敗者の無念を受け止め、彼らが成し得なかった願望を実現することができれば、そのとき初めて日本人は真に偉大な社会を創設したという自己確信を得ることができるだろう。
大澤氏のそこまでの主張にはおおむね賛成である。明治維新が単なる西洋近代の模倣ではなく、前近代的王権神授説を抱え込んだ「いびつな形の模倣」であったという点を除けば・・・。
私が『赤松小三郎ともう一つの明治維新』(作品社)を書いたのも、明治維新における敗者の無念に共感し、その記憶を蘇らせ、長州レジームから脱却することによってこそ、日本は失われた30年の閉塞状況から立ち直ることができるだろうと思ったからである。
しかし、その先の大澤氏の主張はいただけなかった。大澤氏は、敗者である武士たちの「武士道」のエートスを継承しつつ新しい社会をつくること・・・・これが偉大な社会を創設する自己確信につながるという。この点、原田伊織氏の主張と似ている。
国民的人気の新選組や坂本龍馬を引き合いに出して「武士道エートス」と主張するのもいただけない。近藤勇も土方歳三も多摩の百姓の出だし、坂本龍馬ももともと商人の家の出身だ。新選組には百姓のエートスが、坂本龍馬には商人のエートスが濃厚に見て取れる。江戸時代、百姓や商人でも武士になることができたのだ。
武士道的エートスを大事にする人が社会の中に一定いるのはかまわないし、良いことだとすら思うが、それでは国民の大多数は置いてけぼりをくらうだろう。私は、敗者たちの無念を継承し、新しい社会をつくるためのキーワードは、「公議輿論」だと考える。公議輿論こそは、慶応年間の時代変革を先導したキーワードであったにも関わらず、長州的な神国思想に踏みにじられた結果、その後の藩閥・軍閥・そして戦後の従米官閥支配の中、150年間実現することのなかった政治システムだからである。
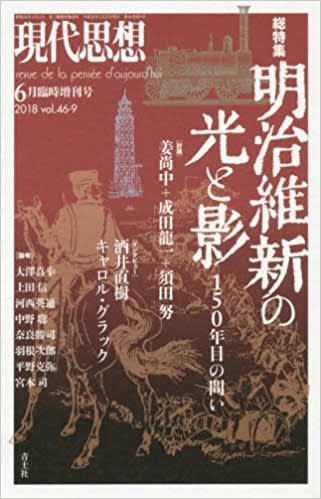
巻頭論文は、大澤真幸氏の「日本人はあの『革命』の敗者に共感している」。同氏の主張の骨子は以下のようなものであった。
日本人は、戦後民主主義体制は、所詮アメリカに与えられたものであり、日本人自らの力で何かを成し遂げたとは思っていない。それゆえ、日本人は、明治維新の記憶に立ち返ろうとする。しかし、実際のところ明治維新も所詮は単なる西洋の模倣にすぎず、日本人自らが何か価値あるものを成し遂げたわけではない。そこで日本人は、明治維新の敗者となった武士にむしろ共感することになる。今後、日本人が明治維新の敗者の無念を受け止め、彼らが成し得なかった願望を実現することができれば、そのとき初めて日本人は真に偉大な社会を創設したという自己確信を得ることができるだろう。
大澤氏のそこまでの主張にはおおむね賛成である。明治維新が単なる西洋近代の模倣ではなく、前近代的王権神授説を抱え込んだ「いびつな形の模倣」であったという点を除けば・・・。
私が『赤松小三郎ともう一つの明治維新』(作品社)を書いたのも、明治維新における敗者の無念に共感し、その記憶を蘇らせ、長州レジームから脱却することによってこそ、日本は失われた30年の閉塞状況から立ち直ることができるだろうと思ったからである。
しかし、その先の大澤氏の主張はいただけなかった。大澤氏は、敗者である武士たちの「武士道」のエートスを継承しつつ新しい社会をつくること・・・・これが偉大な社会を創設する自己確信につながるという。この点、原田伊織氏の主張と似ている。
国民的人気の新選組や坂本龍馬を引き合いに出して「武士道エートス」と主張するのもいただけない。近藤勇も土方歳三も多摩の百姓の出だし、坂本龍馬ももともと商人の家の出身だ。新選組には百姓のエートスが、坂本龍馬には商人のエートスが濃厚に見て取れる。江戸時代、百姓や商人でも武士になることができたのだ。
武士道的エートスを大事にする人が社会の中に一定いるのはかまわないし、良いことだとすら思うが、それでは国民の大多数は置いてけぼりをくらうだろう。私は、敗者たちの無念を継承し、新しい社会をつくるためのキーワードは、「公議輿論」だと考える。公議輿論こそは、慶応年間の時代変革を先導したキーワードであったにも関わらず、長州的な神国思想に踏みにじられた結果、その後の藩閥・軍閥・そして戦後の従米官閥支配の中、150年間実現することのなかった政治システムだからである。