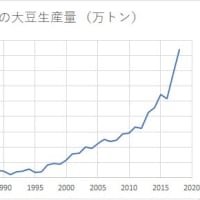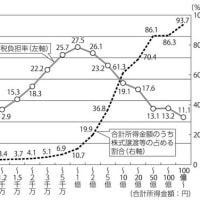「糾弾的知性から止揚的知性へ」という記事のコメント欄の議論の紹介の続きです。
********************
http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/9626ef3f908341f8f20dec7c45ddb4e1
それは難しい (三郎) 2015-08-24 04:30:57
初めまして。
糾弾的知性から止揚的知性へ。このタイトルが興味深かっ
たので、コメントします。
私自身、ほぼ同じようなことを考えたことがありますが、
結論は、「こりゃ、無理だ。」でした。
大学のような討論のために保護された環境でも、実際に行われているのは、
ご存じのような代物ですし、友人間で、議論のルールを決め、議論を実践し
てみても、アウフヘーベンなど不可能で、物別れに終わるか、議論能力に優
れたものが、結論を支配し、そうでないものは、不満を内に秘め、しぶしぶ
賛成する、という結果になるのが関の山です。
そもそも、複数の人間の間で行う「議論」において、止揚的知性の実現は、
可能なのでしょうか?
本家のヘーゲルの弁証法も、彼ひとりの脳内でなされたからこそ、可能だった
のであり、生身の人間を相手とする議論によっては、不可能だったのではな
いでしょうか。
議論の本家であるといわれる欧米の知識人同士の議論を見ていても、止揚的
議論などみられません。お互いを糾弾し、最悪の場合、人間関係も壊してし
まいます。
討議的民主主義なるものも、理想とは程遠いのが実態です。
ただ、非常に興味深いと思った試みと過去の事例があります。
それは、ユング派心理学者アーノルドミンデルの「ディープデモクラシー」
と民俗学者宮本常一の本に出てくるある村の寄り合いでのものごとの決め方
です。どの本だったかわすれました。「忘れられた日本人」だったかもしれ
ません。
どちらも、知的な議論ではなく、その底にだれしもがもつ感情のしこりの解放を問
題にしています。
これが溶けた時、「にせの問題、みせかけの議論」は、自動的に消滅していき、
「ほんとうのポイント」が姿を現してきます。そして、解決は、速やかに訪れます。
議論というものを考える際、私たちは、知的言語的側面のみを考えがちですが、そ
の基底にある非言語的なもの(身体、感情など)を注視することが、可能性を開く
キーになるのだろう、と私は考えているところです。
********************************
糾弾的言語を止揚するものは。 (薩長公英陰謀論者) 2015-08-29 23:24:50
三郎さま:
三郎さまのご投稿に「なるほど・・」と頷きました。ご覧になってきたことについての率直なお話と「知的言語的側面の基底にある非言語的なもの」のご示唆をいただきありがとうございます。
三郎さまがお考えでいらっしゃることことからずれるかと思いつつ、それは「共感力」や「想像力」と言えるものかもしれないとぼんやり考えました。
01 上野千鶴子氏のSEALDsメンバーのスピーチに対する「糾弾事件」に見るケースについて。
http://www.targma.jp/vivanonlife/2015/08/post7505/
「・・・性別役割分業を肯定しないよう慎重に言葉を選んでいました。それでも性別役割分業を想像させるスピーチはいけないと批判があるなら、女性個人の幸せに寄り添えないようなものがフェミニズムであるはずがないと反論いたします」
正木氏がかようなかたち ↑ で上野氏の「糾弾」に対する反論をなさったことに心を動かされました(「寄り添う」という言葉が、著名な某氏の「70年談話」にあったことの気持ちわるさはさておき)。
表層における主張の一貫性に一方的にドライブされるがゆえの上野氏の共感力と想像力の枯渇(?)を正木さんはさりげなく指摘しているのではないかと思えます。
02 そのSEALDsつながりで。お行儀よさを求めるオトナの欺瞞的非難を受けるSEALDsの言葉が排除的な糾弾とならない理由について、内田樹氏が以下のような示唆をしています。
http://blogos.com/article/129745/
8月23日(日)京都円山公園で開催されたSEALDs KANSAIの集会での連帯の挨拶。
「・・・みなさんが語る言葉は政治の言葉ではなく、日常のことば、ふつうの生活実感に裏づけられた、リアルな言葉です。
・・・これまで、ひとまえで『政治的に正しい言葉』を語る人たちにはつねに、ある種の堅苦しさがありました。なにか、外来の、あるいは上位の『正しい理論』や『正しい政治的立場』を呼び出してきて、それを後ろ盾にして語るということがありました。
でも、SEALDsのみなさんの語る言葉には、そういうところがない。自分たちとは違う、もっと『偉い人の言葉』や『もっと権威のある立場』に頼るところがない。
・・・自分たちがふだん・・・ふつうに口にしている言葉、ふつうに使っているロジック、・・・を使って、自分たちの政治的意見を述べている。こういう言葉づかいで政治について語る若者が出現したのは、戦後日本においてははじめてのことだと思います」
・・・と。ここで内田氏は意図せずして、三郎さまが着眼をしておられる「知的言語の基底にある非言語的なもの」により近い言葉があることを示唆しているように思えます。
そのような言葉は、一見糾弾的でありながら、あたえられた弾を出来合いのものめがけて撃つ射的とはまったく異なるものであり、他者を自分の軌道から排除するのではなく、一緒に星雲の渦をつくりだすものであるような気がいたします。
かのガメ・オベール氏は、「糾弾的知性」について、というウェブログ記事で、かような言い方をしています:
https://gamayauber1001.wordpress.com/2015/08/28/challenging-intelligence/
「・・・人間は『他人の話を聴く』状態で、ものを見なければならないので、『他人に対して自分の考えを主張する』ように、ものを見てはならないのだとおもう。
・・・怒りを表明したり、自分の観察を述べることはできても、人間の言葉には現実は、『主張をこめる』というようなことは出来ないのだと思います」
・・・ガメ・オベール氏によれは、主張を薬莢とし、主張の生業的必然性を引き金にした糾弾的主張は、じつは人間の言葉ではないのだと。
03 最後の一つ前に、ホリエモンのケースを。
http://news.livedoor.com/article/detail/10515891/
以下は、りくにすさまにおしえていただいて愛読している「リテラ」の宮島みつやという方による、敬意を払うべき「糾弾」です:
「・・・ 実は、この他者への想像力の欠如という問題はホリエモンのこれまでの言動にもしばしば見られてきた。
・・・ 今回も同じだ。いかに効率の悪い働き方しかできなくても、機械で代行できる単純労働であっても、自分の出来る範囲で仕事をし続けることで、社会や他者とつながり、小さな自信と生き甲斐を得ている人がいることを、ホリエモンはまったくわかっていない。
そして、そういう人が “クズ" の烙印を押されて働く機会を奪われたら、いったいどんな絶望に陥るかも、一切考慮していない。
・・・世界とは、ホリエモンが考えているよりもはるかに複雑で不確実で、多様な可能性をはらんでいるものなのだ。個人の実存や感情も想像以上に大きな作用を社会にもたらす。・・・ ホリエモンが言うような単純な図式に無理矢理であてはめても、なんの問題解決につながらないことは、ちょっと考えればわかることだろう。
・・・世界の複雑さを受け入れられずに、ものごとを単純化しないと説明できない。そして、教養のなさをカバーするために、やたら『経済効率』だのなんだのというリバタリアン経営者的言葉をふりまく」
・・・と。
すみません、ホリエモンと一緒に並んで立たされて、宮島氏に叱られているような気がいたします。
04 引用の最後に、内田樹氏に睨まれるのを覚悟で、アダム・スミスの言葉を呼び出してきます。
アダム・スミスが終生の主著と考え、1759年36歳での初版後、1790年(寛政2年)に67歳で亡くなるまで、40年にわたり増補改訂を続けた『道徳感情論』( The Theory of Moral Sentiments )において、彼はきわめて美しい感動的な文章で、相互的同感( mutual Sympathy )のあり方、方法について語っています。
Every faculty in one man is the measure by which he judges of the like faculty in another. I judge of your sight by my sight, of your ear by my ear, of your reason by my reason, of your resentment by my resentment, of your love by my love. I neither have, nor can have, any other way of judging about them.
「ある人のすべて能力は、それぞれ他人における類似の能力について、かれが判断するさいの尺度である。
私はあなたの視覚を、私の視覚によって、あなたの聴覚を私の聴覚によって、あなたの理性を私の理性によって、あなたの憤慨を私の憤慨によって、あなたの愛情を私の愛情によって、判断する。
私は、それらについて判断するのに、なにもほかの方法はもたないし、またもちえないのである」(水田洋 訳、 アダム・スミス『道徳感情論』岩波文庫、2003年;上巻p50)
ちなみに、水田洋氏によればかの『国富論』(「 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 」勝手な和訳をしますと『国民の豊かさについての考察』)は『道徳感情論』としてのこるアダム・スミスの哲学講義の副産物であったとのことです。
産業革命前夜に書かれた、『国富論』は、働く人々、とりわけ同書のなかで繰り返し出てくる「 下層賃金労働者(@水田洋氏)、 labouring poor 」に対する共感と同情で充ちています。
なお、labouring poor という言葉はアダム・スミス以降の古典派経済学では消失したとのことです。20世紀の初頭の米国において、社会学者、社会運動家によって working poverty, working poor として復活するまでは。
アダム・スミスの働く人々への共感はたとえば:
「さまざまな種類の使用人、労働者、職人は、すべての巨大な政治社会の圧倒的大部分を構成している。
・・・どんな社会も、その成員の圧倒的大部分が貧しくみじめであるとき、その社会が隆盛で幸福であろうはずはけっしてない」(大河内一男 監訳、アダム・スミス『国富論』岩波文庫、1978年;第1巻p133 )
Servants, labourers and workmen of different kinds, make up the far greater part of every great political society. ・・・ No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.
・・・と、いう言葉にあらわれています。
これに対して、アダム・スミスの「資本家」たちに対する冷ややかで突き放した、じつに皮肉に充ちた視線を、かの「見えざる手」に言及した有名な部分においてすら感じます。
この有名な「見えざる手」論において、アダム・スミスにとって重要なのはあくまで社会の利益であり資本家の利益追求の自由ではなかったことが示されていると思います。
彼は労働者を低賃金で酷使する資本家の利己心・利益追求に対して共感のひとかけらすら持っておらず、むしろそれを軽蔑していたことをうかがい知ることができます。
すみません以上の、もったいぶった「糾弾敵視vs.止揚同感」論の最後に、きのう8月28日、金曜日のSEALDs国会前抗議に福岡からやって来た西南学院大学3年の後藤宏基さんのスピーチから引用することをお許しください。「絆」= 共感、rapport 論であると。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/260302
「・・・戦争を起こして何になりますか。誰が得をしますか。僕ら国民には犠牲しかもたらしません!
そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む僕が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
僕自身が抑止力になってやります。抑止力に武力なんて必要ない。絆が抑止力なんだって証明してやります・・・」
☆☆☆
皆様ありがとうございます。
>議論の本家であるといわれる欧米の知識人同士の議論を見ていても、止揚的議論などみられません。
たしかに欧米でも政策レベルの議論は認識の押し付け合いになりがちですが、欧米における学問研究における最先端の認識はやはり弁証法的な対話によって形成されているケースが多いと思います。
科学的認識の形成過程において「対話」が決定的に重要であるという点を実証した本として思い出すのが、量子力学の創始者の一人であるウェルナー・ハイゼンベルクの『部分と全体』(みすず書房)です。ハイゼンベルクは同書の中で、以下のように述べています。
「自然科学は実験に基づくもので、それにたずさわってきた人々は、実験の意味することについて熟慮を重ね、互いに討論しあうことによって成果に到達していくのです。この本を通じて、科学は討論の中から生まれるものであるということを、はっきりさせたいと望んでいます」
(W・ハイゼンベルク(山崎和夫訳)『部分と全体』(みすず書房)序文より)
お互いの「立場」にこだわらない虚心坦懐な対話は、弁証法的発展を促します。日本の大学や学会の中では、「学閥」や「○○先生の弟子」といった「立場」が大きな阻害要因となって、弁証法的対話が行われにくいのだと思います。
>そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む僕が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
後藤宏基さんのこの言葉、本当にその通りだと思います。対話こそが最大の戦争の抑止力になると思います。「糾弾的攻撃」は戦争の原因になり得ますが、「弁証法的対話」は戦争を抑止します。
実際、中国人留学生と日本人学生が対話を通して双方の認識をアウフヘーベンさせることは可能です。私も、教員のはしくれとして教室の中でですが、ささやかに取り組んでまいりました。
太平洋戦争の歴史認識に関しては、日本人、中国人、韓国人の認識が異なるもっともセンシティブな点ですが、それでも弁証法的対話が行われれば、双方の歴史認識は接近していきます。
私が書いたものですと「左右の日本人と中国人の歴史観は弁証法的に統合可能」として、以下のような実践例を投稿しました。
授業での議論を通して、大東亜戦争肯定史観の日本人学生と、日本侵略史観の中国人学生の歴史認識が弁証法的に接近してきたという事例です。
***以下、引用****
http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/fec37401865183b1e1b1e053900eb94f
(日本が太平洋戦争を起こし、大東亜共栄圏を唱えたことによって、アジア諸国の独立が達成されたという主張の是非についての対話)
授業の中では、(アジアの)それぞれの国の事例を紹介し、国により状況は異なるので一つ一つの国々を注意深く見ていかねばならないということは伝えておいた。保守的な歴史観を持っていた学生も、左派的な歴史観を持っていた学生も、中国人留学生も、授業を通して議論をし、自分で調べたりする中で、状況は複雑で一概には言えないという点では、認識が接近する傾向が見られた。
保守的な歴史認識を持っていた2年生(日本人男子)の回答を一つ紹介する。(「日本が起こした太平洋戦争によってアジア諸国が独立できた」という大東亜戦争肯定史観に関して)、「私はこの意見はあながち間違ってはいないと考える」と書き、日本が太平洋戦争中にフィリピンとビルマに独立を与えて「アジア解放」の約束を果たそうとしたことを肯定的に評価した上で、中国に関しては「日本が侵略したのは良くなかったと思うが、しかし中国は共産党と国民党が対立していたので、国共合作という形でまとまり、一つになれたという意味ではその後の中国形成につながったと思われる」と書いていた。これは毛沢東の歴史認識と比べても、そう大差はないと言ってよいだろう。
(中略)
中国人留学生の受講生も多かったので、授業中は議論して大変に盛り上がった。中国人留学生にとっても、それまで認識していた「日本」とは別の姿も見えてきたようだった。
ある中国の女子留学生の回答を紹介する。「日本が起こした太平洋戦争の結果、アジア諸国が独立を早く達成することができた。いかなる事物にも両面性がある。日本が太平洋戦争を起こして、欧米列強と戦って、アジアの国々は革命軍の準備時間を充分取ってきた」。
「毛沢東は私のアイドル」と言ういまどき珍しい中国の女子学生の回答も紹介する。「アジア諸国は長期間欧米列強に植民地として圧迫された。被植民地のアジア諸国は日本に期待した。日本が起こした太平洋戦争は、アジア人の勝利と思われる」。
*********
以上のように、保守的な日本人学生は、大東亜戦争肯定論を放棄してはいませんが、対話を通して中国の立場も認識するようになり、「日本が侵略したのは良くなかった」とまで言うようになっています。逆に中国人学生は、「いかなる事物にも両面性がある」と述べ、日本の主張も理解し、日本を全面的に悪とは断罪しなくなっているのです。弁証法的対話の結果といえるのではないでしょうか。
********************
http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/9626ef3f908341f8f20dec7c45ddb4e1
それは難しい (三郎) 2015-08-24 04:30:57
初めまして。
糾弾的知性から止揚的知性へ。このタイトルが興味深かっ
たので、コメントします。
私自身、ほぼ同じようなことを考えたことがありますが、
結論は、「こりゃ、無理だ。」でした。
大学のような討論のために保護された環境でも、実際に行われているのは、
ご存じのような代物ですし、友人間で、議論のルールを決め、議論を実践し
てみても、アウフヘーベンなど不可能で、物別れに終わるか、議論能力に優
れたものが、結論を支配し、そうでないものは、不満を内に秘め、しぶしぶ
賛成する、という結果になるのが関の山です。
そもそも、複数の人間の間で行う「議論」において、止揚的知性の実現は、
可能なのでしょうか?
本家のヘーゲルの弁証法も、彼ひとりの脳内でなされたからこそ、可能だった
のであり、生身の人間を相手とする議論によっては、不可能だったのではな
いでしょうか。
議論の本家であるといわれる欧米の知識人同士の議論を見ていても、止揚的
議論などみられません。お互いを糾弾し、最悪の場合、人間関係も壊してし
まいます。
討議的民主主義なるものも、理想とは程遠いのが実態です。
ただ、非常に興味深いと思った試みと過去の事例があります。
それは、ユング派心理学者アーノルドミンデルの「ディープデモクラシー」
と民俗学者宮本常一の本に出てくるある村の寄り合いでのものごとの決め方
です。どの本だったかわすれました。「忘れられた日本人」だったかもしれ
ません。
どちらも、知的な議論ではなく、その底にだれしもがもつ感情のしこりの解放を問
題にしています。
これが溶けた時、「にせの問題、みせかけの議論」は、自動的に消滅していき、
「ほんとうのポイント」が姿を現してきます。そして、解決は、速やかに訪れます。
議論というものを考える際、私たちは、知的言語的側面のみを考えがちですが、そ
の基底にある非言語的なもの(身体、感情など)を注視することが、可能性を開く
キーになるのだろう、と私は考えているところです。
********************************
糾弾的言語を止揚するものは。 (薩長公英陰謀論者) 2015-08-29 23:24:50
三郎さま:
三郎さまのご投稿に「なるほど・・」と頷きました。ご覧になってきたことについての率直なお話と「知的言語的側面の基底にある非言語的なもの」のご示唆をいただきありがとうございます。
三郎さまがお考えでいらっしゃることことからずれるかと思いつつ、それは「共感力」や「想像力」と言えるものかもしれないとぼんやり考えました。
01 上野千鶴子氏のSEALDsメンバーのスピーチに対する「糾弾事件」に見るケースについて。
http://www.targma.jp/vivanonlife/2015/08/post7505/
「・・・性別役割分業を肯定しないよう慎重に言葉を選んでいました。それでも性別役割分業を想像させるスピーチはいけないと批判があるなら、女性個人の幸せに寄り添えないようなものがフェミニズムであるはずがないと反論いたします」
正木氏がかようなかたち ↑ で上野氏の「糾弾」に対する反論をなさったことに心を動かされました(「寄り添う」という言葉が、著名な某氏の「70年談話」にあったことの気持ちわるさはさておき)。
表層における主張の一貫性に一方的にドライブされるがゆえの上野氏の共感力と想像力の枯渇(?)を正木さんはさりげなく指摘しているのではないかと思えます。
02 そのSEALDsつながりで。お行儀よさを求めるオトナの欺瞞的非難を受けるSEALDsの言葉が排除的な糾弾とならない理由について、内田樹氏が以下のような示唆をしています。
http://blogos.com/article/129745/
8月23日(日)京都円山公園で開催されたSEALDs KANSAIの集会での連帯の挨拶。
「・・・みなさんが語る言葉は政治の言葉ではなく、日常のことば、ふつうの生活実感に裏づけられた、リアルな言葉です。
・・・これまで、ひとまえで『政治的に正しい言葉』を語る人たちにはつねに、ある種の堅苦しさがありました。なにか、外来の、あるいは上位の『正しい理論』や『正しい政治的立場』を呼び出してきて、それを後ろ盾にして語るということがありました。
でも、SEALDsのみなさんの語る言葉には、そういうところがない。自分たちとは違う、もっと『偉い人の言葉』や『もっと権威のある立場』に頼るところがない。
・・・自分たちがふだん・・・ふつうに口にしている言葉、ふつうに使っているロジック、・・・を使って、自分たちの政治的意見を述べている。こういう言葉づかいで政治について語る若者が出現したのは、戦後日本においてははじめてのことだと思います」
・・・と。ここで内田氏は意図せずして、三郎さまが着眼をしておられる「知的言語の基底にある非言語的なもの」により近い言葉があることを示唆しているように思えます。
そのような言葉は、一見糾弾的でありながら、あたえられた弾を出来合いのものめがけて撃つ射的とはまったく異なるものであり、他者を自分の軌道から排除するのではなく、一緒に星雲の渦をつくりだすものであるような気がいたします。
かのガメ・オベール氏は、「糾弾的知性」について、というウェブログ記事で、かような言い方をしています:
https://gamayauber1001.wordpress.com/2015/08/28/challenging-intelligence/
「・・・人間は『他人の話を聴く』状態で、ものを見なければならないので、『他人に対して自分の考えを主張する』ように、ものを見てはならないのだとおもう。
・・・怒りを表明したり、自分の観察を述べることはできても、人間の言葉には現実は、『主張をこめる』というようなことは出来ないのだと思います」
・・・ガメ・オベール氏によれは、主張を薬莢とし、主張の生業的必然性を引き金にした糾弾的主張は、じつは人間の言葉ではないのだと。
03 最後の一つ前に、ホリエモンのケースを。
http://news.livedoor.com/article/detail/10515891/
以下は、りくにすさまにおしえていただいて愛読している「リテラ」の宮島みつやという方による、敬意を払うべき「糾弾」です:
「・・・ 実は、この他者への想像力の欠如という問題はホリエモンのこれまでの言動にもしばしば見られてきた。
・・・ 今回も同じだ。いかに効率の悪い働き方しかできなくても、機械で代行できる単純労働であっても、自分の出来る範囲で仕事をし続けることで、社会や他者とつながり、小さな自信と生き甲斐を得ている人がいることを、ホリエモンはまったくわかっていない。
そして、そういう人が “クズ" の烙印を押されて働く機会を奪われたら、いったいどんな絶望に陥るかも、一切考慮していない。
・・・世界とは、ホリエモンが考えているよりもはるかに複雑で不確実で、多様な可能性をはらんでいるものなのだ。個人の実存や感情も想像以上に大きな作用を社会にもたらす。・・・ ホリエモンが言うような単純な図式に無理矢理であてはめても、なんの問題解決につながらないことは、ちょっと考えればわかることだろう。
・・・世界の複雑さを受け入れられずに、ものごとを単純化しないと説明できない。そして、教養のなさをカバーするために、やたら『経済効率』だのなんだのというリバタリアン経営者的言葉をふりまく」
・・・と。
すみません、ホリエモンと一緒に並んで立たされて、宮島氏に叱られているような気がいたします。
04 引用の最後に、内田樹氏に睨まれるのを覚悟で、アダム・スミスの言葉を呼び出してきます。
アダム・スミスが終生の主著と考え、1759年36歳での初版後、1790年(寛政2年)に67歳で亡くなるまで、40年にわたり増補改訂を続けた『道徳感情論』( The Theory of Moral Sentiments )において、彼はきわめて美しい感動的な文章で、相互的同感( mutual Sympathy )のあり方、方法について語っています。
Every faculty in one man is the measure by which he judges of the like faculty in another. I judge of your sight by my sight, of your ear by my ear, of your reason by my reason, of your resentment by my resentment, of your love by my love. I neither have, nor can have, any other way of judging about them.
「ある人のすべて能力は、それぞれ他人における類似の能力について、かれが判断するさいの尺度である。
私はあなたの視覚を、私の視覚によって、あなたの聴覚を私の聴覚によって、あなたの理性を私の理性によって、あなたの憤慨を私の憤慨によって、あなたの愛情を私の愛情によって、判断する。
私は、それらについて判断するのに、なにもほかの方法はもたないし、またもちえないのである」(水田洋 訳、 アダム・スミス『道徳感情論』岩波文庫、2003年;上巻p50)
ちなみに、水田洋氏によればかの『国富論』(「 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 」勝手な和訳をしますと『国民の豊かさについての考察』)は『道徳感情論』としてのこるアダム・スミスの哲学講義の副産物であったとのことです。
産業革命前夜に書かれた、『国富論』は、働く人々、とりわけ同書のなかで繰り返し出てくる「 下層賃金労働者(@水田洋氏)、 labouring poor 」に対する共感と同情で充ちています。
なお、labouring poor という言葉はアダム・スミス以降の古典派経済学では消失したとのことです。20世紀の初頭の米国において、社会学者、社会運動家によって working poverty, working poor として復活するまでは。
アダム・スミスの働く人々への共感はたとえば:
「さまざまな種類の使用人、労働者、職人は、すべての巨大な政治社会の圧倒的大部分を構成している。
・・・どんな社会も、その成員の圧倒的大部分が貧しくみじめであるとき、その社会が隆盛で幸福であろうはずはけっしてない」(大河内一男 監訳、アダム・スミス『国富論』岩波文庫、1978年;第1巻p133 )
Servants, labourers and workmen of different kinds, make up the far greater part of every great political society. ・・・ No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.
・・・と、いう言葉にあらわれています。
これに対して、アダム・スミスの「資本家」たちに対する冷ややかで突き放した、じつに皮肉に充ちた視線を、かの「見えざる手」に言及した有名な部分においてすら感じます。
この有名な「見えざる手」論において、アダム・スミスにとって重要なのはあくまで社会の利益であり資本家の利益追求の自由ではなかったことが示されていると思います。
彼は労働者を低賃金で酷使する資本家の利己心・利益追求に対して共感のひとかけらすら持っておらず、むしろそれを軽蔑していたことをうかがい知ることができます。
すみません以上の、もったいぶった「糾弾敵視vs.止揚同感」論の最後に、きのう8月28日、金曜日のSEALDs国会前抗議に福岡からやって来た西南学院大学3年の後藤宏基さんのスピーチから引用することをお許しください。「絆」= 共感、rapport 論であると。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/260302
「・・・戦争を起こして何になりますか。誰が得をしますか。僕ら国民には犠牲しかもたらしません!
そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む僕が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
僕自身が抑止力になってやります。抑止力に武力なんて必要ない。絆が抑止力なんだって証明してやります・・・」
☆☆☆
皆様ありがとうございます。
>議論の本家であるといわれる欧米の知識人同士の議論を見ていても、止揚的議論などみられません。
たしかに欧米でも政策レベルの議論は認識の押し付け合いになりがちですが、欧米における学問研究における最先端の認識はやはり弁証法的な対話によって形成されているケースが多いと思います。
科学的認識の形成過程において「対話」が決定的に重要であるという点を実証した本として思い出すのが、量子力学の創始者の一人であるウェルナー・ハイゼンベルクの『部分と全体』(みすず書房)です。ハイゼンベルクは同書の中で、以下のように述べています。
「自然科学は実験に基づくもので、それにたずさわってきた人々は、実験の意味することについて熟慮を重ね、互いに討論しあうことによって成果に到達していくのです。この本を通じて、科学は討論の中から生まれるものであるということを、はっきりさせたいと望んでいます」
(W・ハイゼンベルク(山崎和夫訳)『部分と全体』(みすず書房)序文より)
お互いの「立場」にこだわらない虚心坦懐な対話は、弁証法的発展を促します。日本の大学や学会の中では、「学閥」や「○○先生の弟子」といった「立場」が大きな阻害要因となって、弁証法的対話が行われにくいのだと思います。
>そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口に住む僕が、韓国人や中国人と話して、遊んで、酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。
後藤宏基さんのこの言葉、本当にその通りだと思います。対話こそが最大の戦争の抑止力になると思います。「糾弾的攻撃」は戦争の原因になり得ますが、「弁証法的対話」は戦争を抑止します。
実際、中国人留学生と日本人学生が対話を通して双方の認識をアウフヘーベンさせることは可能です。私も、教員のはしくれとして教室の中でですが、ささやかに取り組んでまいりました。
太平洋戦争の歴史認識に関しては、日本人、中国人、韓国人の認識が異なるもっともセンシティブな点ですが、それでも弁証法的対話が行われれば、双方の歴史認識は接近していきます。
私が書いたものですと「左右の日本人と中国人の歴史観は弁証法的に統合可能」として、以下のような実践例を投稿しました。
授業での議論を通して、大東亜戦争肯定史観の日本人学生と、日本侵略史観の中国人学生の歴史認識が弁証法的に接近してきたという事例です。
***以下、引用****
http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/fec37401865183b1e1b1e053900eb94f
(日本が太平洋戦争を起こし、大東亜共栄圏を唱えたことによって、アジア諸国の独立が達成されたという主張の是非についての対話)
授業の中では、(アジアの)それぞれの国の事例を紹介し、国により状況は異なるので一つ一つの国々を注意深く見ていかねばならないということは伝えておいた。保守的な歴史観を持っていた学生も、左派的な歴史観を持っていた学生も、中国人留学生も、授業を通して議論をし、自分で調べたりする中で、状況は複雑で一概には言えないという点では、認識が接近する傾向が見られた。
保守的な歴史認識を持っていた2年生(日本人男子)の回答を一つ紹介する。(「日本が起こした太平洋戦争によってアジア諸国が独立できた」という大東亜戦争肯定史観に関して)、「私はこの意見はあながち間違ってはいないと考える」と書き、日本が太平洋戦争中にフィリピンとビルマに独立を与えて「アジア解放」の約束を果たそうとしたことを肯定的に評価した上で、中国に関しては「日本が侵略したのは良くなかったと思うが、しかし中国は共産党と国民党が対立していたので、国共合作という形でまとまり、一つになれたという意味ではその後の中国形成につながったと思われる」と書いていた。これは毛沢東の歴史認識と比べても、そう大差はないと言ってよいだろう。
(中略)
中国人留学生の受講生も多かったので、授業中は議論して大変に盛り上がった。中国人留学生にとっても、それまで認識していた「日本」とは別の姿も見えてきたようだった。
ある中国の女子留学生の回答を紹介する。「日本が起こした太平洋戦争の結果、アジア諸国が独立を早く達成することができた。いかなる事物にも両面性がある。日本が太平洋戦争を起こして、欧米列強と戦って、アジアの国々は革命軍の準備時間を充分取ってきた」。
「毛沢東は私のアイドル」と言ういまどき珍しい中国の女子学生の回答も紹介する。「アジア諸国は長期間欧米列強に植民地として圧迫された。被植民地のアジア諸国は日本に期待した。日本が起こした太平洋戦争は、アジア人の勝利と思われる」。
*********
以上のように、保守的な日本人学生は、大東亜戦争肯定論を放棄してはいませんが、対話を通して中国の立場も認識するようになり、「日本が侵略したのは良くなかった」とまで言うようになっています。逆に中国人学生は、「いかなる事物にも両面性がある」と述べ、日本の主張も理解し、日本を全面的に悪とは断罪しなくなっているのです。弁証法的対話の結果といえるのではないでしょうか。