日曜日は毎年恒例になっている、本多蔵品館主宰の城下町武家地巡りのイベントに参加しました。講師は例によって北陸大の長谷川先生。長谷川先生の人を引き込むトークは毎度のことながら、うっとりしてしまいます。
さて、今回は、加賀八家の一つである横山家の宅地中心の町巡り。横山家は長隆に始まる加賀藩の重鎮ですが、初代長隆は賤ケ岳の戦いで戦死しており、金沢にはやってきていない。来ているのは2代目の長知から。横山長知といえば、関ヶ原前夜、前田家に謀反の疑いがかけられたとき、家康との折衝に周旋した人物として知られています。そのときは、芳春院を人質に出すことで、話がまとまったのでした。

写真は横山家の菩提寺である松山寺。すぐ近くにこれもまた八家の一つ奥村家の菩提寺である永福寺があります。

こちらの写真は、八家ではありませんが、加賀藩の重臣であった成瀬家の門のあったあたりの写真。石垣あとが見られます。左手の用水は、今でこそ小さな用水となっていますが、かつては屋敷の周りにめぐらされ、堀の役目を担っていたとのこと。説明を受けなければ、ただの用水で片付けてしまいそうですが・・・。

こちらは木曽坂。金沢には、このような坂がいくつもあります。まさに坂の町でもあるのです。
横山家の家中町(下屋敷、横山家の家臣たちが住んでいたところ)中心の町めぐりでしたが、複雑にめぐらされた路地を通って行ったので、おそらくは二度と一人では歩けそうにないです。

路地を抜けるとふっと広い空間が。
金沢には「広見」と呼ばれる、おそらくは火よけ地として機能していたのであろう場所が多々ありますが、ここは広見ではなく、馬場のあとだとのこと。
何も知らなければただの狭い路地でとおり過ごしてしまいそうな所ですが、歴史談義を聞きながら町歩きをすると、かつての風景がそこここに現れるような、不思議な感覚が襲ってきたりもします。
心配していたお天気も、何とか持ってくれて、2時間ほどの有意義な歴史散歩でした。










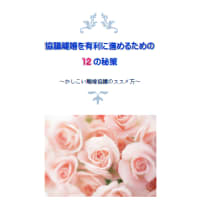
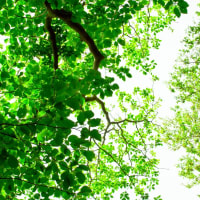








いいですねぇ。歴史香る町に住むって。前田八家が確立されたのは、四代藩主・綱紀の時だったかと記憶しています。外様大名でありながら、将軍家と深く姻戚関係があったからでしょうが、破格の大大名で、八家も、本多家の五万石や、横山家のように富山城代となって三万石であったように、人持組頭の権威は凄いものがありますね。人持組のご家蔵も驚くほどです。安定感を感じます。
ひとえに初代利家公と芳春院さまのお人柄でしょうか。利常公の時代に、加賀藩の基礎がほぼ確立されたことでしょう。前田家ゆかりの江戸上屋敷あとで、僕はいそいそと勉強致しました。
加賀宝生と言われるくらい能は盛んで、近年まで宝生流の家元が加賀にあったぐらいです。(因みに徳川家は観世流)。今は亡き近藤乾三師匠の、美しい謡が思い出されます。四季折々の能はそれはそれは格の高いものでした。ずっと加賀藩にいたからこそ、宝生流の格式と美しさが保たれたのでしょうね。特に謡に特徴があり、若かりし折、水道橋能楽堂の「五雲会」(宝生流若手の会)で鍛えられたものです。僕は金春流ですが。
来月米沢へなんて、最高の季節ですもの。是非訪れて戴きたいものです。ヨサレ前田慶二は最上軍と大奮闘。米沢では兼続に負けないぐらいの人気があります。特に高畠や南陽あたりでは!今は置賜さくら街道沿い、古木名木がぎっしりと花をつけている頃でしょう。
碩水亭さん、加賀藩のことも良く御存知とは。
私などが語るまでもありませんでしたね^^;
そしてまた、お能もたしなんでいらっしゃるのですね。私は能楽堂でちらりとお能を見たことがあるだけなので、流派の違いもよくわかりません。
町並みを歩いているだけでも、歴史の息吹が感じられるのは幸せなことだと思います。