16、17日と夫が休みを取ったというので、私も無理に塾の先生にお願いして、休みをいただきました。
「どこへ行く?」との夫の質問に、迷わず「滋賀。大津に行きたい美術館がある。」と私。
日曜日に出発し、一泊二日の小さな旅に出る。
以前から行きたいと思っていたのは、35歳で夭折した女流画家三橋節子の美術館。ある冊子に載っていた『三井の晩鐘』の絵に、鳥肌が立つくらいの感動を覚えて以来、本物を見たいとずっと思っていました。
彼女は利き腕の右手に悪性の腫瘍ができ、右肩を切断。その後、さまざまな試練を乗り越えて、左手に絵筆を持ち替えて、作品を仕上げていきました。
梅原猛さんが、三橋さんのことを書いていらっしゃいます。詳細はコチラに。
まだ幼い子どもたちを残し、自らの命の短さを知っている彼女の心の闇は想像を絶するものがあります。その中で、絵筆を握り続けた彼女の強さに、少しでもあやかりたいもの。
彼女の絵は、生まれ故郷の滋賀の地の昔話を題材にしたものが多い。『三井の晩鐘』もそのひとつ。彼女の絵の多くは、テーマは母と子に集約されているような気がします。自身の運命を、昔話の中にオーバーラップさせていたのかもしれません。暗さの中にもどこか温かみのある彼女の絵が、私にはひどく心地いい。多分一人だったら、『三井の晩鐘』の前で、ぽろぽろ涙を流していたかもしれません。
記念に求めたのは、『三井の晩鐘」ではなく、『花折峠』の複製画。これも昔話を題材にした絵で、川に沈み行く娘を中央に配置し、素材的には哀しい絵のはずなのですが、さまざまな野の花に囲まれ、色彩も明るく、笑みまで浮かべている娘は、川の流れにたゆとうているだけのようにも見えなくもない。実際、娘は死んではいなかったようで、心優しい娘のために、野の花が身代わりになったもののようでもあります。

美術館のあとは、これもまた、以前から行きたいと思っていた義仲寺へ向かう。
門の前に車一台がようやく 止めることのできるスペースがあるだけのこじんまりしたお寺です。
義仲は、信州で育った私には、ちょっとしたヒーローのような存在。おまけに彼の家臣の一人が直江さんの祖先であると言われているからには、やはり・・・^^;

お盆でもありますので、義仲のお墓にお参り。隣にこじんまりと巴塚も並んでいます。巴塚は小矢部にもありましたが、彼女はさまざまな伝承が残っているのですね。
松尾芭蕉もこの場所をしばしば訪れており、境内には芭蕉の句碑がいくつもあります。芭蕉は大坂で亡くなっていますが、「骸は木曽塚に送るべし」との遺言から、この地にもお墓があるようです。
古池には「蛙」ならぬ、亀がたくさん泳いでいました。
古池や 亀の飛び込む 水の音・・・?
義仲寺を出て、石山寺に向かう。途中、膳所城址の前を通過。現在は公園になっているようです。
膳所といえば、兼続の息子景明が、膳所藩の戸田氏鉄の娘と結婚していますね。そんなことを思い出したので、車窓から、公園入り口の門を写してみました。↓

石山寺は、説明するまでもなく、有名ですね。
紫式部が『源氏物語』の着想をしたという言い伝えも残っているお寺です。
ことに平安時代には、さまざまな人が石山寺に参篭しています。
古典の中にはしばしば出てきますね。
石山寺は、その名のごとく、奇岩とまでは行かないまでも、巨大な岩石の上に伽藍が建てられているといった趣の寺です。岩石マニアの長男がいたら、大喜びしそうな場所でもあります。
この時期、どこへ行っても百日紅の花がきれいですが、このお寺も例外ではなく、百日紅がいたることろで咲いていました。伽藍の屋根と百日紅の花の色がまた美しいコントラストを織り成していました。

この日の最後は三井寺(園城寺)へ。
途中、見たことのある道を通るなあ、と思ったら、三橋節子美術館のごく近くでした。
すでに拝観終了時間20分前で、受付に行くと、
「時間も時間なので、拝観料は、結構です。」
とのこと。お言葉に甘え、時間の許す限り、三井寺を散策。本堂までの階段が、かなりきつかったです。
写真は、本堂の屋根の向こうの大津の町並み。

一日目の行程はここまで。
宿泊は湖を少しだけ北に走った所にある雄琴温泉。
温泉三昧をして、日ごろの鬱屈も、少しは取れた・・・かな・・・?
翌日は彦根方面へ。続く・・・










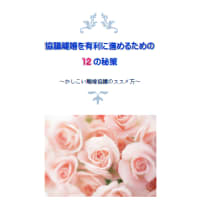
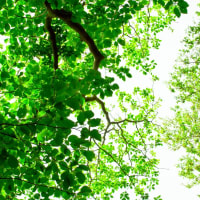








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます