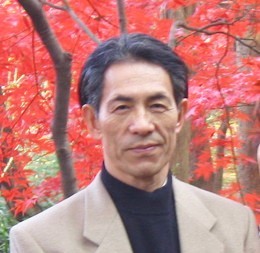写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、コンクリート基礎の立ち上がり部分です。外部に給湯器があって、お湯が作られたら、この赤いパイプを伝わって、お湯が家の中に入っていきます。ですので、ここの孔は基礎を貫通しています。
写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、コンクリート基礎の立ち上がり部分です。外部に給湯器があって、お湯が作られたら、この赤いパイプを伝わって、お湯が家の中に入っていきます。ですので、ここの孔は基礎を貫通しています。
このような孔の周りは、コーキングでふさがねばなりません。理由は、パイプを伝わって雨や虫が入って来るからです。雨が入ってきますと、ベタ基礎で一面コンクリートですから、入った雨水はたまり水となってしまいます。水がたまると、湿気ます、湿気ると土台の木材などを腐らせます。
戸建の場合、水、お湯、ガスなど外から取り込む場合、写真のように基礎の立ち上がりに貫通孔を設け、そこから入れる場合が多いです。そのような場合、パイプの周りが、雨水が入らないように、ちゃんとコーキングでふさがれているかもご確認下さい。(1821)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、玄関ドアを開けて、外の状態です。この家に入るには、前面の道路から階段を上がらなければなりません。道路とこの玄関前のポーチの高低差は約2.5mあります。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、玄関ドアを開けて、外の状態です。この家に入るには、前面の道路から階段を上がらなければなりません。道路とこの玄関前のポーチの高低差は約2.5mあります。
ここで気になるのは前の手すりについてです。気になる点は、手すりの支柱の間隔です。手すりを支えている支柱が前に1本見え、写真には写っていませんが、左の支柱との間隔は1mほどあります。支柱の間隔が広いので、手すりに手を掛けるとグラグラし、ポーチに立つと怖さも感じます。玄関ドアを勢いよく開けて、つまずいたりしたら、下の道路に転落する可能性もあります。前面道路は幅も狭いし車も通るので危険です。
こういう状況ですので、売主に対しては、手すりの支柱を増やすように指示しました。支柱の間隔は、少なくても人が通り抜けられない間隔に配置すべきです。(7312)
 写真は新築一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、付箋が貼ってあるところの外壁のひびわれです。この家の外壁はサイディングボードで作られています。このボードはセメントに繊維質を混ぜプレスしたものです。非常に多くの外壁に使われています。
写真は新築一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、付箋が貼ってあるところの外壁のひびわれです。この家の外壁はサイディングボードで作られています。このボードはセメントに繊維質を混ぜプレスしたものです。非常に多くの外壁に使われています。
サイディングボードを留めるのに、釘が使われることもあります。写真のひび割れも釘によって生じたものです。一戸建ての内覧会では、外壁の状態を良く観察し、反り、膨れ、ジョイントのコーキングの状態、このような点を確認して下さい。外壁は家の中を自然から守る非常に大事なものなので、少しでも異常があれば、売主に相談すべきです。(7729)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは基礎の立ち上がり部分です。緑の付箋を貼ってあるのは、家の中の床下から出てくる排水管です。ご覧になって頂きたいのは、矢印で示されている穴がふさがれていない箇所です。この状態では、雨が床下に入り込んでしまいますし、虫も入ってしまうでしょう。このような箇所は、排水管と穴の周りに隙間がないようにコーキングで埋めなければなりません。(6725)
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは基礎の立ち上がり部分です。緑の付箋を貼ってあるのは、家の中の床下から出てくる排水管です。ご覧になって頂きたいのは、矢印で示されている穴がふさがれていない箇所です。この状態では、雨が床下に入り込んでしまいますし、虫も入ってしまうでしょう。このような箇所は、排水管と穴の周りに隙間がないようにコーキングで埋めなければなりません。(6725)
 写真は戸建の内覧会で撮りました。写している部分は駐車場です。ご覧頂きたいのは、矢印部分の水道の水栓です。ここは駐車場ですので、車の出入りを考えると、水栓が壁から出ていない方が安全です。万が一、水栓に車をぶつけたら大変なことになります。
写真は戸建の内覧会で撮りました。写している部分は駐車場です。ご覧頂きたいのは、矢印部分の水道の水栓です。ここは駐車場ですので、車の出入りを考えると、水栓が壁から出ていない方が安全です。万が一、水栓に車をぶつけたら大変なことになります。
このケースでは、水栓を壁の中に入れるように要望し、売主に受け入れられました。駐車場に水栓はあった方が便利ですが、その位置や状態については、検討が必要となります。建売りの場合でも、水栓の位置が気になる場合には、移設や変更は可能ですので、売主に指摘して下さい。(11.8)
 写真は建売り住宅の内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、2か所の赤の矢印で示したところです。左側の矢印は境界線に沿って建てられた2段積みのブロック塀のひび割れです。このひび割れは、内覧会の数日に前に車がぶつかって生じてしまいました。この補修は、当然ですが、引き渡しの前で管理責任は売主になるので、売主負担で直すことになります。
写真は建売り住宅の内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、2か所の赤の矢印で示したところです。左側の矢印は境界線に沿って建てられた2段積みのブロック塀のひび割れです。このひび割れは、内覧会の数日に前に車がぶつかって生じてしまいました。この補修は、当然ですが、引き渡しの前で管理責任は売主になるので、売主負担で直すことになります。
右側の赤の矢印は、家の周りにある排水溝のカバーが割れていて、中の鉄筋も少し出てきてしまっています。この状態では、歩行や車の走行に対し危険です。これは、いつ、誰が壊したのかは分かりません。この住宅の売主は、家を建てる前からこうだった、と言いました。また、ここは敷地外の道路なので、管理は役所となります。しかしながら、買主にとって危険であるものは、買主への引き渡しの前までに、売主の責任で、自分で直すか、役所に依頼すべきものでしょう。このケースでは、交渉後、売主側で直すことになりました。(41.24)
 写真は、戸建の内覧会で玄関へのアプローチ部分を撮りました。ご覧頂きたいのは、白い↓部分です。この部分のタイルが浮いているので、付箋を貼って不具合としました。タイルが浮いていれば、踏むたびに音がしますし、いずれ、はがれてしまいます。このようなタイルは張り直しとなります。マンションでも戸建でも、タイルの接着不良は時々あります。
写真は、戸建の内覧会で玄関へのアプローチ部分を撮りました。ご覧頂きたいのは、白い↓部分です。この部分のタイルが浮いているので、付箋を貼って不具合としました。タイルが浮いていれば、踏むたびに音がしますし、いずれ、はがれてしまいます。このようなタイルは張り直しとなります。マンションでも戸建でも、タイルの接着不良は時々あります。
タイルの浮きを確認するためには道具を使います。その道具とは打診棒(パルハンマー)で、金属の棒の先に、直径2㎝ほどの金属球が付いたものです。その打診棒で、タイルの表面を軽く叩いてみて、その反射音で判断します。反射音が、つまって重い音なら問題はなく、軽くてカンカンする音なら浮いています。要するに、下地のモルタルにしっかりと接着していれば重い音、しっかりと付いていなければ間に空気があるから軽い音、ということです。
この打診棒を持っていない場合には、ドライバーや家のカギ等を使って、タイルの表面を軽くたたいて、その反射音でも判断できます。タイルが浮いているかどうかの判断は難しい点もありますが、たたいてみて、軽い音がしたら、接着状態について、売主に聞いてみるのが良いでしょう。(0.12)
 写真は、戸建の内覧会の時のものです。内覧会直前まで、結構強く雨が降ってました。この家は、傾斜地に建っていますので、道路から玄関までは階段となります。階段は下地のコンクリート工事が終った段階で、これから仕上げ工事に入っていきます。
写真は、戸建の内覧会の時のものです。内覧会直前まで、結構強く雨が降ってました。この家は、傾斜地に建っていますので、道路から玄関までは階段となります。階段は下地のコンクリート工事が終った段階で、これから仕上げ工事に入っていきます。
ご覧頂きたいのは、階段の踊り場に雨水が溜まっていることです。階段部や踊り場に雨が溜まっては、歩きにくいですし、滑って危険です。屋外の階段、駐車場、玄関周り、雨が掛かるところは、雨水が流れるように適切な勾配を取らなければなりません。写真のケースでは、これから仕上げ工事なので、その際は、ちゃんと雨水が流れるように指摘をしました。
内覧会の時点で晴れていれば、雨水が適切に流れるかは確認できません。出来れば、引渡しまでに雨が降った翌日にでも家を見に行って、このような点を確認するのが良いでしょう。お住まいになってからでも、水たまりが出来てしまう箇所がある場合には、売主に補修を要求すべきです。土地や建物にとって、適切に排水することは極めて大事です。(11.8)
 写真は、戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、玄関へのアプローチ部分です。玄関の階段があり、アプローチのための飛び石となり、右側には郵便受けがあります。↓部分が3箇所ありますが、これは、家から出る排水のマスです。
写真は、戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、玄関へのアプローチ部分です。玄関の階段があり、アプローチのための飛び石となり、右側には郵便受けがあります。↓部分が3箇所ありますが、これは、家から出る排水のマスです。
ここでの問題点は、排水のマスがあるので、玄関への飛び石の位置が、右側に部分的に寄りすぎていることです。飛び石の周りは砂利敷きとなっていて、ここの部分は歩きにくいです。従い、飛び石の上を歩くことになるのですが、これが、曲がっているし、郵便受けに側に寄り過ぎのため、狭くなっているためです。ここでは、汚水マスの位置を郵便受け側に持って来るべきだったと思います。
一般に、汚水マスの位置は、平面図や外構図などには描きこまれないので、どこに来るのか分からない場合多いです。このようなものが、目立たないところに置かれればいいのですが、写真のように、玄関先に来て、ましてや、歩きにくくなっては問題となります。家の設計を決める際には、これらの汚水マスの位置に付いても確認すべきです。
家から出る排水には、キッチン、お風呂、トイレから出る汚水、そして雨水があります。一般に、汚水は集めて処理され、雨水は地面に浸透させます。写真では、マスが3個ありますが、奥からトイレ、キッチンとお風呂、そして、それらの集合マス、となっています。(12.5)