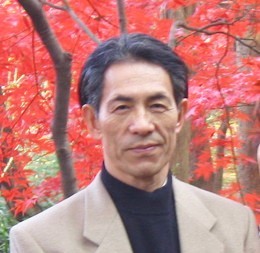一戸建の内覧会の日程を決める際、「引渡しも近くなって来たので、〇月〇日、内覧会を行いたいのですが、ご都合は?」こんな感じで聞かれる場合が多いと思います。ここで、大事なのは、引渡しの日の最低でも1週間前には、内覧会を実施すべきと思います。
一戸建の内覧会の日程を決める際、「引渡しも近くなって来たので、〇月〇日、内覧会を行いたいのですが、ご都合は?」こんな感じで聞かれる場合が多いと思います。ここで、大事なのは、引渡しの日の最低でも1週間前には、内覧会を実施すべきと思います。
なぜなら、内覧会をすれば、必ず不具合が出ます。そして、その不具合の補修期間と、補修の確認が必要となるからです。例えば、「1月31日が引渡しですね、それでは、1月28日に内覧会をしましょうか?」こういうのはダメです。1月31日に引き渡しであれば、最低でも1月23日、理想的には2週間前の1月14日頃に内覧会を実施すべきです。
高価な不動産を購入するわけです。自分達だけでなく、次の世代にも引き継いでいく大事な資産の引渡しです。内覧会の前に、ちらし、売買契約、平面図や仕様書などの契約図書類に、再度良く目を通して、それらの条件に遵守しているかを確かめなくてはなりません。悔いを残さないためにも、内覧会までの準備期間、そして内覧会の後の引渡しまでの期間も充分に取っておいた方が安心と言えます。(612)
 写真は、戸建の内覧会で撮影したバスルームです。ここでご覧頂きたいのは、窓にかかっているブラインドです。このブラインドは標準装備として付いていました。こういうのを見ると、気を使ってるな、と好感が持てます。
写真は、戸建の内覧会で撮影したバスルームです。ここでご覧頂きたいのは、窓にかかっているブラインドです。このブラインドは標準装備として付いていました。こういうのを見ると、気を使ってるな、と好感が持てます。
戸建の場合、バスルームは1階が多く、窓は曇りガラスになっていますが、周りが暗くなって、中で明かりを点けますと、外からどう見えるか、気にはなります。また、ビューバスを売りにしているマンションのお部屋もあります。ゆったりと外の景色を見ながら、お湯に浸かる、考えただけでも気持ちが癒されます。でも、時間と共に環境も変わります。今まで、何も無かった隣の敷地に高層マンションが建ってしまう、こんなこともあります。
以上のようなことを考えますと、バスルームには、写真のようなブラインドを付けておくのが安心かな、と思います。モデルルームに行ったり、お部屋の内覧会に行かれる際には、バスルームの窓にブラインドが設置されているのかもご確認下さい。そして、設置されてなくて、これでは気になる、という場合には、ブラインドの設置を売主に要求してみて下さい。(811)
 写真は一戸建て(建売り)の内覧会で撮りました。写したところは洗面所で、ご覧頂きたいのは、タオル掛けと書いてあるところです。ここに掛けたタオルで手や顔を拭くのは、腰を曲げねばならず面倒だし、濡れた手のしずくが床に落ちるでしょう。
写真は一戸建て(建売り)の内覧会で撮りました。写したところは洗面所で、ご覧頂きたいのは、タオル掛けと書いてあるところです。ここに掛けたタオルで手や顔を拭くのは、腰を曲げねばならず面倒だし、濡れた手のしずくが床に落ちるでしょう。
洗面所のタオル掛けを付ける理想的な位置は、洗面台の左側の壁です。ここであれば、腰も曲げないし、しずくが垂れても、洗面台の上ですから問題ありません。
建売りの場合、このようにタオルハンガーが壁に付いていないケースが非常に多いです。それでは、自分で左側の壁に付ければ良いでしょう、ということになりますが、壁の下地がないとしっかりと付けることはできません。建売りをお買いになる場合には、タオルハンガーが付いているかも確認して下さい。付いていない場合には、壁のどこに下地が入っているかを売主に確認し、その位置に付ければ良いでしょう。(64)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。ここは洋室となっています。ご覧頂きたのは、壁にエアコン設置位置と書いてあるところです。エアコン用のコンセントが壁に設置してあるので、ここにエアコンが設置されると売主側は設計したわけです。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。ここは洋室となっています。ご覧頂きたのは、壁にエアコン設置位置と書いてあるところです。エアコン用のコンセントが壁に設置してあるので、ここにエアコンが設置されると売主側は設計したわけです。
しかし、ここの収納は折戸(おれど)となっていて、外側に開くようになっており、折戸の端部は固定なので、ずらすこともできません。折戸の上端から天井までは、30㎝しかありません。また、窓の上にはカーテンレールも付けるので、エアコンの設置スペースとしては、高さが30㎝で幅は70㎝が限度です。幅はどうにかなるでしょうが、エアコンを設置するための高さが問題となります。これは、設計上のミスで、折戸との関係を確認出来てなかったと思われます。
エアコンを設置するスペースは、このように建具が来たり、カーテンレールが来たり、平面図だけでは読み切れないことが出ることがあります。購入時に、部屋を平面的だけでなく立体的に想像してみることが大事となります。(99)
 写真は一戸建ての中間検査で撮りました。骨組みと外装工事が終わり、内装工事に入っていきます。この家は、屋根と外壁の断熱仕様が発泡ウレタンの吹き付けとなっています。写真は、外壁に吹き付け工事を実施しているところです。
写真は一戸建ての中間検査で撮りました。骨組みと外装工事が終わり、内装工事に入っていきます。この家は、屋根と外壁の断熱仕様が発泡ウレタンの吹き付けとなっています。写真は、外壁に吹き付け工事を実施しているところです。
この方法は、一般的なグラスウールなどのマットを敷き並べる方法に比べ、現場で吹き付けしますので、隙間が出来にくく、断熱性能は高いと言えます。ただ、工事費がグラスウールに比べ、やや高いことから、一戸建ての工事の主流にはなっていません。私は一戸建ての完成検査等で、いろんな種類の家に入りますが、特に夏の内覧会の場合には、吹き付け断熱かグラスウールか、家の中に入れば、確認するまでもなく体感で分かります。(73)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したのは、1階にあるトイレです。ご覧になって頂きたいのは、矢印で示した「間隔が狭い」というところです。私がトイレに実際に座ってみたところ、ほとんど足が開けず、両ひざを接したままになってしまいます。ちょっとこれでは、使いにくいなとなります。売主の担当者にも、実際に座ってもらいました。そしたら、「これでは確かに狭いですね・・・」とのことでした。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したのは、1階にあるトイレです。ご覧になって頂きたいのは、矢印で示した「間隔が狭い」というところです。私がトイレに実際に座ってみたところ、ほとんど足が開けず、両ひざを接したままになってしまいます。ちょっとこれでは、使いにくいなとなります。売主の担当者にも、実際に座ってもらいました。そしたら、「これでは確かに狭いですね・・・」とのことでした。
結局、手洗い器付の便器に変更するということになりました。トイレは、配管がいろいろとあるので、便器の交換も簡単ではありません。ですので、作ってしまってからでは、制約が出てきます。間取り図から、このような状況を予想するのは簡単ではありません。しかしながら、間取り図の段階で、便器と手洗い器の位置関係を把握することで防ぐしかありません。(412)
 写真は、一戸建ての内覧会当日、内覧会が始まる前に撮ったものです。内覧会は、ゴミ置き場の後ろに写っている家で、その日は、たまたま、ゴミ出しの日でした。買主の人は、「エー、敷地の隅がゴミ置き場とは知らされてたけど、まさか、こんな具合にゴミが置かれるなんて!」とびっくりしてました。
写真は、一戸建ての内覧会当日、内覧会が始まる前に撮ったものです。内覧会は、ゴミ置き場の後ろに写っている家で、その日は、たまたま、ゴミ出しの日でした。買主の人は、「エー、敷地の隅がゴミ置き場とは知らされてたけど、まさか、こんな具合にゴミが置かれるなんて!」とびっくりしてました。
設計図面には、確かに敷地の隅にはゴミ置き場の記載があるし、また、重要事項にもその旨が書いてあります。ただ、現実には、ゴミ置き場として置かれている箱には、ゴミは入りきらず、入りきらないゴミ袋は新築の家の前に並べられています。売主も、販売前にはこういう状態を知っていたと思われます。だから、家の窓の前に板塀を設置して、窓から見えなくする応急措置を取ったのでしょう。
戸建の場合、購入した家の隅がゴミ置き場になっている、というケースはあります。通常は、小さなゴミ置きの箱が描かれているだけです。でも、それは、図面上だけの話であって、現実には、写真のような状態になることもあります。そのような条件の家を購入する場合には、事前に、ゴミ出しの日に状況を確認しておくのが良いでしょう。家が完成して、写真のような状態になってしまっていたら、自治会に問題を提起して解決するしかないでしょう。(912)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印の部分です。この家の場合、たまたま、道路の雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。これは、しようがない、としか言いようがありません。家が建設される前に、道路が整備されているので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは公道で役所の管理となりますので、無理な話となります。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印の部分です。この家の場合、たまたま、道路の雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。これは、しようがない、としか言いようがありません。家が建設される前に、道路が整備されているので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは公道で役所の管理となりますので、無理な話となります。
この配置は仕方ないことなのですが、工夫が必要となるのは、この雨水枡にカギやお金が転がり込んだ場合の対策です。玄関ですから、カギを出します。出したカギが、手からすべって、階段をころころ転がって、この中に落ち込んでしまうことも考えられます。ここの中に落ち込んでしまったら、蓋は重いし、枡の底は泥が堆積しまうので、取り出すのは大変です。このようなことを防ぐためには、この枡の蓋の内側に、ネットを置いたら良いでしょう。ある程度目の粗いネットであれば、雨は中に落ちるし、カギやお金はネットの上に載ります。ここの家の場合も、売主に言って、目の粗いネットを蓋の下に敷いてもらいました。(31)
 写真は、内覧会で建売住宅のグルニエ(屋根裏収納)を写しました。グルニエとは、フランス語で屋根裏部屋のことです。ロフトと似ていますが、ロフトとは天井高を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。グルニエとは屋根裏を利用した収納スペースになります。
写真は、内覧会で建売住宅のグルニエ(屋根裏収納)を写しました。グルニエとは、フランス語で屋根裏部屋のことです。ロフトと似ていますが、ロフトとは天井高を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。グルニエとは屋根裏を利用した収納スペースになります。
グルニエは、建築基準法上、小屋裏物置等という扱いになります。面積は下の階の2分の1以下、天井高は1.4m以下、小屋裏に出入りするためのハシゴは固定式でないこと、などの規制があります。そのため取り外し可能なはしごをかけたり、折り畳んで収納できるタイプのはしごを取り付けたものがよく見られます。
このグルニエで気に入ったのは、左側の手すりです。一般には、ここに手すりが無い場合が多いです。元々、この家にも手すりは付いていなかったのですが、ここの買主が安全性を考慮してオプションで付けました。ホームセンターで手すりを購入して自分で簡単に付けることもできます。この手すりの役目は、グルニエに上がる時、そして降りる時、役に立ちます。特に、グルニエから降りる際は、危険ですので、この手すりが有効です。そして、この手すりの更なる役目は、グルニエに置いた荷物などが下に落ちるのも防いでくれます。(0322)
 写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は廊下からトイレの中です。ご覧頂きたいのは、赤い付箋が貼ってある収納の扉です。赤い付箋を貼ったのは、この向きでは、使いにくいのでダメという意味です。この扉の向きでは、物を入れるときに向こう側から入れなくてはならないので、不便です。手前から向こう側に開いた方が使い易いです。
写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は廊下からトイレの中です。ご覧頂きたいのは、赤い付箋が貼ってある収納の扉です。赤い付箋を貼ったのは、この向きでは、使いにくいのでダメという意味です。この扉の向きでは、物を入れるときに向こう側から入れなくてはならないので、不便です。手前から向こう側に開いた方が使い易いです。
売主には、これでは使い勝手が悪いから手前から開くようにしてと要求しました。売主は、この要求を受けて、扉を付け替えることになりました。間取り図だけから、このような箇所の扉の向きを把握するのは簡単ではありません。でも、出来てからでは、売主もお金がかかるので簡単に承諾はしません。ですので、可能であれば、図面の段階で、このような点も確認しておいた方が良いでしょう。(35)
 写真は戸建の建築中のもので、写っているのは1階の天井裏です。ご覧頂きたいのは矢印部分の断熱材を天井裏に敷きこんだ部分です。手前の天井裏には、断熱材は入っていませんが、これから敷きこんでいきます。
写真は戸建の建築中のもので、写っているのは1階の天井裏です。ご覧頂きたいのは矢印部分の断熱材を天井裏に敷きこんだ部分です。手前の天井裏には、断熱材は入っていませんが、これから敷きこんでいきます。
一般に、屋根裏、外壁、床下には断熱材を敷きこみますが、写真のような1階の天井裏や部屋の間仕切り壁の中には、入れ込まない場合が多いです。この住宅の設計も、元々は1階の天井裏には断熱材を敷きこまないことになっていました。そこを途中で変更して、1階の天井裏にも、厚さ55㎜のロックウール断熱材(グラスウール断熱材でも良い)を敷きこむように指示をしました。
戸建住宅の設計で最も注意が必要となるのが断熱と遮音だと思います。外からの断熱と遮音だけでなく、家の中でも独立性を高めたいものです。例えば、1階の天井裏、部屋と部屋の間仕切壁、水周りの壁、このようなところの断熱性と遮音性を高めることは大事なことでしょう。断熱材は遮音材としても使えますので、断熱材を入れ込むことは、遮音性も高まります。また、断熱材は建築基準法上は不燃材料ですから、火事の際など、1階から2階への延焼時間が少し長くなることも考えられます。
1階の天井裏、間仕切壁の中、このようなところに断熱材を入れるように設計変更しても、金額は僅かのアップで済みます。断熱材を並べたり、入れたりするだけですから、材料費と工事費込みで、4~5千円/坪程度です。但し、天井や壁を張ってしまった後では、厄介なので、契約時、上棟時など、壁や天井を張る張る前に、なるべく早い段階で要望しなければなりません。(64)
 写真は、一戸建ての内覧会で、玄関周りを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、玄関ポーチとフェンスブロック塀との隙間です(赤の矢印部分)。塀とポーチを一体に作ることは出来ませんので、このような隙間があるわけです。
写真は、一戸建ての内覧会で、玄関周りを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、玄関ポーチとフェンスブロック塀との隙間です(赤の矢印部分)。塀とポーチを一体に作ることは出来ませんので、このような隙間があるわけです。
ここで気になるのは、この隙間に何かを落し込んでしまった場合です。玄関ですからカギを出します。その時にカギがすべって、この隙間に転がりこんでしまうこともあるでしょう。また子供の遊び道具や枯葉やゴミなども入るでしょう。そういう時に、この隙間には手が入りませんので、拾い上げたり、掃除するのが厄介になります。
それでは、どうすれば良いのでしょうか?玄関ポーチが出来上がる前であれば、目地モルタルなどを隙間に打ち込んでもらえば良いでしょう。出来上がってしまった後では、目地モルタルなどを打ち込むのは難しいでしょうから、隙間の寸法に合ったゴム系の板などを詰め込むのが良いと思います。(755)
 写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるガスメーターの位置です。ガスメーターが家の側面、駐車場側に取り付けられています。ここで心配になることは、駐車する際に、間違って、車をガスメーターにぶつけてしまうことです。
写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるガスメーターの位置です。ガスメーターが家の側面、駐車場側に取り付けられています。ここで心配になることは、駐車する際に、間違って、車をガスメーターにぶつけてしまうことです。そこで、内覧会の時に、このガスメーターの位置では車をぶつける可能性があるので、家の正面側に移設して欲しい、という要望を出しました。移設工事は大変なので、最初は業者も渋っていましたが、どうにか説得して、最終的には、無償で移設することを了解してくれました。
移設することを無償で了解してくれましたが、このような設計上の問題は、計画の段階でチェックしておく方が手間がかかりません。ガスメーターは月に一度は検針に来ます。ですから、人が入れない位置に置くことは出来ません。検針も問題なく出来て、危険性もないところ、設計の段階で吟味して、適切な位置に置かれるべきです。(76)
 写真は戸建の内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、床下収納の位置です。この位置が気に入りました。床下収納の位置が、キッチンの奥の端にあれば、その分、その上を歩くことは少なくなります。床下収納とは、床下を利用して、中に収納ボックスを置いて、その上にカバーを掛けます。また、キッチンなどの漏水があった場合には、ここから床下に入って行きます。
写真は戸建の内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、床下収納の位置です。この位置が気に入りました。床下収納の位置が、キッチンの奥の端にあれば、その分、その上を歩くことは少なくなります。床下収納とは、床下を利用して、中に収納ボックスを置いて、その上にカバーを掛けます。また、キッチンなどの漏水があった場合には、ここから床下に入って行きます。
カバーですから、収まりが結構難しくて、上を歩くと、カタカタしてしまうケースが多いです。また、カバーの取っ手も付きますから、その上を歩きますと、少し引っ掛かったり、冷たかったり、気になる場合もあるでしょう。床下収納を設置しようとお考えの際は、その位置は、少しでも、上にいる時間が短い方が良いと思います。そう考えると、写真のように、キッチンのなるべく奥の方が良いでしょう。
また、収納ボックスの下に、砂袋を置いてある場合もあります。これは、重くなりすぎて、ボックスの底が抜けるのを防ぐためです。もし砂袋がなくて、重くて底が抜けるのが心配であれば、ビニール袋に砂を入れて、収納ボックスの下に置く事もできます。(03)
 一戸建ての売買契約時に、買主として入手すべき建築図書(図面や書類)が揃っているかを確認します。売買契約書や重要事項、平面図や立面図、これらは一般的に売主が買主に渡しています。しかしながら、家の地盤の状態や骨組みは見えないので、これらが分かる資料も買主は保管しておくべきです。内覧会で家を検査する以前に、買主が入手している建築図書の内容を確認し、以下の図書が無いようであれば、売主に対し、提出するように要望すべきです。以下に、その内容を記します。
一戸建ての売買契約時に、買主として入手すべき建築図書(図面や書類)が揃っているかを確認します。売買契約書や重要事項、平面図や立面図、これらは一般的に売主が買主に渡しています。しかしながら、家の地盤の状態や骨組みは見えないので、これらが分かる資料も買主は保管しておくべきです。内覧会で家を検査する以前に、買主が入手している建築図書の内容を確認し、以下の図書が無いようであれば、売主に対し、提出するように要望すべきです。以下に、その内容を記します。
1.一般的に配布される建築図書
・売買契約書関連(需要事項説明書等)
・確認申請及び確認済証
・地積測量図、配置図、各階平面図、立面図、設備図(電気、給排水)
・仕様書(外装、内装、設備にどういう材料を使ったかを書いたもの)
2.一般的に配布されていないケースが多い建築図書
・地盤調査報告書:地盤についての調査結果です。中に、考察があることも確認要。
・地盤改良報告書:地盤を改良した場合、その内容について書いたもの。
・矩計図(かなばかりず):家の断面詳細図。
・構造図:各階別に家の骨組みの状態を示したもの。
・壁量計算書:建物の風及び地震に対する強さを示したもの。
・構造計算書:建築基準法では3階以上は構造計算することになっている。
・外構図:庭の状態を示したもの。
2に示した建築図書は、少し専門的になりますが、外からは見えないところを表していたり、家の強さ等を証明する重要なものとなりますので、売主から入手して保管しておくべきものです。(32)