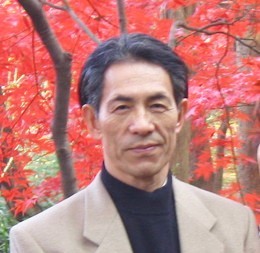写真は、一戸建ての内覧会で、2階の洋室からバルコニーへ出るドアを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、赤い矢印の部分です。2階の洋室からバルコニーに出る際に、このドアを開きます。このドアをいっぱいに開けようとすると、ドアの取っ手が壁にぶつかってしまいます。取っ手が壁にぶつかれば、取っ手も壁も傷付いてしまいます。これでは問題です。それでは、こういう場合はどうしたら良いのでしょう?
写真は、一戸建ての内覧会で、2階の洋室からバルコニーへ出るドアを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、赤い矢印の部分です。2階の洋室からバルコニーに出る際に、このドアを開きます。このドアをいっぱいに開けようとすると、ドアの取っ手が壁にぶつかってしまいます。取っ手が壁にぶつかれば、取っ手も壁も傷付いてしまいます。これでは問題です。それでは、こういう場合はどうしたら良いのでしょう?
解決方法は、ドアが壁にぶつかる前に止めてしまうか、壁にぶつかった時の為に緩衝材(例えばゴムの受け等)を壁に付けるか、この2通りです。壁にぶつかる前にドアを止めようとすると、床や壁にストッパーを付けることになります。ただ、この方法は条件が難しくなります。写真の場合には、壁とドアの取っ手、両方にゴムの緩衝材を付けることにしました。(911)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。この家は大規模開発で分譲された建売り住宅の一つです。このような開発された場合、先ず、全体の整地がなされ、道路が作られ、その時に道路脇の雨水の側溝も設置されます。側溝には、間隔をおいて、このような雨水枡が置かれます。この家の場合、たまたま、雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。家の細かい平面図を決める前に、道路が整備されるので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは市の管理となりますので、無理な話となります。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。この家は大規模開発で分譲された建売り住宅の一つです。このような開発された場合、先ず、全体の整地がなされ、道路が作られ、その時に道路脇の雨水の側溝も設置されます。側溝には、間隔をおいて、このような雨水枡が置かれます。この家の場合、たまたま、雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。家の細かい平面図を決める前に、道路が整備されるので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは市の管理となりますので、無理な話となります。
この配置は仕方ないことなのですが、工夫が必要となるのは、この雨水枡にカギやお金が転がり込んだ場合の対策です。玄関ですから、カギを出します。出したカギが、すべって、階段をころころ転がって、この中に落ち込んでしまうことも考えられます。ここの中に落ち込んでしまったら、蓋は重いし、枡の底は泥が堆積しまうので、取り出すのは大変です。このようなことを防ぐためには、この枡の蓋の内側に、ネットを置いたら良いでしょう。ある程度目の粗いネットであれば、雨は中に落ちるし、カギやお金はネットの上に載ります。ここの家の場合も、売主に言って、目の粗いネットを蓋の下に敷いてもらいました。(131)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、赤い矢印で示した部分です。お分かりにくいと思いますが、ここは外からの電力の引込線となっています。気になったのは、この引込線の一部が隣の敷地に僅か越境していることです。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、赤い矢印で示した部分です。お分かりにくいと思いますが、ここは外からの電力の引込線となっています。気になったのは、この引込線の一部が隣の敷地に僅か越境していることです。
上空であっても、電柱から引き込む配線は隣地に出ることはできません。 土地を所有することは地上権及び地下権も持ちます。地上権と言っても、飛行機や高圧線などは除外となりますから、常識的には高圧線の高さぐらいと考えれば良いでしょう。また地下権につきましては地下鉄を通すなとも言えませんので、そのあたりまでとなるでしょう。
戸建ての内覧会では、上の方なので分かりにくいですが、このような部分も確認して下さい。同じようなものとして植栽の枝などがあります。尚、越境してるどうかの基準点は土地の境界線となります。(528)
 写真は中古一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、矢印で指した「外壁ボードの反り」と書いたところです。この家の外壁は、よく使われるサイディングボードで作られています。このボードはセメントに繊維質を混ぜプレスしたものです。
写真は中古一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、矢印で指した「外壁ボードの反り」と書いたところです。この家の外壁は、よく使われるサイディングボードで作られています。このボードはセメントに繊維質を混ぜプレスしたものです。
新築の場合には、このような例は稀と思いますが、内覧会では、外壁の状態を良く観察し、反り、膨れ、ジョイントのコーキングの状態、このような点を確認して下さい。外壁は家の中を自然から守る非常に大事なものなので、少しでも異常があれば、売主に相談すべきです。(77)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。矢印の箇所を見て頂くと、縦樋(たてどい:雨水を排出する管)がへこんでいるのが分かります。施工業者が何かをぶつけたのでしょう。樋がへこんでいては、雨水の流れもスムーズでなくなりますし、新築ですから見栄えも悪くなります。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。矢印の箇所を見て頂くと、縦樋(たてどい:雨水を排出する管)がへこんでいるのが分かります。施工業者が何かをぶつけたのでしょう。樋がへこんでいては、雨水の流れもスムーズでなくなりますし、新築ですから見栄えも悪くなります。
戸建ての内覧会に行きましたら、内部だけでなく、外部のこのような箇所もしっかりと隅々観察すべきです。(878)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したものは境界標(きょうかいひょう)です。敷地の境界点を示すものを境界標と言います。境界標にはいくつかの種類があります。これは、境界点を矢印の先で示す貼り付けタイプのプレートで、最も単純なものです。そのプレートを手に持っていますが、これは簡単に取れてしまったからです。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したものは境界標(きょうかいひょう)です。敷地の境界点を示すものを境界標と言います。境界標にはいくつかの種類があります。これは、境界点を矢印の先で示す貼り付けタイプのプレートで、最も単純なものです。そのプレートを手に持っていますが、これは簡単に取れてしまったからです。
本来は、ブロックの真ん中に取れないように、しっかりと設置されていなければなりません。敷地の境界点を示す大事な標(しるし)を示すプレートが外れてしまっては困ります。こういうものは、個人が勝手に接着剤で付けられるものではありません。土地家屋調査士が敷地の広さや境界を確認して、設置したものだからです。
戸建ての内覧会では、自分の敷地が明確に分かるように境界標が設置されているか、また、その境界標はしっかりとずれないようになっているか、これらの点も確認して下さい。土地の境界は非常に大事で、隣家同士でもめると大変です。内覧会で、境界標が不明、もしくは境界標がしっかりと設置されていない、このような場合には、売主に不具合として指摘して下さい。(48)
 写真は一戸建ての確認会で撮りました。確認会とは、内覧会で指摘した不具合が補修されて、その完成具合を確認する日です。この家の場合、内覧会が2週間ほど前に行われ、その際に、樋の延長と雪止め金具を設置するように指示しました。
写真は一戸建ての確認会で撮りました。確認会とは、内覧会で指摘した不具合が補修されて、その完成具合を確認する日です。この家の場合、内覧会が2週間ほど前に行われ、その際に、樋の延長と雪止め金具を設置するように指示しました。
樋の延長につきましては、屋根から鉛直に降りてきている樋の矢印部分をご覧下さい。ここで茶色の樋は後から付け足した部分です。内覧会の時点では、樋は白色部分だけでした。白色部分だけですと、屋根に相当量の雨が降った場合には、そのまま樋を落ちて来るので、雨の勢いが強く、樋の先端から雨が噴き出すようになります。そうしますと音もしますし、隣の家の庭にも、雨が撥ね飛ぶ可能性があります。それを防ぐために、茶色の樋の部分を延長し、軒樋につなぐようにしました。
また、もう一つの矢印で示した雪止め金具につきましては、内覧会の時点では、ここの屋根には雪止め金具は付いていませんでした。雪止め金具とは、屋根に降った雪が、融けて落ちる際に、大きな塊で落ちて、人の上に落ちたり、樋を壊したりしないようにするためのものです。屋根に雪止め金具を付けるかどうかは、屋根の種類、向き、勾配などによって決まります。この屋根は北側に向いてますので、安全のため、雪止め金具を設置するように、内覧会で指示しました。
以上のような指摘事項は、一般の方には、ちょっと難しいかもしれません。でも、家の周りを見回して、疑問に思った事項があったら、売主に確認してみることが必要となります。(3826)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したのは、玄関のドアをいっぱいに開けた状態です。玄関ポーチの周りには手すりがあります。わかりにくいのですが、ポーチの床には、玄関ドアが手すりに当たらないように、戸当たりが付いています。黄色の字で、「ドアが戸当たりに当たらない」と書いてある↑の先です。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したのは、玄関のドアをいっぱいに開けた状態です。玄関ポーチの周りには手すりがあります。わかりにくいのですが、ポーチの床には、玄関ドアが手すりに当たらないように、戸当たりが付いています。黄色の字で、「ドアが戸当たりに当たらない」と書いてある↑の先です。
本来なら、玄関ドアは、手すりに当たらないように、戸当たりに先に当たらなければなりません。写真のケースでは、手すりに先に当たってしまうので、勢いよくドアを開けると、手すりに当たってしまって、ドアも手すりも傷つく、ということになります。これでは、何のために床に戸当たりを付けたのか、分からなくなってしまいます。
内覧会に行きましたら、このような箇所も確認してみて下さい。玄関ドアは、スムーズに開くか、万が一、開き過ぎた場合に支障はないか、このような点です。(312)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。この家のフェンスは、前面は黒の縦格子で後面はネットフェンスとなっています。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印で示した箇所です。ここは黒の縦格子の端の部分ですが、切ったまんまで端部にキャップがありません。これでは手が触れた時に危険ですし、雨が中に入ってしまいます。これは業者が付けるのを忘れていました。内覧会に行きましたら、細かいところですが、こういうところも確認下さい。(69)
写真は戸建ての内覧会で撮りました。この家のフェンスは、前面は黒の縦格子で後面はネットフェンスとなっています。ここでご覧頂きたいのは、白い矢印で示した箇所です。ここは黒の縦格子の端の部分ですが、切ったまんまで端部にキャップがありません。これでは手が触れた時に危険ですし、雨が中に入ってしまいます。これは業者が付けるのを忘れていました。内覧会に行きましたら、細かいところですが、こういうところも確認下さい。(69)
 写真は、戸建ての内覧会で撮りました。写した箇所は、新築の家の周りに立てられたネットフェンスです。ここで、ご覧になって頂きたいのは、キャップなし、キャップあり、と書かれている矢印の先です。
写真は、戸建ての内覧会で撮りました。写した箇所は、新築の家の周りに立てられたネットフェンスです。ここで、ご覧になって頂きたいのは、キャップなし、キャップあり、と書かれている矢印の先です。
ここの部分は、ネットが切断されたところで、本来、キャップで端部は処理されなければなりません。上の方はあるのですが、下の方はキャップがありません。これでは、指が触れれば傷つく可能性もありますし、錆びても来るでしょう。細かいことですが、内覧会に行きましたら、こういう箇所も確認して下さい。(871)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、屋外にある給湯機の下の部分です。基礎の立ち上がり部分に穴を開けてパイプを通し、床下を伝わって水が来て、給湯器に入ってお湯となり、また床下を通って家の中に運ばれます。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、屋外にある給湯機の下の部分です。基礎の立ち上がり部分に穴を開けてパイプを通し、床下を伝わって水が来て、給湯器に入ってお湯となり、また床下を通って家の中に運ばれます。
ここでご覧頂きたいのは、白い←の部分です。右側の穴の周りはコーキングでちゃんとふさがれていますが、左側の←で示した穴の周りはふさがれていません。これでは、雨や虫が入って来てしまいます。右側はちゃんとしていて、左側は忘れてる、ちょっと理解に苦しみますが、こういうこともあります。(6826)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、家の外側から、1階の洗面所の窓のサッシ部分です。写真の赤い付箋が貼ってある横を見て頂きますと、サッシの下の部分が少し折れ曲がっているのが分かります。折れ曲がった原因は、工事中に何かを上から落としたか、ぶつけたからだと思います。外周りのサッシの不具合、それほど多くはないですが、あるものです。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは、家の外側から、1階の洗面所の窓のサッシ部分です。写真の赤い付箋が貼ってある横を見て頂きますと、サッシの下の部分が少し折れ曲がっているのが分かります。折れ曲がった原因は、工事中に何かを上から落としたか、ぶつけたからだと思います。外周りのサッシの不具合、それほど多くはないですが、あるものです。
内覧会の日は雨が降っていたので、サッシが濡れています。特に、内覧会の日に雨が降っていると、外周りを見ることが面倒になりますが、サッシの状態も確認して下さい。(475)
 建売住宅をお買いになる場合には、植栽も決まっています。通常、外構図に植栽計画が描かれています。自分の好みのようになっていれば、言うことないのですが、必ずしもそうではありません。写真は、玄関の周りの植栽を撮りました。ここで、気になったのは、門から玄関までのアプローチの横にある木です。写真では、木の幹と細い枝が茶色になっている落葉樹です。この木がこの位置では、木が大きくなってきますと、枝が通行の邪魔になってきます。また、落葉樹は秋には葉が落ちますので、玄関周りではその掃除も大変です。
建売住宅をお買いになる場合には、植栽も決まっています。通常、外構図に植栽計画が描かれています。自分の好みのようになっていれば、言うことないのですが、必ずしもそうではありません。写真は、玄関の周りの植栽を撮りました。ここで、気になったのは、門から玄関までのアプローチの横にある木です。写真では、木の幹と細い枝が茶色になっている落葉樹です。この木がこの位置では、木が大きくなってきますと、枝が通行の邪魔になってきます。また、落葉樹は秋には葉が落ちますので、玄関周りではその掃除も大変です。
内覧会に行きましたら、外の植栽の状態もご覧下さい。植物は大きくなる、また、落葉樹は秋には葉が落ちます。このようなことを考えて、邪魔になったり、木の種類や配置が気になる場合には、移植、除去など売主に依頼してみて下さい。内覧会の時点であれば、除去、移植ぐらいは無料で実施してくれるでしょう。また、植栽は1年間の保証が付いています。内覧会で枯れていたり、引渡し後の1年の間に枯れてきてしまったら、新しい木に取り替えてもらう事はできます。(8.12)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。この家は大規模開発で分譲された建売り住宅の一つです。このような開発された場合、先ず、全体の整地がなされ、道路が作られ、その時に道路脇の雨水の側溝も設置されます。側溝には、間隔をおいて、このような雨水枡が置かれます。この家の場合、たまたま、雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は玄関前です。この家は大規模開発で分譲された建売り住宅の一つです。このような開発された場合、先ず、全体の整地がなされ、道路が作られ、その時に道路脇の雨水の側溝も設置されます。側溝には、間隔をおいて、このような雨水枡が置かれます。この家の場合、たまたま、雨水枡が玄関前に来てしまったわけです。
これは、しようがない、としか言いようがありません。家の細かい平面図を決める前に、道路が整備されるので、このようなケースも生じてしまいます。これではイヤだから、移して下さい、と言いたいところですが、ここは市の管理となりますので、無理な話となります。この配置は仕方ないことなのですが、工夫が必要となるのは、この雨水枡にカギやお金が転がり込んだ場合の対策です。玄関ですから、カギを出します。出したカギが、すべって、階段をコロコロ転がって、この中に落ち込んでしまうことも考えられます。ここの中に落ち込んでしまったら、蓋は重いし、枡の底は泥が堆積しまうので、取り出すのは大変です。
このようなことを防ぐためには、この枡の蓋の内側に、ネットを置いたら良いでしょう。ある程度目の粗いネットであれば、雨は中に落ちるし、カギやお金はネットの上に載ります。ここの家の場合も、売主に言って、目の粗いネットを蓋の下に敷いてもらいました。(3122)
 写真は一戸建ての内覧会で、庭の端の方を撮りました。手前はきれいな芝に見えますが、人口芝です。一戸建てで庭に人工芝が敷かれているのは珍しいです。人工芝とフェンスとの間は、写真では草が生えていますが、花でも植えられるようにと土の表面になっています。
写真は一戸建ての内覧会で、庭の端の方を撮りました。手前はきれいな芝に見えますが、人口芝です。一戸建てで庭に人工芝が敷かれているのは珍しいです。人工芝とフェンスとの間は、写真では草が生えていますが、花でも植えられるようにと土の表面になっています。
ここで問題なのは、土の部分に残されているガラや石などです。ここには、いずれ、花や木が植えられていくわけですが、これだけガラや石があると、穴を掘るのも大変ですし、花や植木もしっかりと育ちません。また、ガラや石の処分は、お金がかかります。一戸建ての内覧会に行って、将来植栽しようと思っている庭に、このようなガラや石が残っている場合には、売主に処分をお願いするのが良いでしょう。(7822)