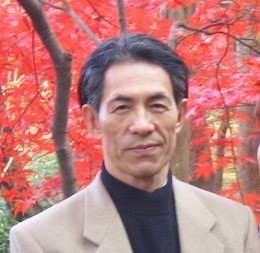写真はマンションの内覧会で撮りました。写しているのはバスタブです。ご覧頂きたいのは、紅いテープが貼ってあるところで、キズが2箇所あります。何かを落としたのか、ぶつけたのか、小さなキズですが、表面の仕上げがはがれています。このようなキズを見つけたら、不具合として指摘すべきです。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写しているのはバスタブです。ご覧頂きたいのは、紅いテープが貼ってあるところで、キズが2箇所あります。何かを落としたのか、ぶつけたのか、小さなキズですが、表面の仕上げがはがれています。このようなキズを見つけたら、不具合として指摘すべきです。
バスタブの表面の塗装がはがれてはまずいです。このような不具合は住んでしまってから気が付いても、売主の責任か、買主の責任か、責任の所在が不明確になりやすいものです。ですので、まだ、誰も住んでいない状態で指摘をした方が、売主の管理下にあるわけですから、不具合として指摘がし易いです。
内覧会に行きましたら、バスタブにも入って、表面の状態も良く観察して下さい。そこでキズなどを発見しましたら、売主に不具合として指摘すると共に、補修で直すのか、交換するのか、どのように補修するのかも聞いておくと良いでしょう。
バスルームの壁のパネルも同様です。バスタブや壁パネルにキズが入っているケースはあります。お湯をためたり、シャワーを使ったり、相手はお湯や水ですから、このような不具合は、漏水の原因になりますので、しっかりと直してもらわねばなりません。(611)
 写真はマンションの内覧会の時のものです。写したところはウォークインクローゼットの中です。ここでメジャーを当てているのは、ハンガーパイプから天井までの高さで、50㎝あります。ここのクローゼットの天井の高さは230㎝(2.3m)でパイプは上下2本設置されています。下のパイプは床から90㎝、上のパイプは床から180㎝となっています。つまり、ここのウォークインクロゼットは、天井の高さが230㎝、床から90㎝の位置に下のパイプが1本あって、そこから90㎝上に、もう1本上のパイプがあって、そこから天井まで50㎝ということです。
写真はマンションの内覧会の時のものです。写したところはウォークインクローゼットの中です。ここでメジャーを当てているのは、ハンガーパイプから天井までの高さで、50㎝あります。ここのクローゼットの天井の高さは230㎝(2.3m)でパイプは上下2本設置されています。下のパイプは床から90㎝、上のパイプは床から180㎝となっています。つまり、ここのウォークインクロゼットは、天井の高さが230㎝、床から90㎝の位置に下のパイプが1本あって、そこから90㎝上に、もう1本上のパイプがあって、そこから天井まで50㎝ということです。
身長が170㎝と考えて、パイプに男性のスーツを掛ける場合、95㎝以上ないと、下に付いてしまいます。ハンガーパイプから床、もしくは下のハンガーパイプまで、100㎝は欲しいところです。ですので、上のクローゼットのケースでは、下のパイプから床までも、上のパイプと下のパイプの間隔も、それぞれ90㎝ですから、スーツが付いてしまうことになります。このクローゼットの場合、上に50㎝のスペースがあるので、あと30㎝程上げるべきだったと思います。ハンガーパイプの位置が床から2mであれば、男性なら届くでしょう。また、ハンガーパイプの上のスペースは、棚もないので、何も使えず、もったいないと思います。クローゼットにハンガーパイプが上下に付いている場合には、その間隔も確認して下さい。(13.3)
 内覧会で、床鳴りと思われる箇所がありましたら、写真のように、テープを×印に付けておくのが良いでしょう。直してもらいたい重要な箇所だからです。また、ワックスを塗り終えて、あまり歩いていない床では、パリッと、乾いたワックスが割れる音がします。この音は数回しかしません。ワックスが割れたら、もうしないからです。これは、床鳴りではありませんので、心配は要りません。(610)
内覧会で、床鳴りと思われる箇所がありましたら、写真のように、テープを×印に付けておくのが良いでしょう。直してもらいたい重要な箇所だからです。また、ワックスを塗り終えて、あまり歩いていない床では、パリッと、乾いたワックスが割れる音がします。この音は数回しかしません。ワックスが割れたら、もうしないからです。これは、床鳴りではありませんので、心配は要りません。(610) 写真はマンションの内覧会でキッチン吊り戸棚の扉を開けたところを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、白い矢印の部分です。これは、あおり止めと呼ばれるもので、扉をこれ以上開かなくするための金具です。キッチンの吊り戸棚の横には、冷蔵庫やレンジフードなども来ますので、扉を開けた時、ぶつからないようにしています。
写真はマンションの内覧会でキッチン吊り戸棚の扉を開けたところを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、白い矢印の部分です。これは、あおり止めと呼ばれるもので、扉をこれ以上開かなくするための金具です。キッチンの吊り戸棚の横には、冷蔵庫やレンジフードなども来ますので、扉を開けた時、ぶつからないようにしています。
金具を付けないで、ぶつかるの衝撃を防ぐ方法として、バンポン(通称:なみだ目)と呼ばれる直径5mm程の半球状の透明なクッションゴムを、ぶつかるところに貼っておくこともあります。バンポンの方が、安上がりだし、簡単なので、この方法が一般的ではあります。でも、このバンポンの難点は、接着剤で貼ってあるだけですので、長い間には、取れてしまうこともありますし、透明と言えども、光るので、見た目が少し気になります。
写真のように、金具を使っている方が、高級感があって、格好はいいな、とは言えるでしょう。ただ、ぶつからないように金具を付けるので、付け方によっては、もっと開きたいのに止められてしまう、こともあります。その際は、金具を付ける位置を少しずらして、目一杯扉が開くようにすれば良いでしょう。
モデルルームに行った際には、戸棚などの建具類の扉も開けてみて、扉の対処がどうなっているのかもチェックして下さい。特に冷蔵庫など、後から持ち込む器具にもこのような扉がぶつからないように注意が必要となります。この金具はホームセンターで売ってますので、自分で取り付けることも出来ます。(719)
 写真は、マンションの内覧会で引戸の戸袋部分を撮ったものです。戸袋の下(赤い矢印部分)にも幅木が設けられていることが分かります。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。幅木の目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分に幅木があるか、ないか、どちらが正しいということはないのですが、私は、ここに幅木があった方が良いな、と思っています。なぜなら、ここの部分も掃除をしますし、汚れやすいからです。
写真は、マンションの内覧会で引戸の戸袋部分を撮ったものです。戸袋の下(赤い矢印部分)にも幅木が設けられていることが分かります。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。幅木の目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分に幅木があるか、ないか、どちらが正しいということはないのですが、私は、ここに幅木があった方が良いな、と思っています。なぜなら、ここの部分も掃除をしますし、汚れやすいからです。それでは、内覧会に行って、この部分に幅木がない場合はどうしたら良いのでしょう? 答えは、「戸袋部分に幅木が付いていませんが、付けて頂くことは可能ですか?」と聞いてみることです。それで、売主の返事が、「設計上付けていないので付けられません」ということであれば、それで仕方ありません。
幅木の種類は、大きく分けて2種類あります。一つは厚みのある木製幅木(厚さは7㎜程度、木製でなく樹脂製もある)、もう一つは薄いソフト幅木(厚さは2㎜程度、材質はビニール系)です。上の写真で、赤い矢印はソフト幅木、緑の矢印は木製幅木です。木製幅木は釘で、ソフト幅木は接着材で壁に取り付けられます。ソフト幅木は値も安いので、このような戸袋、トイレ、洗面所などに使われます。
幅木の取り付けを売主に聞いてもダメだった場合には、自分で取り付けることも出来ます。この部分は引戸がありますので、厚い木製幅木はこすれてしまうこともあります。そんな時は、薄いソフト幅木であれば、接着剤で付けられますので、簡単です。壁の最下部に幅木があった方が、壁が傷つきにくくなります。真っ白い幅木はキズが目立ちやすいので、少し色が付いているのが良いでしょう。(81)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところはバスルームです。照明のスイッチを入れても、右側は点灯しますが、左側の赤い付箋が貼ってある方は点灯しません。電球を入れるのを忘れたのか、球切れかのどちらかでしょう。極めて稀ですが、こういうこともあります。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところはバスルームです。照明のスイッチを入れても、右側は点灯しますが、左側の赤い付箋が貼ってある方は点灯しません。電球を入れるのを忘れたのか、球切れかのどちらかでしょう。極めて稀ですが、こういうこともあります。
内覧会に行きましたら、付いている照明は全て点灯してみて下さい。また、照明のカバーもキズが付いたり、欠けたりしている場合もありますので、カバーもよく見て下さい。(710)
 写真は、戸建の内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、矢印の先の部分です。よくご覧頂くと、水滴があるのが分かると思います。ここは洗面台の下の扉を開けたところです。水をしばらく出して、様子を見ていましたら、排水管の継ぎ目から水滴が落ちてきました。継ぎ目の接着不良です。漏水は僅かであっても、家を傷めますし、カビも生えますので、完全に止めなければなりません。
写真は、戸建の内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、矢印の先の部分です。よくご覧頂くと、水滴があるのが分かると思います。ここは洗面台の下の扉を開けたところです。水をしばらく出して、様子を見ていましたら、排水管の継ぎ目から水滴が落ちてきました。継ぎ目の接着不良です。漏水は僅かであっても、家を傷めますし、カビも生えますので、完全に止めなければなりません。
新築の内覧会で漏水があるかどうかを確認するには、まず、水が出るところは全て出してみることです。そして、水を出しながら、下の扉や点検口を開けて状態を見てみる、手で触れてみる、ことが必要となります。そして、確認するところは、主に、継ぎ目の部分となります。(2108)
 写真はマンションの確認会で撮りました。これは24時間換気の部屋側の給気口です。吸気口ではなく、給気口と書きます。ここは、外壁に貫通した穴が開いていて、そこから外の空気が部屋の中に入ってきます。建材のホルムアルデヒド等に起因するシックハウスが社会問題となり、対策として、各居室に新鮮な空気を取り込むための給気口の設置が、2003年に建築基準法に盛り込まれました。ですので、それ以前のマンションや戸建てにはありません。居室とは人が定常的にいる部屋で、例えばリビングや寝室です。トイレや廊下は居室ではありません。
写真はマンションの確認会で撮りました。これは24時間換気の部屋側の給気口です。吸気口ではなく、給気口と書きます。ここは、外壁に貫通した穴が開いていて、そこから外の空気が部屋の中に入ってきます。建材のホルムアルデヒド等に起因するシックハウスが社会問題となり、対策として、各居室に新鮮な空気を取り込むための給気口の設置が、2003年に建築基準法に盛り込まれました。ですので、それ以前のマンションや戸建てにはありません。居室とは人が定常的にいる部屋で、例えばリビングや寝室です。トイレや廊下は居室ではありません。
住宅の居室には、必ず、このような給気口が壁のどこかに設けられています。この給気口にはレジスターと呼ばれる風量調節器が取り付けられます。ここから外気を取り込みますので、レジスターにはフィルターも内蔵されています。このフィルターも汚れてきますので、カバーを外し、水洗いが出来るようになっています。写真のカバーは45度回転して、外すタイプとなっています。
この部屋の内覧会は2週間ほど前にありました。その時点では、このカバーを45度回転させると、角の部分がぶつかってしまって45度回転させることは出来ませんでした。取り付けただけで、外すチェックをしてなかったのです。内覧会ではその点の指摘をして、2週間後の確認会では、ちゃんと外せるように直っていました。内覧会に行きましたら、このような給気口が各部屋にありますので、カバーがちゃんと外せるかも確認して下さい。(7623)
 写真は、戸建の内覧会で玄関へのアプローチ部分を撮りました。ご覧頂きたいのは、白い↓部分です。この部分のタイルが浮いているので、付箋を貼って不具合としました。タイルが浮いていれば、はがれて来てしまいます。このようなタイルは張り直しとなります。マンションでも戸建でも、タイルの接着不良は時々あります。
写真は、戸建の内覧会で玄関へのアプローチ部分を撮りました。ご覧頂きたいのは、白い↓部分です。この部分のタイルが浮いているので、付箋を貼って不具合としました。タイルが浮いていれば、はがれて来てしまいます。このようなタイルは張り直しとなります。マンションでも戸建でも、タイルの接着不良は時々あります。
タイルの浮きを確認するためには道具を使います。その道具とは打診棒(パルハンマー)と言い、金属の棒の先に、直径2cmほどの金属球が付いたものです。その打診棒で、タイルの表面を軽く叩いてみて、その反射音で判断します。反射音が、つまって重い音なら問題はなく、軽くてカンカンする音なら浮いています。要するに、下地のモルタルにしっかりと接着していれば重い音、しっかりと付いていなければ間に空気があるから軽い音、ということです。この打診棒を持っていない場合には、ドライバーや家のカギを使って、タイルの表面を軽くたたいて、その反射音でも判断できます。タイルが浮いているかどうかの判断は難しい点もありますが、たたいてみて、軽い音がしたら、接着状態について、売主に聞いてみるのが良いでしょう。(1012)
 内覧会に行きまして、気になるのはフローリングの状態です。キズもなく、ワックスも一様にきれいに塗られ、歩いてもしっかりしているフローリングはとても気持ちの良いものです。フローリングの状態を観察するには、リビングから始めるのが良いでしょう。大事な部屋ですし、部屋も窓も広く、明るいので、状態が確認しやすいからです。
内覧会に行きまして、気になるのはフローリングの状態です。キズもなく、ワックスも一様にきれいに塗られ、歩いてもしっかりしているフローリングはとても気持ちの良いものです。フローリングの状態を観察するには、リビングから始めるのが良いでしょう。大事な部屋ですし、部屋も窓も広く、明るいので、状態が確認しやすいからです。
チェックの仕方は、フローリングのキズや汚れ、ワックスの塗りムラ、フローリングの隙間、、床鳴りなどを主にチェックします。キズ、汚れ、ワックスの塗りムラはフローリングの表面を上、斜め、横、角度を変えて観察します。フローリングの隙間は、名刺1枚分が目安となります。それ以上開いていて下地が見えるようなら不具合として指摘となります。床鳴りは、床の上を歩き回って、床からきしむような音が出ないかを調べます。歩いてきしむ音が出たなら、そこで止まって、1本足で立って、更に数回体重をかけて踏み込んでみて下さい。それでもきしむ音が都度すれば床鳴りです。
写真のようなキズはささくれて危険ですので補修してもらわねばなりません。フローリングについては、不具合の判断が難しいこともあります。気になる場合には、業者に、これはいかがですか?と聞いてみてください。業者は、プロですから、補修すべきかは判断できます。フローリングに付きましては、ほとんど全ての不具合が直せますので気になる箇所は指摘すべきです。最後は、張替えれてもらえば良いのですから。(6115)
 マンションでも戸建てでも、コンクリートが使われます。コンクリートの弟分でモルタルというのがあります。コンクリートは、セメント、水、砂そして砂利を混ぜたもので、モルタルは、セメント、水、砂です。砂利が入っていれば、コンクリートと呼ばれます。通常、コンクリートは鉄筋と組み合わせて使われます。組み合わせて使う理由は、コンクリートは圧縮には強いけど、引っ張られた場合には極めて弱いからです。コンクリートの圧縮強度は300kg/cm2以上なのですが、引っ張られた場合には、その1/10程しか耐えられません。一方、鉄筋は引っ張られた場合、4000kg/cm2以上の強度を持っています。
マンションでも戸建てでも、コンクリートが使われます。コンクリートの弟分でモルタルというのがあります。コンクリートは、セメント、水、砂そして砂利を混ぜたもので、モルタルは、セメント、水、砂です。砂利が入っていれば、コンクリートと呼ばれます。通常、コンクリートは鉄筋と組み合わせて使われます。組み合わせて使う理由は、コンクリートは圧縮には強いけど、引っ張られた場合には極めて弱いからです。コンクリートの圧縮強度は300kg/cm2以上なのですが、引っ張られた場合には、その1/10程しか耐えられません。一方、鉄筋は引っ張られた場合、4000kg/cm2以上の強度を持っています。
建物は、ピアノなどの上からと地震時などのように横からの荷重を受けます。そうすると、押されたり、引っ張られたりします。押された場合はコンクリートが、引っ張られた場合は鉄筋が抵抗します。これがコンクリートと鉄筋を組み合わせて使う理由です。鉄筋は非常に強い材料なのですが大きな欠点もあります。それは錆びてしまうことです。錆びては困るので、アルカリ性であるコンクリートで被覆します。
コンクリートは水で練って使われます。セメントの硬化に必要な水の量はセメントの重量の20%程(これを水セメント比と呼びます)です。でも、これでは粘土のように硬くて、鉄筋の間に流し込めないので、水セメントは50~60%になります。そうすると硬化に必要のない水分は蒸発しますので、コンクリートの容積は減少します。この容積の減少分が一部ひび割れとなって現れてきます。従い、コンクリートにひび割れは起きてしまうものなのですが、問題は、ひび割れにによって中に水が入り、鉄筋を錆びさせることです。
コンクリートのひび割れは宿命的なものなのですが、そのひび割れが建物の致命的なものとなってはなりません。構造的に影響を及ぼすひび割れ幅は0.4mm以上と言われています。目に見えて、シャープペンシルの鉛筆の先は0.5mmですから、先が入るようであれば問題となります。ただ、0.4mm以下でも、はっきりと見えて、気になるようであれば、売主に言って補修してもらうべきです。