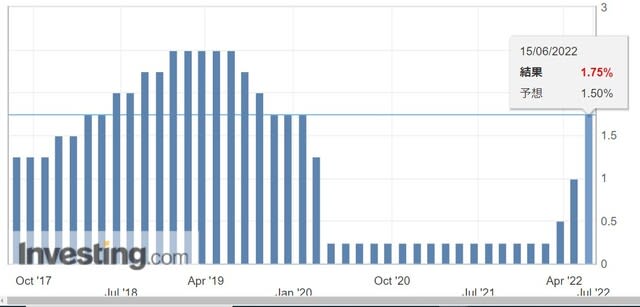■ グレートリセットって持続可能社会の実現が目的なの? ■
前回に引き続きダボス会議(世界経済フォーラム)が提唱する「グレートリセット」について妄想を膨らめてゆきます。
ダボス会議が提唱するグレートリセットですが、その内容で具体的なのは「資源を節約して持続可能な社会を実現する」というものです。その一環としてCO2の削減などお決まりのお題目が並んでいます。どんなリセットがされるのか戦々恐々の私には、いささか肩透かしの感が否めません。しかし、以前にも書いた様に1970年代のローマ会議の時代から、世界の経営者の一部は一貫して「持続可能な社会の実現」を目標としています。
■ 人口が国力とならない時代の到来 ■
一見すると「素晴らしい?」事に思える「持続可能社会」ですが、世界の経営者の視点から見れば、「有限な地球の資源を愚民どもに浪費させたくない」とい考え方になるでしょう。ここで、前回の内容に繋がりますが、近代から現代はでは「人口=国力」の時代でした。国土が大きく、国民が多く、資源が豊富な国は大国として君臨する時代でした。「人口=労働人口=国力」、さらに「人口=兵力=国力」という時代だった。
ところが、今後50年、100年といった未来を予見した場合、「AI化」や「自動化」は相当に進むハズです。「AIが人の知能を凌駕する(シンギュラリティーポイント」が来るとか来ないとかの議論を置いておくとしても、「知的作業の効率性」においてAIは近い将来に人間を越えるハズです。AIはデジタル化された仕事が得意ですから、経理や会計といった会社の事務作業からAI化は進みます(既に会計ソフトで自動化は進んでいます)。ビックデータを扱う事を得意とする事から、「分析や判断」の大部分もAIに置き換わって行くかも知れません。既に投資銀行ではコンピューターが短時間で多量の取引を自動で行っています。
この様に従来高い能力の人材が必要とされた、ホワイトカラーと呼ばれる職種から「自動化」が進み、これらの仕事に携わっていた人達が職を失います。「頭を使う仕事=コンピューターで自動化し易い仕事」だからです。
一方、建設業や介護や医療の現場は自動化が難しい。これらの仕事は「リアルな空間」にて行われるので、コンピューターやAIが進化しても、あまりメリットはありません。ロボットによる自動化も可能ですが、費用対効果を考えれば、安い人件費で人を雇用した方が経営者には有利です。例えば、飲食店の場合、発注までは既に自動化されています。テーブルに食事を運ぶ作業の一部もロボットが運ぶ店がチラホラ出て来ました。しかし、客の前に配膳する作業は人が行っています。この作業を自動化する事は不可能ではありませんが、ロボットアームヤセンサー類など高いコストを掛けた割りには客の満足度は低いはずです。ウエイトレスがにこやかに配膳してくれる方が嬉しい。
話が逸れますが、配膳の自動化などは大昔に実現しています。マクドナルドなどのセルフサービスです。或いは回転ずしなども配膳の自動化です。サービスの一部を客にやらせる代わりに安く食事を提供するというバーターによって自動化を実現しています。
上記の様なバーターが存在しない分野は自動化が難しい分野です。医療における看護や、老人介護は客が自分の世話を出来ないのでバーターが成立しません。患者の容体を観察し、ケアーをし、処置をするという行為も複雑で機会やロボットによる自動化が難しい。建設などの分野も、自動化から取り残されるでしょう。機械による自動化よりも、安い人材を使った方がメリットが大きいからです。
この様に、AIやロボットによる自動化が進んで、失われる職種は「知能労働」が多く、人の手に残る職種は「自動化が割りに合わないサービス業」となる。これは多くの本にも書かれている事です。
■ 社会を維持する最低限の人しか必要としない社会 ■
AI化や自動化が進んだ社会では、現在のホワイトカラーと呼ばれる様な職業はほぼ失われ、農林水産業や、建設業や、医療介護、サービス業、システムの保守の分野などで働く職種が残ります。しかし、これらの残された職種に従事する人口は少ない。
では、仕事を失った多くの人(或いは今後仕事を失うであろう多くの人)をどうするのか?
最近盛んなベーシックインカムはこの問題の解決策と期待されていますが、「国家がタダ飯を食らう大多数の国民の生活を支える」というのは怠け者の妄想です。
AIを駆使する様な企業が、多額の税金を国家に払うでしょうか?答えはNOです。デジタル空間を主戦場とする様な企業は、本社をタックスヘブンに移す事が容易です。工業にしても、自動化が進めば労働者の質に縛られる事はありません。土地が安く、消費地に近く、電力などのインフラが安定して、政治的に安定し、税金の安い国が最適立地となります。
「AIや自動化の時代に人々は労働から解放される」というのは身勝手な願望に過ぎない。国家間の競争は熾烈ですから、国家が衰退しない為に、「タダ飯を食らう大多数の国民」を淘汰する選択をするはずです。
■ 新型コロナウィルスとワクチンのコンボ攻撃で人口を大幅に削減する ■
人口削減の仕掛けは世界中で既に発動しています。新型コロナウィルスとワクチンです。
私は新型コロナウイルスの毒性が低い事から、最初は「経済兵器」だと考えていました。ロックダウンで経済を麻痺させて、リーマンショック後のバブルを確実に崩壊させる為の仕掛けだと考えていた。
しかし、執拗に接種が推奨され、人権の一部を制限してまで接種が強要されるワクチン政策が各国で行われるに至り、新型コロナワクチンこそが、この騒動の目的ではないかと疑い出した。そしてワクチンの作り出すスパイクタンパク質自体がウイルスの毒性である事、実験的なm-RNAワクチンが免疫抑制をして多くの疾患を促進させる事、アジュバンドとして使われている脂質ナノ粒子(LNP)が強力なアジュバンド(免疫賦活剤)で接種後にサイトカインストームを起こしたり、長期に渡る炎症作用でガンの原因になる事に気付きました。
しかし、足りない・・・。AI化や自動化した社会に対応する様に人口を大幅に削減するには、新型コロナワクチンでは不確定過ぎる気がします。確かに精巣や卵巣に影響を及ぼすワクチンによって出生率が10%程度下がるかも知れませんが、その効果が確実な人口抑制として機能するまでには20年、30年という年月が必要となります。そして、出生率の低下は少子高齢化の歪を拡大するので、国家の財政を破綻させる。
では新型コロナウイルスとワクチンの組み合わせで、一気に人口を減らす方法があるのか・・・・。京都大学の免疫学の専門家の宮沢先生がちょっとコワイ話をしています。
1)人体はコロナウイルスに対しては抗体を作らずに、細胞免疫で対抗している
2)コロナウイスは抗体を作ると抗体依存性増強(ADE)を起こし易くなるなど、不都合がある事を身体は知っているのだろう
3)武漢型ウイルスは毒性はあまり強く無く、抗体依存性増強も起こしにくい型のウイルスだった
4)武漢型ウイルスの恐怖を煽って、半ば強制的に武漢型ワクチンを接種させ、武漢型の抗体を作らせた
5)コロナウイルスは一度免疫記憶させると、変異株でも最初の武漢型の抗体を免疫系は主に生産する
6)武漢型で免疫記憶された所に、武漢型の抗体で抗体依存性増強を起こす強毒型のコロナウイルスが発生するとワクチン接種者はADEによって感染・重症化して多くの死者が出る
7)自然感染によって得られる抗体は、新型コロナウイスの様々なタンパク質に対応している為にADEを起こし難い
8)武漢型のスパイクタンパク質のみの抗体を生産するワクチンによって得られた単一の抗体はADEを起こし易い
9)上記の内容は、ウイルステロのシミュレーションとして専門家ならば誰でも考える
10)現在の遺伝子操作の技術があれば、北朝鮮でも実行出来るウイルステロの手法だ
ちょっと恐ろしい内容ですが・・・、この方法ならば、ビル某が言う様に世界中で10億人を削減する事も可能です。「新型コロナの強毒性の変異株が流行して多くの人が亡くなった」と後の歴史には書かれるでしょう。スペイン風邪と同様です。
ここで注意すべきは、高齢者とハイリスクの方はワクチンが優先接種されている点です。ワクチンの含まれるm-RNAを操作してADEを起こし易くする事が出来るかも知れません。一方、医療関係者や一般の人、子供が接種したワクチンはADEを起こしにくい抗体を作る様な仕掛けがしてあるかも知れません。この方法によって短期的には、高齢者やハイリスクの方を選択的に淘汰し、長期的にはm-RNAワクチンの効果によってガンの量産や出生率の低下によって、緩やかに人口を削減できます。高齢になった時のガンの発生率が高くなれば、高齢者対策にもなります。
WHOは全てのワクチンをm-RNAにする計画を立てている様なので、「長生き出来ない子供」を計画的に生み出すのかも知れません。(妄想です)
■ 家畜としての人 ■
経済活動の主役がAIや自動機械になった時代に人々の役割は現在と大きく変わるでしょう。人間の役割は、最低限の社会インフラを維持して、AIや自動機械の効率を最大化する事が求められる。当然、ベーシックインカムの様な方式で、人々の生活は保障されますが、利益の大半は、AIや自動機械を所有し使役する人達が独占します。
これは言うなれば「人の家畜化」です。陰謀論者は、ユダヤ支配に絡む「家畜としての人=ゴイム」という言葉を好んで使いますが、私が予測しているのはAI化や自動化の帰結としての「人の家畜化」です。家畜はオオカミなどの外敵から守られ、美味しい牧草や飼料を保証されて一生を終えます。その代償に家畜は「人の役に立つ」事を求められます。これと同じ事は、AI化と自動化の進んだ未来に、人はAIや自動化を支える仕事に従事して、生活を保障される存在となる。
■ ベーシックインカムと資産保有の制限 ■
人に残された仕事の生産性が下がると、賃金が低下します。それを補うのがベーシックインカムです。
MMT支持者は「ベーシックインカムは夢の制度」と夢想していますが、現在の人口規模でベーシックインカムを実施する為には政府通貨の様なシステムが必要になります。民主主義の制度では、政府はは国民の要求に屈してベーシックインカムで配る金額が拡大して行き、インフレを招いたり、市場がバブル化します。
そこで、ベーシックインカムが実施される為には、貨幣の在り方も変わる必要があります。私は電子マネーがこれを実現する鍵だと妄想しています。電子マネーは個人が所有するお金が個人情報に紐付いています。現在のお金は、人の手に一旦渡れば、その使い道を制限する事は出来ませんが、電子マネーならばそれが可能になります。
例えばベーシックインカムで配分したお金は3カ月後に政府に戻るとか、或いは投資に使えないといった制限をお金自体に与える事も可能です。だから政府はマイナンバーカードを必死に国民に取得させようとしているのだと私は確信しています。マイナンバーカードが電子マネーのプラットフォームとなるからです。そして、政府の必死さから推測して、3~5年の内に、現在の通貨が電子マネーに置き換わる様なイベントが発生すると妄想しています。
■ デジタル管理社会という家畜に居心地の良い環境 ■
少し過激な内容が続きましたが、「人の家畜化」というと聞こえが悪いですが、既に私達は「家畜化」されています。国家は外国の攻撃から国民を守り、福祉によって最低限の生活を保障してくれています。TVは人々に娯楽を与え無駄な思考を停止させています。その代償として、私達は社会を乱す行動を慎み、勤労に励んで税金を国家に収めます。この関係が成り立つのは、労働によって生み出される価値が経済的利益を人々と国家にもたらすからです。
因みに経済的利益を生み出す労働とは「第一次産業」と「鉱工業(第二次産業)」だけです。サービス業は消費するだけですから、第一次産業と第二次産業で生み出された富を消費する事で成り立っています。(金融業は他国が生み出した富を搾取しますが、日本の様に搾取される国もある事に注意が必要です)
先日、阿修羅掲示板に面白い書き込みがありました。ヨーロッパのシステム開発の会社が政府に極秘に依頼された仕事の内容です。それは国民をA~Dの4段階に分けて管理するシステムの構築で、内容的にはAランクは資産保有の自由が認められている、そしてB~Cになるに従って資産保有に制限が掛けられるといったシステムだったそうです。真偽は明らかでは有りません・・・。
仮に私がベーシックインカムを基本とした社会の設計を任されたら、同じ発想をすると思います。生産性の高いスキルを持つ者に資産保有を認め、生活の基盤をベーシックインカムに置く生産性の低い人には、資産保有に制限を掛ける。但し、最低限の生活は政府が保証する。
「資産保有の自由=豊かな生活」ですから、能力と向上心のある者は、そのステージを目指して努力し、社会の発展に貢献します。一方で、ベーシックインカムの議論でいつも問題となる「怠惰な人達」は、スキルをあまり必要としないが、社会基盤を支える為に不可欠な仕事に従事して、生活の保障を得る。
「努力すれば報われる」事と、「努力しなくても救われる」事がセットになっていれば、人々に不満は溜まりません。
■ 資源の乏しい西側諸国は、ネットの中に経済の主体を移す ■
AI化や自動化はデジタルと親和性が高い分野です。ですから、それらが生み出す価値の多くが、ネット空間で流通するものになる可能性は高い。金融サービスなどが最たる例ですが、銀行を介さずにお金の決済が出来る電子マネーは、これらの取引のスピードを飛躍的に向上させます。お金の余っている所から、必用な所にスムーズに資金を流す事が出来、リスクの計算もビックデータを活用して正確に行えます。
さらに娯楽もネット空間に移って行くでしょう。バーチャルリアリティーの技術が進歩すれば、ドラマや映画は主観体験に変わって行く。人々は実生活では質素な生活をしていても、仮想空間では華やかな生活が体験でき、美女やイケメンと恋に落ちる事も可能です。これこそ現在の弱者が望む「異世界転生」です。こうして家畜化された人達は、現在のTVに依存する以上に、バーチャルな現実に逃避する様になるでしょう。そして、これらのコンテンツを提供する産業が今のハリウッドを引き継ぐのでしょう。
西側の国々は資源に乏しいので、出来るだけ資源を消費しない産業を発展させると私は妄想しています。それは上記の様な、デジタル金融業で他の国や誰かの利益を掠め取ったり、魅力的なデジタルコンテンツで世界の人々をシャブ漬けにする分野でしょう。AIを使役する一部の人達が、この分野の利益を独占します。
■ 人としての従来型の幸せを選んだプーチン ■
ダボス会議や世界の経営者は、「物質消費を最小化するデジタル管理社会」を実現したい様ですが、プーチンはダボス会議の演説で、「ロシアは従来の人の幸せを追求する社会を目指す」と宣言して、その後ダボスと袂を分かちます。プーチンは「家族や地域と一緒に伝統を守って生活する幸せ」を強調しました。
プーチンや習近平は「独裁者」として国民を管理している様に思われていますが、彼らの政治手法は独裁的ですが、彼らの国民は伝統的です。これは大陸国家の特徴とも言えます。ロシアはツァーリズム(皇帝主義)の伝統を持つ国で、国民は強い指導者を求めます。中国も同様で、古来より強い皇帝が支配して来ました。広大な領土に様々な民族が住む大国では、強権でしか国家の統一が保てないからです。
中国やロシアで社会主義に実験が行われた事には実は意味があったと私は考えています。世界の経営者は、社会主義革命によって皇帝主義を駆逐しようと試みたのでは無いか。それは、世界の経営者「強い独裁者」を邪魔者と考えたから。
しかし、この実験は失敗したのでしょう。ソ連は崩壊して、ロシア人はプーチンというツァー(皇帝)を望んだ。家族を否定した社会主義に反動で、家族を大切にする文化が残った。中国も共産党独裁が資本主義を取り入れて、習近平独裁で政治の意思決定を高速化している。そして家族愛や地域愛はそもそも中国人の伝統でもある。
この様に中国やロシアはダボス会議や世界の経営者の目指す「省資源なデジタル管理社会」を選択せずに、伝統的な社会の持続を選んだ。これが可能なのは、広大な土地に多くの資源を持ち、食料も自給出来るからです。ブラジルやサウジアラビア、インドなど、南アフリカなどが、この陣営に加わりました。
尤も、中国やインドなどは人口問題を抱えていますから、新型コロナによる人口削減には参加している様です。但し、ワクチンがm-RNA型でない点に注意が必要です。イギリスもチャッカリ、アストラゼネカのウイルスベータ型にワクチンを接種しています。
■ 世界は冷戦によって二分される ■
第二次世界大戦後の社会実験はソ連や中国で実施されました。人権を制約された社会主義や、怠け者を生み出す共産主義は失敗に終わります。
これから始まる「省資源のデジタル管理社会」の実験は、どうやら西側の国々を中心に行われる様です。人々は最低限の生活を保障されながら、デジタルでソフトに管理される。この社会を作る為に「資源の制約」が不可欠です。だから、東西対立が煽られ、再び冷戦構造が作られ様としている。資源を多く有する国々と対立する事で、「省資源のデジタル管理社会」の必要性を強引に作っているとも言えます。
■ これから世界は混乱期に入る ■
私の陰謀論は、「世界は全て結託している」というものですから、プーチンや習近平の選択が正しく人間的と主張する気は毛頭ありません。伝統的な幸せに魅力は覚えますが、ソフトなデジタル管理社会にも興味はあります。
ただ、残念な事に、新しい社会を生み出す為には、「破壊と混乱」が必要です。短期間の内にシステムは再構築する為には、古いシステムは一度徹底的に破壊する必要があります。
「新型コロナ&ワクチン」「金融緩和バブルの大崩壊」はその為に仕掛けで、これから10年間は、世界は大きな混乱に陥る可能性が高い。そして、その間、国民の不満を抑える為に戦争が利用されるでしょう。アジアにおいても台湾有事は十分に起こり得る。中国と東側世界を完全に分断する為に・・・。但し、アメリカと中国のデカップリングが未だ完了していないので、今は危機を煽る段階です。米国企業や、西側企業か中国から撤退して、生産拠点を自国内や、西側経済圏の国に移転し終わった時に、台湾有事(或いは尖閣有事)が発動すうのでしょう。
日本は中国に近過ぎ、ヨーロッパはロシアに近過ぎる。そして、イギリスやアメリカはそれらの国から適度に離れて海の上に浮かんでいる・・・。
本日は50年後の世界をSF的な思考で妄想してみました。これからの10年間・・・世界も社会も大きく変わって行くのでしょう。それを体験出来るのは楽しみではありますが・・生活の保障は・・・。
<追記>
私はダボス会議の提案する「グレートリセット」は、ワンマンな経営者が打ち出した「無理の多い経営戦略」だと考えています。実現性の詳細は詰められておらず、実施の方法は社員に丸投げされた状態。だから、今後、色々な不都合が生じて、思った様な結果を生まない、或いは技術的な問題で進捗が思わしく無いケースも出て来るでしょう。
ダボス会議や世界の経営者は、デジタル化を過大評価している様にも感じます。その保険として、ロシアや中国が伝統的な社会として残されるのかも知れません。第二次世界大戦後とは立場が逆転している点が面白い。