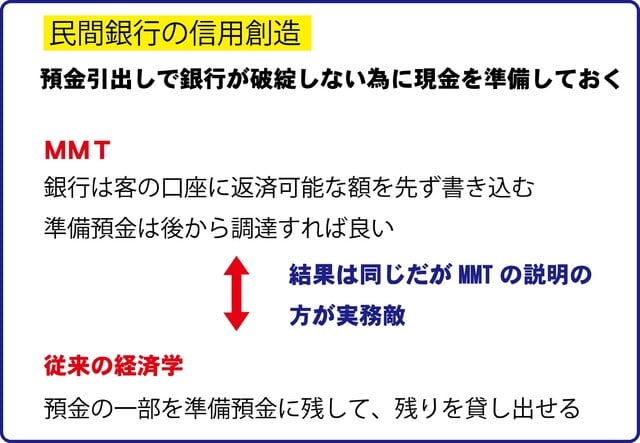東地中海ガス田の行方―欧州向けガス輸出ルートの可能性と課題―より
■ イスラエル沖のガス田からエジプトへのガス供給が絶たれた ■
今回のハマスの大規模なイスラエル攻撃と、それを受けたイスラエルのガザ地区への反撃は、イスラエル沖のカリシュ・ガス田からエジプトを経由したヨーロッパへの天然ガスの輸出に影響を与えます。カリシュ・ガス田の権益は、イスラエルとレバノンの間で争われています(一応、話し合いで)。
現在、イスラエルが米シェブロンのカリシュ・ガス田の操業許可を与えて、採掘船が創業を開始しています。ここで採掘されたガスは、パイプラインでガザを経由してエジプトに運ばれ、エジプトのLNG工場で液化された後、ヨーロッパに輸出される計画でした。エジプトは地中海沿岸のガス供給のハブ国を目指して、地中海地域で唯一のLNP工場を建設して、ヨーロッパへの輸出を計画しています。しかし、ガザ沖を通るパイプラインの安全が確保出来なくなったので、計画を変更してヨルダンを経由するを検討している。
今回の戦闘で、イスラエル政府は安全が確保出来ないとして、シェブロンに創業停止命令を出しています。これでイスラエル政府やエジプト政府が目論んでいた、ヨーロッパへの天然ガスの輸出で一儲けという計画が、しばらく中断します。
■ ハマスを排除して、海底油田を開発? ■
イスラエルはガザへの地上攻撃に先立ち、ガザ地区の北部からの住民の退去を呼び掛けています。ガザ北部の沖合には別の海底油田が有ります。ここはイスラエルに近いので、明らかにイスラエルの権益となります。ただ、パレスチナ自治政府も当然権利を主張しています。
今回のハマスの攻撃とそれを受けたイスラエルのガザ攻撃を、「イスラエル政府がハマスを裏で操って、ガザ北部からパレスチナ人を追い出して、ガス田の権利をイスラエルが一人占めるするものだ」との憶測が出ています。イスラエルが「わざわざ」ガザ北部からのパレスチナ人の退去を要求している事から、素直に考えればこの読みは正しいかも知れません。ガザ沖の油田からヨルダンへのパイプラインはガザ北部の近くを通っているので、ハマスがこれを攻撃する可能性は否定できない。
■ 短期的にはヨーロッパへのガスの供給を絶つ ■
私は、もう少し穿った妄想をしています。短期的にではあれ、創業が開始されようとしていたカリシュ油田の操業を止める事で、ヨーロッパ諸国はガスの供給先の一つを失います。ウクライナ戦争以降、米英は裏で、ヨーロッパへのエネルギーの兵糧攻めを画策している様に見えるます。ロシアからドイツにガスを供給するノードストリーム1,2の破壊の背後には米英の影が色濃くチラつく。
但し、カリシュ油田の操業停止が、国際世論や中東諸国を敵に回してのガザ侵攻と吊りあうかと言えば・・疑問です。長期的に見れば、ガス田やパイプラインからハマスを遠ざける目的と考える方が自然です。
■ イスラエルの地上侵攻をイランは見逃すのか ■
イスラエルは期限を切ってガザ北部から住民の退去を宣告しています。今の所、期限を過ぎても地上戦力を投入していませんが、退去が完了する前に地上戦力を動かすと、ガザ地区の一般人の被害が拡大するので、中東諸国を必要以上に刺激します。イスラエルとしては「ハマスとの戦闘」に限定する為にも、一般人の非難完了を待つ必要があります。
アメリカは完全にイスラエルを支持して、空母を地中海に配備しています。流石に直接戦闘に参加する事な無いと思いますが、イランへの圧力にはなります。イスラエルのガス田で操業するのは、アメリカの石油大手となるでしょうから、ここはイスラエル政府を前面バックアップです。G7では日本とカナダを除く5か国がイスラエル支援を明確にしています。ここら辺にも利権の影がチラつく。
問題はイランがイスラエルのガザ地区の侵攻にどう反応するかですが、ヨルダンのヒズボラがイスラエルを攻撃しして、ハマスを支援するでしょう。ヒズボラの後ろにはイランが着いています。しかし、イランが直接イスラエル軍と衝突したら、イスラエルやアメリカのイラン攻撃の口実を与える様なものなので、イランは動きが取れない。
イランがイスラエルやアメリカやNATOに攻撃されたら、中露は黙って観ている訳には行きません。中国はイランとの関係が深く、そこを起点に中東の石油利権に喰い入っていますし、ロシアとしても、関係の深いイランを見殺しにしたら、面目が立ちません。さらにドサクサに紛れてシリアを攻撃されて、租借してるシリアの軍港を失うのは戦略的な損失が大きい。
イランの参戦は、第5次中東戦争や、第三次世界大戦の引き金を引きかねないので、無いのでは無いかと・・・・。但し、イランが参戦するかも知れないと考えられるだけで、原油価格は上昇します。私はイランが口先でイスラエルを「口撃」して、中東の緊張を高めると妄想しています。イランはそういう役回りなのだと。
■ 対岸の火事では済まされない西側諸国 ■
アメリカを始め、ヨーロッパ諸国や日本では、中東は対岸の火事の様で、人々の議論は「人道的」な内容に終始しがちです。「今回はハマスが先に手を出したけど、イスラエルもガザ地区の住人を殺すだろうから、双方が悪い」という不毛な議論を繰り返すでしょう。
しかし、原油価格次第では、西側諸国のインフレ率はさらに上昇して、金利の上昇はバブルの息を止め、米国債金利の上昇は、米地銀を危機的な状況に追い込みます。実はガザ地区の紛争で尻に火が着くのは、西側諸国の可能性が高いと私は妄想しています。
問題は、バブルが崩壊して経済が大混乱に陥った時に、戦争が起こされて、全てがウヤムヤにされるケースです。世界大恐慌の後の、第二次世界大戦の様に、「強引なリセット」が計画されていないとも限りません。核兵器を保有する世界で、核保有国同士の戦争は、基本的には起こらないハズですが・・・フォークランド戦争の様に、イギリスは意外に血の気が多い。自分の得物に手を出されるとマジ切れします。