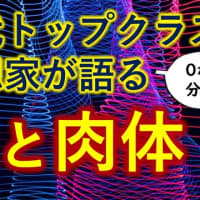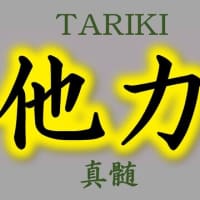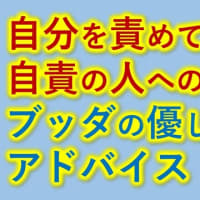「今の生活に何も問題はない。けれども、なぜか満たされない。何かが足りないと感じてしまう」
「今の生活で不平をいったら罰が当たる。でも、毎日、同じことの繰り返しで、虚(むな)しさを感じる」
「成功して達成感があったはずなのに、今はポッカリ胸に穴があいている」
「特別に何、というわけでもないのに、いつでも心の底に不安を感じている」
「幸せって続かないですよね。本当の幸せなんてあるのかな。もしも、あるのなら、ぜひ知りたい」。
こんなことを感じている人が増えているようです。
この心は一体どこからくるのでしょう?
そのヒントとなるのが「相対的貧困」という言葉と「幸」という字の語源です。
まず、「相対的貧困」というちょっと難しげな言葉からお話ししましょう。
実は、「絶対的貧困」と「相対的貧困」ということが、ちょくちょく話題になっています。
ここで「絶対的貧困」っていわれるのは、食べるものがない、住むところがない、お金がない、寝るところもない、といった、普通「貧困」と聞いてイメージするものです。
(「絶対的」という言葉はちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、いわんとしていることは分かられると思います)
では「相対的貧困」とはなんぞや。
このことについて、哲学者の内田樹氏が、こう語っていました。
相対的貧困は解決できるか(内田樹の研究室)より
http://blog.tatsuru.com/2010/02/15_1127.html
「相対的貧困」とは私が「貧乏」と呼ぶものである。
それは数値的には表示できないし、何か決定的条件の欠如としても記述できない。
それは
「隣の人はプール付き豪邸に住んでいるが、私は四畳半一間に住んでいる」
「隣の人はベンツに乗っているが、私はカローラに乗っている」
「隣の人はスコッチを飲んでいるが、私は焼酎を飲んでいる」
「隣の人はパテック・フィリップをはめているが、私はカシオをはめている」
というかたちで、どちらも同一カテゴリーの財を所有しているのだが、その格差を通じて欠落感を覚えるということである。
相対的貧困は、物資の絶対的な多寡とかかわりなく、隣人があるかぎり、つねに示差的に機能する。
だから、無人島に漂着した人々が隣人に感じる羨望と、ウォール街の金融マンが隣人に感じる羨望は、それが羨望である限り同質である。
そして、相対的貧困感は人間が複数で暮らす限り、決して消すことができない。
確かに、あるあるですね。
相対的貧困はいろんな場面に現れます。
よく、他人の幸福を見ておちこみ、インスタ疲れ、SNS疲れになる、とか聞きますが、これもその類です。
この問題はあちこちにあって、しかも解決しがたい。
絶対的貧困は、問題がハッキリしていて、解決した状態がイメージしやすいのですが、相対的貧困は問題が見えにくく、どうなったのが解決なのかもイメージしにくく、まして解決の糸口が見えない分、ややこしい問題なのです。
その問題の大きさについて内田樹氏が引用していた
『貧困を救うのは、社会保障政策か、ベーシック・インカムか』
(山森亮・橘木俊詔、人文書院、2009)
という本には、こう書かれてあります。
「橘木:アフリカのように水しか飲めないというような貧困が日本には少ないことは認めますが、我々は一定のコミュニティなり地域に住んでいる。
そのコミュニティの他の人々と比べて、自分がどれだけ悲惨な状況にあるかということから、貧困を感じるのです。
(中略)
例えば、私には100万円くらいの年収しかないけれど、隣に何億円もの年収の人がいて毎日パーティやって、おいしいものを食べて、ベンツに乗ったりしているのを見ていて、自分がいかにみじめな状況にいるかということを考えたら・・・。
こんな大金持ちではなくて普通の家庭でもいいですが、自分がいかに悲惨な状況にあるか、剥奪されているかと感じたら、最悪の場合その人は自殺するかもしれない。
これがまさに相対的貧困の定義ですから、相対的貧困も非常に重要ですよ。
平均的家計所得が高いから、あるいは食べられずに死んでいく人はいないから、日本の貧困は深刻ではないという論には、私は賛成しません。」(76-77頁)
ここでポイントは、「相対的貧困は大したことない、深刻ではない」という一般的な意見にNOを唱えている部分だと私は思います。
「相対的貧困」は、みんなに関係する大きな問題であり、解決が極めて難しい、つまり「ややこしい」問題なのです。
ここでは「貧困」という視点で語られていますが、その裏返し「幸せ」という観点で、『第3の幸せ』という本の第6章に、こう書いてみました。
第6章「幸」の字の語源が深い
さて、普通なら「幸せは物や金ではない、心の持ちようによって決まるのだ」で、話はめでたく終わりそうです。
しかし、この本では、さらに「幸せの本質」についての考察を深めていきます。
実は、「幸」の字の語源は、なかなか意味深長で「第2の幸せ」の理解を深めるものなのです。
「幸」の字の成り立ちは、難易度が高いので、いくつかヒントを出しましょう。
(ヒント1)これは象形文字です。
(ヒント2)こんな形がもとになっています。
 △
△
(ヒント3)それは、現在もあるものです。
(ヒント4)身体につけるものです。
(ヒント5)ほとんどの人はつけることがありません。
さあ、もうお分かりになったでしょうか。
実は、「幸」という字は、「手かせ」を描いた甲骨文字なのです。
現代でいえば、「手錠」。
「手錠」と「幸せ」。イメージは正反対ですね。一体どういうことでしょう。
この語源について、漢字学の権威である白川静氏の『常用字解』によるとこういうことです。
古代中国は、刑罰が非常に残酷でした。足を切ったり、腰を切ったり、手足を四方、動物に縛りつけ、動物を走らせて体を裂くなどなど。
聞くだけでも身の毛いよだつような罰を受けず「手かせ(手錠)で済むなんて、なんて、幸せなんだろう!」ということなのです。
つまり、「幸せ」は、比較して感じるもの、なのです。
あれよりまし、あの人よりいい、という相対的に感じるのが「幸せ」ということ。これが「幸」の語源です。
先に紹介した、「下見て暮らせ」という言葉は、確かに生活の知恵ではありますが、同時に他人の不幸を幸せのタネにしていることでもあります。
そのことを指摘した言葉が多く残されています。そのいくつかを紹介しましょう。
・幸福……他人の不幸を見ているうちに沸き起こる快い気分(ビアス 『悪魔の辞典』)
・不幸なものがもっと悪い目にあった他のものから慰めを得る(アイソポス『イソップ寓話集』)
・富者の満足は貧者の涙によって得られる。(トルストイ『トルストイの言葉』)
本当の幸せを知るには、一度は見たくないものも見なければならないのです。
さらに考察は進みます。
普通は問題提起で終わってしまうこの問題に、「答えをだしちゃいました!」と
いうのが『第3の幸せ』という大胆な本なのです☆
ハッタリか、ホンモノかは、実際に読んで確認してみてくださいね。
12月中旬発売予定です!
今、この本の最初の60ページを特別に無料公開していますので、よかったらご覧になってください。
コチラからどうぞ。
↓↓↓
https://www.freiseinstory.net/wordpress/gift/3goo