大阪府の橋下知事が,学校への携帯電話持ち込みを禁止する方針を打ち出しました。これをうけて,文部科学省などからもこの方針について歓迎する以降であるとのことです。一方で,生徒や父兄などからは,携帯電話が使用できなくなることによる弊害もあるなどとして,この方針に反対する動きも出ているようです。
携帯禁止「歓迎したい」=大阪府教委の方針受け-塩谷文科相(時事通信) - goo ニュース
なぜ法律ができるか考える良い機会になるのでは
携帯電話持ち込み禁止の是非については,既に多くの方が議論をしていますので,ここでは特に触れません。
例によって,この問題を全く違う視点から見ていきたいと思います。
携帯電話の学校への持ち込みが禁止されたというと,どうしても携帯電話のことだけに視点がいきがち,実は,ここに面白い問題が含まれているのです。それは,「なぜ世の中に法律ができ,刑罰ができるか」を考えることができるということです。つまり,「実社会におけるリーガルマインド」を小中学生からこの問題を通じて教え,考えさせることができるのです。
具体的にはこうです。
そもそも,なぜ知事は学校に携帯を持ち込むことを禁止しようとしたのでしょうか。その理由を考えてみましょう,っていうことになります。
「わからん」「考えたって嫌なものは嫌」というのが子供の発想になると思いますが(まあ,中にはこういう発想の大人もいますが),そこで理由なしに禁止することはない。理由なしに禁止したとすれば,説得力のない禁止規定だよ。」ということになります。
そして,禁止した理由を考えると,大きくいうと「授業中にケータイが鳴ったり,メール操作するなどマナーができていない」「怪しいサイトの情報に騙されて犯罪に巻き込まれる可能性がある」「適当な情報を書き込んでいじめの原因になる」などいくつかでてくるでしょう。
すると,次に考えるのが,「こういう目的を達成するために,持ち込みを禁止をするということが妥当なのか」ということです。それを考えさせますと,「なるほど」という子もいれば「ならばマナーや使い方のルールを守るようにみんなで注意すればよい。」などという意見も出てくると思います。
そこで,後者の意見が出たら,「じゃあ,いままでしっかりマナーやルールを守っていたか?」という点を考えます。
全員がマナーやルールを守っていれば,そもそも問題にならないわけですから,「たしかに」となります。もちろん,「私は守っていた」というこれまた子供の反論が予想されますが,これは想定内。
ここで,「物事はいきなり何か規制するわけではない。最初はみんなに迷惑をかけないようにするためのマナーやルールができてくる。ところが,誰かがのマナーやルールを守らないと,他の人に迷惑をかけてします。こういう人がどんどん増えてくると,もはやマナーやルールといったみんなの気持ちだけでは解決ができない問題になってしまう。そうなると,もっと厳しい決まりを作らなければならない。もちろん,そうなるとまじめにやっていた人も同じ厳しい決まりの枠に入ることになるが,他の人に迷惑をかけないというためには仕方がないこと。そして,それでもその決まりを守らない人がいたら,罰を与えてでも止めさせなければならない。そうしなければ,みんなが迷惑しっぱなしになるから。」と説明します。
そして,「実は,日本にはたくさんの法律がある。この多くは,そうしたマナーやルールを守らない人がいたことから,みんなの生活を守るためにできたものなんだ。そして,それでも守らないで迷惑をかける人がいるので,刑罰を与えることができる法律までできているんだよ。」と,法律がなぜ,どのような理由でできるのかを説明するのです。そして,これが「今の社会の仕組みなんだ」とはっきりいうのです。
最後に,「今回のケータイ禁止ということも,全く同じこと。みんながルールやマナーを守れば,こういう問題にまでならなかった。ところが,こういうことを守れなかった人が結構いたので,禁止することになった。法律が作られる仕組みと実は全く同じなんだよ。」ということで一応着地となります。
補足的に「もちろん,ケータイに限った話ではなく,すべてのことで同じ問題が起こるよ。それが学校内なら校則になり,国全体なら法律になる。」と説明します。
もちろん,ここからはいろんな反論が出てくるはずです。それで良いのです。日本の法律も,一度作ったらそのまんまではありません。いろんな反論や社会の変化があるので改正します。だから,ケータイ問題についても「みんなの反論がなるほど,ということがあれば,この規則も変わるかもしれないね。ただ,そのためには何をすればよいか考えよう。ただ反対,って叫ぶだけで本当に良いのかなあ?」などとふれば,「権利と義務」の関係も何となく分かってくるのではないでしょうか。
とまあ,長くなりましたが,ケータイ問題は,単純な「ケータイの是非」ではなく,「法律がどう作られ,権利義務がどういう関係にあるのか」をちゃんと教えるよい機会になるのではないでしょうか。裁判員制度が始まる今,このようなリーガルマインドを理解してもらうことも大切だと思います。
もっとも,橋下知事がそこまで考えて発言したとは思えませんが・・。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ

TB先一覧
http://palodysong.exblog.jp/9833004
携帯禁止「歓迎したい」=大阪府教委の方針受け-塩谷文科相(時事通信) - goo ニュース
なぜ法律ができるか考える良い機会になるのでは
携帯電話持ち込み禁止の是非については,既に多くの方が議論をしていますので,ここでは特に触れません。
例によって,この問題を全く違う視点から見ていきたいと思います。
携帯電話の学校への持ち込みが禁止されたというと,どうしても携帯電話のことだけに視点がいきがち,実は,ここに面白い問題が含まれているのです。それは,「なぜ世の中に法律ができ,刑罰ができるか」を考えることができるということです。つまり,「実社会におけるリーガルマインド」を小中学生からこの問題を通じて教え,考えさせることができるのです。
具体的にはこうです。
そもそも,なぜ知事は学校に携帯を持ち込むことを禁止しようとしたのでしょうか。その理由を考えてみましょう,っていうことになります。
「わからん」「考えたって嫌なものは嫌」というのが子供の発想になると思いますが(まあ,中にはこういう発想の大人もいますが),そこで理由なしに禁止することはない。理由なしに禁止したとすれば,説得力のない禁止規定だよ。」ということになります。
そして,禁止した理由を考えると,大きくいうと「授業中にケータイが鳴ったり,メール操作するなどマナーができていない」「怪しいサイトの情報に騙されて犯罪に巻き込まれる可能性がある」「適当な情報を書き込んでいじめの原因になる」などいくつかでてくるでしょう。
すると,次に考えるのが,「こういう目的を達成するために,持ち込みを禁止をするということが妥当なのか」ということです。それを考えさせますと,「なるほど」という子もいれば「ならばマナーや使い方のルールを守るようにみんなで注意すればよい。」などという意見も出てくると思います。
そこで,後者の意見が出たら,「じゃあ,いままでしっかりマナーやルールを守っていたか?」という点を考えます。
全員がマナーやルールを守っていれば,そもそも問題にならないわけですから,「たしかに」となります。もちろん,「私は守っていた」というこれまた子供の反論が予想されますが,これは想定内。
ここで,「物事はいきなり何か規制するわけではない。最初はみんなに迷惑をかけないようにするためのマナーやルールができてくる。ところが,誰かがのマナーやルールを守らないと,他の人に迷惑をかけてします。こういう人がどんどん増えてくると,もはやマナーやルールといったみんなの気持ちだけでは解決ができない問題になってしまう。そうなると,もっと厳しい決まりを作らなければならない。もちろん,そうなるとまじめにやっていた人も同じ厳しい決まりの枠に入ることになるが,他の人に迷惑をかけないというためには仕方がないこと。そして,それでもその決まりを守らない人がいたら,罰を与えてでも止めさせなければならない。そうしなければ,みんなが迷惑しっぱなしになるから。」と説明します。
そして,「実は,日本にはたくさんの法律がある。この多くは,そうしたマナーやルールを守らない人がいたことから,みんなの生活を守るためにできたものなんだ。そして,それでも守らないで迷惑をかける人がいるので,刑罰を与えることができる法律までできているんだよ。」と,法律がなぜ,どのような理由でできるのかを説明するのです。そして,これが「今の社会の仕組みなんだ」とはっきりいうのです。
最後に,「今回のケータイ禁止ということも,全く同じこと。みんながルールやマナーを守れば,こういう問題にまでならなかった。ところが,こういうことを守れなかった人が結構いたので,禁止することになった。法律が作られる仕組みと実は全く同じなんだよ。」ということで一応着地となります。
補足的に「もちろん,ケータイに限った話ではなく,すべてのことで同じ問題が起こるよ。それが学校内なら校則になり,国全体なら法律になる。」と説明します。
もちろん,ここからはいろんな反論が出てくるはずです。それで良いのです。日本の法律も,一度作ったらそのまんまではありません。いろんな反論や社会の変化があるので改正します。だから,ケータイ問題についても「みんなの反論がなるほど,ということがあれば,この規則も変わるかもしれないね。ただ,そのためには何をすればよいか考えよう。ただ反対,って叫ぶだけで本当に良いのかなあ?」などとふれば,「権利と義務」の関係も何となく分かってくるのではないでしょうか。
とまあ,長くなりましたが,ケータイ問題は,単純な「ケータイの是非」ではなく,「法律がどう作られ,権利義務がどういう関係にあるのか」をちゃんと教えるよい機会になるのではないでしょうか。裁判員制度が始まる今,このようなリーガルマインドを理解してもらうことも大切だと思います。
もっとも,橋下知事がそこまで考えて発言したとは思えませんが・・。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://palodysong.exblog.jp/9833004










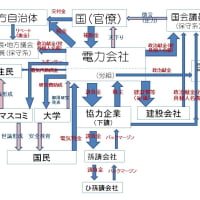




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます