これまでは,主にお金がどう動いているのかについて説明してきました。一方で,道路について無駄だと指摘されるもう一つの要素として「やたら大きい道路造って」などという「道路の規模」に関する点があげられます。
ところが,この道路の規模,何も適当に幅を決めているのではなく,「道路構造令」という法律に則っているのです。もちろん,大阪の御堂筋のように建設当初は大きすぎるなど批判されていたものの,現在ではこのくらいの広さが無ければむしろ交通網として成立しなかったなどという事例もありますので,何でもかんでも「大きいことが悪いこと」とまでは言えません。
そこで,今回は,道路の大きさがどうやって決まるのか,道路構造令を中心に表街道を説明した上で,これに補助金が絡むとその理念がどこまで曲がってしまうのかという裏街道を説明していきます。
第1 道路の大きさの決め方(表街道)
1 すべての基準は「道路構造令」にあり
前述のとおり,道路の基準は「道路構造令」に細かく定められています。簡単に言うと,道路を第1種から第4種まで分類し,さらに各種別の中で1級から最大5級まで細分化します。そして,それぞれに見合った幅員や付帯施設,舗装方法等の基準を定めています。
そして,この種別は高速道路か否かと,都市か地方かで分類します。級別についていは,想定交通量で分類します。当然,道路の構造も都市一般道の4種よりも地方高速道路の1種の方が良くなりますし,同じ地方一般道たる3種だとしても,交通量の少ない5級よりも交通量の多い1級の方が当然構造は良くなります。
2 補助金の基準は道路構造令
次に,前回説明したように,道路工事には様々な補助金制度があり,これを活用して道路建設をします。
補助金にはそれぞれ目的があるため,その目的に応じた道路工事に対して交付されることになります。そして,その際の条件として「道路構造令に合致した道路」を造ることになるのです。
したがって,地域の事情で道路構造令の基準未満の道路を造ろうとした場合,「不適格道路」となり,補助事業としては認定されないことになります。ただし,単独事業で不適格道路を造ること自体は特段問題はありません。
3 補助金の用途
ここで,簡単に補助金システムについて説明します。
補助金は,事業費の一部を補助するという性質であるため,まず用途が限定されます。当然,道路工事で補助金が出た場合,これをその道路工事以外で使用することは許されません。
また,入札などで当初予算より安く済んだ場合,それで仮に補助金にあまりが出れば,それは返還しなければなりません。
つまり,補助金は自由に使えるものではないのです。
裏街道は次回へ
インデックスに戻る
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ

ところが,この道路の規模,何も適当に幅を決めているのではなく,「道路構造令」という法律に則っているのです。もちろん,大阪の御堂筋のように建設当初は大きすぎるなど批判されていたものの,現在ではこのくらいの広さが無ければむしろ交通網として成立しなかったなどという事例もありますので,何でもかんでも「大きいことが悪いこと」とまでは言えません。
そこで,今回は,道路の大きさがどうやって決まるのか,道路構造令を中心に表街道を説明した上で,これに補助金が絡むとその理念がどこまで曲がってしまうのかという裏街道を説明していきます。
第1 道路の大きさの決め方(表街道)
1 すべての基準は「道路構造令」にあり
前述のとおり,道路の基準は「道路構造令」に細かく定められています。簡単に言うと,道路を第1種から第4種まで分類し,さらに各種別の中で1級から最大5級まで細分化します。そして,それぞれに見合った幅員や付帯施設,舗装方法等の基準を定めています。
そして,この種別は高速道路か否かと,都市か地方かで分類します。級別についていは,想定交通量で分類します。当然,道路の構造も都市一般道の4種よりも地方高速道路の1種の方が良くなりますし,同じ地方一般道たる3種だとしても,交通量の少ない5級よりも交通量の多い1級の方が当然構造は良くなります。
2 補助金の基準は道路構造令
次に,前回説明したように,道路工事には様々な補助金制度があり,これを活用して道路建設をします。
補助金にはそれぞれ目的があるため,その目的に応じた道路工事に対して交付されることになります。そして,その際の条件として「道路構造令に合致した道路」を造ることになるのです。
したがって,地域の事情で道路構造令の基準未満の道路を造ろうとした場合,「不適格道路」となり,補助事業としては認定されないことになります。ただし,単独事業で不適格道路を造ること自体は特段問題はありません。
3 補助金の用途
ここで,簡単に補助金システムについて説明します。
補助金は,事業費の一部を補助するという性質であるため,まず用途が限定されます。当然,道路工事で補助金が出た場合,これをその道路工事以外で使用することは許されません。
また,入札などで当初予算より安く済んだ場合,それで仮に補助金にあまりが出れば,それは返還しなければなりません。
つまり,補助金は自由に使えるものではないのです。
裏街道は次回へ
インデックスに戻る
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ










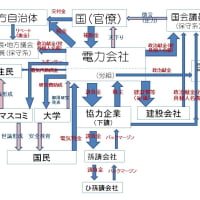




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます