小さい時に、自分の中の「攻撃性」なるものを
十分 発揮なり 発散できなかった場合に、
あとから それを 補うために 親や きょうだいや
友人、あるいは物に対して 攻撃と言うか破壊行動と言うか、
そういう形ででてくるのではないかと
いうような 書き込みを見た。
わが家の 子ども達は 別に 破壊行動を 起こしたことはないように思うが、
小さい時に 攻撃性なるものを 発散させる場が あったか、と思い出してみた。
攻撃性、と言う言葉が 私にはしっくりこない。
自己能力確認の機会、というほうが しっくりくる。
たとえば この石なら 持ち上げられるが、投げる事はできない、と言う場合。
投げられる大きさの石を 水辺で投げても、大きな音は出ないし、
達成感は少ないだろう。
何回も チャレンジするうち、大きな石を 投げる事に成功すれば、
びっくりするほど 大きな水音がするし、魚も逃げる。
音が大きくなれば、向こう岸の カモも 逃げる。
砂山に 水をかける時も、少ない水では一度に崩せる砂の量は少ない。
でも、重い物が持てて、しかもそれを 加減して
砂山にかける事ができれば、見事に 砂の山が
自分の 思うように 崩れていく様子を見る事ができる。
抜こうとしても びくともしない草、やっと抜けたと思っても 根っこが残ったまま、
でも 力がついたら 草も 一本だけでなく、握れるだけ握ってそのまま
引っこ抜くことができる。
家の中でも、茹でたものを つぶす事などは、どちらの子も喜んでやった。
形があったものが、自分が すりこ木で つぶすたびにみるみる形が
崩れていく。崩れた後は、目標が小さくなるので、そこからは
難易度が高くなる。
それを 全部 つぶし終えて 次の工程に移る時には
どちらの子も なんともいえない顔になっていた。
段ボールを 崩して紐でしばる、大根や 山芋をすりおろす、
そうした事を生活の中で する事が、力や 感情のコントロールをする事の
役に立ったのではないか、と言う気がしている。
私は よく子どもを 布団蒸しにしたが、
そこから出ようと もがき、重い布団(わが家の布団は昔ながらの綿布団で重い)の
圧力を感じる事や、ようやく出られたときの 顔も、いい顔だったなあと思いだす。
どんな子どもも、人も、自分の能力を 発揮できない環境にいたら、
良くないだろうなあとは 思う。
今の 自分の 能力は このくらい、でもあそこまでは できるようになりたい、と
意識するには、やっぱり 体を動かすことが 一番いいように思う。
十分 発揮なり 発散できなかった場合に、
あとから それを 補うために 親や きょうだいや
友人、あるいは物に対して 攻撃と言うか破壊行動と言うか、
そういう形ででてくるのではないかと
いうような 書き込みを見た。
わが家の 子ども達は 別に 破壊行動を 起こしたことはないように思うが、
小さい時に 攻撃性なるものを 発散させる場が あったか、と思い出してみた。
攻撃性、と言う言葉が 私にはしっくりこない。
自己能力確認の機会、というほうが しっくりくる。
たとえば この石なら 持ち上げられるが、投げる事はできない、と言う場合。
投げられる大きさの石を 水辺で投げても、大きな音は出ないし、
達成感は少ないだろう。
何回も チャレンジするうち、大きな石を 投げる事に成功すれば、
びっくりするほど 大きな水音がするし、魚も逃げる。
音が大きくなれば、向こう岸の カモも 逃げる。
砂山に 水をかける時も、少ない水では一度に崩せる砂の量は少ない。
でも、重い物が持てて、しかもそれを 加減して
砂山にかける事ができれば、見事に 砂の山が
自分の 思うように 崩れていく様子を見る事ができる。
抜こうとしても びくともしない草、やっと抜けたと思っても 根っこが残ったまま、
でも 力がついたら 草も 一本だけでなく、握れるだけ握ってそのまま
引っこ抜くことができる。
家の中でも、茹でたものを つぶす事などは、どちらの子も喜んでやった。
形があったものが、自分が すりこ木で つぶすたびにみるみる形が
崩れていく。崩れた後は、目標が小さくなるので、そこからは
難易度が高くなる。
それを 全部 つぶし終えて 次の工程に移る時には
どちらの子も なんともいえない顔になっていた。
段ボールを 崩して紐でしばる、大根や 山芋をすりおろす、
そうした事を生活の中で する事が、力や 感情のコントロールをする事の
役に立ったのではないか、と言う気がしている。
私は よく子どもを 布団蒸しにしたが、
そこから出ようと もがき、重い布団(わが家の布団は昔ながらの綿布団で重い)の
圧力を感じる事や、ようやく出られたときの 顔も、いい顔だったなあと思いだす。
どんな子どもも、人も、自分の能力を 発揮できない環境にいたら、
良くないだろうなあとは 思う。
今の 自分の 能力は このくらい、でもあそこまでは できるようになりたい、と
意識するには、やっぱり 体を動かすことが 一番いいように思う。
 | 人間脳の根っこを育てる 進化の過程をたどる発達の近道 |
| クリエーター情報なし | |
| 花風社 |
















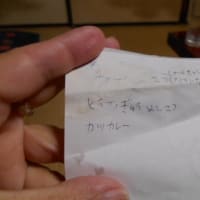



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます