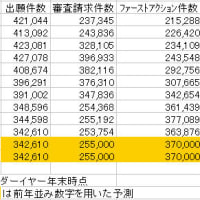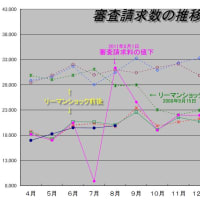事件番号 平成17(ワ)8359等
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成19年03月23日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 その他
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 市川正巳
『(2) 判断
ア「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうことから,真の発明者といえるためには,当該発明における技術的思想の創作行為に対して現実に加担したことが必要である。したがって,具体的着想を示さずに,単なるアイデアや研究テーマを与えたにすぎない者は,技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから,真の発明者ということはできない。もっとも,化学関連の分野においては,一般的に,着想を具体化した結果を事前に予測することは容易でないため,実験の結果予測したのとは異なる結果を生じ,それが発明に結びつくことも少なくない。このような場合,当該結果の技術的な意義を見いだすとともに,その有用性を確認した者をもって真の発明者と見るべき場合がある。
イ(ア) 上記(1)に説示の事実によれば,本件共同研究の実験に第一線で従事していたのはC1であるものの,研究の主体は飽くまで原告A1であり,C1はその補助として実験を実施していたにとどまるものというべきである。また,そうした実験の結果得られたガラス固化体の多孔化に技術的な意義を見いだし,有用性を確認したのも,原告A1であると認められる。
したがって,原告A1のみが,本件多孔化技術であるガラス固化体の多孔化技術という技術的思想の創作行為に対して現実に加担した者,すなわち発明者であるということができる。
これに反する被告の主張は,採用することができない。
(イ) よって,
a 本件請求項1~6の発明の発明者は,原告A1である。
b 本件請求項7~11の発明の発明者は,原告A1並びに被告及びC1である。』
『3 第1事件について
(1) 被告の行為の違法性の有無
ア 前記2(2)のとおり,本願発明の発明者は,原告A1並びに被告及びC1であるところ,本件出願は,被告のみを発明者として行われており,冒認出願に当たる。
イ (ア) 原告会社が本件共同研究の結果生じた発明で高知大学に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得された特許権につき優先的実施権を有すること(11条)は,前提事実(2)アのとおりである。
(イ) しかし,実施許諾の対象となる権利は,高知大学に承継された特許を受ける権利等であり,そもそも本件共同研究の結果,発明が得られたとしても,高知大学がその特許を受ける権利を承継すること又は特許出願することが本件共同研究契約上義務づけられているわけではない。
しかも,原告会社が有する上記優先的実施権は,飽くまで高知大学が原告会社等に許諾することができるというものであるにとどまり,契約上,原告会社が当然に優先的実施権を取得するとか,高知大学が優先的実施の許諾を義務づけられるという内容とはなっていない。
したがって,原告会社が本件共同研究契約に基づいて有する優先的実施権とは,本件共同研究の結果生じた発明が特許要件を充たすものである場合に,当該特許を受ける権利等が高知大学に承継されたときは,高知大学から,当該特許権等を一定期間優先的に実施し得るように許諾されることを期待し得る地位にとどまるものと理解するのが相当である。
(ウ) しかも,原告会社は,契約当事者ではない被告やTN 四国に対しては,そのような地位を当然に主張し得るものではない。
ウ (ア) 被告が本件共同研究契約とは何のかかわりもない全くの第三者であるとして検討すると,特許出願は特許法により認められた権利の行使であるから,後日拒絶査定が確定して特許を得られないことが確定しても,原則として,違法性が阻却されると解される。
しかし,特許権の設定登録がされた場合,特許権者以外の者は当該特許発明の業としての実施をすることができなくなり(特許法68条),このような事態から逃れるために,第三者は,費用をかけて無効審判請求等を行わざるを得なくなるから,特許出願人が事実的,法律的根拠を欠くことを知りながら,又は特許出願人として特許出願に当たり通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば,事実的,法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのに,あえて特許出願をした場合には,違法性が阻却されないことがあると解すべきである。
(イ) 登録拒絶理由のうち,冒認出願の点は,原告会社との関係において,不法行為法上違法とはならないと解される(特許法123条2項参照)。
また,新規性,進歩性等の欠如については,出願審査の請求(特許法48条の2)後に不法行為法上違法となることがあると解すべきである。本件では,本件出願につき,出願審査の請求はされていない。
したがって,被告が全くの第三者であるとして検討した場合であっても,原告会社との関係で,被告がTN 四国をして本件出願をさせたことにつき不法行為法上違法であると認めることはできない。
エ 以上によれば,本件出願は,原告会社との関係では,不法行為法上の違法性を有しないというべきである。
(2) まとめ
よって,原告会社の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
なお,契約責任の点については,原告会社は,300万円近い研究経費を負担して大学との共同研究を行ったにもかかわらず,その成果である多孔性ガラス材料が,原告A1の後任教授である被告により,原告会社に無断で,他社との間で実用化が図られようとしたものであり,原告会社に納得できない気持ちが残ることは,十分理解することができる。
しかしながら,本件共同研究契約上の原告会社の地位は,上記(1)イで述べたとおり,さほど強いものではないから,被告が他社と組んで公知化された技術の実用化を目指すことを阻止することは,道義的にはともかく,契約条項上はできないものである。原告会社としては,高知大学又は原告A1に特許出願をしてもらうか,研究成果の公表時期を協議により定めるものと規定した16条により,本件多孔化技術を一定期間秘匿しておくしかなかったものである。ところが,特許出願については,原告らは,長期間放置していたと評されてもやむを得ないものであるし,公表時期の協議については,C1の修士論文の課題変更が認められたことが同修士論文の備付け及び国際会議での発表による本件多孔化技術の公知化,被告による研究及び実用化につながっていったものである。公表時期の協議の点については,原告A1が自認するとおり,同原告の責任も重いといわなければならない。』
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成19年03月23日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 その他
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 市川正巳
『(2) 判断
ア「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうことから,真の発明者といえるためには,当該発明における技術的思想の創作行為に対して現実に加担したことが必要である。したがって,具体的着想を示さずに,単なるアイデアや研究テーマを与えたにすぎない者は,技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから,真の発明者ということはできない。もっとも,化学関連の分野においては,一般的に,着想を具体化した結果を事前に予測することは容易でないため,実験の結果予測したのとは異なる結果を生じ,それが発明に結びつくことも少なくない。このような場合,当該結果の技術的な意義を見いだすとともに,その有用性を確認した者をもって真の発明者と見るべき場合がある。
イ(ア) 上記(1)に説示の事実によれば,本件共同研究の実験に第一線で従事していたのはC1であるものの,研究の主体は飽くまで原告A1であり,C1はその補助として実験を実施していたにとどまるものというべきである。また,そうした実験の結果得られたガラス固化体の多孔化に技術的な意義を見いだし,有用性を確認したのも,原告A1であると認められる。
したがって,原告A1のみが,本件多孔化技術であるガラス固化体の多孔化技術という技術的思想の創作行為に対して現実に加担した者,すなわち発明者であるということができる。
これに反する被告の主張は,採用することができない。
(イ) よって,
a 本件請求項1~6の発明の発明者は,原告A1である。
b 本件請求項7~11の発明の発明者は,原告A1並びに被告及びC1である。』
『3 第1事件について
(1) 被告の行為の違法性の有無
ア 前記2(2)のとおり,本願発明の発明者は,原告A1並びに被告及びC1であるところ,本件出願は,被告のみを発明者として行われており,冒認出願に当たる。
イ (ア) 原告会社が本件共同研究の結果生じた発明で高知大学に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得された特許権につき優先的実施権を有すること(11条)は,前提事実(2)アのとおりである。
(イ) しかし,実施許諾の対象となる権利は,高知大学に承継された特許を受ける権利等であり,そもそも本件共同研究の結果,発明が得られたとしても,高知大学がその特許を受ける権利を承継すること又は特許出願することが本件共同研究契約上義務づけられているわけではない。
しかも,原告会社が有する上記優先的実施権は,飽くまで高知大学が原告会社等に許諾することができるというものであるにとどまり,契約上,原告会社が当然に優先的実施権を取得するとか,高知大学が優先的実施の許諾を義務づけられるという内容とはなっていない。
したがって,原告会社が本件共同研究契約に基づいて有する優先的実施権とは,本件共同研究の結果生じた発明が特許要件を充たすものである場合に,当該特許を受ける権利等が高知大学に承継されたときは,高知大学から,当該特許権等を一定期間優先的に実施し得るように許諾されることを期待し得る地位にとどまるものと理解するのが相当である。
(ウ) しかも,原告会社は,契約当事者ではない被告やTN 四国に対しては,そのような地位を当然に主張し得るものではない。
ウ (ア) 被告が本件共同研究契約とは何のかかわりもない全くの第三者であるとして検討すると,特許出願は特許法により認められた権利の行使であるから,後日拒絶査定が確定して特許を得られないことが確定しても,原則として,違法性が阻却されると解される。
しかし,特許権の設定登録がされた場合,特許権者以外の者は当該特許発明の業としての実施をすることができなくなり(特許法68条),このような事態から逃れるために,第三者は,費用をかけて無効審判請求等を行わざるを得なくなるから,特許出願人が事実的,法律的根拠を欠くことを知りながら,又は特許出願人として特許出願に当たり通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば,事実的,法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのに,あえて特許出願をした場合には,違法性が阻却されないことがあると解すべきである。
(イ) 登録拒絶理由のうち,冒認出願の点は,原告会社との関係において,不法行為法上違法とはならないと解される(特許法123条2項参照)。
また,新規性,進歩性等の欠如については,出願審査の請求(特許法48条の2)後に不法行為法上違法となることがあると解すべきである。本件では,本件出願につき,出願審査の請求はされていない。
したがって,被告が全くの第三者であるとして検討した場合であっても,原告会社との関係で,被告がTN 四国をして本件出願をさせたことにつき不法行為法上違法であると認めることはできない。
エ 以上によれば,本件出願は,原告会社との関係では,不法行為法上の違法性を有しないというべきである。
(2) まとめ
よって,原告会社の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
なお,契約責任の点については,原告会社は,300万円近い研究経費を負担して大学との共同研究を行ったにもかかわらず,その成果である多孔性ガラス材料が,原告A1の後任教授である被告により,原告会社に無断で,他社との間で実用化が図られようとしたものであり,原告会社に納得できない気持ちが残ることは,十分理解することができる。
しかしながら,本件共同研究契約上の原告会社の地位は,上記(1)イで述べたとおり,さほど強いものではないから,被告が他社と組んで公知化された技術の実用化を目指すことを阻止することは,道義的にはともかく,契約条項上はできないものである。原告会社としては,高知大学又は原告A1に特許出願をしてもらうか,研究成果の公表時期を協議により定めるものと規定した16条により,本件多孔化技術を一定期間秘匿しておくしかなかったものである。ところが,特許出願については,原告らは,長期間放置していたと評されてもやむを得ないものであるし,公表時期の協議については,C1の修士論文の課題変更が認められたことが同修士論文の備付け及び国際会議での発表による本件多孔化技術の公知化,被告による研究及び実用化につながっていったものである。公表時期の協議の点については,原告A1が自認するとおり,同原告の責任も重いといわなければならない。』